『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
17 寡黙と「いま・ここ」の感覚
聞き上手は寡黙
「巧言令色少なし仁」とはよくいったものです。(抜粋)
宗教家や占い師、セールスマンなど雄弁な人の言葉ほど、あまり信じられない。他人には現実と事実を見せるだけでいい、饒舌に売り込むのは、事実が劣っているからである。饒舌な相手の言葉やまず疑っていい、冷静にしていると相手のことがわかるが、こちらが多弁になると相手のことが分からなくなる。
聞き上手になるには、寡黙であることが必要である。ただし、この寡黙は相手との関係が切れた孤独からの寡黙でではありません。
「巧言令色少なし仁」って言葉は知らなかった。
三省堂辞書編集部の「ことばの壺」によると、論語の言葉であるとの事。意味は、自明だけど
口先だけうまく、顔つきだけよくする者には、真の仁者はいない。(抜粋)
ということ。そして、正確な表記は、
巧言(こうげん)令色(れいしょく)鮮(すく)なし仁(じん)(抜粋)
であるようです。(つくジー)
「いま・ここ」の感覚
ここで著者は、妄想をもった相談者の例をあげて、聞き上手に大切な「いま・ここ」の感覚について説明している。
あるときに一人の相談者が「自分のまわりの人が、みんな自分の考えていることがわかってしまう」という恐怖から憔悴しきって訪ねてきた。著者は、相談者を安心させるように話を聞いて、その後入院できる病院を紹介した。相談者は納得して入院したので回復も早く、現在はふつうの生活をしている。
聞き手の私にとって、彼の話が妄想レベルであることはすぐにわかります。しかし、彼が病院でなくて、逃げ回ったあげくカウンセラーをたずねてきたことに意味があるのです。彼の状態が心配ですぐに病院を紹介する必要があっても、一分一秒を争う外科的な病気と異なって、まずは心のケアを必要とします。カウンセラーが落ち着いて、相談者と「いま・ここ」のレベルの話ができますと、相手も落ち着いてこられるのです。(抜粋)
18 嘘はつかない、飾らない(オープンということ)
相手を素直に受け入れる
人は、相手がオープンだと話がしやすい。このオープンであるということは、相手に偏見をもたずに素直に受け入れることです。たとえ相手がどのような話をしても「あなたがそう思っているのなら、あなたにとってはそうなんでしょう」と受けられる人がオープンな人である。
オープンな人は自分を飾らず自分をさらしてくれる、それが相手に安心感を与える。そして、自分の欠点も素直に認めるので、相手も自分の欠点もそのまま認めてくれるという信頼感が生れる。
オープンの反対は、ディフェンシブ(防衛的)であるが、世の中はよこしまな考えの持ち主もいるのである程度の守りは必要だが、過度に防衛的な人は、基本的に人を信用していないところがあり、それが人間関係を阻害する。
大切な話をするとき、人は防衛的になる。聞き手が防衛的だと話が進まなくなるので、自分の方が相手よりもオープンになる必要がある。ここでオープンになるというのは自分の欠点や失敗談を話すということではない。ふつう失敗談は、もっと大きな失敗や欠点を隠すためであることが多く、じつはオープンではない。むしろ、ある種のユーモアをもって堅い雰囲気を和ますのがよい。
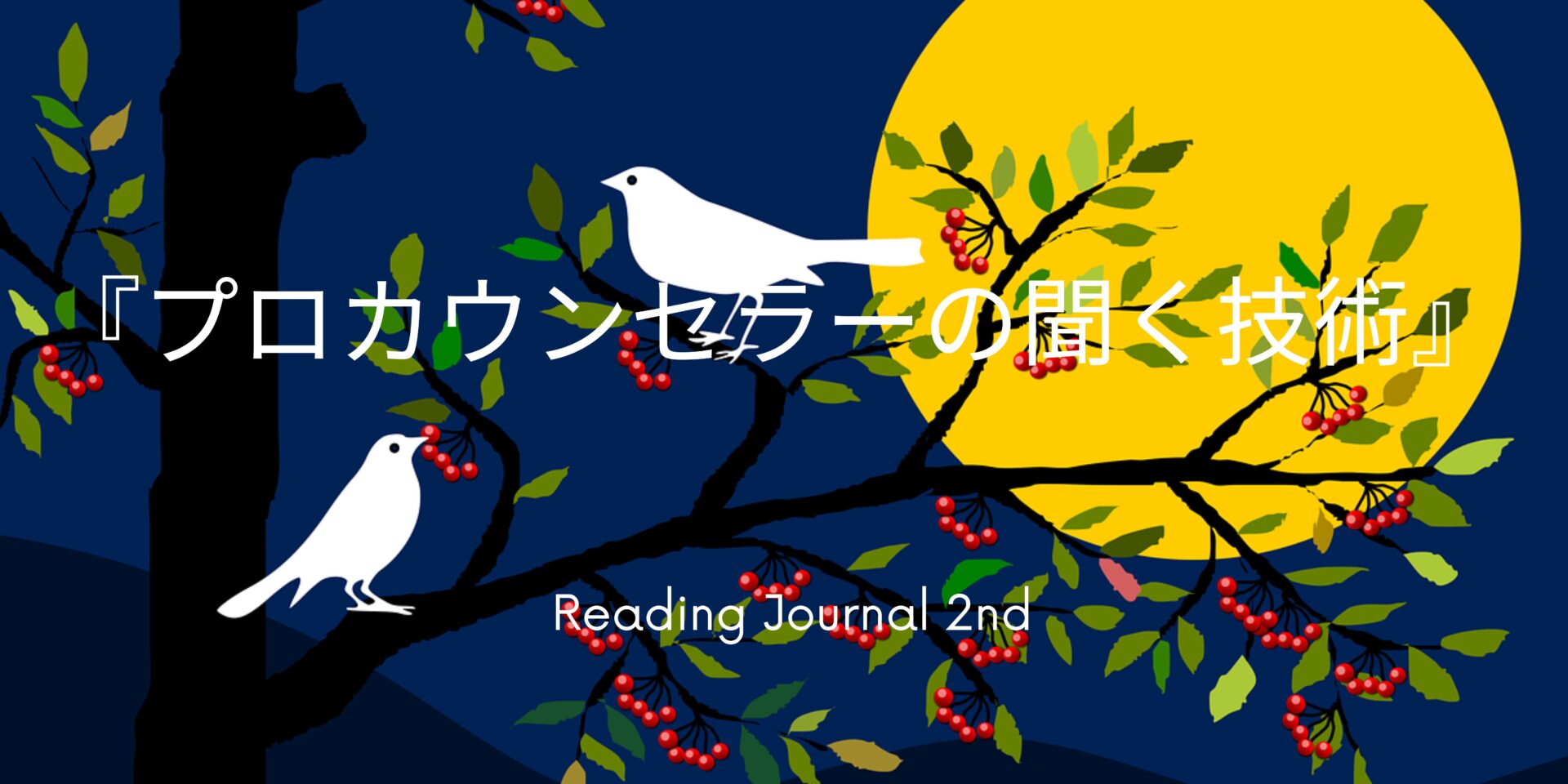


コメント