『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
レトリックへの誘い
「はじめに」が終わっていよいよ本文に入る。今日のところは、「レトリックの誘い」である。まずは、そもそもレトリックが如何なるものか?ということについての解説である。そして、本書の狙いと構成について言及されている。では読み始めよう。
レトリックとは何か
レトリックは、古代ギリシャで生まれ二五〇〇年の歴史がある。古代ギリシャでは、「共和制」がしかれ人々は議場での議論の結果によって重要な方針が決められた。そのため、いかに「よく話す」かが大きな意味を持った。この「よく話す」こと「説得力をもって話す」ことがしだいに体系化されていく。それがレトリックで、「説得術」を意味していた。
レトリックは、体系化された技術であり、非常に効果的であった。そのため、詭弁術のようなだましのテクニックにも使われた。そして説得術としてのレトリックは、より広くは「弁論術」と理解された。
レトリックは、古代の哲学者アリストテレスが『弁論術』に書いているように、どのようなテーマに対しても応用できる一般的な技術体系でした。(抜粋)
そのため悪用することもでき、国民を大規模な戦争に向かわせる政治レトリックにも応用された。
この意味で、レトリックは両刃の剣です。説得力が悪い方向に暴走しないように、知性による見張りが必要なのです。(抜粋)
レトリックには、説得するという面もあるがもう一つ大事な面がある。それは「表現そのものの魅力」である。日本では説得術としてのレトリックは体系化されず、もっぱら表現美を追求するレトリックに始終した。そのためレトリックというと「表現美」の方を思い浮かべる人が多い。
「はじめに」で「ちょっとした言い回し」といったのは、この意味でのレトリックです。(抜粋)
この意味でのレトリックは、「ことばを飾りたてるばかりで、実質内容が乏しい」という批判もあるが、じつは、「魅力的な表現」を求めるレトリックは、別なところに力点がある。魅力を美文や修飾に直結するのではなく「より適切な表現」に求める。
つまり、ことばにどれだけの仕掛けがあり、その潜在的な活力を明らかにするのが、「表現の魅力」のレトリックであり、それは「説得力」の面と矛盾しない。
レトリックとは、あらゆる話題に対して魅力的なことばで人を説得する技術体系である。(抜粋)
なるほどなるほど、いきなり古代ギリシャが出てきて驚いたがそういうわけですね。つまりは、レトリック=「弁論術」とは、
- 「説得術」のレトリック
- 「表現の魅力」のレトリック
あるってことですね。(つくジー)
論証と説得
レトリックを考えるうえで「論証」と「説得」の意味の違いを知っておく必要がある。論証ができるところは説得する必要はないからである。
- 「論証」・・・(数学的に)完全に正しいことを論証(証明)できる。魅力的な言い回しなど関係なく、最短距離を進めばよい。
- 「説得」・・・100%の確証が得られない時に必要。
そして、「説得」とペアになるものが「納得」である。説得がうまくいくと、納得してもらえる。
この納得は、考えると不思議なのですが、必ずしも論証や照明などによってえられるとはかぎりません。むしろ、「ああなるほど」と思ったときに納得するのです。(抜粋)
つまり、説得が必要な場合は100%の確証得られない(論証できない)場合である。そして、ほとんど疑いの余地がない真実でも、よく言葉を尽くさないと人に伝わらない。
そのため、相手に納得してもらうために、頼りになるのは言葉である。そのためにレトリックが必要になる。
レトリックの五部門
レトリックには「発想・配置・修辞(文体)・記憶・発表」の五つの部門がある。最初の三つは、何を、どの順序で、どのような言葉で述べるかを考える。そして後の二つは、内容をしっかり記憶し、見ばえよく発表することを受け持つ。あとの二つは、弁論術の伝統である。
- 「発想」・・・・素材を集める。テーマを決め、それに関係する材料を探し、データを収集する。
- 「配置」・・・・素材を適切に並べる。起承転結など
- 「修辞(文体)」・・・・文章の肉付けをする。ここがレトリックの中心であり、本文で取り上げるのは、この部門である。
本書では、表現の肉づけのために、ことばのちょっとした言い回しのパタンを整理する。それは整理することによって気づきをうながすためである。
次章より実際に修辞部門の代表的な三〇項目のレトリック型についてそれが実際にどのように応用されるのかを観察する。そして、最後に「レトリックを文章で生かす」の章で、レトリックを応用して魅力的な文章を書くことについて、そのさわりを解説する。
比喩の女王
比喩は、レトリックを代表するものである。ここで著者は、比喩について誤解・「比喩は飾りだ」という誤解を解くために、隠喩(メタファ―)の例を示して解説している。
隠喩を分析すると、同じような構造が日常語にもある。つまり、比喩は単なる言葉の飾りではなく、自分たちの思いを表わす根源的な表現方法である。
魅力ある各種の言い回しを分類整理すると、それほど魅力的と思えない日常のことばの中に、そっくり同じパタンが見つかるのです。(抜粋)
レトリックの幾つかのパタンは、私たちの思考方法そのものに近く、そのための気づきをうながす、というのが本書のねらいである。
30項目のレトリックの型
本書では、修辞のレトリックの型として30項目を選んだ。そしてその30項目は三つのグループに分類される。
- 意味にレトリック・・・言葉のあや(文を対象とする)。意味の変化に関係する。(直喩・隠喩など)
- 形のレトリック・・・型のあや(文を対象とする)。形の変化に関係する。(倒置法など)
- 構成のレトリック・・・思考のあや(文章を対象とする)。文より大きな単位の構成の変化に関係する。(パロディーなど)
関連図書:アリストテレス(著)『弁論術』、岩波書店(岩波文庫)、1992年
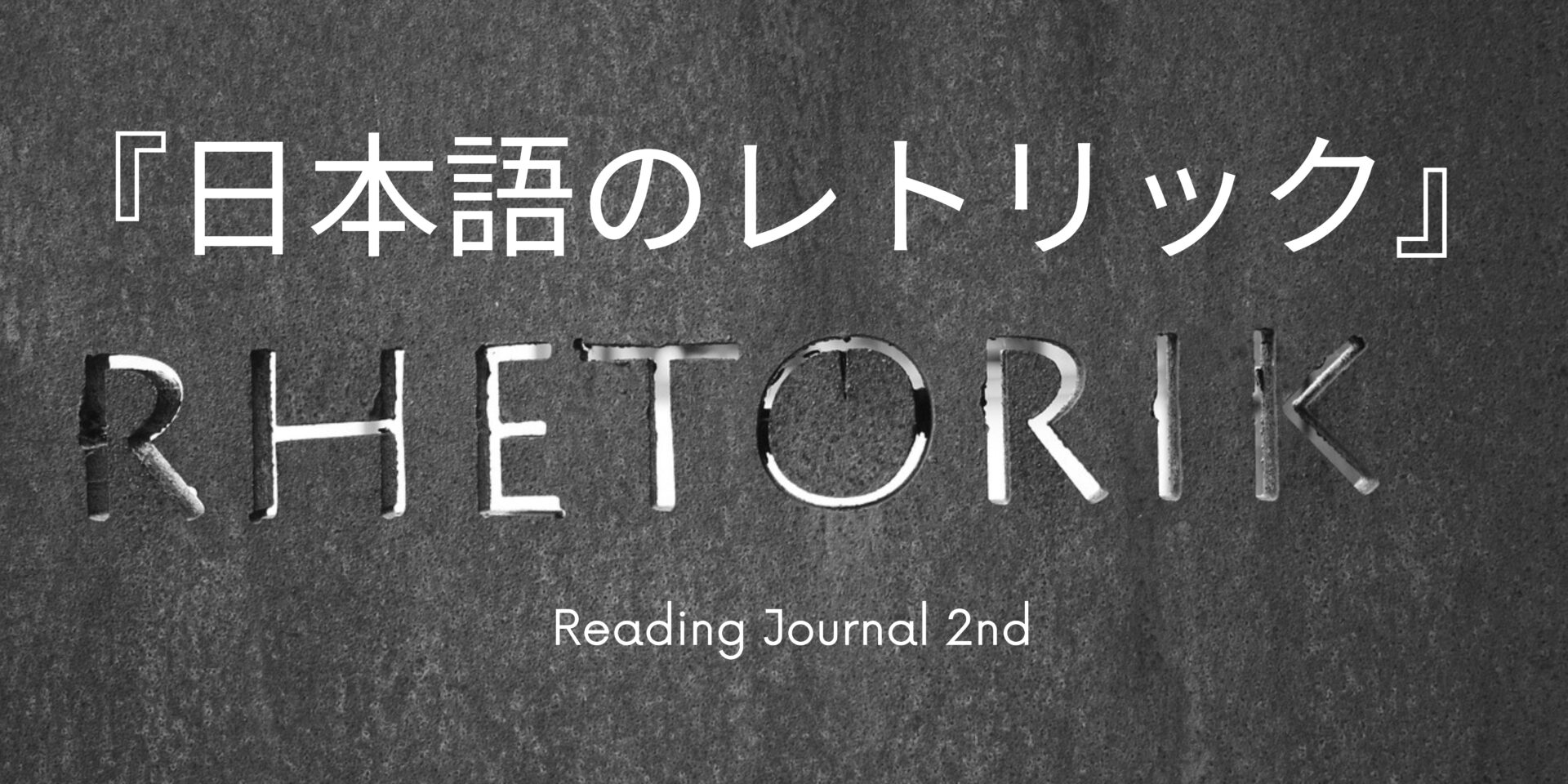


コメント