『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
9 他人のことはできない
親が子どもに出来ること
人は他人のことに口を出したくなり、また相手が親しい身内だと、当人に代わってやってあげたくなる。
しかし、人が成り代わってやれることはほとんどありません。(抜粋)
このことは年齢と反比例する。
乳幼児ならば、親がしてやったり、手伝ってやったりすることが多い、しかし、五歳以上になると八~九割は自分でできる。思春期以降になると親が行動で助けてやれるのは、年に数回。しかも、必要な時は本人が求めてくる。
当人が求めているのに自分でしなさいと突き放したり、当人がしようとしているのに口出ししたり、違うやり方を横から教えたりすることは、子どもの成長にとって大きな妨げとなります。(抜粋)
子どもは失敗から学ぶので、応援することは大切だがそれ以上することは成長の妨げになる。親が子供にしてあげるのは、一〇歳以上になれば、年に数回、知らないことを聞いてきたとき、知識が無いため誤った行動をしているのを是正してやることくらいである。
親ができることは、対社会面で子どもを守ってやること、いっしょに遊んでやること、子どもの話を聞いてやることです。(抜粋)
口出ししてしまう親(上司、教師)
親や上司、教師などが口出ししてしまう場合は、自身の不安や心配が関連していることが多い。この態度は「聞きモード」になることである程度抑えられる。子育て、生徒育てには、言って聞かせるモードよりも聞きモードの方が効果的である。
子育てのコツ
親の教えを守る子どもに育てるコツは、第一に「小さいときに子ども中心に遊んでやること」そして、「すこし大きくなたら、話を聞いてやること」である。
子どもに親がしてあげられることはほとんどなく、大切なのは自分のことは自分で出来る能力をつけることである。悩みや心理的葛藤に関しても同じで、自分で解決する能力をつける事が大切である。そして、悩みを解決できるように他者ができることといえば、心のケア、つまり聞いてあげることである。
しかし、「遊ぼう」とか「聞いて」とかは、忙しいときに言われることが多い。人間は自分中心で物事を考えるので、相手がしてほしいと思っている肝心なことはなかなかできない。
要は相手のタイミングで遊び、相手のタイミングで話を聞いてあげる、これが相手に対してできる最大のことなのです。それ以外は、他の人のことはできないのです。(抜粋)
10 聞かれたことしか話さない
この項は、8の「自分のことは話さない」と対になっている。
話し手の質問への答え方
話し手が「自分のことは話さない」ということは、「聞かれなかったら話さないということで、聞かれたらそのことだけ話す」ということである。話し手は、自分の関連することを聞いてくる。その時、聞き手は、話し手の立場に立って答えることが必要である。聞き手の立場から答えると話が行き違う。そう思うと、ほとんどの場合は答える必要はない質問である。ほとんどは質問というよりも、相手の同意を求めているので、同意するか、考えるためにちょっと間をおけば済む。しかし、話し手が聞き手の具体的な情報を必要としている時は、答える必要がある。
質問以外は答えない
また、話の内容に引っかかり感情的になるのは一番いけない。話の内容に引っかかると話し手が質問していないことまで、自分の意見を言ってしまう。それは、聞き役の放棄である。
質問していないときに答えてはだめなのです。このキー(指標)をおぼえておきますと、けっして論争になることはありません。(抜粋)
相手の鏡となる
日常生活の場合、相手からの質問は「自分のことでなく、相手に関すること」がほとんどで、相手は自分が聞いて欲しい話を質問の形で聞いてくる。そのため、聞き役は相手がしたのと同じ質問をするのがよい。
聞き手はいつも相手の会話の鏡となるような応答をすることが、聞き役を持続するコツなのです。(抜粋)
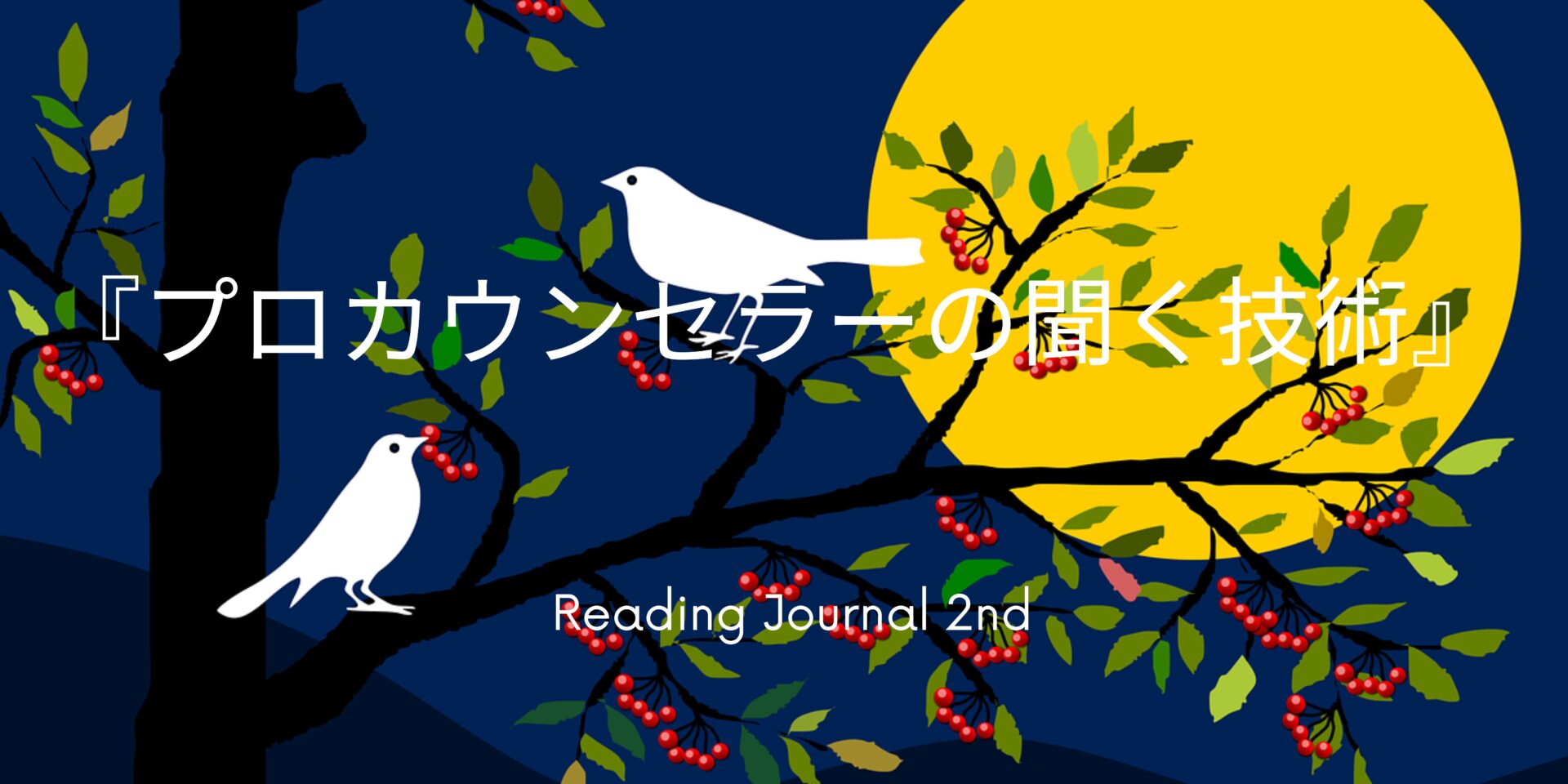


コメント