『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
強烈な色がひらく異界
ここでは、特定の色をテーマに結びつけて作品を作っている、フランスのイザベル・シムレールさんの作品を三冊紹介している。
『あおのじかん』
一冊目は『あおのじかん』である。この作品は、文字通りに絵本全体を『あお』が支配している。
シムレールさんの絵の特徴は、銅版によるエッチングのような極細の線を全面的に密度濃く使い、山並みも空も水面も、樹や花も、小鳥や動物も昆虫も、建物も、すべてその技法で描いていくところにある。(抜粋)
幾重にも重なる山並み、一面の雪と氷の世界、ページをめくっていくと、繊細なブルーの世界が広がっている。
この絵本には、他の作品もそうであるが、積極的な物語の展開があるわけではない。作家が自然のなかを歩き、目に映ったものをスケッチして、そこに備忘メモを記していき、そのスケッチ帳から絵本を組み立てていく、という印象を受ける。
『はくぶつかんのよる』
二冊目は、『はくぶつかんのよる』である。この絵本も基調となる色は「あお」だが、描く世界はガラッと変わって博物館の中である。夜、博物館のなかを黄色い蝶が飛び回り始める。そして、恐竜の骨格の部屋、動物や鳥たちの剥製の部屋へと読者を案内する。そのうち、展示物の生きものが夜の間、生き返り、館内は大賑わいとなる。
『シルクロードの あかい空』
三冊目は、『シルクロードの あかい空』である。この絵本は、日の出や日没時の強烈な「あか」が印象的である。シムレールさんは、「チョウ専門の昆虫学者」でもある。彼が「チョウの王女である『香妃』という蝶を探すために、中国西部の新疆ウイグル自治区を旅した時のスケッチがもとになっている。
その旅の始まりの風景がすごい。空も山々も近景も、日の出も光で一面真っ赤に染め抜かれている。歩いてくる牛と荷台にある三輪車を運転する農家の人々。中央アジアならではの風景だ。その手前を歩く女性はシムレールさんか。極細のエッチング風の赤い線が徹底的に重ねられ、そこに黄色い線を極めて細かく混入させることによって赤を一段と映えさせている。(抜粋)
関連図書:
イザベル・シムレール(作)、石津ちひろ(訳)『あおのじかん』、岩波書店、2016年
イザベル・シムレール(作)、石津ちひろ(訳)『はくぶつかんのよる』、岩波書店、2017年
イザベル・シムレール(作)、石津ちひろ(訳)『シルクロードの あかい空』、岩波書店、2018年
静寂のなかの音、のどを潤す冷水
絵本には、心に安らぎを与える能力がある。ここでは、そのようなほっとする安らぎを感じさせる絵本を四冊紹介される。
『よるおおと』
一冊目は、『よるおおと』である。夜、ホタルの舞う池のほとりを少年が、懐中電灯の明かりを照らして歩いている。池の端では、<リリリリリリリ>と虫の声が聞こえる。遠くを走る汽車の汽笛の音が響く。池のほとりを進む少年の耳には、さまざまな音が響いてくる。
やがて少年がおじちゃんの家の前まで来ると、犬が<ワンワン>と嬉しそうに迎えてくれ、<クゥーン>とすり寄ってくる。その瞬間、木の上にいたフクロウが突然、急降下して池の蛙を襲う。蛙は<バシャッ>と飛び込んで、危うく水中に逃れる。水面には、水の輪が広がっていく。(抜粋)
柳田は、これは芭蕉の世界ではないかと思う。そして、あとがきを読むと、その通りであった。
『よあけ』
二冊目は『よあけ』である。これは、第二次世界大戦後、旧ソ連に支配されていたポーランドからアメリカに移住したユリー・シュルヴィッツさんの絵本で、一九七〇年に翻訳されていらい、ずっと読み継がれているものである。
朝の湖畔の大きな木の下に老人と孫二人が眠っている。そしてあたりがほんのり明るくなり、おじいさんは孫を起こして、ボートに乗りこぎ出す。
山と湖が緑色になり、ピンク色の山の端から太陽が姿を現す。この夜明けの前の静寂と光の変化が、抑えたトーンで描かれ、それだけで、読む者はその時間と空間のなかに誘いこまれる。不思議な魅力だ。(抜粋)
『みずくみに』
三冊目は『みずくみに』である。これは飯野和好さんが描いた庶民感覚のあふれる絵本である。野良仕事をする一家と少女の風景が描かれ、汗を流して働く両親と祖父のために、少女と子犬が竹の水筒をもって谷川に向かう。
谷川のほとりに着くと、澄んだ冷たい水が、<ざあー ざあー びちゅ びちゅ ぴちゅ>。水筒に水をいっぱい汲んで、自分も<ごく ごく ごく ごく>。畑に帰ると、まずはおじいちゃんが、<おお、ありがとう ごくごく ごくごく>。次はおかあさんが・・・・・。
それだけの話なのだが、一読すると何とも爽やかな気持ちになる。(抜粋)
『おじいさんとヤマガラ ―― 3月11日のあとで』
四冊目は『おじいさんとヤマガラ ―― 3月11日のあとで』である。この絵本は、東日本大震災い伴う原発事故後の、放射性物質による自然界の汚染が生態系にもたらす異変に対する危惧を描き出している。
おじいさんは、毎年冬になるとヤマガラのために巣箱を作り山林に打ち付ける。ヤマガラは巣箱の中に巣をつくり、ひながかえる。
ところが原発事故後、巣箱に来るヤマガラが少なくなる。おじいさんは悲しむが、再びヤマガラが増えるようにと、次のとしはより多くの巣箱を作るのだった。(抜粋)
おじいさんとヤマガラたちの共生をあたたかく描くことによって、自然界のいのちを愛おしむこころが伝わってくる。
関連図書:
たむらしげる(作)『よるおおと』、偕成社、2017年
ユリー・シュルヴィッツ(作)、瀬田貞二(訳)『よあけ』、福音館書店、1977年
飯野和好(作)『みずくみに』、小峰書店、2014年
鈴木まもる(作)『おじいさんとヤマガラ ―― 3月11日のあとで』、小学館、2013年
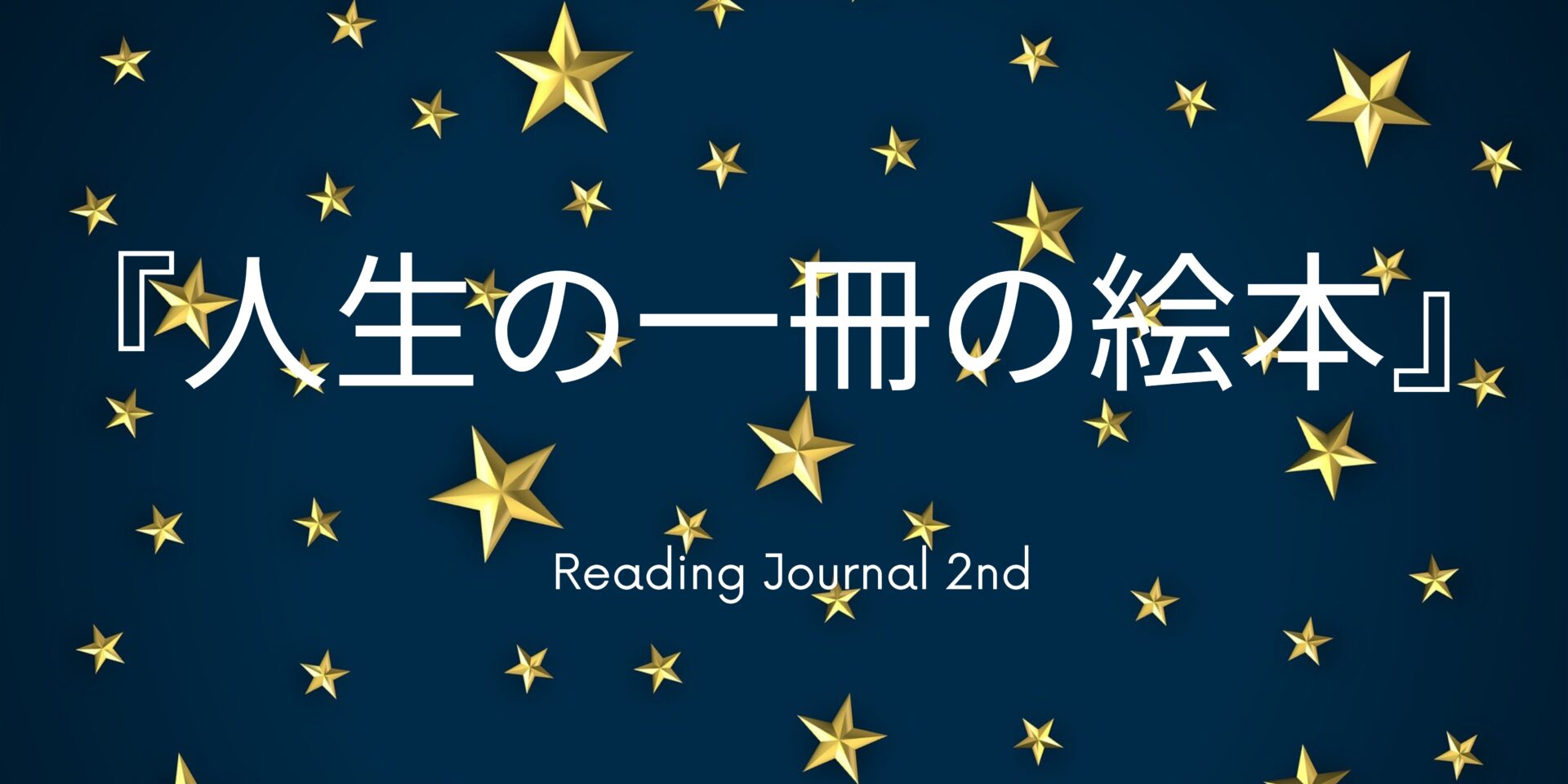


コメント