『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著、創元社、2000年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序 人はなぜ聞き上手になりたいのでしょうか
『聞く技術 聞いてもらう技術』を読み終えた。『聞く技術 聞いてもらう技術』では、対立した状態があって「聞く」が難しくなった場合に、どのように「聞く」を再始動するかという問題から始まり、難しい状況で「聞く」ためには、自分自身も「聞いてもらう」必要があるということであった。メンタルヘルスの根本は「聞く」に支えられていること、まともな社会になるためには、「聞く」と「聞いてもらう」うまく循環する必要があることなどが語られていた。っで、次は何を読もうかと思ったとき、『聞く技術 聞いてもらう技術』でも、紹介された東山紘久の『プロカウンセラーの聞く技術』にしてみようと思った。それでは、読み始めよう。
今日のところは「序 人はなぜ聞き上手になりたいのでしょうか」である。
臨床心理士である著者は「聞く」のが仕事であるから、聞き上手になりたいと思っている。では、なぜ一般の人が聞き上手になりたいのか?
一般には、「話す」ことよりも「聞く」ことの大切さが強調されていて、「聞き」ことの方が「話す」ことよりも価値があるとされる。
それは、情報の「発信者」(話す)と「受信者」(聞く)の行動と考えるとわかりやすい。発信者は、相手の反応が返ってこないと相手が情報をどう思ったかわからない。反対に受信者は、情報を受取も放棄もできる。その意味で発信者が情報をコントロールしているようで、本当は受信者がコントロールしている。
われわれは、真実の人間関係、嘘のない人間関係、信頼できる人間関係をもちたいとつねづね思っています。そのためには、相手の話を聞くことが必要になります。「聞く」ということは、ただ漫然に耳に入れることではありません。聞くことは理解する事なのです。(抜粋)
「話す」ことは、比較的簡単に出来るが、「聞く」ことは、苦行になることさえある。しかし相手の理解は聞くことしでしか生まれない。そのため、「聞き上手」になることは大切である。
関連図書:東畑開人 (著)『聞く技術 聞いてもらう技術』、筑摩書房(ちくま新書)、2022年
目次
序 人はなぜ聞き上手になりたいのでしょうか [第1回]
1 聞き上手は話さない [第2回前半]
2 真剣に聞けるのは、一時間以内 [第2回後半]
3 相づちを打つ [第3回前半]
4 相づちの種類は豊かに [第3回後半]
5 相づちはタイミング [第4回前半]
6 避雷針になる [第4回後半]
7 昔の主婦は聞き上手 [第5回前半]
8 自分のことは話さない [第5回後半]
9 他人のことはできない [第6回前半]
10 聞かれたことしか話さない [第6回後半]
11 質問には二種類ある [第7回前半]
12 情報以外の助言は無効 [第7回後半]
13 相手の話に興味をもつ [第8回前半]
14 教えるより教えてもらう態度で [第8回後半]
15 素直に聞くのが極意 [第9回前半]
16 聞き上手には上下関係なし [第9回後半]
17 寡黙と「いま・ここ」の感覚 [第10回前半]
18 嘘はつかない、飾らない(オープンということ) [第10回後半]
19 相手の話は相手のこと(わかるが勝ち) [第11回前半]
20 評論家にならない [第11回後半]
21 共感とは芝居上手 [第12回前半]
22 LISTENせよ、ASKするな [第12回後半]
23 話し手の波に乗る [第13回前半]
24 言い訳しない [第13回後半]
25 説明しない [第14回前半]
26 話には小道具がいる [第14回後半]
27 お茶室は最高の場 [第15回前半]
28 したくない話ほど前置きが長い [第15回後半]
29 聞きだそうとしない [第16回前半]
30 秘密の話には羽がある [第16回後半]
31 沈黙と間の効用 [第17回前半]
あとがき [第17回後半]
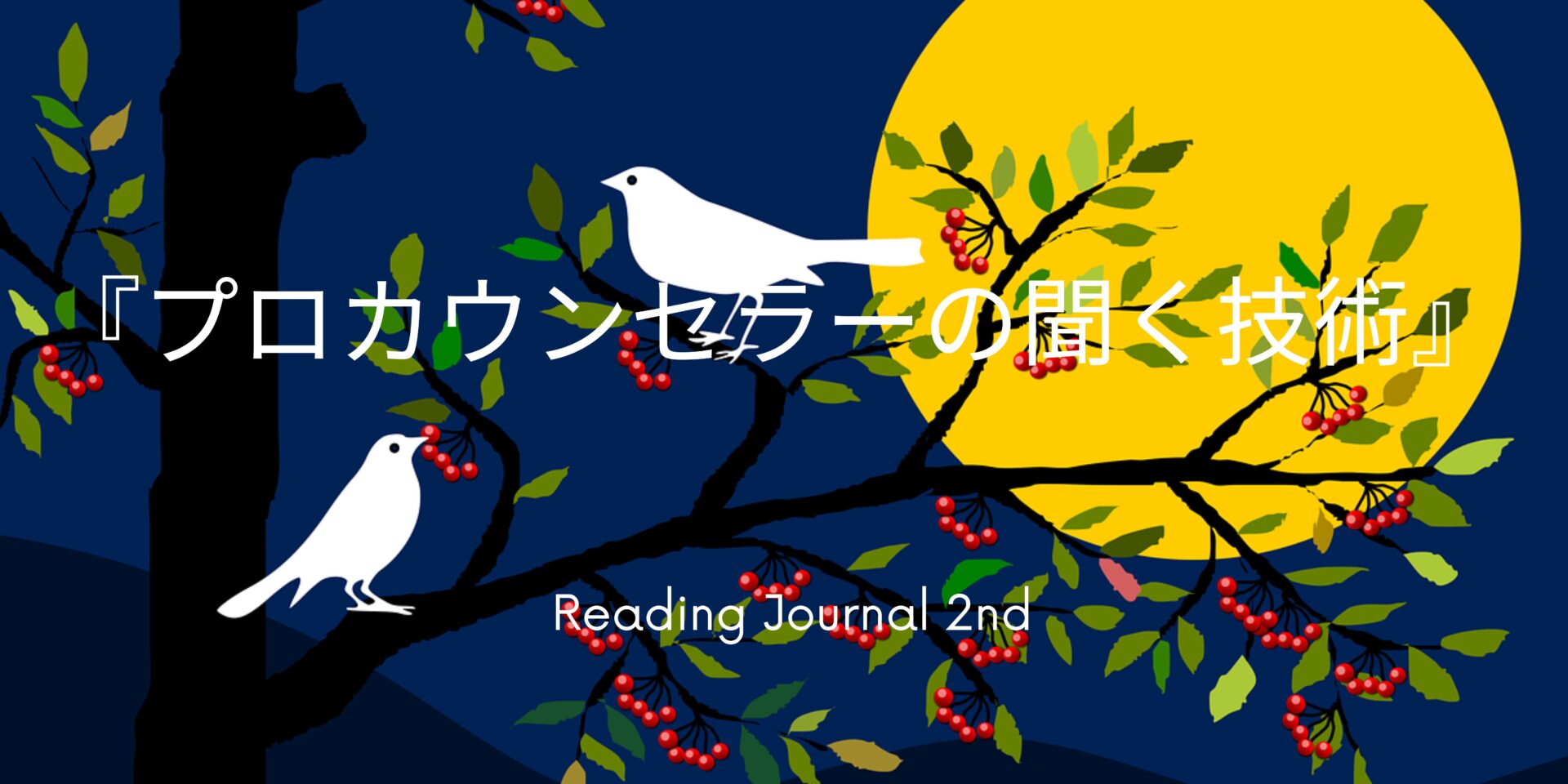


コメント