『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 王朝貴族に愛された猫たち(後半)
今日のところは、第二章の「王朝貴族に愛された猫たち」の後半、前半に続いて、猫がまだ貴重品であった平安時代の猫の話。そして最後に「ね・こらむ1 和歌のなかの猫」。
『更科日記』の猫
『更科日記』の作者は、菅原孝標の女である。彼女は姉と一緒に父親の赴任地の東国から京に帰ってきて暮らしていた。そして館に迷い込んできた猫を姉と一緒にひそかに飼うことにした。
隠して飼っていたが、この猫は身分の低い者の方には行かず、いつも私たちと一緒にいて、食べ物もあまりきたなげなものは顔をそむけて食べなかった。(抜粋)
作者は姉と共に猫を可愛がっていたが、姉が病気になり猫をかまう余裕がなくなってしまう。すると猫がやかましいほど鳴く。作者が困っていると姉が目を覚まし、
「どこなの、猫は? こっちに連れてきてちょうだい」私が不審に思って、「どうしたの?」と聞くと、姉は、「夢を見たのよ。夢の中で、この猫が私の傍らに来て『私は侍従の大納言の娘が猫に生まれ変わったものなのです。あなたがた姉妹とまんざらご縁がないわけではないので、このように可愛がっていただけることになったのですが、このごろ身分の低い者たちの間で過ごさねばならないので、とてもわびしいのです』と言い、たいそう鳴く様子は、しかれべき身分の人なのだと思っているうちに、目が覚めたら本当に猫が鳴いていたのよ。かわいそうだわ」と語った。それを聞いてとても哀れになり、一人でいるとき猫を撫でながら「あなたは侍従の大納言の姫君なのね。大納言さまに報せなきゃ」と言いかけると、猫は私の顔を見て長い声で鳴く。それを見ていると、なんとなく普通の猫のようではない気がして、かわいそうになった。(抜粋)
この話からは、猫が単なる動物ではなく、神秘的な力を宿した存在である、という意識が当時の人にあることがうかがわれる。
しかし、この猫と姉妹の生活は、長く続かない。この後、姉妹の家が火事に会い猫は焼け死んでしまった。
『たまきはる』の猫
猫と夢の話は、藤原定家の姉の健御前の日記『たまきはる』にも登場する。健御前が春華門院に出仕したときのこと。
八条女院さまがお亡くなりになって、その喪も明けないうち、久しく御前に参らなかったころの夢である。春華門院さまが幼くていらっしゃるのをお抱き申し上げていると、突然美しい唐猫におなりなさったので、「これはなんとしたこと」と驚いて夢から覚めたことがある。なんとなく胸騒ぎがして、思い至る限りあちことに祈禱させ、女房仲間にもお祈りのことを申し伝えたけれど、人々はそれほども思われず・・・・(抜粋)
猫とは、最高にかよわい被庇護者の象徴である、ということである。
猫と夢は切っても切り離せない関係であるようである。それは「こころ」(「たましい」)がある懐に抱くという親密さからきているのかもしれない。著者は、『ねこだましい』という著書がある河合隼雄氏に意見を聞きたいと言っている。
『今昔物語集』の猫
今までの猫は、王朝時代の雅な猫であった。しかし、平安時代も末期になると可愛い猫が恐怖の対象となる話が出てくる。
『今昔物語集』の巻二十八の第三十一話には、猫を怖がる主人公が出てくる。山城・大和・伊賀の三国の荘園領主である藤原清廉は、猫が怖く「猫恐の大夫」と呼ばれていた。この清廉が国府に収めるべき税米を滞納していることに業を為した国府は、秘密の作戦にでた。国府は清廉を館に呼びつける。そして清廉が部屋に入ると、大きな猫が部屋に入ってきた。
同じような猫が五匹うち続いた。猫が怖い清廉は、目からぼろぼろ涙を垂らし、国府に向かって手を摺り合わせて「止めてください」と頼む。しかし猫たちは、清廉の袖の匂いをかいだり、あっちの隅、こっちの隅を走り回るので、清廉は顔色を変えて耐えること限りない。(抜粋)
猫攻めにあった清廉は、その場で国府に税米の支払いを確約した。
『古今著聞集』の猫 1
猫は、しだいに怖いもの、不思議な力があるものとして認識されるようになる。十三世世紀の説話集『古今著聞集』にはそんな猫が出てくる。
ひとつは、ある高僧の飼っていた猫の「しろね」が、ねずみなどの獲物をとっても、食べずに話してやるという記事である(巻二十・六八七話)。
この「しろね」は、僧の飼い猫だから殺生戒を守るっている。しかし、ここで重要なのは、この猫が「しろね」という名前が与えられていることだと、著者は指摘する。
それまで、飼い猫についての記述はたくさんあった、名前がつけられているのは『枕草子』の「命婦のおとど」とこの「しろね」だけである。「命婦のおとど」は殿上しなければならないという必要上つけられた名前だったが、「しろね」はいわば普段の呼び名とでもいうべきものだ。(抜粋)
『古今著聞集』のもう一つの説話(巻二十・六八六話)は、猫が年をとれば不思議な力を得るというものである。
この猫は、十歳あまりになったとき、夜見ると背中に光が見え、飼い主の宰相中将の乳母が「お前が死ぬときは、私に姿をみせないでおくれ」という言葉の通り、十七歳になった年に行方知れずになった。
著者は、猫の背中に光が見えるのは、猫も十年生きると不思議な力がを得るに至ることを意味するのだろうと言っている。そして十七歳という高齢になると、猫も人間の言葉がわかるようになり、この猫は乳母の言葉のとおりに死に際を見せなかった。
貴族たちに愛された猫は、平安時代から中世にかけて、次第にその様相を変えていく。単に「可愛い美しい」だけの猫ではなくなってくるのである。中世は、いわば猫にとって暗黒時代でもあった。もちろん飼い猫の数はふえ、絵巻に見られるように庶民でも猫を飼うようになっていたのだから、猫と人間の距離は縮まったはずだ。だが、人間の日常生活に猫が入り込んでいくにつれて、猫と人間の関係はより複雑になっていったのではなかろうか。(抜粋)
関連図書:河合隼雄(著)『ねこだましい』、新潮社、2000年
ね・こらむ1 和歌のなかの猫
猫は昔から人間と共に暮らしていたが、和歌に読まれた猫は少ない。その理由は、和歌では鳥を除いてあまり動物を詠み込まないからである。
ここでは、和歌をテーマ別に分類した『類聚和歌集』のうち平安末期から鎌倉時代にかけて作られた『古今和歌六帖』と『夫木和歌抄』により猫の項目を探っている。
まず、『古今和歌六帖』には、猫の『雅称』=「手飼ひの虎」で詠まれた句とし、
浅茅生の小野の篠原いかなれば手飼ひの虎のふしどころみる(九五二番)
人心手飼ひの虎にあらねどもなれしもなどかうとくなるらん(一二九一八番)(抜粋)
がある。
二番目は恋の歌である。相手の心を猫にたとえ、どうしてうとくなったのか、と疑念を抱いている。
王朝時代でも、現代でも、猫の性格はまったく変わっていないのがおもしろい。(抜粋)
鎌倉時代になると「のらねこ」という語が和歌に詠まれる。『夫木和歌抄』には「のらねこ」の歌がある(手飼ひの虎もでてくる)。
余所にだによどこも知らぬのらねこのなく音は誰に契りおきけん(一三〇四三番)
まくず原下はひありくのらねこの夏毛かたきは妹が心か(一三〇四四番)(抜粋)
いづれも、寝床の定まらないのらねこを主題とし、恋心を隠している。
のらねこを読んだ歌はこれっきりしかないが、王朝時代には家猫とのらねこがはっきりと分かれていたことがわかる。興味深い例である。(抜粋)
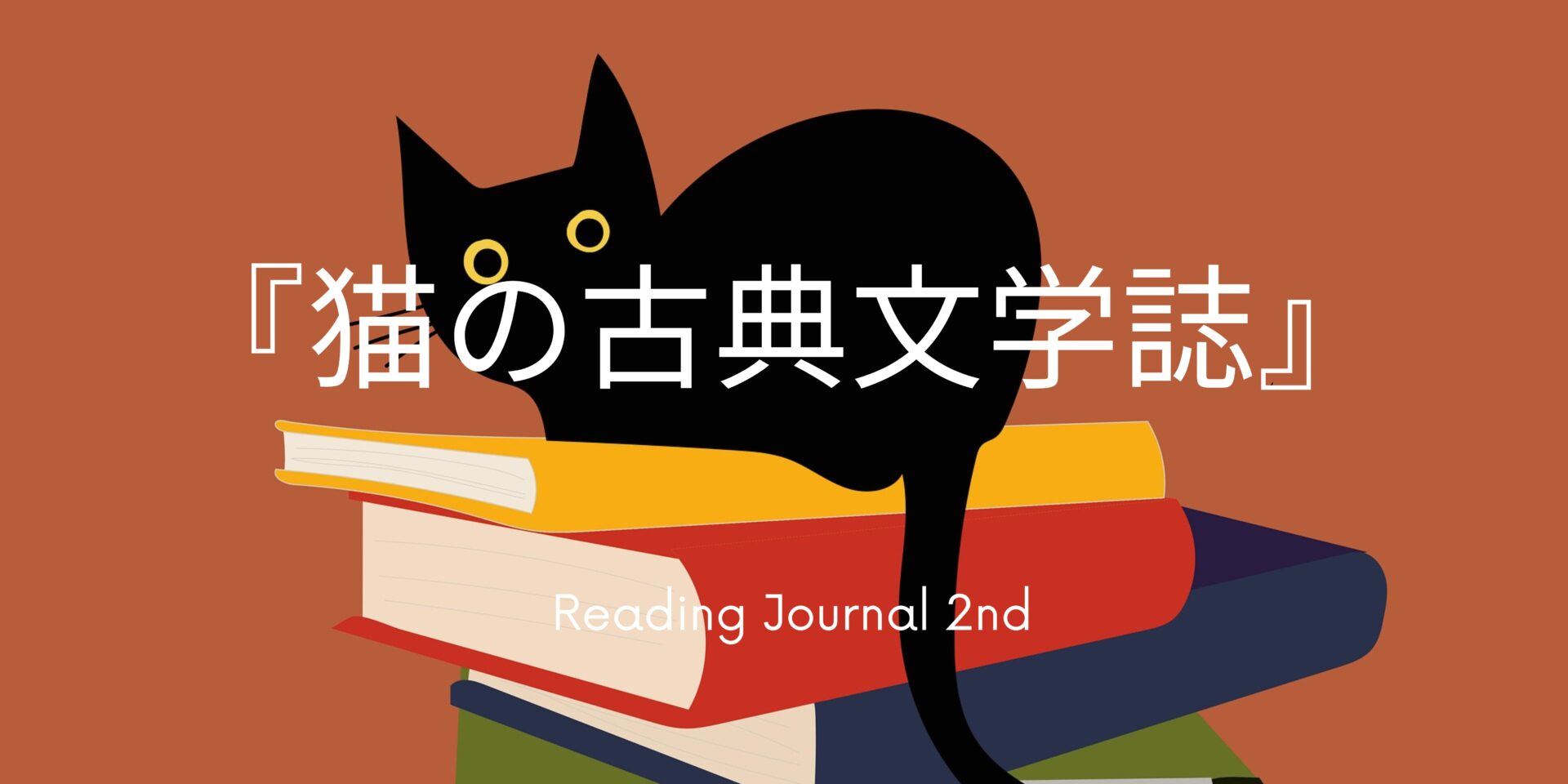


コメント