『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 王朝貴族に愛された猫たち(前半)
第一章では、猫が日本の文献にあらわれた最初、九世紀の『日本霊異記』では、「狸」と書いて「ネコ」と訓ませていたことに始まり、辞書に当たったり中国に遊んだりして「猫」の字のルーツを探り、その他もろもろの猫の話などが語られた。第二章は、猫がまだ貴重品であった平安時代の猫の話をまとめている。第二章は、長いので前半後半にわけ、後半は「ね・こらむ1」と合わせてまとめようと思う。それでは、読み始めよう。
『寛平御記』の猫
平安時代には、猫も次第に人々の生活に入り込んで、多くの王朝人が猫を飼うようになった。宇多天皇の日記『寛平御記』の寛平元年(八八九)、二月六日の条に、寵愛する黒猫のことが書き綴られている。
この猫は、大宰府の役人・源精が献上した「唐猫」(=高級輸入猫)である。天皇は、猫の変幻自在にしなやかなところに注目している。そして、ねずみを捕るのがうまいから飼うのではなく、愛玩の対象として飼われている。
河添房江の『光源氏が愛した王朝ブランド品』では、猫はブランド品として王侯・貴族の珍重するものであったと論じられている。ただし、
唐猫は単に猫好きな人が愛玩するために飼うわけではなかったらしいことに注意したい。(抜粋)
とし、猫を飼うのは「唐猫」を持つこと自体がステータスであるからで、現代のように猫と人との特別な愛情が基本にあるのでなない。「唐猫」ならばどの猫を飼っても同じ価値を持つと考えられていた。
『台記』の猫
平安時代には猫を愛玩動物として飼うことは珍しくなくなっていた。平安末期の藤原頼長の『台記』、永治二年(一一四二)八月六日の条に子どものころに飼っていた猫の思い出が記されている。
頼長は子どものころ飼っていた猫が病気になったとき、千手観音の像を描いて、
「猫の病気を早く治してください。そして、猫に十年の寿命を与えてください」(抜粋)
と祈った。すると猫の病気は治りその後ちょうど十年後に亡くなった。
この頼長の場合は、ステータスのために猫を飼うのではなく、現代人と同じように愛情を注いでいる。院政期には、猫と人間の関係が少し変化したのかもしれない。
王朝貴族は、猫派であり犬派はほとんどいなかった。それには理由があり、犬は野犬が多く、ペットとして飼われている犬はほとんどいなかった。また、綱につないで飼われているのは犬でなく、貴重品だった猫の方である。
『枕草子』の猫
『枕草子』にも猫に関する記述がある。まず理想の猫については、
猫は、背中だけ黒くて、腹の部分がたいそう白いのがよい。(三巻本、第四十九段)(抜粋)
と清少納言は言っている。そして猫をつなぐ綱にかんしては、
今ふうでしゃれているものといったら、簾の外の高欄を、美しい猫に赤い綱、白い札をつけてひき歩くこと。(第八十四段)(抜粋)
と注文を付ける。
しかし、清少納言は猫がさほど好きでなかったようである。『枕草子』の有名な第六段「うへにさむらふ御ねこは・・・」の段を読むとそれがわかる。
この段には、「命婦のおとど」と名と五位の位をもらった猫と「翁丸」という犬との間のいさかいについて書かれている。
猫が簾の外で寝ているときに、猫の乳母の「馬の命婦」がたわむれに、「翁丸」という犬をけしかける。びっくりした猫は、簾の中に逃げ込んだ。そこにいた一条天皇は、びっくりして、翁丸を犬島に流してしまえと命令する。翁丸は、散々に打たれて、遠く離れた犬島に棄てられてしまう。
そして、後日清少納言はひどく痩せた犬が内裏に戻ってきたという話を聞いた。みな、これをあの翁丸であるという。
犬は棄てられても元の家に戻ってくると言われているが、翁丸もそうだったのである。清少納言はこれを美談としてこの章段を締めくくっている。(抜粋)
この「命婦のおとど」という猫は、一条天皇にことのほか愛された猫であるようで、小野宮実資の日記『小右記』の長徳五年(九九九)に、命婦のおとどが生れたとき「産養い」をしたことが書かれている。命婦のおとどは人間の赤ちゃん並みに育てられていた。
『源氏物語』の猫
『枕草子』につづき『源氏物語』に登場する猫について書かれている。紫式部は、猫好きというよりは、物語の一要素として効果的に猫を描いている。
『源氏物語』で猫が登場するのは、光源氏の中年期の「若菜の巻」上・下においてである。ここで猫を飼っているのは、若くして源氏に降嫁してきた朱雀院の娘・女三宮である。
女三宮が猫を飼っているという設定にした理由は、一つには彼女がまだ少女といってもよい年頃に源氏の正妻になったことがあるだろう。一人前の大人の女ではなく、猫を可愛がるような子どもの心を残した女ということである。またもう一つの理由は、猫が高級な愛玩動物として貴族の間に広まっていたことにより、女三宮の高貴な身分を象徴しようとするものである。(抜粋)
この猫を通じて思いがけない出来事が起こる。源氏の屋敷・六条院で蹴鞠が行われた。そこに女三宮が源氏の正妻になる前から想いを寄せている柏木もいた。六条院の女たちは蹴鞠を御簾の中から見学していた。
その御簾のなかで、小さな唐猫が少し大きな猫に追いかけられ女房達が大騒ぎになる。そして、唐猫の綱に簾が絡まり巻き上がってしまう。
女三宮の姿が外にいる男たちの目に触れてしまったのである。柏木はそこで初めて女三宮を見るが、その上品で可愛い姿が目に焼きついてしまった。(抜粋)
この一瞬が後の女三宮と柏木の密通の端緒となる。そしてこの猫は、明らかに女三宮の「形代」の性格をになっている。
柏木はこの女三宮の猫を東宮を通じて手に入れてたいそうかわいがる。そして、柏木が物思いにふけっているとやってきて「ねうねう」と鳴く。
この「ねうねう」の鳴き声は、猫の鳴き声の表現として初めて登場したものである。そして、「ねうねう」には「(早く)寝よう寝よう」という裏の意味が隠されている。
そして、柏木はついに女三宮と結ばれる。これはけして源氏にしられてはならない秘密の関係である。そんなある日柏木は夢を見る。
ただちょっと、眠るというほどもなくまどろんだ夢に、この手に馴れた猫が、たいそう可愛げに鳴いて寄ってきたのを、女三宮さまにさしあげようと思っているうち、目が覚めた。どうしてこんな夢を見るのだろう、と柏木は思った。(抜粋)
この夢について、『源氏物語』の注釈書の一つの三条西実隆の『細流抄』には、「懐妊の事である。獣の夢を見るのは、妊娠したことを意味する」と注釈がある。その夢の通りに女三宮は懐妊する。源氏は二人の仲に気づき、源氏に激しく責めさいなまれた柏木は、病に倒れなくなってしまう。
この一連のエピソードに見える猫は、可愛らしいが「魔性」をも秘めた猫であることが知れるだろう。猫によって結ばれた二人は、猫によって生死を分かつことになるのだ。この猫は二人にとって運命の猫であったのかもしれない。清少納言が『枕草子』の章段で「猫の耳の中って、うろんだわ」と言い放つような単純さは、紫式部にはないのだ。彼女は、猫という存在を用いて、柏木の悲劇をいっそうドラマティックに仕立てているのである。(抜粋)
関連図書:河添房江(著)『光源氏が愛した王朝ブランド品』、角川書店(角川選書)、2008年
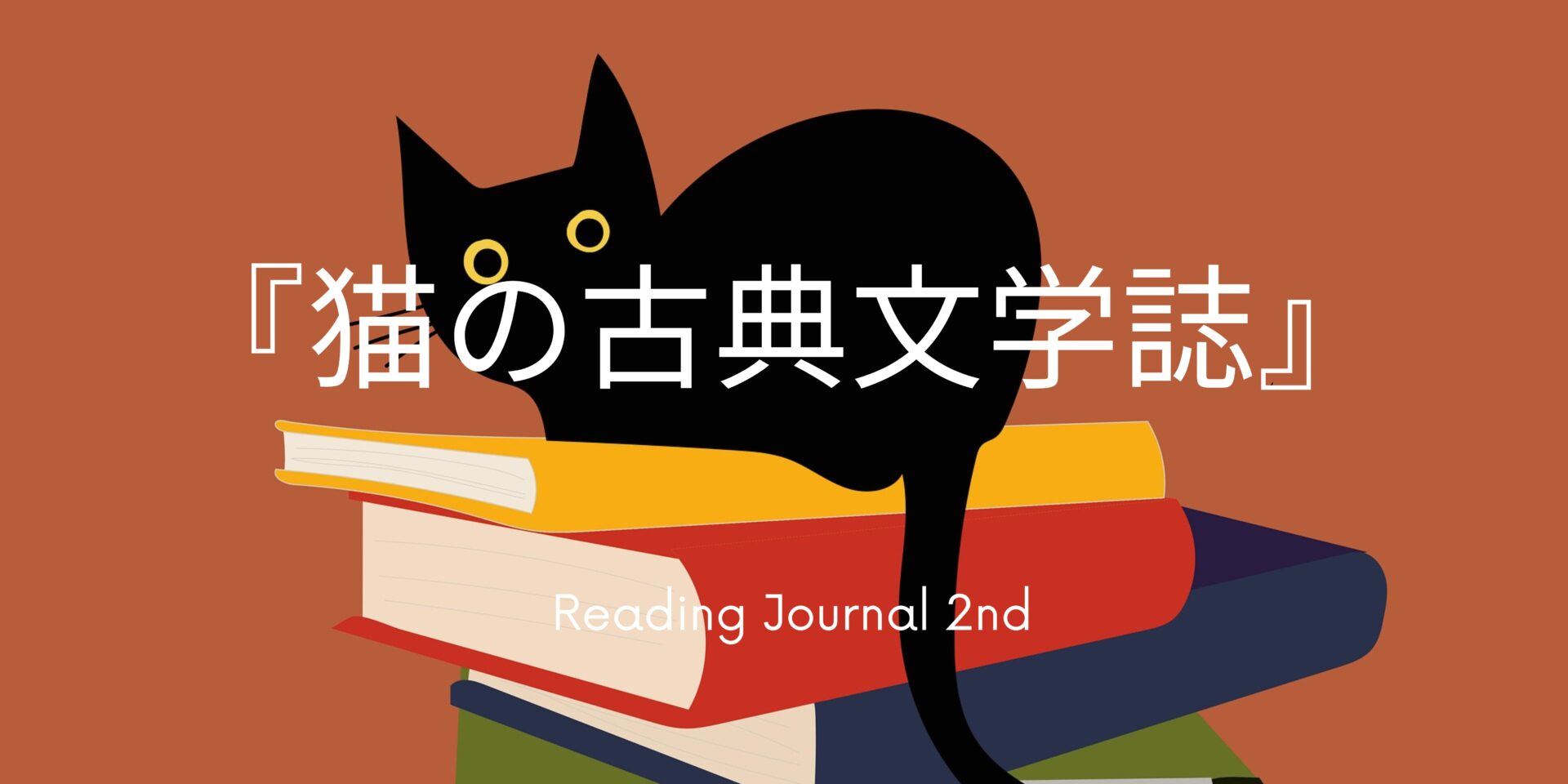


コメント