『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
ずっこけ、でも明日があるさ
冒頭で柳田は、ナイーブという語の意味について解説をする。
ナイーブという語は、日本では「生まれたままのように純粋な」とか「子供のように素直」なという意味であるが、欧米では、「世間知らず」とか「無知な」とか否定的な意味で使われている。しかし、欧米でのナイーブの否定的な意味も、本来は、日本での用法のように「生まれたままのように純粋な」という意味であり、日本ではその用法を素直に守っている。
柳田は、ナイーブの語の意味についてこだわるのは、絵本のにとってとても大事だと思うからだとして、次のように言っている。
絵本の多くは、主役が子どもだったり動物だったりする。そして、主役のキャラクターの点でも、物語の展開のうえでもナイーブな視点がベースになっている。生きるうえで大事なことは、すべて絵本から学べると、私はしばしば語ってきたが、生きるうえで大事なことは、穢れた世の中なのだから、ずる賢くなれなどということではない。純真さや素朴さを失わないで、信頼できる人間関係を築いたり、信念のある人生の歩み方を貫いたりするといったことを学ぶという意味だ。(抜粋)
この章で、柳田は「純粋さ」という意味のナイーブさをストレートに出した絵本を3点取り上げている。
『あたしもびょうきになりたいな!』
『あたしもびょうきになりたいな!』では、ねこの家族が登場する。弟のねこが病気になり、みんなに大切にされるのを見て、お姉ちゃんねこが自分も病気になりたいと思う。やがて弟が治り自分が病気になる。すると元気に学校に行く弟を、うらやむ。
この絵本は、こうした子どもたちのナイーブさのゆえの「こころの微妙な揺れ動き」を、やさしく見守る雰囲気で淡々と描いていく。(抜粋)
『あなたって ほんとうに しあわせね!』
あかちゃんが生まれて「おねえちゃん」になった「わたし」は、みんなに「あなたって ほんとうに しあわせね!」といわれるが、お母さんにもっと一緒にいて欲しいかったおねえちゃんは、自分ではそう思えない。
しかし、お母さんの大変さを知り、赤ちゃんをあやしてあげたり、絵本を見せたり、踊ってあげたりするうちに、赤ちゃんと一緒にいることが楽しくなってくる。
子どもでも自分の役割あるいは出番に気づくと、ひがみや疎外感を乗り越えられることを暗に語っている。子どものそういう気づきの力もまた、ナイーブさの力なのだと言えるだろう。(抜粋)
『こんな日だって あるさ』
小学生の男の子の主人公・ロナルドは、ある日、学校で失敗ばかり、あれやこれやへまをして先生に怒られてばかりだった。しかし先生は下校時に手紙を渡す。
<きょうは、たいへんな いちにちだったわね。おきのどくさま。あしたは、きっと、いいひになるよ。だって、わたしのたんじょうび ですもの。おたがい すてきなひに しましょうね>
失敗を責めるだけでなく、明日をよりよくするように励ます。子どものナイーブな感性を呼び覚ます先生は、すばらしい。子どもは失敗してあたりまえ、可能性を信じて励ます。子どものこころの発達をうながす鉄則だろう。(抜粋)
関連図書:
フランツ=ブランデンベルク(作)、アリキ=ブランデンベルク(画)、福本友美子(訳)、『あたしもびょうきになりたいな!』、偕成社、1983年
キャスリーン・アーンホールト(作)、星川菜津代(訳)『あなたって ほんとうに しあわせね!』、童話館出版、1994年
パトリシア・ライリイ・ギフ(作)、スザンナ・ナティ(絵)、秋野翔一郎(訳)『こんな日だって あるさ』、童話館出版、2006年
ファンタジーはグリーフワークの神髄
子どもは、お母さんやお父さんに負けないくらいおばあちゃんやおじいちゃんが大好きである。そのため、おばあちゃんやおじいちゃんが亡くなると、子どもは大きなショックを受ける。そのような子どものグルーフケアやグリーフワークをテーマとした絵本が最近多くなっている。
子どもの喪失感や悲しみを癒す道筋は、大人と違う。子どもの感性がナイーブで、イマジネーションに富むため、ファンタジーの世界にすぐに溶け込み現実の世界と一体化してしまう。
この章で柳田は、そのような子どもならではの感性を生かした絵本を二冊紹介している。
『おじいちゃんの トラのいる もりへ』
物語を創作したのは、書家の乾千恵さんである。柳田は、乾の書と谷川俊太郎のことば、写真家の・川島敏生で構成される絵本『月人石』もとても良い絵本であると勧めている。
主人公の「サカ」は、おじいちゃんに釣りの仕方や竹かごの作り方、太鼓の叩き方などの手ほどきを受け、いつも一緒にいた。ところが、ある日おじいちゃんは元気が無くなり、ニ、三日寝込んだらそのまま亡くなってしまった。サカは、さびしくて太鼓に布をかけて隠してしまう。
ある日、夢の中で一頭のトラが現れた。トラは、<おじいちゃんに あいたいか?>ときく、サカが会いたいと答えると、トラはサカを背中に乗せて森のなかへ。
たくさんのトラがいるところに着くと、群れのなかから一頭のトラが、あの<ドン タッタ、ドン タッタ、ドン>の音とともに近づいてきて、<サカ、よく きた>と言い、いろんなことを話してくれる。(抜粋)
おじいちゃんの魂はトラに宿り、ご先祖さまや昔の仲間たちもみな、トラのなかにいる、と教えてくれた。
サカがわしのことを思ってくれれば、それはちゃんとわかる。さびしがることはなく、わしらのことを思ってくれればいいのだ---と。(抜粋)
サカは、ありがとうと言って、再びトラに乗って村に帰った。そしてサカは太鼓を引っ張り出してきて、祭りの日のために練習をはじめた。
『おじいちゃんの ゆめの しま』
幼い少年シドが、おじいちゃんの家に行くとおじいちゃんがいない。でもはしごを登って屋根裏部屋に入ると、おじいちゃんが世界中から集めた珍しい物であふれていた。そして、多い扉を開けて外に出ると、大きな汽船の上だった。船はおじいちゃんの操縦で熱帯の島に着き、楽しく過ごした。
やがて、おじいちゃんは島に残るがシドは帰らなければならなくなる。シドは悲しいけど船を操縦して帰路についた。
この絵本の場合は、大好きなおじいちゃんとの別れを、死別という気配は全く漂わせないで、島で暮らすことにしたおじいちゃんとの別れというかたちで語っている。(抜粋)
関連図書:
乾千恵(文)、あべ弘士(絵)『おじいちゃんの トラのいる もりへ』、福音館書店、2011年
ベンジー・デイヴィス(作)、小川仁央(訳)『おじいちゃんの ゆめの しま』、評論社、2016年
乾千恵(書)、谷川俊太郎(文)、川島敏生(写真)『月人石』、福音館書店、2005年
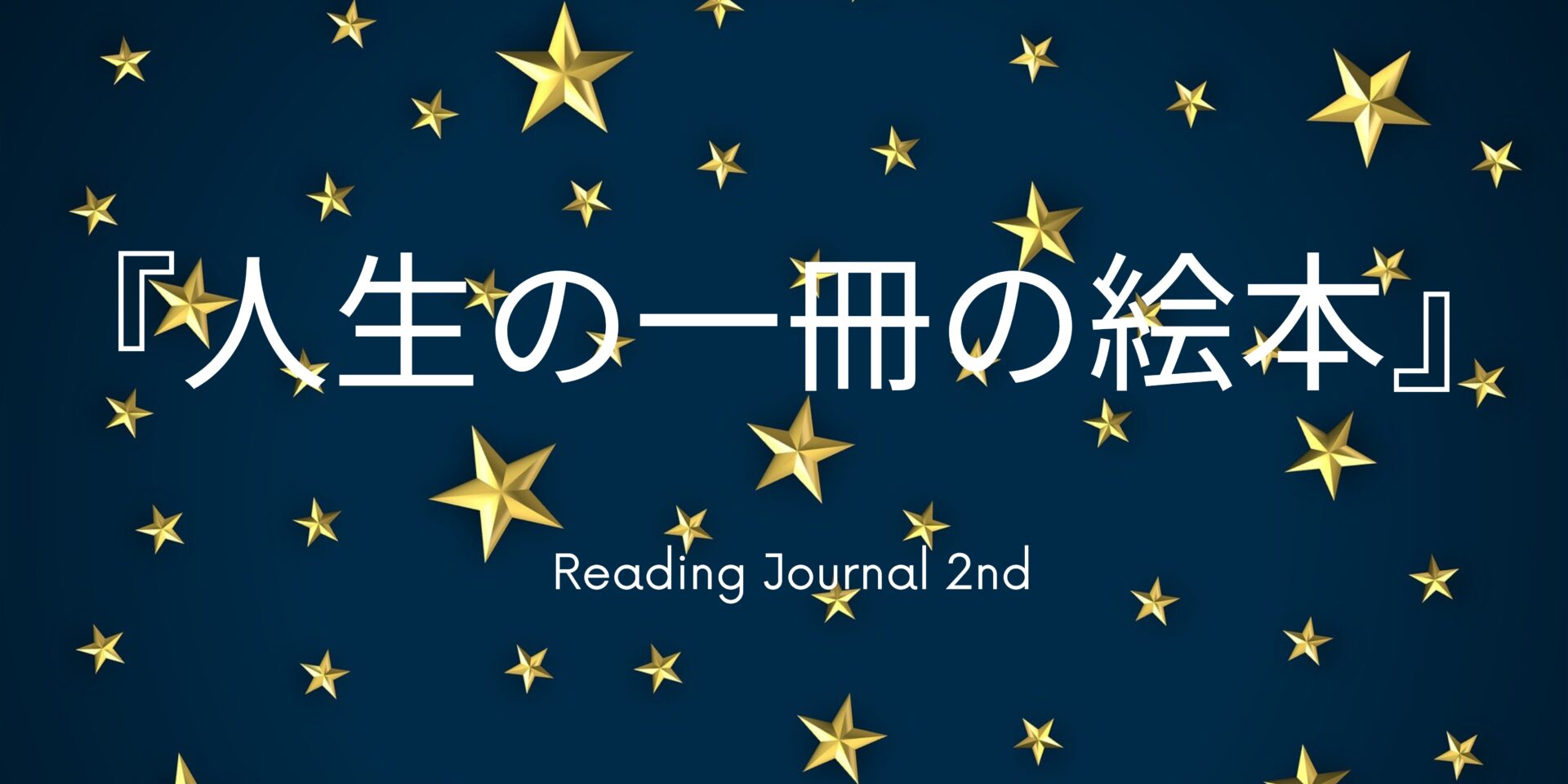


コメント