『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤 陽子著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
1章 日清戦争 日清戦争まで
前節を受けてここでは、なぜ日清戦争が起こったのか、それまでに何があったかについて解説する。
列強が中国の朝貢体制に便乗している間に中国が変わっていった。この変化の中心人物は、李鴻章(りこうしょう)である。李鴻章は中国の軍隊を近代的なものに改革しようとした。
李鴻章は新疆のイリ地方でヤクーブ・ベクがロシアの援助を受けて新国家を作った際には、軍隊を派遣してこれを倒した。従来の華夷秩序の枠内ならば、まずロシアと話をつけるのであるが、これを武力で応じたのである。
次に朝鮮で日本への接近をはかっていた閔氏に反対して起こった壬午事変(じんごじへん)(一八八二年)を清国が鎮圧する。その後に親日改革(独立党)は人々が起こした甲申事変(こうしんじへん)(一八八四年)も清国によって鎮圧された。これにより朝鮮政府に対する日本の影響力は決定的に低下することになる。
さらに、フランス安南(ベトナム)の港を独占的に使用するような動きを見せた時、清仏戦争を起こした。清国は武力に訴えてでも華夷秩序にあった安南(ベトナム)を守ろうとした。
ロシア、フランス、日本というような国々が深刻の華夷秩序=朝貢体制に挑戦するような紛争を起こしたとき、清国がきちんと一つひとつ対応をとることようになった。また、それだけの力をつけてきた。ですから、八〇年代半ばの時点においては、日本型の発展の方向性、中国型の発展の方向性、どちらもが、可能性が十分あった。中国側の場合は、中国自身が華夷秩序を近代国家的に適応できるように少しずつ手直ししながらだんだんと力をつけていったわけですが。(抜粋)
次に著者は、このように中国が変化しつつあるときの日本の状況を福沢諭吉と山形有朋の言葉から当時の日本人がどのように取られていたかを解説する。
まず、福沢諭吉は一八八五年に有名な『脱亜論』を書いた。朝鮮の独立党の人に期待していた福沢がなぜこの本を書かなければならなかったのかについて、著者は坂野潤治の説に沿って解説する(坂野潤治『体系日本の歴史13 近代日本出発』小学館)。『脱亜論』は、甲申事変で朝鮮への日本の影響力が決定的に下がったあとに書かれた、坂野は、
欧米列強によるアジア分割が迫っているから、日本は泣く泣く連帯をあきらめて朝鮮や中国を捨てる、というような文意ではなく、朝鮮に日本が進出するには内部から改革する方法ではなく、中国を討ってから朝鮮に進出するという武力路線でいきますね、と、このように理解するべきだというのです。(抜粋)
次に山形有朋とローレンツ・フォン・シュタインの話に移る。
山形は、一八八八からのヨーロッパ派遣で、ウィーン大学のシュタインと面会した。このシュタインは、伊藤博文に憲法における権力分立の基本や国家による社会改革を教えた人である。彼は、伊藤に憲法を教えたように、山形には主権線・利益線という考え方を教えた。
山形がシュタインに、シベリア鉄道ができた時に日本に脅威になるかを問うた。これに対してシュタインは、シベリア鉄道自体は日本の脅威にならないことを、説明した。しかし、
シベリア鉄道は、ロシアが朝鮮を占領しようと思ったときに、決定的に重要な役割を果たすのだ。つまり、ロシアはこれによって、アジアに海軍を興すことができる。朝鮮に対する支配権ということと、海軍の根拠地を朝鮮半島の東側に置きうる、という点で、シベリア鉄道の着工は日本にとって大問題になる。(抜粋)
と説明する。
シュタインは、
「主権線」・・・主権の及ぶ国土の範囲
「利益線」・・・国家の存亡に関係するが機構の状態
という言葉を使って山形に「朝鮮を中立に置くことが日本の利益線となる」と教えた。
朝鮮を日本がただちに占領する必要はない、・・・中略・・・朝鮮を中立国とすることについて、イギリス・ロシア・ドイツ・フランスなど複数の国家から承認をとるようにすればよい、これがシュタインの教えでありました。(抜粋)
これにより、日本が中国のかわりに朝鮮の中立を保証する、担保するという考え方が生まれた。ここで担保するというのは、武力なりなんならかの実力で、ある状態を維持するという意味である。
関連書:坂野潤治(著)『体系日本の歴史13 近代日本出発』小学館(小学館ライブラリー)1993年

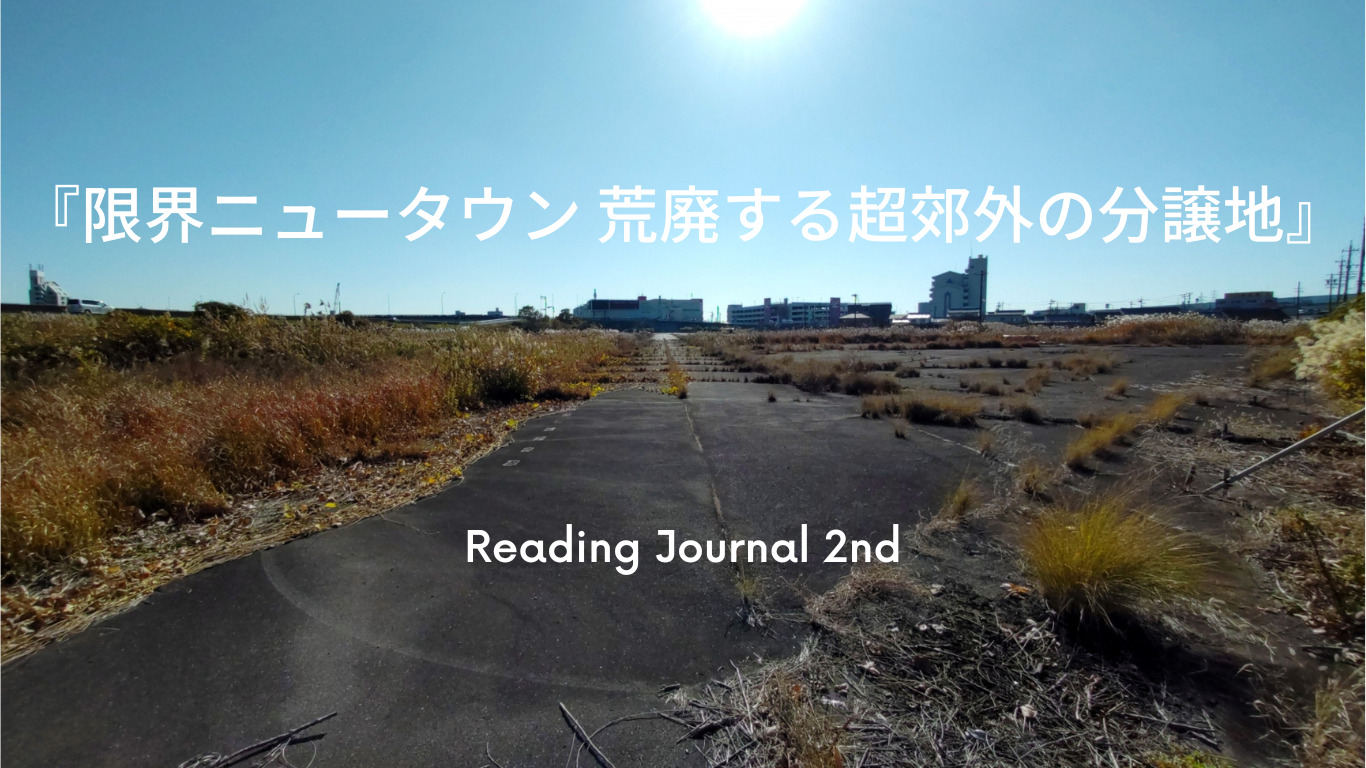
コメント