『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤 陽子著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 日本近現代史を考える なぜ二十年しか平和は続かなかったのか [後半]
ここで話は、カーの「歴史は科学だ」との主張に移る。
カーは、「歴史は科学だ」と主張して、科学でないとの主張に反論をしている。この反論では、「歴史は科学だ」との主張と「歴史は進歩する」という主張の両方を行っている。
カーは歴史は科学でないとする論者は、
- 科学は一般的なものを扱う、だから歴史は科学じゃない。
- 歴史は何の教訓も与えない。
の二つの点を指摘するとして、それに反論をしている。
一つ目の論点に対しては、
歴史が特殊なものを扱い、科学が一般的なものを扱うという分け方は不当だといいます。歴史家が本当に関心を持つのは特殊なものでなく、特殊的なものの内部にある一般的なものだ。(抜粋)
と反論し、二番目の論点に対しては、
歴史は教訓を与える。もしくは歴史上の登場人物の個性や、ある特殊な事件は、その次に起こる事件に何らかの影響を与えていると。(抜粋)
と反論している。
この、歴史上の一つの事件が、他の事件に強く影響力を及ぼしたケースとして、カーは、ロシア革命時にレーニンの後継者がトロツキーではなく、スターリンが選ばれたことを例として挙げている。
ロシア革命をけん引したボリシェビキと言われる人たちは、フランス革命が、ナポレオンという軍事的なカリスマの登場によって変質した結果、ヨーロッパが長い間、戦争状態になったと考えた。
そして、レーニンの後継者として、軍事的にカリスマ性を持っているトロツキーではなく、国内の支配をしっかりやりそうなスターリンを選んだ。
ロシア革命を担った人たちが、フランス革命の帰結、ナポレオンの登場ということを知ったうえでスターリンを選んだというのは、かなり大きな連鎖であり、教訓を活かした結果の選択です。(抜粋)
しかし、その教訓が必ずしも正しい選択出ない事もあると著者はいう。
ここが大切なところですが、これが人類のための教訓、あるいは正しい選択であるとは限らない。スターリンは一九三〇年代後半から、赤軍の関係者や農業の指導者など、集団化に反対する人々を粛清したことで悪名高い人ですね。犠牲者な何百万ともいわれる。(抜粋)
以後、同様な例として、「西郷隆盛と統帥権の独立」の関係について議論している。
先に、レーニンの後継者がスターリンにされたことで人類の歴史が結果的にこうむってしまった災厄をはなしましたが、この西郷の一件と統帥権独立の関係も、人類の歴史が結果的にこうむってしまった災厄の一つといえるかもしれませんね。日中戦争、太平洋戦争のそれぞれの局面で、外交・政治と軍事が緊密な連携をとれなかったことで、戦争はとどまることを知らず、自国民にも他国民にも多大な惨禍を与えることになったからです。(抜粋)
関連書:
E.H.カー(著)『危機の二十年』岩波書店(岩波文庫)2011年
E.H.カー(著)『歴史とはなにか』岩波書店(岩波新書)1962年
E.H.カー(著)『歴史とはなにか 新版』岩波書店2022年
ジョナサン・ハスラム(著)『誠実という悪徳 E・H・カー1892-1982』現代思想新社2007年

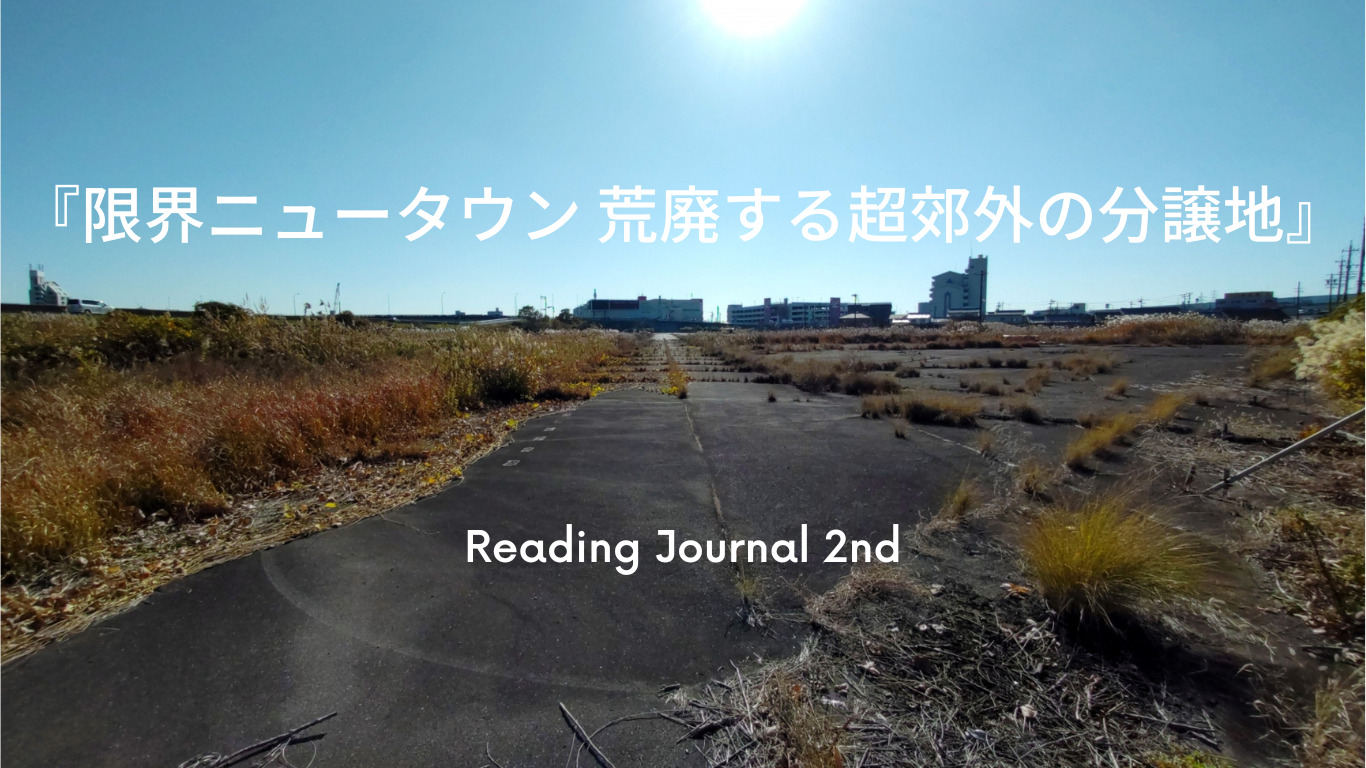
コメント