『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
品格について(その3)—- 三 文章の要素
今日のところは、「品格について」の“その3”である。ここでは“その2”で取り扱われた「一 饒舌を慎むこと」に続き、「二 言葉使いを粗略にせぬこと」「三 敬語や尊称を疎かにせぬこと」が、取り扱われる。それでは、読み始めよう。
二 言葉使いを粗略にせぬこと
礼儀をわきまえ「饒舌を慎むこと」と言っても、無暗に言葉を略すればよいというものではない。略すれば礼節に外れることもある。
いやしくも或る言葉を使う以上は、それを丁寧な、正式な形で使うべきであります。(抜粋)
若い人になかには、ぞんざいな発音をそのまま文字に移すことが珍しくない、として谷崎は次のような例を挙げている。
- してた (していた)
- でなこと (と云うようなこと)
- 詰まんない (詰まらない)
- あるもんか (あるものか)
- もんだ (ものだ)
- そいから (それから)
孰れも括弧の中に書いてある方が正しい。このような言葉は、口でしゃべってもあまり感心できないものである。
今日では東京の言葉が標準語とされておりますが、真に嗜みのある東京人は、日常の会話でも、割合正確に、明瞭に物を云います。(抜粋)
ここで谷崎は、写実を貴ぶ小説家が、青年男女の会話の実際を移す場合は、趣味の高下を論じてはいられないとしながらも、
小説家が会話を写す時といえども、その相当に「薄紙一と重を隔てる」と云う心づかいがあっても宜しいと思うのであります。(抜粋)
と言っている。
三 敬語や尊称を疎かにせぬこと
古典文においては、主格が略されることが多い。それが可能となるのは、敬語の動詞助動詞があるからである。他人の動作を敬う意味の動詞助動詞があり、自分の動作を卑下する意味の動詞助動詞がるため、主格がなくともその動作の主が分かる。そのためいろいろな重要ならざる言葉を省くことができ、文章の構成上も役立つ。
敬語の動詞助動詞を使いますと主格を略し得られますので、従って混乱を起こすことなしに、構造の複雑な長いセンテンスを綴ることが出来るようになります。(抜粋)
日本語の敬語の動詞助動詞は、単に儀礼を整えるだけでなく、主格がなくともそれが分かる効用もある。また、古典文の文章の妙味は、敬語の利用と密接に結びついている。
敬語の動詞助動詞は、美しい日本語を組み立てる要素の一つとなっております。(抜粋)
今日では、階級制度が撤廃されつつあり、煩瑣な敬語は実用にならないが、かといって、儀礼が廃れたわけではなく、将来においてもなかなか廃れそうにない。
このような敬語の動詞や助動詞は、われわれの国語が文章の構成上に持っている欠点を補っている利器である。その利器を捨てて顧みないために日本語特有の長所や強みを発揮できないのは、もったいない話である。
ここでは、敬語の動詞や助動詞のみを扱っているが、ほぼ同じことがあらゆる品詞の敬語にも言えることである。
現代でも、敬語はこのように重宝なものであるにも関わらず、あまり文章に用いられないのかと云うと、叙述に個人的な感情の混ざることを嫌うからである。文章は後世まで残るものであるので、たとえ尊敬している人のことについてでも、科学者のように冷静な態度で述べるべきであるという信念に基づいている。
しかし谷崎は、書く物の種類によっては、もう少し親愛や敬慕の情を交えてもよいのではないかとし、次のように提案している。
この際特に声を大きくして申し上げたいのは、せめて女子だけでもそう云う心がけで書いたらどうか、と云うことであります。男女平等と云うのは、女を男にしてしまう意味でない以上、また、日本文には作者の性を区別する方法が備わっている以上、女の書く物には女らしいやさしさが欲しいのでありまして、・・・後略・・・・(抜粋)
と提案している。そのためには、講義体は、敬語を多く使うのには不適当であるので、他の文体、兵語体、口上体、会話体の孰れかを選ぶのがよい。
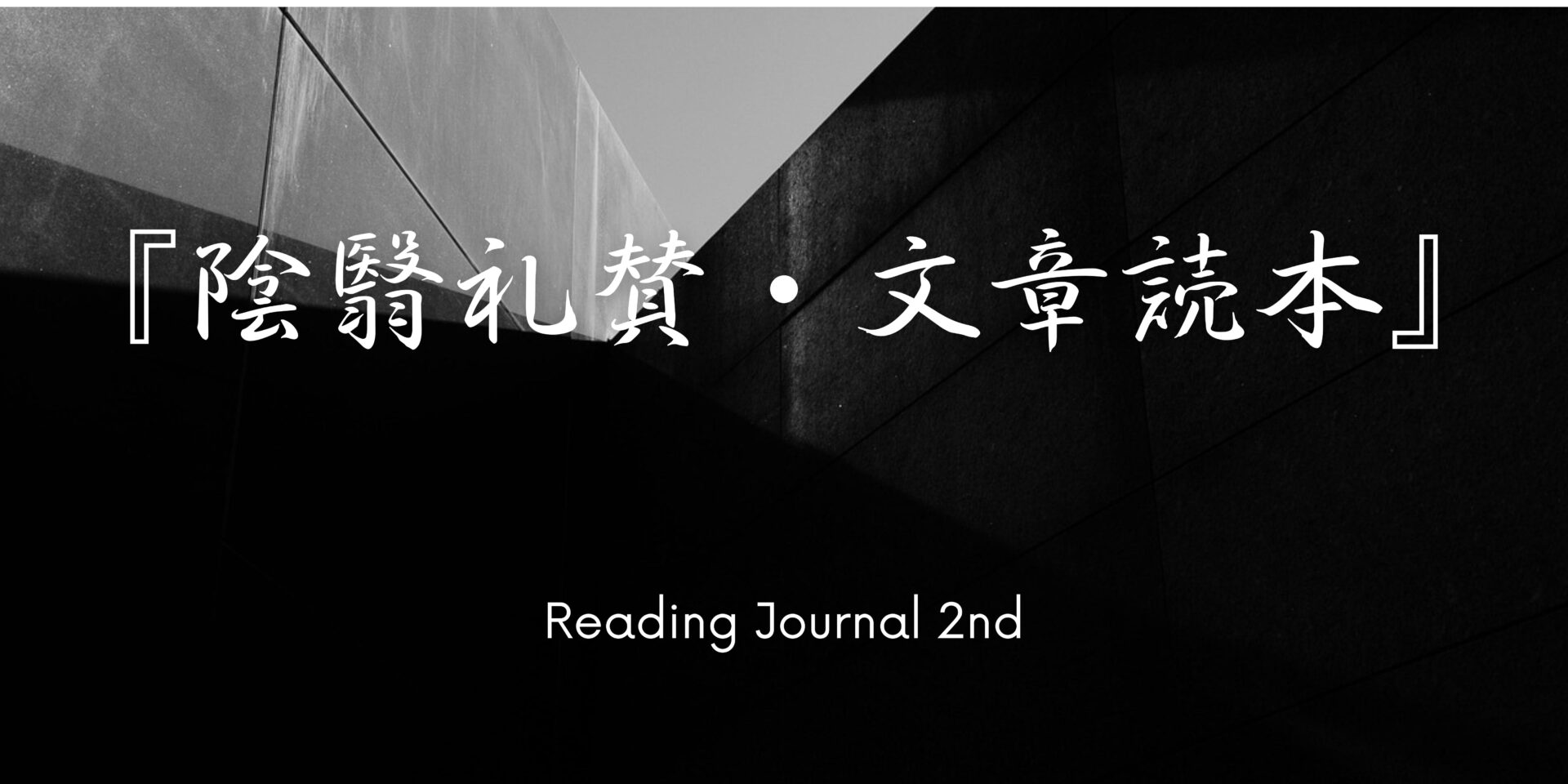


コメント