『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
文体について—- 三 文章の要素
これまで文章の要素として 用語(“その1”、“その2”)、調子(“その1”、“その2”)と学んできた。今日のところは、文章の要素の3つ目「文体について」である。
谷崎は、ここで口語体を様式で① 講義体、② 兵語体、③ 口上体、④ 会話体に分けて解説している。それでは読み始めよう。
文体と口語体の分類
文体とは、文章の形態、姿である。調子も文体も文章の分類であるが、文体は様式という方向から眺めている。
文体は、ふつう「文章体」「口語体」、或いは「和文体」「和漢混合体」のように分けられたが、現代ではほぼ「口語体」だけである。明治の中葉頃まで口語体に文章体を加味した「雅俗折衷体」というものがあったが、それも廃れてしまった。
そして谷崎はこの口語体を
- 講義体
- 兵語体
- 口上体
- 会話体
に分類し、以下でそれを説明する。
一 講義体
これは、実際の口語には最も遠く、従って文章体に最も近い文体であります。(抜粋)
谷崎はその例を挙げ、
- 彼は学校に通う。
- 彼は学校に通った。(過去)
- 彼は学校に通うであろう。(未来)
そらに、形容詞止めの文章として、
- 彼は賢い。
- 彼は賢かった.
の例をあげる。これが最も単純な形だが、実際には、センテンスの終わりを強める目的で、「のである」「のであった」「のだ」「だった」等を付け加える形にすることが多い。
このような文体は、個人を相手に話すときは使わないが、大勢の聴衆を前にしてしゃべる時、教師が教壇に立って講義する場合には、このような文体を使うのが普通である。
現在、一般に普及している口語文の大部分はこれであり、現代文と言ってもよい。明治大正期における諸文豪の散文文学は、ほとんどこの文体で綴られている。
二 兵語体
これは「である」「であった」の代わりに、「であります」「でありました」を加えるものであります。(抜粋)
これの最も単純な形は、
- 彼は学校へ通います。
- ——– 通いました。
- 彼は賢くあります。
である。また、「のである」「のであった」 → 「あります」「ありました」と変えて
- 通うのであります。
- 通うのでありました。
- 賢いのでありました。
と云う風にもする。
この文体は、軍隊において兵士が上官にものを云うときに用いられるもので、儀式場ってはいるが、礼儀深く、慇懃な心持が籠っている。講義体よりも親しみやすいため広くいきわたっている。
代表的なものとして、中山介山の『大菩薩峠』があり、さらにこの読本も兵語体で書かれている。
三 口上体
これは「あります」「ありました」の代わりに「ございます」「ございました」を使うももで、兵語体より一層丁寧な云い方になります。(抜粋)
この文体は、改まった席で口上を述べ挨拶を交わすときに用いられる。
- 口上体 = 講義体+「ございます」
- 通うのでございます
- 通ったのでございました
さらに馬鹿丁寧な人になると、
- (馬鹿丁寧)口上体 = 兵語体+「ございます」
- 通いますのでございます。
- 通いましたのでございました。
のようになる。
最も極端な場合には、
- (極端な)口上体 = 口上体 + 「ございます」
- ございますのでございます。
となってしまう。
口上体のみならず講義体も兵語体も、回りくどい言い方である。それは、「ある」「あった」で済むところを「あるのである」「あるのであった」「あったのであった」「あるのでありました」「ありましたのであります」と長ったらしくなるからである。
以上の三つの文体は、センテンスの終わりに「る」、「た」、「だ」、「す」等の音がくりかえされる場合が多いので、都合がよいこともありますけれども、文章体に比べますと、形が決まりきってしまって、変化に乏しい欠点があります。(抜粋)
四 会話体
上の三つの文型にはそのような欠点があるため、いっそ口でしゃべる通りに、自由に書いたらどうかと言うのが、会話体である。そしてこれこそ本当の口語体と言うべきものである。
通常の会話では、センテンスの終わりにもっと音の変化がある(たとえば、「・・・さ」「・・・よ」「・・・なぁ」など)。それは決して無意味な付け足しでは無く、語尾を強めたり弱めたり、皮肉や、愛嬌、風刺や、反語など微妙な心持を伝えている。
文章には、声音、言葉の間、眼つき、顔つき、身振、手真似などはないが、
唯今のこれらの音は、その文章にない要素を補って、多少書いた人の声音とか眼つきとか云うものを、想像させる役をしております。(抜粋)
さらにこれらの音を使って、作者の性を区別することさえできる。
この、男の話す言葉と女の話す言葉と違うと云うことは、ひとり日本の口語のみが有する長所でありまして、多分日本以外のどこの国語にも類例がないでありましょう。(抜粋)
そして「会話体」と云う別な様式があるのではなく、講義体、兵語体、口上体をいろいろとまぜて使い、センテンスが切れても、中途から始まっても構わない。名詞止め、副詞止めなどもできるため、最後に来る品詞が種々雑多である。
これらの「会話体」の特徴をもう一度数えると、
- イ 云い廻しが自由であること
- ロ センテンスの終わりの音に変化があること
- ハ 実際にその人の語勢を感じ、微妙な心持や表情を想像し得られること
- ニ 作者の性の区別がつくこと
などがある。しかし、会話体と言っても実際にしゃべる通りに書けば、無駄や不都合なことが多く、自ずから程度がある。
ここで谷崎は、講義体や兵語体の不自由さを考えると、この会話体の自由さを現代文に適用する道はないかと思っていると言っている。そして、その利点の一例として、作者の性について述べている。
読書は、全然声と云うものを想像しながら読むことはない。
然らば男女の孰れの声を想像しながら読むかと申しますと、女子の読者は知らず、われわれ男子が読みます時は、男の声(多くは自分自身の声)を想像するのでありまして、それを書いた人の性の如何を問わないであります。(抜粋)
しかし、すべての文章に作者の性が現れたとすれば、
定めしわれわれは、男の書いたものは男の声、女の書いたものは女の声を聴きながら読むのではありますまいか。それを考えましただけでも、会話体を応用すると云うことはなかなか意義が深いのであります。(抜粋)
関連図書:中山介山 (著)『大菩薩峠』(1~20)、筑摩書房 (ちくま文庫) 、1995年~1996年
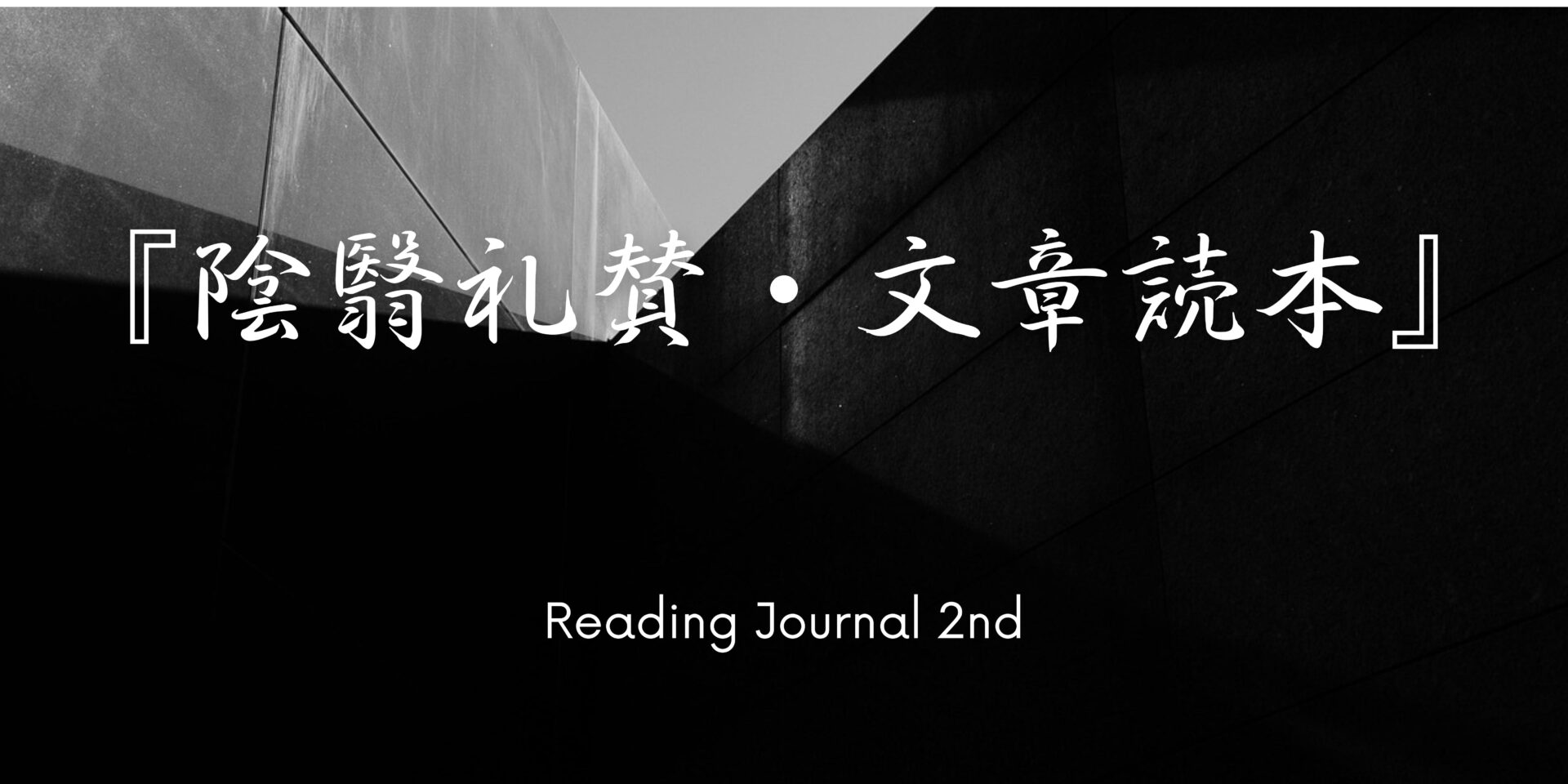


コメント