『続・日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 近代日本の戦死者と戦病死者(前半)
今日から、「序章 近代日本の戦死者と戦病死者」に入る。ここでは、本編に入る前に、近代日本が戦った対外戦争を、主として戦病死という視点から概観している。軍事衛生や軍事医学に焦点を合わせることにより、戦争の別の特質が浮かび上がる。
序章は、”前半“と”後半“に分け、前半で軍事衛生や軍事医学の発展から徐々に戦病死者の割合が減っていく日清戦争~満州事変までをまとめ、後半で軍事衛生が対抗し、戦病死者が激増する日中戦争、アジア・太平洋戦争期をまとめる。それでは読み始めよう。
はじめに近代日本が戦った対外戦争を、主として戦病死という視点から概観してみたい。軍事衛生や軍事医学の問題に焦点を合わせることによって、これまであまり認識されてこなかったそれぞれの戦争の別の特質が、浮かびあがってくるはずである。(抜粋)
日清戦争 — 疾病との戦い
日清戦争では、戦闘死(戦死)者は、一四〇一名、戦病死者は一万一七六三名で合計一万三一六四名の戦没者をだした。そして戦没者に占める戦病死者の割合は八九.三六%に達する。
一九世紀後半の戦争は、戦病死者が戦死者の数を大きく上回るのが普通であるが、日清戦争も赤痢・マラリア・コレラなどの疾病との闘いであった。
日清戦争では、伝染病や脚気以外に、凍傷による死者も多く、それは軍靴の補給が間に合わず、草鞋を履いた兵士が少なくなかったことによる。日清戦争は、装備の近代化という面でも過渡期であった。
さらに、輸送や輜重兵の編成が遅れたため、軍夫と呼ばれた臨時の人夫(民間人)が大きな役割を果たしたことも、日清戦争の特徴であり、軍夫の死亡者は七〇〇〇人と推定され、全体の戦没者は二万名であった。
日露戦争 — 戦病死の割合の低下
日露戦争では陸軍は一一〇万人の兵力を動員する。戦死者は六万三一名、戦病死者は二万一四二四名、戦没者は合計八万一四五名である。全戦没者に占める戦病死者の割合は、二六.三〇%まで低下した。(海軍の戦没者は二九〇〇名で、戦没軍人の圧倒的多数は陸軍)
日露戦争は「疫学的にいて画期的な戦争」であり、戦死者数が戦病死者数を上回った「史上最初の戦争だった(『疫病の時代』)。(抜粋)
日露戦争時には伝染病による死者が大きく減少し、凍傷も減少した。
また、日露戦争では軍夫に代わり輜重輸卒という専門の補給部隊が兵站を支え、軍医要請の教育体制など衛生部の近代化がはかられた。
疾病上未解決であった課題として最大のものは、脚気であった。脚気による死者は五八九六名に達する。脚気の原因はビタミンB1の不足であるが、原因が軍内で確定するのは一九二〇年代前半である。しかし、白米と麦との混食により、脚気患者が減少することは、軍内でも経験的に知られていた。それにもかかわらず、軍医関係者が白米食に固執したため、多数の死者をだすことになった。
凍傷の現象は軍靴の普及であるが、軍靴の質の劣化はアジア・太平洋戦争期まで兵士を悩ませ続けた。
この軍靴の劣化に関しては、『日本軍兵士』に詳しいよ。ココとかココを参照してね。(つくジー)
第一次世界大戦
日本は第一次世界大戦に日英同盟を口実に参戦しドイツと戦った。この日独戦争における陸軍の戦死者数は、四〇八名、戦病死者数は、一一五名であり合計で五二三名であった。全戦没者に占める戦病死者の割合は二一.九九%であり、日露戦争よりも低下している。
シベリア干渉戦争 — スペイン風邪の流行と法定伝染病死の減少
第一次世界大戦の末期に日本は米・英などの連合国との共同出兵という形でシベリアに出兵した。陸軍はこの戦争に一三万人の兵力を動員した。
陸軍の戦死者は、原暉之の推定で、一七三七名、戦病死者は一五五五名であり、合計三二九二名となる。全戦没者数に占める戦病死者の割合は、四七.二四%となる。
また、陸軍省の『西伯利出兵衛生史』によると、戦死者一五三九名、戦病死者一二四〇名となり、合計二七七九名である。全戦没者に占める戦病死者の割合は、やはり四四.六二%となる。
日露戦争時の戦病死者の割合をはるかに超えた数字だが、戦病死の実態をもう少し詳しく見てみる必要がある。(抜粋)
ここで重要なのが、「流行性感冒」であり、『西伯利出兵衛生史』では、三三〇名を数える。この「流行性感冒」とは、パンデミックとなった「スペイン風邪」のことである。つまり、シベリア干渉戦争で戦病死者数が多いのは、「流行性感冒」が数値を押し上げたからである。
他方、シベリア干渉戦争は、法定伝染病による死者が激減した。これは、日露戦争後に法定伝染病の予防接種が実施されるようになったことが大きく影響している。脚気についても大きく減少していて、それは、原因が確定していなかったものの、米麦混食の励行、パン食の採用、野菜や肉類の支給などを行ったことによる。
また、極寒地での戦争であったにもかかわらずシベリア干渉戦争での凍傷の患者数は意外に少ない。それは、防寒装備の改良や早期治療の成果であった。
満州事変 — 最低の戦病死率の戦争
満州事変では、一三万人の陸軍兵力が動員された。しかし戦死者数、戦病死者数についてははっきり分かっていない。
しかし満州事変での靖国神社への合祀者数は一万七一七四名であり、これには「準軍属」の合祀者も含んでいるため、陸軍・軍属の戦没者はもう少し少ない数字となる。また、陸軍省の『満州事変陸軍衛生史』に幾つかの統計資料が記載されていて、満州事変では、出動人員に対する戦病患者の発生率は、過去のどの戦争よりも低率となっている。戦死者一名に対する戦病死の比率は、日露戦争の〇.三九名に対して満州事変は〇.二一名となる。
ここで、靖国神社への合祀者数を戦没者とみなし、戦没者数を一万七〇〇〇名とすると、全戦没者数の中で戦病死者の比率は、一七.三五%となり、これが近代日本が戦った戦争で最も低い戦病死率である。
また、脚気についてもシベリア戦争時よりさらに低下した。これは脚気の原因がビタミンB1の不足であることが明らかになり、胚芽米やビタミン剤の支給などが行われたからである。
満州事変は、軍事衛生や軍事医学の面での改善や改良が、大きく進展していることを示した戦争だった。(抜粋)
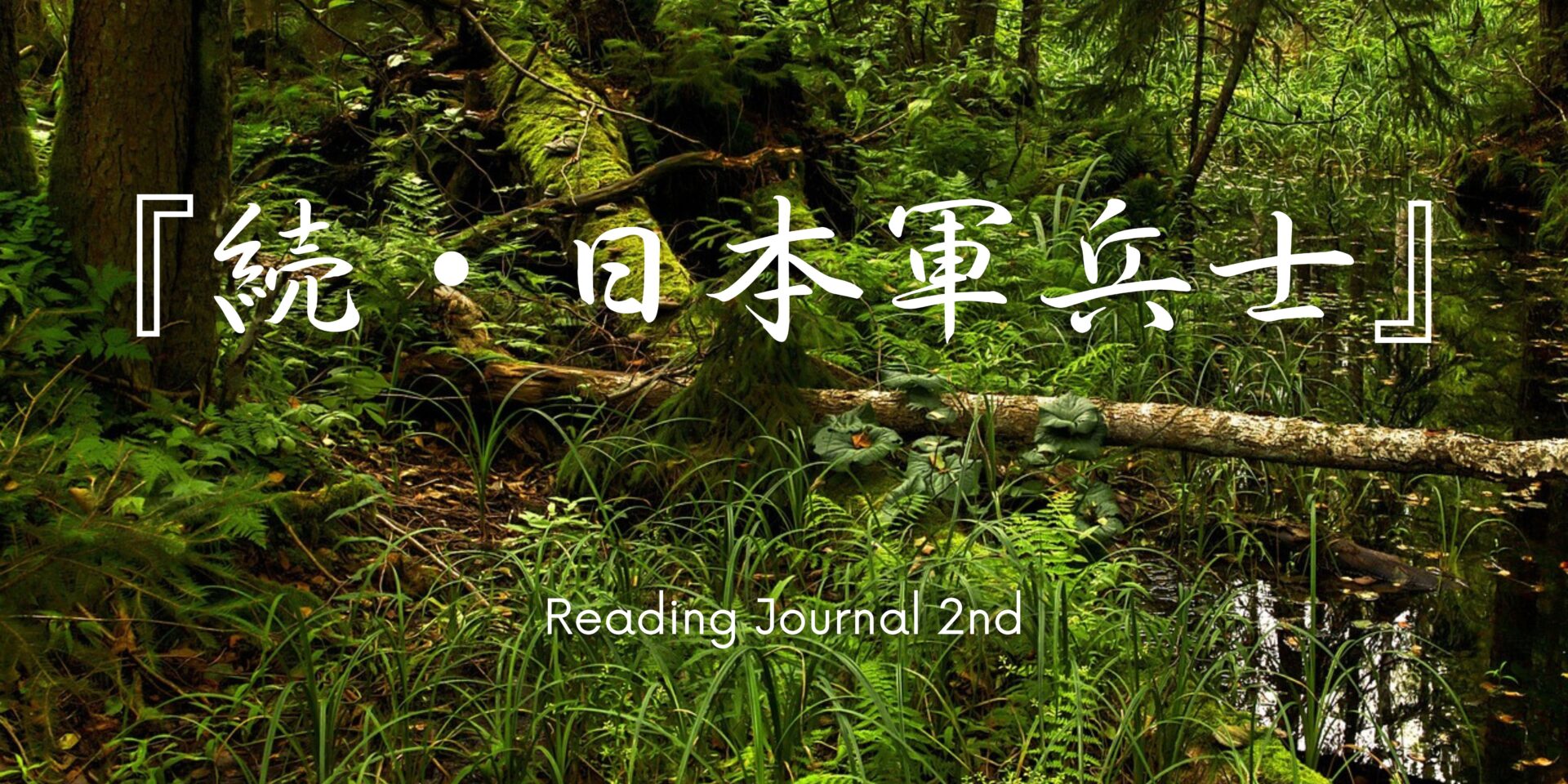


コメント