『続・日本軍兵士』 吉田 裕 著、中央公論新社(中公新書)、2025年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに
やっと『日本軍兵士』が読み終わった。そもそも『日本軍兵士』を読み始めた理由は、この『続・日本軍兵士」の書評を読んで、興味を持ったからでした。
今日のところ「はじめに」では、前著の『日本軍兵士』との本書との違いと狙い、さらに執筆の際に重要視した三つの視角についてである。それでは、読み始めよう。
『日本軍兵士』との違いと、本書の狙い
アジア・太平洋戦争期には、多くの兵士が戦闘による死ではなく、餓死や戦病死、海没死や特攻死などで亡くなった。著者は、前著、『日本軍兵士 — アジア・太平洋戦争の現実』において、このことを明らかにした、としている。
しかし、このような大量死の歴史的背景やどうして大量死が引き起こされたのかという問題に対しては、「陸海軍の軍事思想」「統帥権の独立」「日本の資本主義の後進性」などについて簡単に触れただけである。
そして、本書の狙いについて
そこで本書では、無残な大量死が発生した歴史的背景について、明治以降の帝国陸海軍の歴史に即しながら、できる限り具体的に明らかにしたいと思う。(抜粋)
と言っている。
重要視した三つの視角
そして、その際に次の三つの視点を重視した。
第一の視点:正面装備の重視、「間口」だけの日本
第一の視点は、「正面装備」の整備・充実を最優先し、兵站、情報、衛生・医療、給養を軽視したことである。そして著者は、それは大日本帝国そのものの危うさであると指摘し、夏目漱石の『それから』の文章を引いている。
日本は西洋から借金でもしなければ、とうてい立ち行かない国だ。それでいて、一等国をもって任じている。そうして、むりにも一等国の仲間入りをしようとする。だから、あらゆる方面に向かって、奥行きをけずって、一等国だけの間口を張っちまった。(中略)牛と競争する蛙とおなじことで、もう君、腹が裂けるよ。(「それから」)(抜粋)
著者は、この間口だけの日本の状況について、実際の数値をもって解説している。それによるとアメリカのGNPは日本に比べて12倍あった。しかし、アメリカの軍事費は、日本の2倍程度となっている。さらに日本はアメリカに先んじて軍備の拡張を行っていた。そのため開戦時の日本はアメリカと同等の軍事力を保有していた。著者は、そのような説明をした後、次のように言っている。
国力が一二倍の国に対して、「腹が裂ける」ほどの軍事力を拡大していることがわかるだろう。そうした無理のある軍拡の結果、漱石の言い方を借りるならば、帝国陸海軍自体も、間口ばかり立派で、奥行きの無い軍隊となった。そうのことが兵士にとって何を意味していたか、という問題を本書では具体的に考えてみたい。(抜粋)
第二の視点:軍隊の階層と負担の不平等
第二の視点は、将校の温存・優遇と下士官、兵士に負担を強いる特質である。
まず軍隊の階級的・権力的秩序は、指揮・命令系統の中核が将校であり、中間に戦場や兵営で兵士を掌握し、軍隊秩序に服従させ、戦闘を指揮する下士官である。そしてその下に、最底辺の兵士がいる。
ここで著者は、軍隊階層のピラミッドの頂点から底辺に行くほど負担が大きかったか。「犠牲の不平等」があったかを具体的に検討したいとしている。
さらに、戦前の日本は極端な学歴社会で、大学生は、ごく少数のエリートであった。この経済的にも恵まれた家庭に育った若者たちも、兵役を平等に担ったのかという問題も検討すると、言っている。
第三の視点:兵士の「生活」「衣食住」
第三の視点は兵士の「生活」「衣食住」の重視である。見ていくとしている。
たとえば、日本の軍艦の優越は、攻撃力、防衛力、機動力で測られるが、艦内の生活空位間の優越は論ぜられない。しかし、「衣食住」などの居住空間を充実させることは、乗員の戦闘意欲を高め、ひいては軍艦の戦闘力を強化することにつながる。
しかし、戦闘第一主義の日本には「生活」や「衣食住」への配慮が極めて乏しかった。
この問題に対して、著者は、深緑野分の発言を引いている。
深緑は、「戦争を調べていくと、結局、兵士や市民の生活を保てない国が最終的に負けるとわかってきました。戦争を語るとき、戦闘のことが中心で、生活という視点が抜けがちです」と語っている(『朝日新聞』二〇二三年八月一六日付)(抜粋)
本書では、この指摘も踏まえて「生活」や「衣食住」に焦点を合わせる。
関連図書:吉田 裕(著)『日本軍兵士』、中央公論新社(中公新書)、2017年
目次
はじめに [第1回]
序 章 近代日本の戦死者と戦病死者――日清戦争からアジア・太平洋戦争まで [第2回][第3回]
疾病との戦いだった日清戦争 戦病死者が激減した日露戦争 第一次世界大戦の戦病死者 シベリア干渉戦争の戦没者数 伝染病による死者の激減 軍事衛生の改善・改良と満州事変 退行する軍事衛生――日中戦争の長期化 アジア・太平洋戦争の開戦 陸海軍の戦没者数 日露戦争以前に戻った戦病死者の割合
第1章 明治から満州事変まで――兵士たちの「食」と体格
1 徴兵制の導入――忌避者と現役徴集率 [第4回]
徴兵令の布告 現役徴集率二〇%の実態 沖縄の現実、徴兵忌避者の減少 軍医の裁量権――高学歴者への配慮と同情
2 優良な体格と脚気問題――明治・大正期 [第5回]
明治の兵士――身長一六五センチ、体重六〇キロ 脚 気――総人員三割から四割の罹患 兵士たちを魅了した白米
3 「梅干主義」の克服、パン食の採用へ [第6回]
栄養学の発展――第一次世界大戦後の日本 陸軍の兵食改善 一九二〇年のパン食導入 冷凍食品の導入と大型給糧艦 洋食の普及と充実――満州事変期 壮丁と兵士の体格
4 給養改革の限界――低タンパク質、過剰炭水化物 [第7回]
シベリア干渉戦争の失敗 飯盒炊さん方式による給養 兵食における質の問題 陸軍でのパン食のその後 揺れる海軍のパン食――「皇軍兵食論」の登場
第2章 日中全面戦争下――拡大する兵力動員
1 疲労困憊の前線――長距離行軍と睡眠の欠乏 [第8回]
苦闘を強いられる日本軍 萎縮し「奮進」できない兵士たち 多発する戦争栄養失調症 「殆ど老衰病の如く」
2 増大する中年兵士、障害を持つ兵士 [第9回]
低水準の動員兵力 軍隊生活未経験者の召集 召集が原因の出生率低下 国民兵役までも 知的障害の兵士 吃音の兵士 野戦衛生長官部による批判 攻撃一辺倒の作戦思想
3 統制経済へ――体格の劣化、軍服の粗悪化 [第10回]
総力戦の本格化、国民生活の悪化 軍隊の給養――副食の品種減少、米麦食偏重 劣化する軍服――絨製から綿製へ 向上しない体格、弱兵の増加
4 日独伊三国同盟締結と対米じり貧 [第11回]
ドイツの大攻勢による政策転換 資源の米英依存による新たな困難 石油禁輸とジリ貧論――アジア・太平洋戦争の開戦へ 中国戦線にくぎ付けにされ続けた陸軍
第3章 アジア・太平洋戦争末期――飢える前線
1 根こそぎ動員へ 植民地兵、防衛召集、障害者 [第12回]
植民地から日本軍兵士へ――朝鮮・台湾から 防衛召集による大量召集 視覚障害者たちの動員開始 強制動員されるマッサージ師たち
2 伝染病と「詐病」の蔓延 [第13回]
戦争末期の戦没者急増 栄養失調の深刻化 マラリアの多発 「現場」での非現実的予防対策 精神病の「素因」重視 詐病の摘発 詐病の増大 戦力を大きく削ぐ皮膚感染症
3 離島守備隊の惨状 [第14回]
「自給自足の態勢」強化の指示 不十分なままの海軍の給養 兵員の体格劣化、栄養失調による死者 違法な軍法会議と抗争 食糧をめぐる陸海軍の対立
4 かけ声ばかりの本土決戦準備――日米の体格差 [第15回]
野草、貝類、昆虫…… 「こんな軍隊で勝てるのだろうか」 兵士たちによる盗み 体格・体力のさらなる低下 アメリカ軍の給養と体格
第4章 人間軽視――日本軍の構造的問題
1 機械化の立ち遅れ――軍馬と代用燃料車 [第16回]
「悲惨なともいうべき状態」――国産車の劣悪な性能 代用燃料車の現実 軍機械化の主張とその限界 断ち切れない「馬力」への依存
2 劣悪な装備と過重負担――体重40%超の装備と装具 [第17回]
過重負担の装備 戦闘の「現場」、兵士の限界点 一〇〇日間、二〇〇〇キロを超える行軍 中国人から掠奪した布製の靴、草履一六六名の凍死者 粗悪な雨外套
3 海軍先進性の幻想――造船技術と居住性軽視 [第18回]
造船技術は先進的だったか 居住性の軽視 一般の兵員に対する差別 「松型駆逐艦」の居住性 「世界に類のない非常対策」高カロリー食の失敗 特殊環境下の乗員の健康 アメリカ海軍の潜水艦との比較 ドイツ海軍Uボートの徹底検証
4 犠牲の不平等――兵士ほど死亡率が高いのか [第19回]
兵役負担の軽重 大学生の戦没率 召集をめぐる贈収賄 食糧の分配をめぐる不平等 戦死をめぐる不平等 メレヨン島とパラオ本島 長台関での階級間格差 正規将校の戦病死率
おわりに
日中全面戦争下、野放図な軍拡 宇垣一成の陸軍上層部批判 騎兵監・吉田悳の意見書 日本陸軍機械化の限界 追いつかなかった軍備の充実
コラム
①戦史の編纂――日清戦争からアジア・太平洋戦争まで
②戦場における「歯」の問題再び
③軍人たちの遺骨
④戦争の呼称を考える――揺れ続ける評価
あとがき
参考文献
近代日本の戦争 略年表
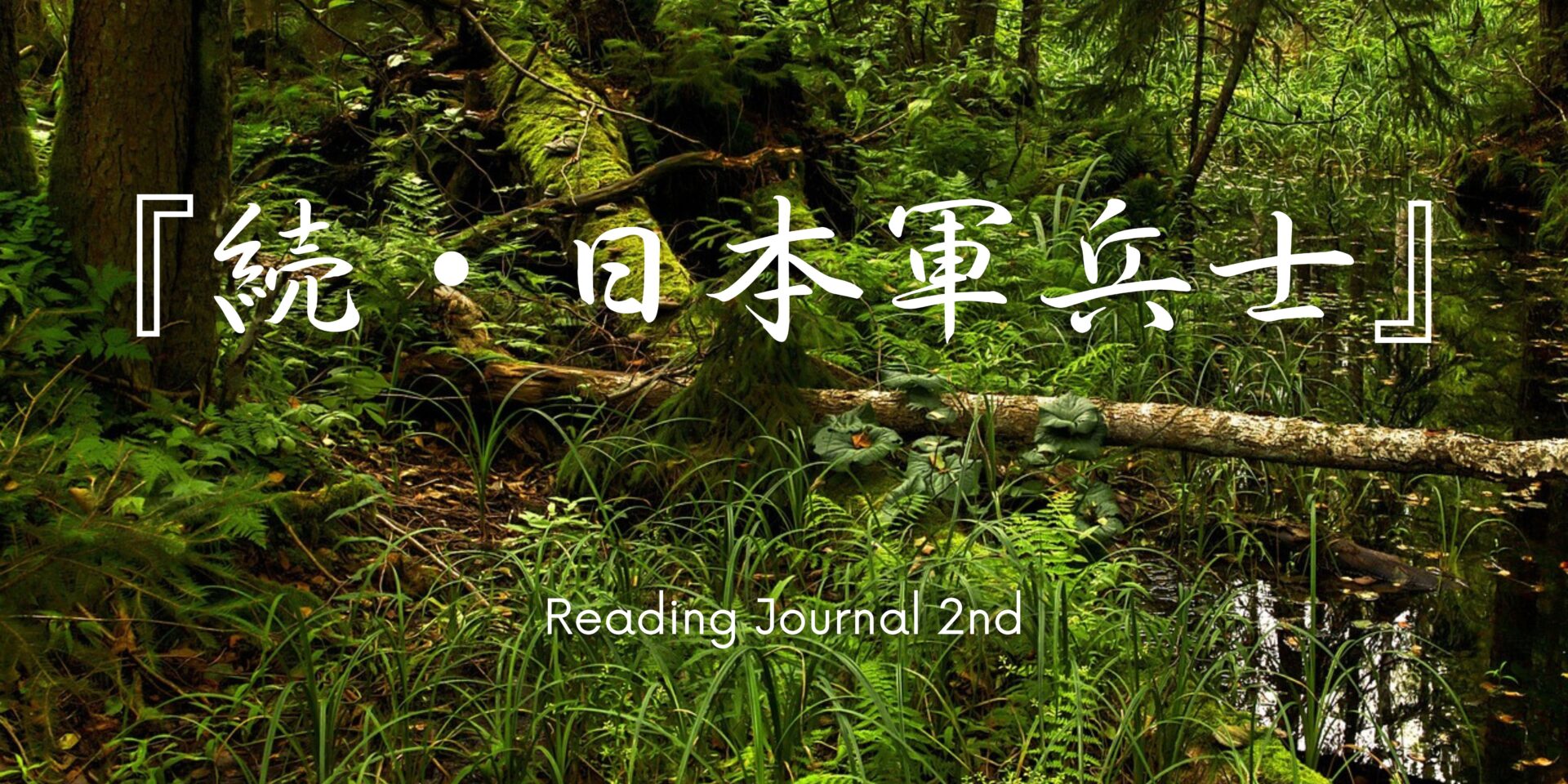


コメント