『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
現代文と古典文(前半) —- 一 文章とは何か
今日のところは、「実用的な文章と芸術的な文章」である。前回の「実用的な文章と芸術的な文章」において、文章で一番大事なことは「自分の云いたいことを明瞭に伝えること」であり、分かりやすい実用的な文章ほど良いと説明された。
それを受けて「現代文と古典文」では、口語体でない文章体の文章は、もう用が無くなったかというと、そうではなく、文章体の精神を無視した口語体は、決して名文とはいえないことが示される。
この「現代文と古典文」は、”前半“と”後半“に分けてまとめることにする。それでは、読み始めよう。
口語の欠点と文章体
まず谷崎は、前段(ココ参照)で、口語体の文章が今日の時勢に適すると言ったが、文章体の全然参考にならないと言うわけではないと指摘する。そして、
口語体を上手に書くコツは、文章体を上手に書くコツと、変わりはない。文章体の精神を無視した口語体は、決して名文とは云われない。(抜粋)
と言い、文章体の文章を研究する必要があるとしている。
まず、文章体は、和文調と漢文調に分けられる。
- 和文調:昔の口語が文章体として残ったもの。源氏物語、土佐日記など。明治時代まで擬古文として残るが、廃れてしまった。
- 漢文調(和漢混合文):従来の和文に漢語を読み下した時に言い廻しを交えたもの。保元物語、平治物語などの軍記物。幾分使われている。教育勅語などの詔勅の文体。礼辞、式辞、弔辞など
ここで谷崎は、先に「現代人に「分からせる」ようにするには、是非とも口語体でなければならない」と言い「昔のように字面や音調の美しさを気にしてはいられない」と言ったが、
ここで皆さんの御注意を喚起したいのは、「分からせる」ということにも限度があると云う一事であります。(抜粋)
と言っている。文章は分からせるように書かなければならないが、それには限度があることも常に念頭に置かなければならない。
口語体では、多くの語彙を使うことができ、明治以降に言葉の数自体も増えたため自然文章が、冗長となる。文語体で一行か二行で書けることも、五行も六行も書く、しかし、だからといって分かりやすくなるわけでなく、かえって分かりづらくなることも多い。
実に口語体の大いなる欠点は、表現法の自由に釣られて長ったらしくなり、放漫に陥り易いことでありまして、徒らに言葉を積み重ねるために却って意味が酌み取りにくくなりつつある。(抜粋)
と言い、そして、
文章のコツ、即ち人に「分からせる」ように書く秘訣は、言葉や文字で表現出来ることと出来ないことの限界をしり、その限界内に止まることが第一でありまして、古の名文家と云われる人は皆の心得を持っていました。(抜粋)
と文章のコツを述べている。
昔の文章は、言葉数が少なくかつ前例や出典にうるさいため使う場所が限られていた。しかし、古典の文章を見ると、同じ言葉が何度も出て来るが、その言葉が独特の広がりを持っている。
ここで著者は、このことを『更級日記』を引用し、具体的に説明している。そして、
やさしい、分かり易い文字を使ったからと云って、人に与える感銘の深さは、必ずしも饒舌な口語文に劣らないのであります。(抜粋)
と言っている。
関連図書:菅原孝標女 (著)『新版 更級日記 全訳注』 、講談社(講談社学術文庫)、2015年
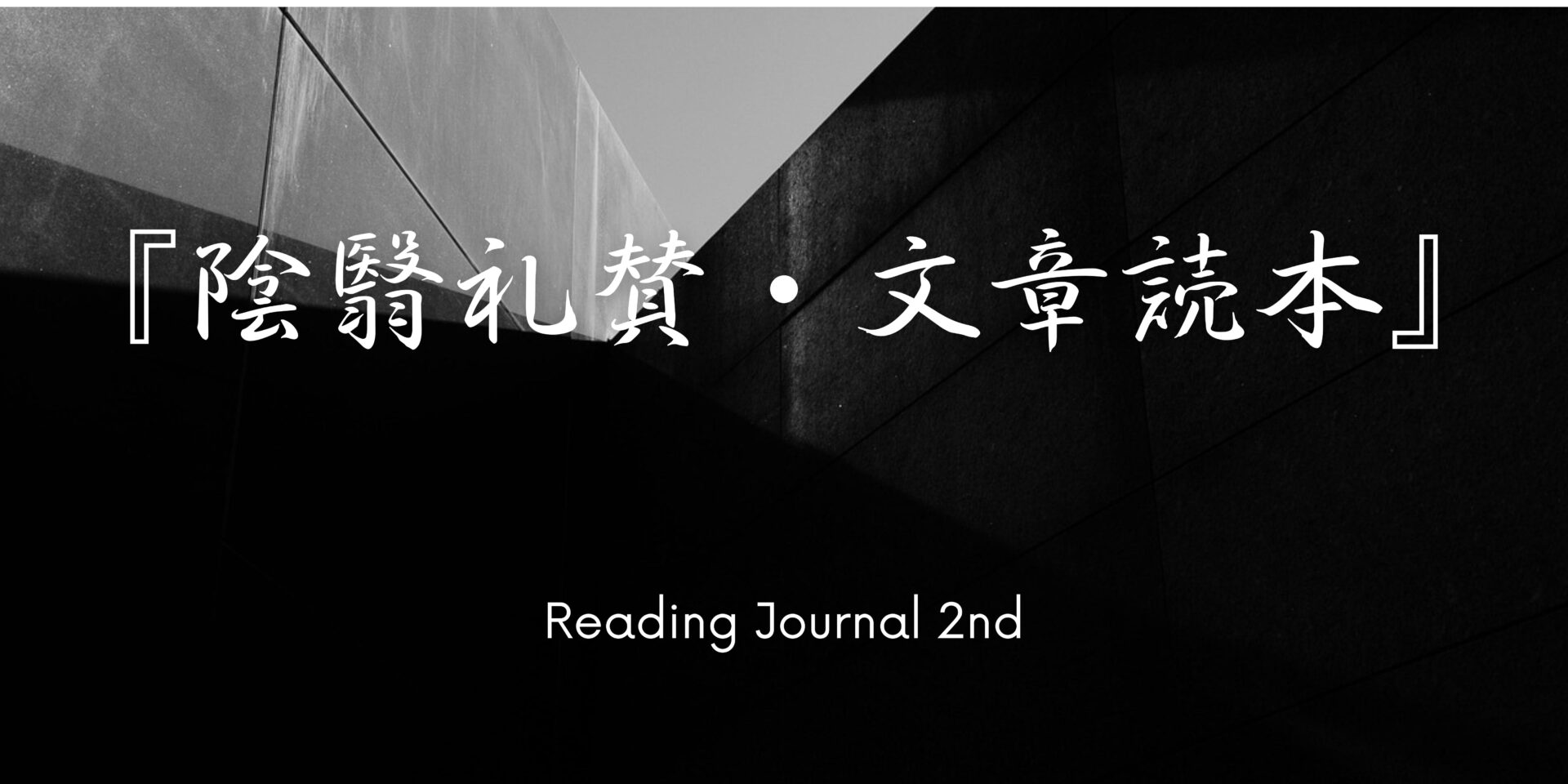


コメント