「漱石」 三浦 雅士 著(読了09)
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2009-01-30)
第九章 承認をめぐる闘争 - 『明暗』、あとがき
漱石は、母に愛されなかった子という主題を背負って長い道のりを歩んだが、それが母の問題でなく、自身の心の癖の問題であることが明らかになってきた。そしてその総仕上げが『道草』であった。
『道草』の銀時計のエピソードが示すように、母に愛されなかった子という主題の背後には、家族に認められなかった子、社会に認められなかった子というものが潜んでいる。そして単に愛されることと認められることは違う。
人間はたんに愛されることを望むのではない、人格として認められたうえで愛されることを望むのである。漱石が『道草』において明確に把握したことはこの事実であったように思われます。(抜粋)
『道草』は、夫に敬意を払われることを要求する妻の物語であると言える。そして、漱石は母に愛されなかった子供という主題の背後に、母に認められなかった子という問題が潜むこと、そしてそれが家族を含めた社会というもの本質であると気づいた。
『明暗』は、まさにその承認をめぐる闘争の物語になっている。
『明暗』は、妻が夫に自分を認めさせようとする物語であり、貧乏人が金持に自分を認めさせようとする物語です。要するに、力を持たないものが力を持ったものに自分を承認させようとする闘争の物語である。(抜粋)
『明暗』の主人公は津田とその妻のお延であるが、その背後に闘争を夫婦の闘争を見守る第三者が見事に配置されている。承認するものとしての第三者を配置したのである。そして、この小説は津田とお延が対等の立場で描かれ楕円形の作品となっている。津田の葛藤もお延の葛藤も対等に描かれているのである。さらに会話は第三者を含む三つ巴の会話が展開される。小説の主題が承認をめぐる闘争であるために、必然的に第三者が必要だったのである。
『明暗』が、承認をめぐる闘争という主題のもと、世間というもの、社会というものを活写して見事なのは、その主題が、母に愛されなかった子というのっぴきならない主題から必然的に派生し展開するものとして、漱石自身によって見出されたものにほかならかなったかれであると思われます。(抜粋)
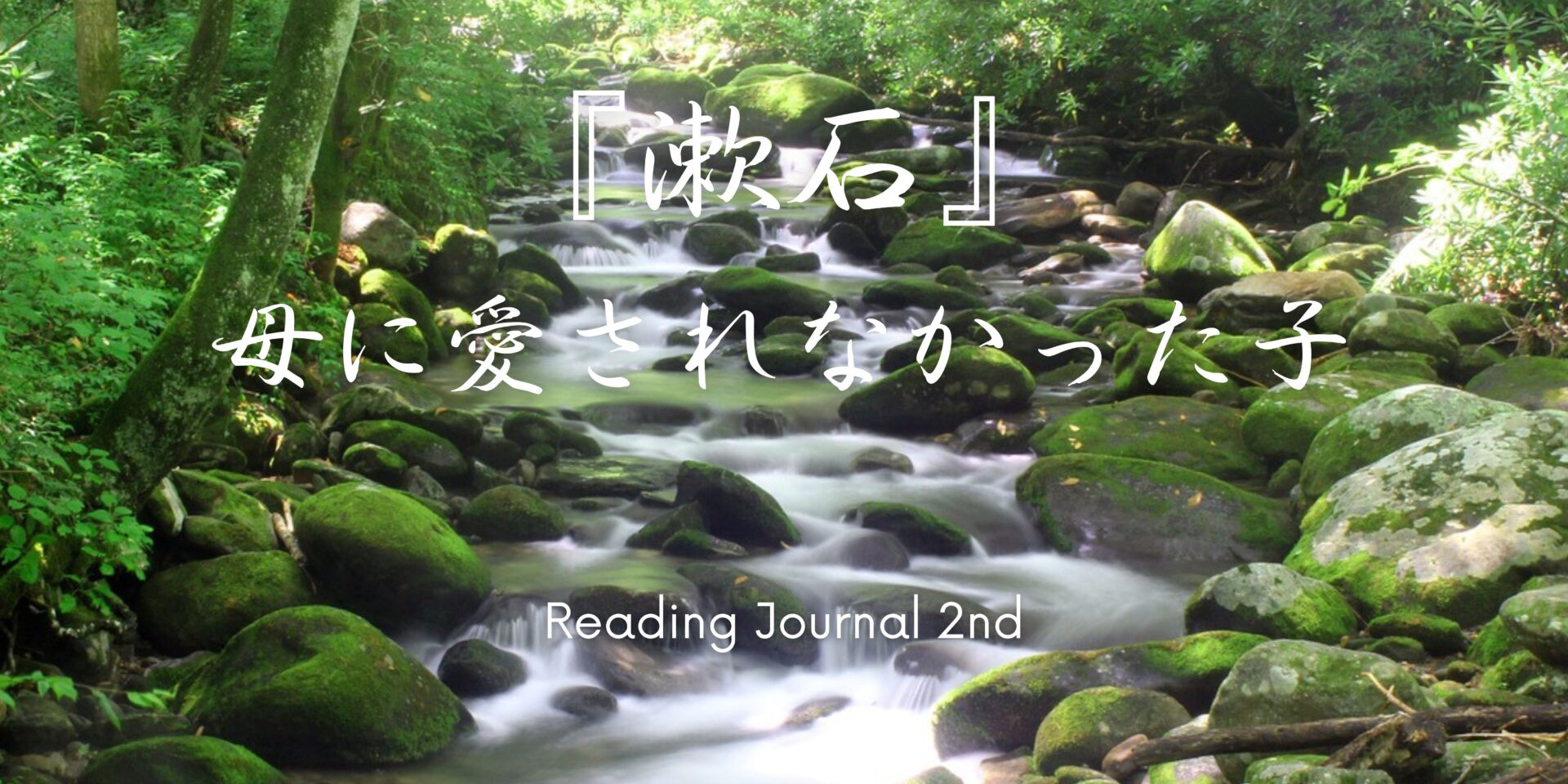


コメント