『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
終章 深く刻まれた「戦争の傷跡」
今日のところは、「終章 深く刻まれた「戦争の傷跡」」である。ここでは、これまであまり取り上げられてこなかった、戦後も長く続いた戦争の傷跡について論じられている。そして、最後に、「戦場の悲惨な現実を見すえる」という本書の方針について、「はじめに」で述べたこと以外に理由があるとし、近年の日本社会における「非現実的な戦争観」や「日本礼讃」「日本軍礼讃」の風潮に対して事実に即して反論している。それでは、読み始めよう。
アジア・太平洋戦争は日本の敗北で終わった。しかし、戦争終結後もアジアや連合軍の戦争犠牲者はもとより、日本の元兵士たちも、自らの心と体に刻まれた戦争の傷痕に悩まされることになる。ここでは、これまであまり取り上げられることのなかったいくつかの傷痕について論じてみよう。(抜粋)
再発性マラリア
日本の土着マラリアは、八重山諸島にわずかに存在するだけだった。それが、敗戦による引き揚げのため海外で感染し国内で発祥する「海外マラリア」の増大が危惧された。実際には一九四六年に三万人近い患者が出ただけで、その後は急速に減少していった。
しかし、戦地で罹患した帰還者が帰国後、再発を繰り返す「再発性マラリア」に悩まされる元兵士も多くいた。この「再発性マラリア」は、帰国後、一~三ヶ月の間に、一、二回再発し、半年を経過すると再発者数は半減し、五年後になると再発を繰り返す者はきわめて少なくなる。しかし、この年限を過ぎてもしつこく再発する例もあった。ここで、著者は、そのような事例をいくつか消化している。中には復員後、三十年も悩まされる例もあった。
栄養失調の痕跡
また、栄養失調も体に目立った痕跡を残した。栄養失調なると独特な土色の膚となるが、それが人並みになるには早い人で二年、遅い人だと五年くらいかかった。
水虫との闘い
次に水虫の問題である。第一次世界大戦では、塹壕戦が長期化したため、兵士は水に濡れたまま軍靴を長期間吐き続けた。そのため、深刻な凍傷や水虫、その合併症が蔓延した。これがいわゆる「塹壕足」(トレンチ フット)である。
日本軍の場合は、もともと靴を履く習慣がなかったため、この水虫の感染は大きな問題だった。ここで著者は、衆議院議員園田直をはじめとした終戦後も長い間水虫に悩まされた事例を紹介している。
日本軍の場合は、陸海軍共に、水虫の予防と治療は軽視され、水虫は完治しないという誤った概念が広がった。
覚醒剤の副作用と中毒と夜間視力増強食と昼夜逆転訓練
さらに、覚せい剤の副作用や覚醒剤中毒の問題も深刻だった。(抜粋)
ここで著者は、夜間戦闘機の搭乗員の話を紹介している。日本では、敵の艦船や飛行機を探知するレーダーなどの開発が遅れ、その結果、夜間の戦闘では、搭乗員の視力に依存するしかなかった。そのため陸軍では夜間視力増強食が使用された。また、陸海軍がともに昼夜逆転訓練も実施している。このような訓練によりノイローゼ患者も何人かでたという。
この夜間戦闘機訓練では、疲労回復、眠気や眼精疲労の緩和の目的で、「除倦覚醒剤」を常用させていた。そのため、軍が軽視していた覚醒剤の副作用が敗戦後に深刻な問題となる。ここでは、夜間戦闘機「月光」の搭乗員だった黒島四朗の事例などがしょうかいれている。
さらに、軍隊や軍需工場での覚醒剤使用による覚醒剤中毒も大きな問題だった。覚醒剤は服用している軍関係者が覚醒剤中毒になっただけでなく、その人々を媒介者にして、戦後社会に広がっていった。
さらに、著者は、実態はよくわかっていないが麻薬の一種であるモルヒネによる中毒者もいたと指摘している。
近年の「礼讃」と実際の「死の現場」
本書では、戦場の凄惨な現実を見すえることを重視してきた。それには、「はじめに」で述べたこと以外にも理由がある。(抜粋)
それは、一九九〇年前後から「非現実的で戦場の現実とかけ離れた戦争観が台頭してきた」からである。
戦争に「イフ」を設定する「架空戦記」「仮想戦記」ブーム
その一つは、さまざまな「イフ」を設定した「架空戦記」「仮想戦記」である。ここで、著者は、この「イフ」ブームを批判した『やっぱり勝てない?太平洋戦争』(二〇〇五年)を紹介している。その本では、このブームの背景には『日本は戦争に負けても戦艦大和は世界一』的な考え方がある」と指摘している。そして、過大評価されている日本海軍の実力について、説得的な分析を行っている。
『日本礼讃本』『日本軍礼讃本』ブーム
そして、竹田 恒泰の『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』に代表される「日本礼讃」がブームとなる。そして軍事の分野でも井上和彦の『大東亜戦争秘録 日本軍はこんなに強かった!』のような「日本軍礼讃本」が目立ち始めた。
ここで著者は、このような日本陸海軍を「礼讃」の中心となるのは、パラオ共和国のペリリュー島の戦いであるとし、その戦いについて事実の即し反論している。
このペリリュー島の戦いにおいて日本軍は、それまでの米軍上陸直後に決戦する水際撲滅作戦を取らずに、頑固な陣地洞窟に立てこもって粘り強く反撃した。
戦力に勝る米軍に多大な損害を与え日本軍の精強さを示した戦闘として、取り上げられることが多い。(抜粋)
ここで著者は、井上の著作も含め、米軍の損害についてあまり触れられることはない、と指摘している。アメリカ軍側の損害は、戦死一九五〇人、戦傷八五一六人であり、日本側の損害、戦死者一万二二人対して圧倒的に小さい。
戦闘の実際も、通信網の寸断によって、指揮中枢は早い段階で失われ、日本軍は孤立した非組織的な抵抗を続けていただけである。
日本側のペリリュー島の戦いに関する認識は、日本軍の戦闘力に対する過大評価とある種の思い入れがある。そして、そんな風潮が根強く残っているからこそ、戦場の凄惨な現実を直視する必要があるのだと思う。トラック諸島で従軍した俳人の金子兜太氏が繰り返し強調する「死の現場」が、それである。(抜粋)
関連図書:
「やっぱり勝てない?太平洋戦争」制作委員 (著)『やっぱり勝てない?太平洋戦争: 日本海軍は本当に強かったのか』、シミュレーションジャーナル、2005年
竹田 恒泰 (著)『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』、PHP研究所(PHP新書)、2010年
井上和彦(著)『大東亜戦争秘録 日本軍はこんなに強かった!』、双葉社、2016年
[完了] 全14回
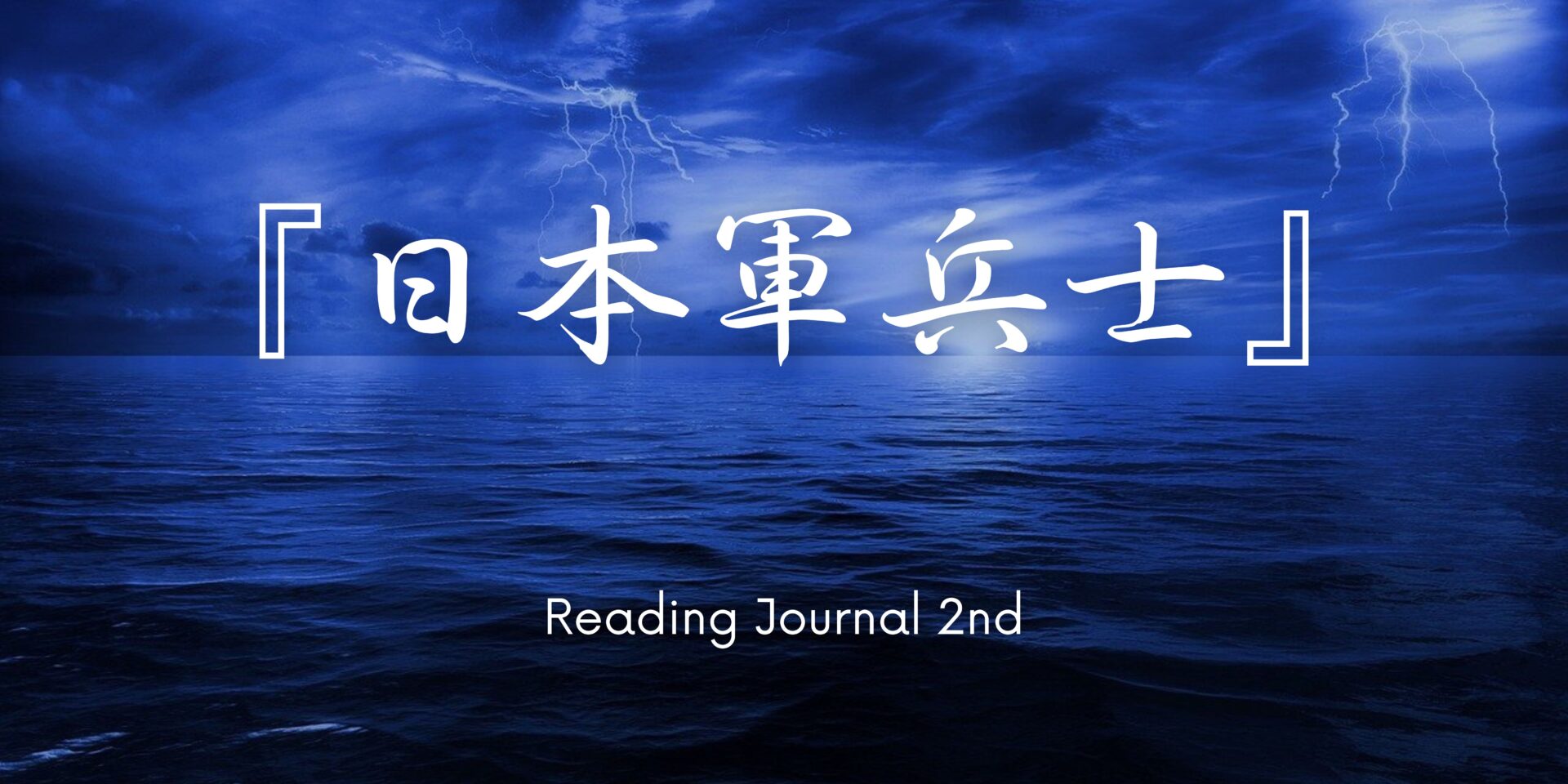


コメント