「漱石」 三浦 雅士 著
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2008-10-21)
第四章 母を罰する - 『草枕』と『虞美人草』
この章で著者は『草枕』と『虞美人草』の底流を流れるのは、漱石の母への愛憎であったと書いている。
一般に漱石は晩成型の作家であるといわれているが、実際は少年のころから作家を目指していた。その気になれば彼は早熟の天才として活躍することは十分できたが、そうしなかったのは、「なにを文学として文学としないか」であった。
当時は、文学と言えば漢詩文であり、戯作から発達した小説などは、漱石から見れば物の数ではなかった。このような漢詩文の世界はその後の日本近代文学によって抹殺されてしまったが、
この抹殺された世界こそが少年漱石にとって文学だったのだと思われます。(抜粋)
漱石が松山中学から熊本五校に移ったとしに『人生』という文章を書いている。このなかで
空間を画しているものを物といい、時間に起こるものを事という、事物を離れて心はなく、心を離れて事物はない、事物の変遷推移を名づけて人生という、小説はこの人生の一側面を写すものだが、その一側面にしても単純ではない、(抜粋)
と漱石は言っている。そして、小説は、
- 境遇を語るもの
- 品性を描写するもの
- 心理を分析するもの
- 直感的に人生を看破するもの
の四つがあるが、そのほかに不思議はもの、因果の法則から離れ、意志とは無関係にだしぬけに直線的に来る、狂気と呼ばれるものがあると書いている。
このような視点は表現者を志していなければ出てこないものである。
『人生』に書かれているように漱石は常に狂気にかられ、不安にかられていた。そしてそれが漱石に漢詩文が必要であった理由である。
漢詩文は、漠とした不安、漠とした疑い、すなわち自分は母に愛されなかった子、生まれてくるべきでなかった子ではないかという疑いを封じるために―ー論じるためではなくあくまでも封じるために、絶対必要だったということを説明しているのだと言っていい。(抜粋)
『草枕』はそれを説明するために書かれた作品である。
『草枕』で目論んでいるのは、自分にはなぜ漢詩的な世界が必要であったか、自分自身に納得させることであった。(抜粋)
「詩人には憂いはつきものかも知れないが、苦しみがない」、なぜか、それは「世界を第三者お立場で眺めているからである」。芝居や小説が面白いのは、そのあいだだけ自分の利害を忘れる事ができるからである。しかし、芝居も小説も人情を離れて存在しない、とくに西洋物はくどい。それは解脱をしらないからだ。
そこへ行くと東洋の詩歌はいい、解脱している。
漱石は、少しのあいだでも非人情の世界の遊びたいから漢詩に向かったのである。
・・・・・・中略・・・・・・
目を細めて見れば、世界はすべて美しい。『草枕』の核心にあるのはこの思想です。漱石は、世間で起こることのすべてを落ち着いて見られる間三尺を隔てるその手段として漢詩文の世界にがむしゃらに近づいたのである。(抜粋)
小説では、非人情の世界に遊ぼうとする画家が、ある温泉に逗留する。そして温泉の若女将がこの非人情を標ぼうする画家をしきりに誘惑するのである。この若女将は薄情であるが美人である。画家の方も漢詩によって俗世間から距離を置くことができるから余裕がある。
画家が若女将に惹かれるのは、自分と同類を見るからであり、自分と同じように非人情をすすめている。
だが、小説の魅力は、語り手すなわち画家が説明する那美さんにあるのではない。画家の思惑を超えてだしぬけにまっすぐ振る舞う那美さんにあるのだ。次々と謎をかけては、ほゝゝゝと笑って逃げ去る女にあるのだ。画家が捉えようとしても捉えきれない、知的で美しく謎をかけて消え去る女に。
その奥底に母が潜んでいることは疑いないと思えます。(抜粋)
なぜ、母が潜んでいるといえるのだろうか。それは『虞美人草』を見れば分かる。
『虞美人草』は、『草枕』の主人公であり語り手でもある画家が下界に降りてきてからの話にほかならない。(抜粋)
そしてこの『虞美人草』は、母に愛されなかった子が、母を罰するという小説である。
『虞美人草』の冒頭は、主人公が従兄と比叡山に登るという場面から始まる。この冒頭は、『草枕』の冒頭に重なる。
主人公は、若くして母と死別し、そして養母に育てられていた。養母と父の間には絶世の美女の藤尾が生まれる。やがて父は外国で客死するという設定である。
養母も藤尾もこの主人公を全く愛していない。母に愛されなかった子という主題を真正面から取り上げているのである。もちろん主人公は、これに対して「じゃあ、消えてやるよ」と『坊ちゃん』そっくりに言ったのである。
小説は、主人公が家を出る寸前になって、従兄の活躍で大団円になるのだが、そのために藤尾が自殺するのである。
まるで、復讐である。母に愛されなかった子が、母を罰するためにその最愛の娘を死に追いやったようなものです。『虞美人草』は母に愛されなかった子の復讐劇なのだ。(抜粋)
しかし、この養母のモデルが漱石の母では無い。むしろ漱石の標的は藤尾である。そして、藤尾は『草枕』の那美さんの延長上にある。漱石は、残酷にもこの藤尾を死に追いやらなければいられなかった。
だが、漱石は残酷なだけではなかった。残酷な仕打ちをしながらも、その藤尾を愛していた、憧れてもいたのです。項羽の寵姫、虞美人さながらに自決した藤尾の死の床には抱一の描く虞美人草すなわち雛罌粟の逆さ屏風を用意し、さらにその死の顔を克明に描くのです。すなわち、すべてが美しい、美しいもののなかに横たわっている人の顔も美しい、驕る眼はとこしなえに閉じた、驕る眼を眠った藤尾の眉は、額は、黒髪は、天女のごとく美しい、と。じつに激しい愛憎です。藤尾すなわち虞美人草は、最高に美しいものとして描かれているのです。(抜粋)
記憶があると書いている。そして、母の衣装の中には錦絵に出てくるような着物があった、しかしその衣装をつけた母の姿は想像しても目に浮かばない、なぜなら私の知っている母は、常に大きな老眼鏡をかけたおばあさんだったからと、書いている。
小説のなかで、漱石は『草枕』の那美さんや『虞美人草』藤尾に、このようは豪華な衣装を着せているのである。
漱石にあっては、愛と憎しみはつねに手をたずさえている。愛しているとしか思えないあなたが、それではなぜ私を捨てたのか。母へのこの問いは愛憎そのものである。(抜粋)
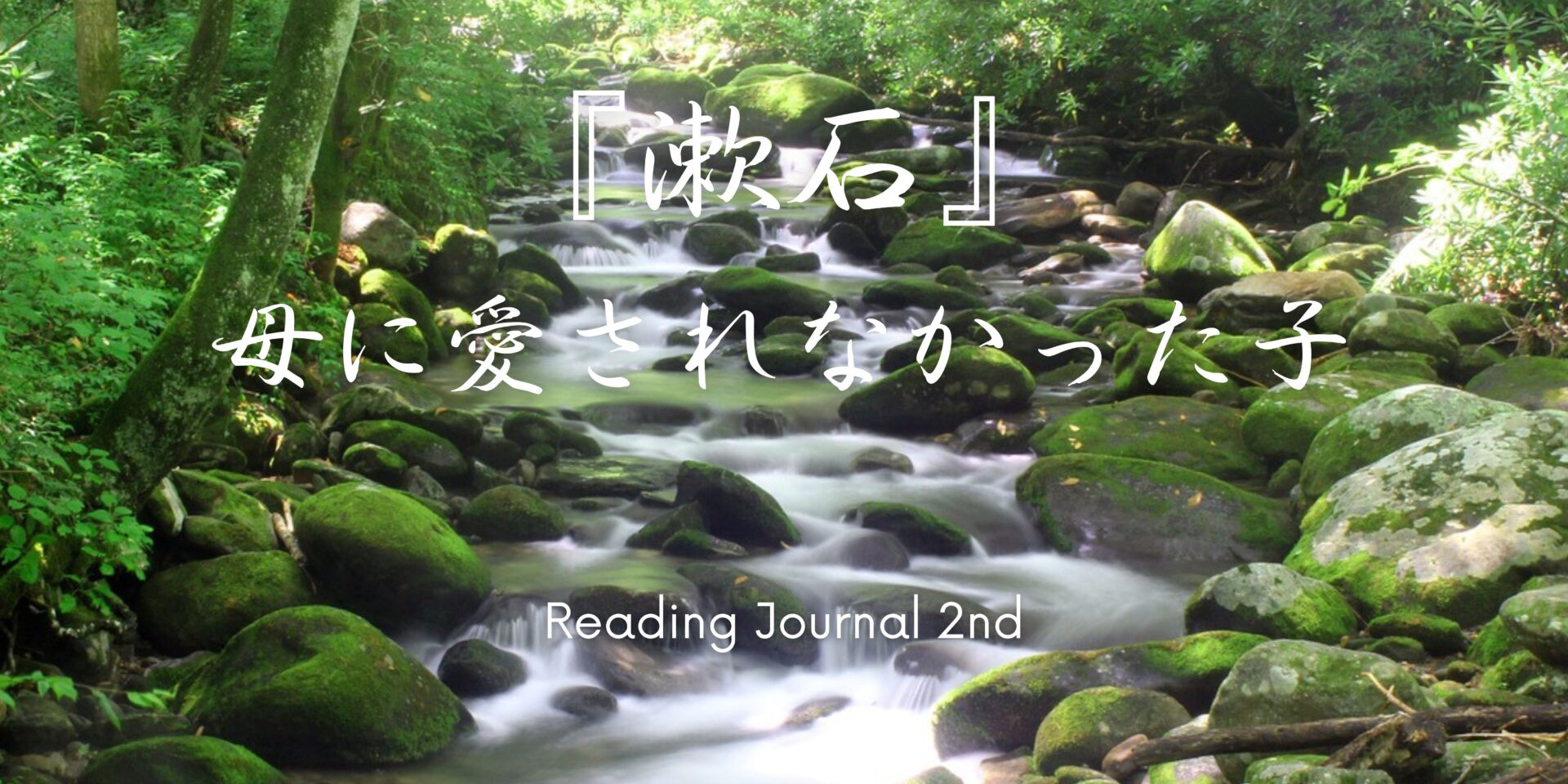


コメント