『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 無残な死、その歴史的背景 (その1)
ここから「第3章 無残な死、その歴史的背景」に入る。これまで第1章、第2章において、身体の問題と関連づけながら兵士の無残な死について書かれていた。ここで著者は、このような前線の兵士たちに大きな負荷をかけるような構造が日本陸海軍に内在していたと強調している。第3章ではこの問題が取り上げられている。
第3章も節ごとにまとめることにする。今日のところ“その1”は、「短期決戦の重視」、「作戦至上主義」、そして「極端な精神主義」という陸海軍の軍事的思想の問題である。それでは、読み始めよう
1 異質な陸海軍の思想
短期決戦と、作戦至上主義
著者は、日本の陸海軍の軍事思想の特徴として、
- 短期決戦、速戦即決の重視
- 作戦至上主義
- 極端な精神主義
を挙げている。
日本は、長期にわたる欧米列強との長期戦を回避するために「短期決戦」「速戦即決」を重視した。一九〇七年に制定された「帝国国防方針」では、そのような思想が書かれている。そして、第一次世界大戦後の一次改定は、長期の総力戦を戦い抜くという思想が加わったが、その後の第二次改定において、再び短期決戦思想に回帰してしまう。
②の「作戦至上主義」というのは、戦闘をすべてに優先させるということである。これは、補給、情報、衛生、防禦、会場護衛などを軽視するということと表裏の関係にある。
そのため相次ぐ船舶の喪失にかかわらず、船団護衛などの任務とする海上護衛司令部が発足したのは、一九四三念である。また、陸軍おいては、必要な食料・生活物資を後方から補給せずに「現地徴発」とした。ここで「徴発」といっても対価を支払わないことが多く、実際には民衆からの「略奪」であった。
極端な精神主義
日露戦争後に確立した日本軍の極端な精神主義のため、火力や航空力の充実や機械化や軍事技術の革新などに大きな関心を払わず、精神的優位性だけを強調する風潮が生まれた。
日本軍は「戦闘の決は銃剣突撃をもって決する」という白兵主義を信条とし、それを可能とするのは攻撃精神・突破精神であるとした。ここで白兵とは銃剣、刀剣など格闘戦用武器を意味し、銃剣を装着した小銃による突撃を重視するのが白兵主義である。
そのため近接戦闘用の短機銃(サブマシンガン)の開発を怠るという結果をもたらした。短機銃は第二次世界大戦における歩兵の標準装備であったが、日本ではほとんど実用化されなかった。
米英軍の過小評価
また、このような風潮のなかで、連合軍の戦力を過小評価し、連合軍に関する研究を怠った。
アジア・太平洋戦争の開始前の段階では、対ソ戦を想定して作られた典範令 — 戦闘や教育、訓練などの教本 — を対米英戦向きに改定する意思を持っていなかった。その代わりにいくつかの参考書を作成した。その一つが『これだけ読めば戦は勝てる』である。しかし、これは中国における「治安戦程度」の戦争しか想定していないものだった。また、教育、訓練は対ソ戦に関するものばかりが行われていた。
陸軍は伝統的にロシア・ソ連を仮想敵国としていたが、日中戦争が長期化し、アジア・太平洋戦争が始まったこの段階でも、対中国戦争や対米英戦の研究・教育が大幅に立ち遅れていたのである。(抜粋)
一九四三年中頃からの対米戦重視
このような状況は、連合軍の反撃が始まると変化が生まれる。そのきっかけは、第一線の将兵たちの発言である。ここで著者はそのような発言をいくつか取り上げている。彼らはみな連合軍の戦意の高さを指摘している。
こうしたなかで一九四三年後半頃から、陸軍中央部の認識も転換しはじめ、教育訓練、情報収集の重点、戦法研究などを対米軍重視に切り替えたが、それは遅すぎる転換であった。
陸軍は『米英軍常識』を編集・編纂し米英軍の戦意の高さを冷静に評価し、また米軍の戦法に関する調査・研究をまとめ『敵軍戦法早わかり(米軍の上陸作戦)』なども発行した。このなかで、米軍の戦法は従来の戦術的奇襲ではなく、戦術的強襲を採用し「膨大なる物量」、なかでも圧倒的な砲撃で「我が防御を震倒せしめんと企画」すると特徴づけている。
戦車の脅威と「肉攻」
陸上戦闘における日本軍兵士の最大の脅威は、七五ミリ砲を搭載した米軍のM4中戦車だった。このM4戦車は第二次世界大戦における米軍の代表的戦車であるが、日本軍は性能の劣る戦車や貧弱な対戦車兵器しか持っていなかったため、大変な猛威を振るった。
この戦車に対する最大の問題は、日本軍の唯一の対戦車火器である三七ミリ連射砲ではM4戦車の装甲を打ち抜けないことであった。そして、この状況の下「肉攻主体」の対戦車戦闘が提唱された。この「肉攻」とは、爆薬を抱いた兵士による体当たり攻撃である。
「肉攻」に使用する兵器は、五キロから一〇キロの爆薬を収納した箱に簡単な点火装置をつけた「急造爆雷」であった。そしてそれは事実上、生還不可能は攻撃であった。
このような攻撃に対しては、軍部でも批判があった。しかし、「国家自体が体当たりを必要とする時代にまで進んできている」と反論しあくまでも肉攻を対戦車攻撃の中心に置いた。このような論理について著者は、
正規の対戦車戦闘を遂行する国力はすでに日本にはない、それでも、あくまで戦争を継続するとすれば兵士の生命を犠牲にするしかない、そういう関係性が後宮の「論理」のなかによく示されている。(抜粋)
と言っている。
見直される検閲方針
ここで注目されることは、一九四四年に入ったころから、軍事雑誌に戦局の深刻な実相を部分的な形ではあれ、認めるような論説が掲載されるようになったことである。ここで著者は、それがわかる幾つかの実例を挙げている。そして、このような変化な検閲政策の変化と連動していると思われるとしている。
一九四四年、日本海軍最大の前進根拠地であるトラック島がアメリカの機動部隊の攻撃を受け、多数の艦船、航空機、施設が損害を被り、トラック島は基地機能を喪失した。しかしこれを新聞ではアメリカの機動部隊を撃破したと報道された。
これをきっかけに海軍省は、国民の奮起を促すため悲観的にならない範囲内で、悪化する戦況について報道するように指示し、陸軍当局も同様な申し入れをした。これは、「戦局の劣勢を掲載可能」とした新たな検閲政策の採用であった。
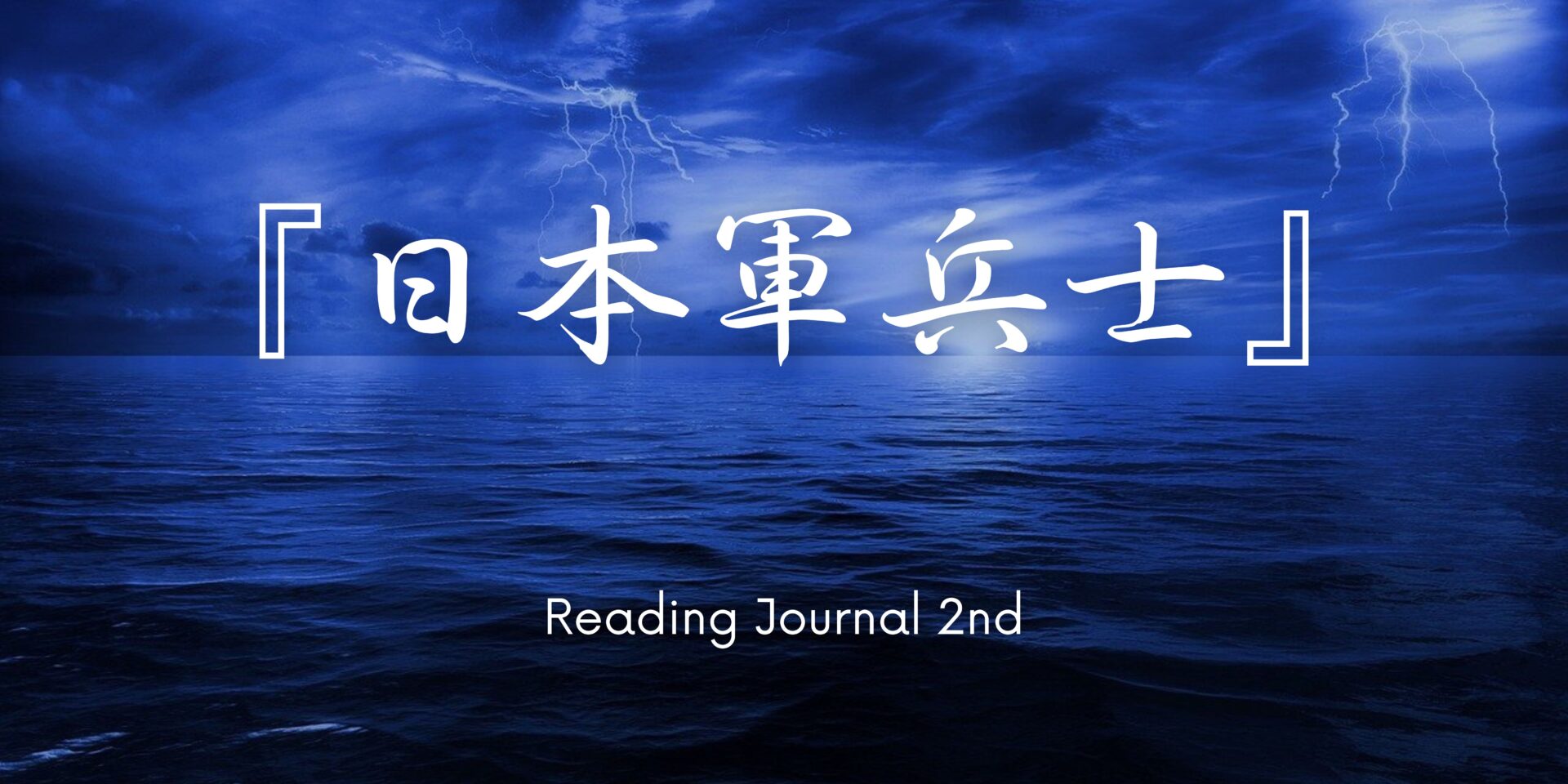


コメント