『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 身体から見た戦争 — 絶望的抗戦期の実体II (その4)
今日のところは「第2章 身体からみた戦争」の“その4”である。本章では、“その1”、“その2”、“その3”で、日本軍兵士の精神面を含めた身体に関する問題が取り扱われてきた。
今日のところ“その4”では、前節までとは少し変わって、日本軍兵士の被服・装備の問題が取り上げられている。日本軍兵士の被服・装備は経済的な窮乏のため、しだいに劣悪化され、最後期には基本的な装備まで整わない兵士も多くいた。それでは、読み始めよう
4 被服・装備の劣悪化
日本軍の被服の劣化
兵士たちの身に着ける被服の良否は、兵士の身体に大きな影響を及ぼす。そしてその被服が急速に劣化していった。ここでいう被服とは、軍服、下着、軍靴だけでなく、背嚢、飯盒、水筒、携帯天幕など、武器以外の装備の総称である。
日本軍の軍服は、一九三八年の服制改正により、楯襟式から折襟式への変更や肩章から襟章への変更以降は、大きな変更はなかった。しかし、素材が地の厚いも毛織である絨製から綿製に変わったため地質は洗濯のたびに急速に悪化した。
そのため、外套などは、明治、大正年間の旧外套の方を使った方が保温力なども遥かに優れているという状態となった。前線に送り出す兵士の服装もみすぼらしくなっていった。多くの兵士が略奪した「支那服」を着用し、ゲートルの代わりに布を足に巻き、これが皇軍かと思わせるような格好となっていった。
鮫革軍靴と無鉄の軍靴
軍靴の粗悪化が進み、アジア・太平洋戦争期に入ると物資不足が深刻となり、牛革で作られていた軍靴も馬革や豚革が使用されるようになり、鮫革の軍靴まで登場した。このゴム底鮫革の軍靴は、草によく滑りそして水を通した。
さらに前戦への補給が途絶えると行軍の際に軍靴を履いていない兵士も多かった。ゲートルを靴の代用としているもの、靴の底が抜けているもの、靴の無いもの、略奪したつっかけ草履や支那靴を履いているものなどもいた。
革の問題と共に重要なのは「無鉄軍靴」である。軍靴は革や縫い糸などの他に、強度を増すために釘や鋲などの鉄が使用されているが、資源不足から鉄の大幅な節約が断行された。このような無鉄の軍靴は、軍靴としての使用に耐えられるものではなかった。
孟宗竹の代用飯盒・代用水筒
日本軍は最後まで兵士が携帯する飯盒による炊飯方式に依存し続けた。そのため飯盒は兵士にとって最も基本的な道具である。しかし、部隊史などの記述を読むと時にこの飯盒を携帯していない兵士の存在に気がつく。
兵士の数が徐々に増え、兵員の増加にその生産が追いつかなくなったため、飯盒はおろか竹筒の水筒しか持たない兵士(「竹筒補充兵」)が増えていった。
兵士たちは飯盒という最後の「命綱」さえ失いつつあった。(抜粋)
背嚢から背負い袋へ
兵士には背嚢というリュックサックが支給されていた。これは防水帆布と牛皮によって作られていて、下着や食料を詰め込み、外側に外套、飯盒、携帯天幕(テント)、円匙(シャベル)などを装着する。
しかしこの背嚢は、ひもの部分が牛皮から紐で固定する方式に変わり、背嚢は次第に背負い袋に変わっていった。この背負い袋は形を整えるのが難しく厄介な存在だった。
以上のように、兵士たちの身体をめぐるさまざまな問題からみても、戦争が長期化するなか敗戦は急速に現実のものとなりつつあった。(抜粋)
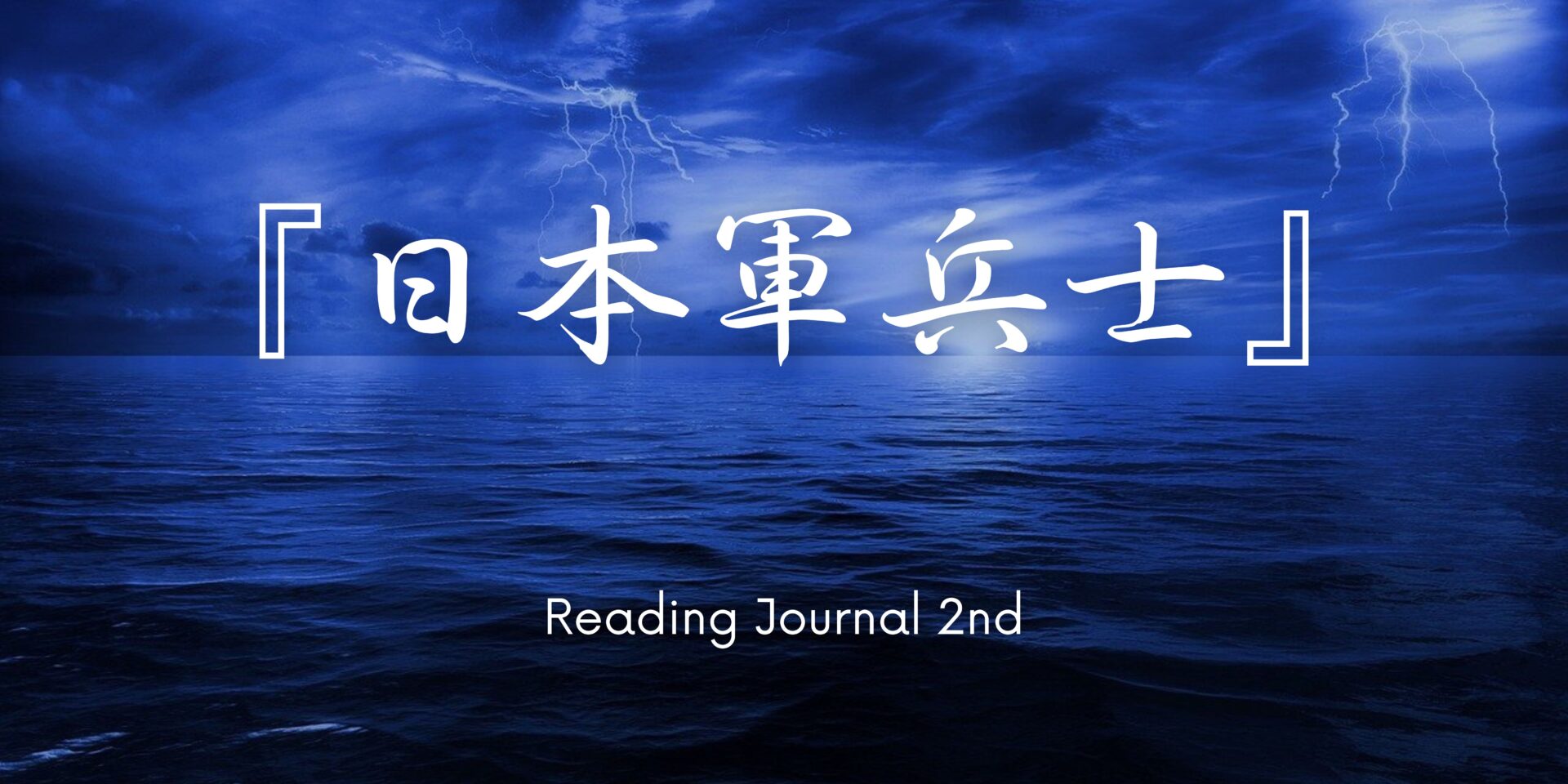


コメント