『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 身体から見た戦争 — 絶望的抗戦期の実体II (その3)
今日のところは「第2章 身体からみた戦争」の“その3”である。“その1”、“その2”では、日本軍兵士の身体に関する問題がその軍の対応と共に取り上げられた。
今日のところ“その3”では、日本軍兵士の心の問題が取り上げられている。苛酷な環境の下、兵士たちの精神は衰弱し、精神疾患を伴う兵士も多くなる。ここではそのような問題と共に、兵士の疲労を和らげるために使ったヒロポンなどの「戦力増強剤」や兵士に休暇がなかった問題などが取り上げられている。
3 病む兵士の心 — 恐怖・疲労・罪悪感
入隊前の精神教育
兵士たちには、強い「軍人精神」が求まられた。そのため日本では、徹底した「忠君愛国」教育が行われた。義務教育を終えると、社会に出てからも青年訓練所(後に青年学校に改組)で入営前の予備訓練が行われた。さらに中学校以上の学校には現役将校が配置され軍事訓練が開始された。
軍事熱や排外熱をあおるためにマスメディアが大きな役割を果たす。地域社会では、除隊した在郷軍人や帰還兵が残虐行為を正当化する言説で若者を教育した。
戦場教育の仕上げ・「刺突」訓練
このように入隊前から中国人に対する蔑視感、軍事至上主義的な価値観、残虐行為を容認する価値観などが身について行った。そして、その総仕上げは「刺突」訓練だった。
刺突訓練とは、初年兵や戦場経験を持たない補充兵などに、中国人の農民や捕虜を小銃に装着された銃剣で突き殺させる訓練である。
この「刺突」訓練は、初めて体験する兵士にとっては衝撃的な出来事だった。初年兵はこのような非人道的な訓練や戦闘を繰り返すことにより、「戦場慣れ」をしていった。
「戦場神経症」の拡大
そうした訓練にもかかわらず戦況の悪化に従い、精神疾患患者は増大していった。
近年、戦時中における兵士の精神疾患の問題に関して、「戦場神経症」を中心に研究が進んでいる。このような「戦争神経症」は、現代では戦争が兵士にもたらすトラウマ反応の一環として理解されている(中村江里『戦争とトラウマ』など)。
「戦争神経症」とは、戦時に軍隊に発生する神経症の総称で、ヒステリー性痙攣発作、驚愕反応、不眠、記憶喪失、失語、歩行障害、自殺企画、夜驚症などがある。そしてその原因として、「戦闘行為での恐怖・不安によるもの」「戦闘行動での疲労によるもの」「軍隊生活への不適応によるもの」「軍隊生活での私的制裁によるもの」「軍事行動に対する自責感にようるもの」「加害行為に対する罪悪感によるもの」などがある。
ここで著者は、この「戦場神経症」の問題の例として、海軍航空機搭乗員の精神疾患を解説している。このような「戦場神経症」の症状は、戦闘が激ししさを増すにつれ航空機の搭乗員にも広がっていたが、海軍中央部は本格的な対策に乗り出そうとせず、「疲労回復」の問題とすり替えてしまった。そして、
海軍軍部医学研究部に「除倦覚醒を目的とする特殊製剤」=「除倦覚醒剤」の研究を命じた。(抜粋)
覚醒剤ヒロポンの多用
当時、疲労回復や眠気防止の効力を謳った覚醒剤ヒロポンが市販されていた。ヒロポンは、商品名だが広く普及したため覚醒剤の総称のようになった。ヒロポンはその副作用や薬物依存の問題が十分認識されていなかったため、製造中止となったのは、敗戦後の一九五〇年である。上の海軍軍部医学研究部には、このヒロポンの効果や、より強力な新薬の研究が命じられたと考えられる。
このヒロポンは戦場では、かなり早い段階から使用されていた。そのここではそのような事例が示されている。
海軍では、この「除倦覚醒剤」に関する実験も行われていた。それによると、副作用は「ほとんど問題にする程度ではないが、食欲の減退がある」としている。そして、この実験の最大の問題点として「これが長期運用による影響は今後の研究にまつ」としているところである、著者は指摘している。
航空疲労と覚醒剤
ここで著者はソロモン諸島やニューギニアの戦局の悪化に伴い、同地方に派遣された陸軍航空部隊の状況とその航空疲労を取り上げている。
彼らは連日の出勤と緊張の連続によって食欲を失い、心身の衰弱を深めた。そして、「死ななければ(日本には)帰れない」という言葉までささやかれ始めた。しだいに肉体的疲労よりも精神的な疲労がたまり戦意はがた落ちになった。
このとき、岡本修一・第一二飛行団長は、四至本中尉に、「きさまは、いったい、いつまで生きとるつまりか」と罵声を浴びせた。(抜粋)
戦争が長引き負け戦が多くなると、いつまでも生きている将や兵が白い目で見られたり、皮肉や嫌味を言われたりする奇妙な現象が現れ始めた。
このような状況を陸軍中央は「航空疲労」の問題として捉えた。しかし、陸軍では「航空疲労」の中の精神的要素について海軍よりも注意を払っていたと著者は指摘している。
しかし、陸軍も海軍同様に、このよう状況に対して覚醒剤に依存していた。ヒロポンを航空兵や第一線兵士の戦力増強剤としてチョコレートなどに加え使用していた。疲労が激しい戦闘機操縦者は、疲労回復のため注射を打ちつつ出撃するものも多数であった。
ちなみに、陸海軍が保有していた大量のヒロポンは、戦後、民間に放出された。敗戦直後から一九五六年までの時期は、「第一期覚せい剤黄金時代」と呼ばれているが、その供給源となったのは陸海軍のヒロポンだった。(『覚せい剤』)。(抜粋)
休暇なき日本軍
精神的にも肉体的にも消耗しきった兵士たちの存在を制度の問題としてとらえ直してみたとき、日本軍の場合、総力戦・長期戦に対応できるだけの休暇制度が整備されていなかったことが大きな問題だった。(抜粋)
第一次世界大戦の教訓から、欧米諸国では前線で戦闘に従事した兵士たちを、後方に下げて休養を取らせる休暇制度が整備されていた。日本陸軍でも陸軍軍人休暇令により休暇が認められていたが、戦地の動員部隊に所属している兵員には本令による休暇さえ認められていなかった。
関連図書:
中村 江里 (著)『戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦争神経症』、吉川弘文館、2017年
室生 忠 (著)『覚せい剤: 白い粉の恐怖』、三一書房 (三一新書)、1982年
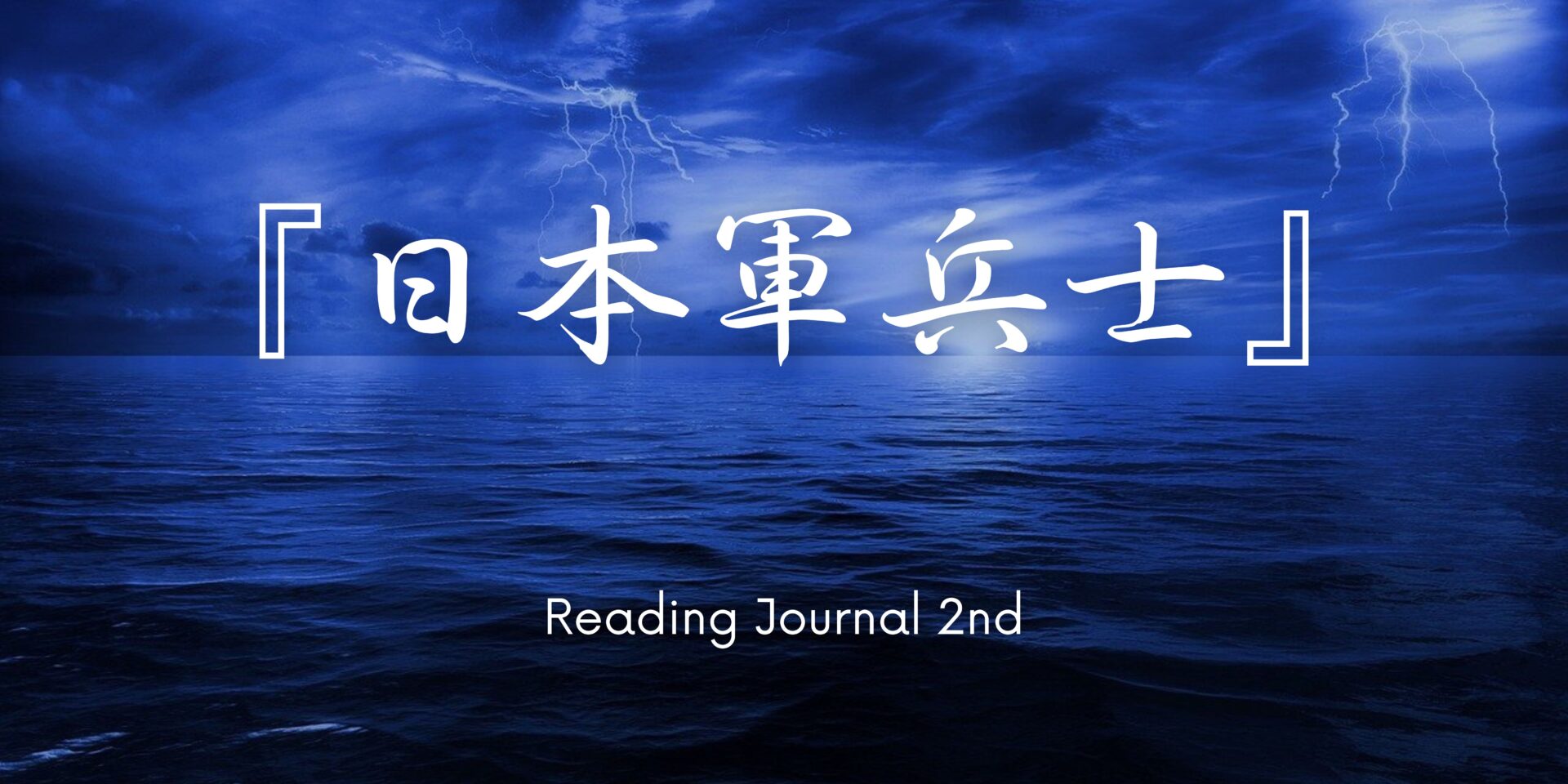


コメント