『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
七 ヨブの立場と友人の立場(前半)
今日から、「七 ヨブの立場と友人の立場」である。前章「友人の説得」(“前半”、“後半”)では、伝統的な賞罰応報的な立場から友人がヨブを説得した。しかし、ヨブのおかれている状態は、その逆であった。
それを受けて第七章では、苦難の当事者・役者であるヨブの立場と、あくまでも観客の立場である友人の立場の違いを問題とする。第七章も前半と後半に分けてまとめるとする。それでは、読み始めよう。
ヨブの訴え
友人の説得を受けたヨブは、次のように答える。
たといわたしは正しくても、
わたしの口はわたしを罪ある者とする。
たといわたしは罪がなくても、
彼はわたしを曲った者とする。
わたしは罪がない、しかしわたしは自分を知らない。
わたしは自分の命をいとう。
皆同一である。それ故、わたしは言う、
『彼は罪のない者と悪しき者とを
共に滅ぼされるのだ』と。(九ノ二〇―二二)
冒頭の二行目に「わたしの口はわたしを罪ある者とする」とあるが、「彼(神)の口は・・・」とする方がよい。原文はただ「口が・・・」である。(抜粋)
ヨブはこのように善悪無差別の錯乱状態に陥っていた。我々は順境の時は、世界の秩序という問題に冷静に客観的に取られるが、一度逆境に陥ると、そのような冷静な見方を失ってします。
実はヨブと友人の発言の相違はこのようなところに原因している。(抜粋)
善には善という応報的賞罰主義は友人には当然なことであるが、ヨブにとっては当然でも自明なことでもなくなっている。
これを著者は、演劇の観客と役者にたとえている。つまり友人は演劇を見る観客で、演ぜられている悲劇喜劇を楽しんでいるが、ヨブは観客でなくその舞台の俳優である。
健康者は、病人の苦悩に同情することはできても、それを実感することは困難である。そのため、ヨブが訴える不平や抗議は、友人からすると無い物ねだり、無理な注文に思われる。人間は他人と真に苦痛を共にすることは不可能である。ヨブと友人との喰い違いはそのあたりにある。
ここで著者は、このように真に苦痛を共にすることは不可能であることを知ったうえで寄り添うことが重要であるとしている。
例えば我々が健康な場合、病人とまったく同じ心理になることは不可能である。しかしせめて病人の立場に立って考えるように努める。しかもそれが非常に困難であり、否、不可能であることを承知の上でそのように努めることが肝要であろう。もっと具体的にいえばまず病人が苦痛を訴えることを良く聴いてやる。病人に頭から説教じみたことを語るのではなく、彼の不平、不満、悲しさ、苦しさ、それが如何に聞きづらいことであっても、寛容と真実をもって心から聴くということがまず考えられるべきことであり、そのことにより病者と健康者の会話の通路が開かれてくるのだと思う。(抜粋)
ここに書いてあることは、なるほどって思った。カウンセリングなどでは、”傾聴法“、つまり人のいうことを聴くという技術が重要である。さらにコーチングなどの本を読んでも同じようなことがいわれる。
「なるほど、そんなもんなのかなぁ~」と思っていたが、つまりはこのような理屈であるんですね。ガッテン!ガッテン!ガッテン!って感じですね
「人が神の前に正しくあり得ようか」エリパズの言葉
ここで著者は、次のエリパズの言葉に注目している。
人は神の前に正しくあり得ようか。
人はその造り主の前に清くあり得ようか。
見よ、彼はそのしもべさえ頼みとせず、その天使をも誤れる者とみなされる。(四ノ一七、一八)(抜粋)
この「人は神の前に正しくあり得ようか。人はその造り主の前に清くあり得ようか。」は、つまり「人間とは弱いものである」という意味である。そして神は天使さえも信頼を寄せていないと言っている。そして同じことを友人のビルダデもいい、さらにヨブ自身も
しかし人はどうして神の前に正しくあり得ようか、
よし彼と争おうとしても、
千に一つも答えることができない。(九ノ二、三)(抜粋)
と、同じようなことを言っている。
しかし、ここで重要なのは、友人とヨブではその響きが違うことである。
ヨブは自分が完全に正しとは言っていない。プロローグに「ヨブは全くかつ正しくあった」(ココ参照)と言われるが、これは神の言葉であって、ヨブ自身の言葉ではない。ヨブは自分が信仰的に、道徳的に完全無欠な人間だとは何処にも言っていない。
この友人とヨブとの言葉の響きの違いは、観客と俳優の声の違いである。ヨブには友人からの慰めの言葉、励ましの言葉、戒めの言葉は、その一つ一つが心に実感として響いてこない。
エリパズの二つの「拠り所」とその根拠
このエリパズの言葉には、二つのよりどころがあった。
- 善人は栄え、悪人は滅びるという原則
- 人間は皆汚れており、罪深い。そしてそのような人間に対して神の刑罰が下り、災禍に出会うのは当然だという見方
ここで著者は、エリパズの「拠り所」の根拠について言及している。
さてわたしに言葉がひそかに臨んだ、
わたしの耳はそのささやきを聞いた。
すなわち人の熟眠するころ、
夜の幻によって思い乱れている時、
恐れがわたしに臨んだので、おののき、
わたしの骨はことごとく震えた。
時に霊があって、わたしの顔の前を過ぎたので、
わたしは身の毛がよだった。
そのものは立ちどまったが、
わたしはその姿を見分けることができなかった。
一つのかたちがわたしの目の前にあった、
わたしは静かな声を聞いた。(四ノ一二―一六)(抜粋)
この言葉はエリパズの神秘体験を語っているものである。つまりエリパズがヨブに語った言葉の根拠の一つは、このような体験である。そして、今一つは
わたしはあなたに語ろう、聞くがよい。
わたしは自分の見たことを述べよう。
これは知者たちがその先祖たちから受けて、
隠すこところなく語り伝えたものである。(一五ノ一七、一八)(抜粋)
とあるように、自分が「見たこと」、「知者たちが先祖たちから受けて語り伝えたもの」が根拠である。
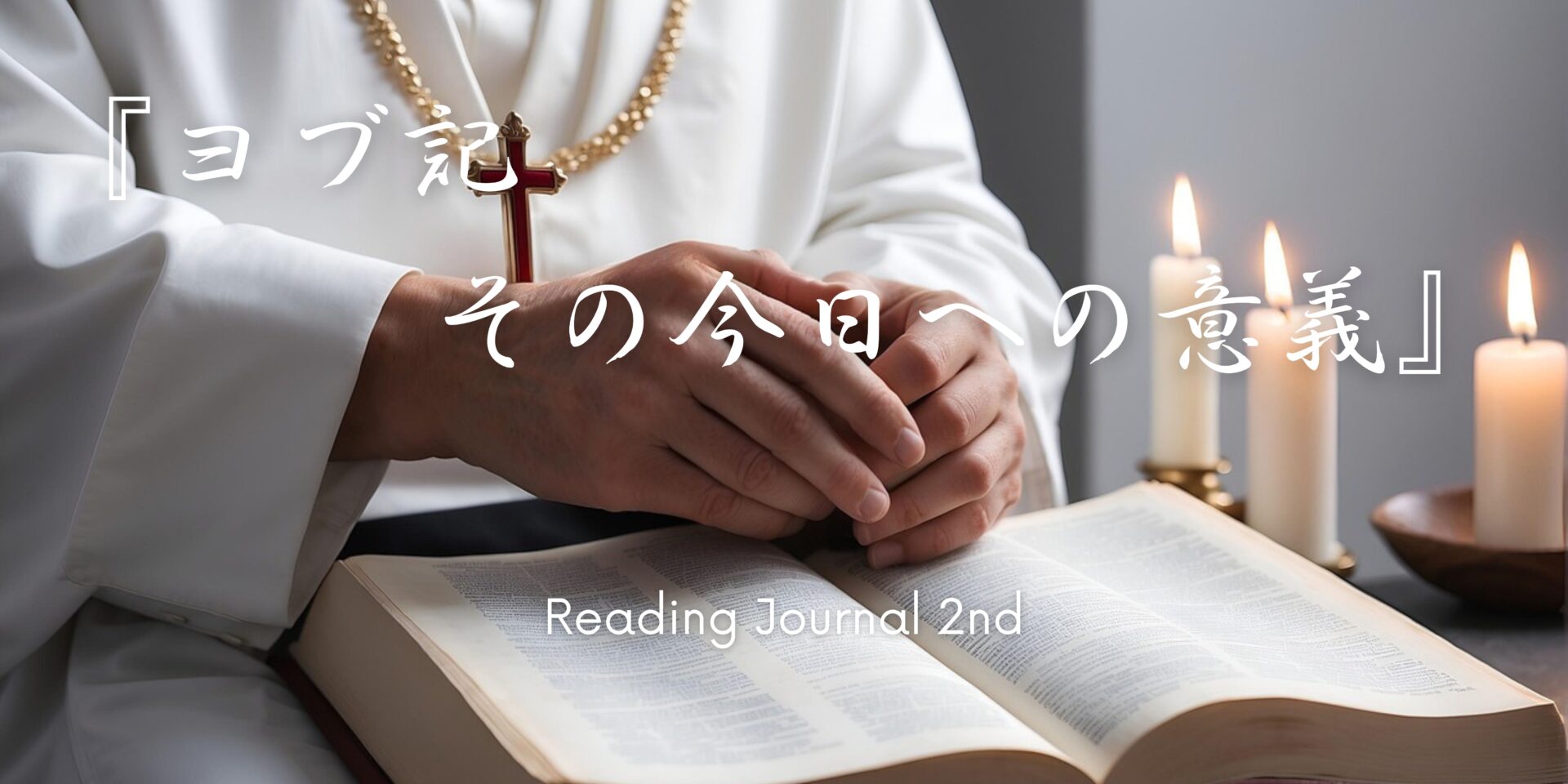


コメント