「漱石」 三浦 雅士 著
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出;2008-10-17)
第二章 捨て子は自殺を考える - 『吾輩は猫である』
漱石の出生の秘密を知った後で、『吾輩は猫である』を読み返すと胸に迫ってくるものがある。この小説では主人公は猫であり、それも捨て猫、さらに言えば殺されかけた猫である。
漱石はこの猫を通して自分自身を観察している笑っているのである。
著者は、『吾輩は猫である』の主題である、笑いや自殺そして狂気の根底にやはり「母に愛されなかった子」とものが潜んでいると考えている。
『吾輩は猫である』の重要な主題のひとつが自殺であることは明らかである。全編にわたって自殺の主題が見え隠れする。
諸先生の説に従えば人間の運命は自殺に帰するそうだ、と、猫は思う。こうして、繰り返しますが、『吾輩は猫である』の最後に猫の自殺で幕を閉じることになります。小説を一貫している主題が自殺であることはまぎれもありません。(抜粋)
漱石の中には、人間の運命は自殺に帰するという考え方が抜きがたくあった。これは、母に愛されなかったから死を選ぶというような次元ではなく、自殺は人間の意識に必然と考えていた。
自殺について考えてみれば、自分で自分を殺すということは、原理的に不可能であり、これを達成しようとすれば死ぬ自分と殺す自分とは他者になる必要がある。
自殺しようとしている人間は、自分の人生という舞台の観客の立場に立って、自分という主人公に死を命じているだけだからです。
とはいえ、ここにも、人間の驚くべき特性が示されている。観客の立場というその立場は、その人間にとって永遠なのだといいうことです。
小学生は簡単に自殺すると言われます。日常行為のように自殺する。自殺しても、自分という現象は持続すると思っているのです。(抜粋)
自殺が行われるには、自分が他者により成立している必要がある。ではこの他者は、どこからやってくるのか、それは母からやってくると考えるほかはない。母は人にとって初めての他者であり、母の視線の先を自分として引き受けることにより自分が始まるのである。
漱石は自分が母に愛されていなかったのではないかという疑いを終世、払拭できなかった。母の愛など証明できるものではないのである。そして、母に愛されていないということも同様に証明できるものではない。
愛は証明できない。じつは、証明できないそのことが、母に愛されていなかった子といいう主題の核心である。だからこそ、笑いや自殺や狂気を引き寄せもするのだ。(抜粋)
『吾輩は猫である』を貫く主題が自殺であることは疑いもないことだが、これは、母に向かって、じゃあ、消えてやるよと言うときの仕組みときわめて似ている。つまり、母に顔を見たくないといわれ、じゃあ消えてやるよと言う自分は、自分ではなく自分のなかの母に所属しているのである。自分は母に愛されていないという疑うことは母の身になって初めてできることなのである。
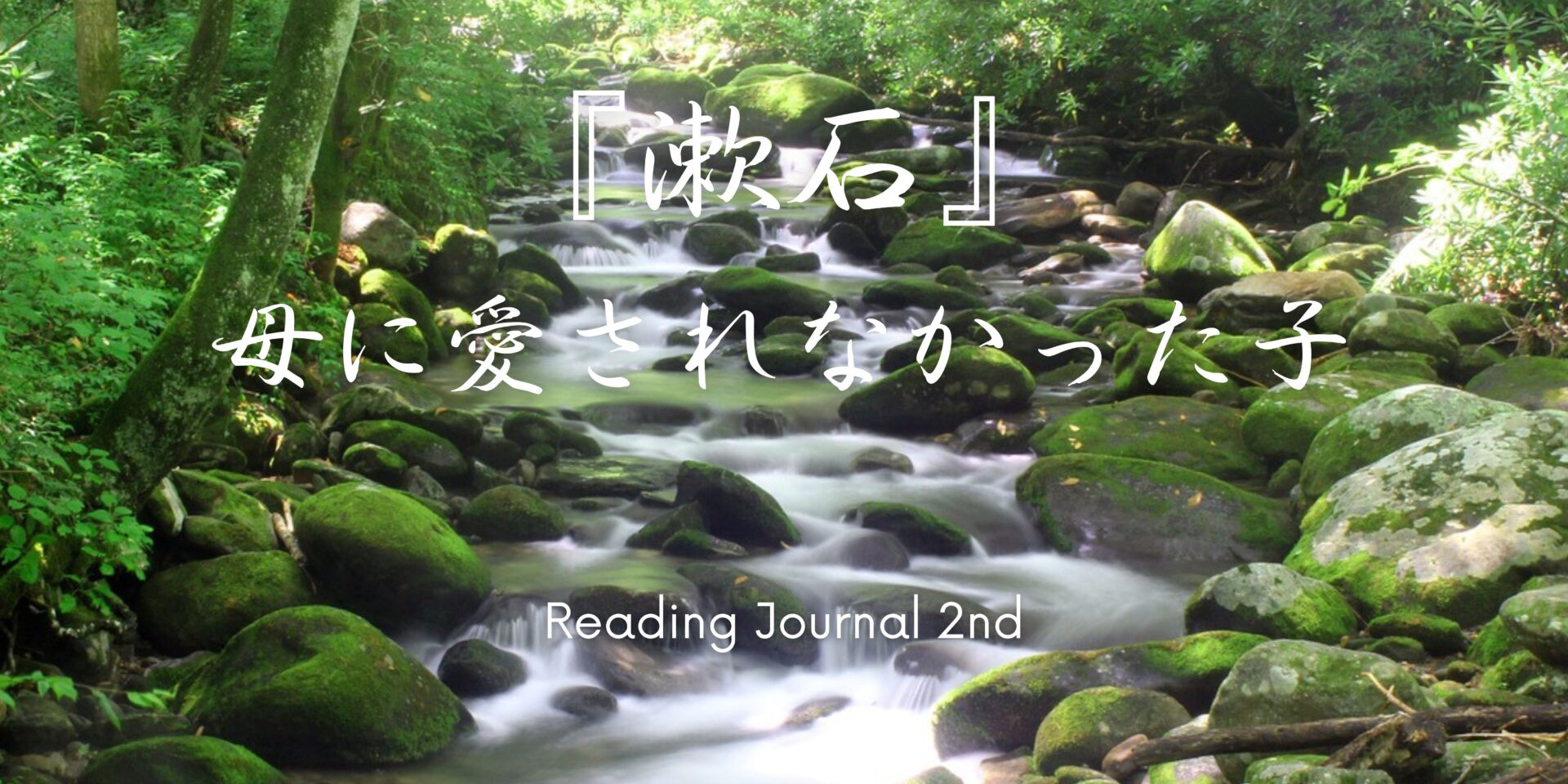


コメント