少しずつ[再掲載]している昔のブログ[Reading Journal 1st]ですが、今回は『漱石』にしてみようかな?と思いました。いや、思っただけですけどもね。
(2025年10月5日)
「漱石」母に愛されなかった子
三浦 雅士 著 岩波書店(岩波新書1129) 2008 740円+税
[Reading Journal 1st:再掲載]
(初出:2008-10-16)
第一章 母に愛されなかった子 - 『坊ちゃん』
漱石は母に愛されなかった子だった。少なくとも漱石はそう思っていた。そんなことはたとえば『坊ちゃん』を読めばすぐに分かります。(抜粋)
子供は、幼年時代に自分が親、とりわけ母親に愛されていないのではないかと一度は疑う。しかし、この疑いは、すぐに自分で自分に隠すことで覆い隠される。母に愛されていないのではという疑いは、子供にとっては死を意味するからである。
にもかかわらず、母の愛を疑い、その疑いを覆い隠す。(抜粋)
本書の目的は、どうしてそのような事をするのかを、漱石を手がかりに考える、あるいは、そのことを手がかりに漱石について考えることである。
坊ちゃんは父にも母にも愛されなかったが、長く奉公していた清という下女だけは坊ちゃんを愛してくれた。これは父母の向き合い方と正反対である。
坊ちゃんの言い方を借りれば、一方は教育のある愛、他方は教育のない愛、つまり理性的な愛と盲目的な愛ということになるが、子供は少なくとも三、四歳くらいまでは清のような愛、愛することだけを目的にするような無私の愛を必要とするものです。あなたがいるということは、いるというそのことだけで十分いいことなのだと、言い含めるような愛情がぜひとも必要とする。そうでなければ、子供は、自分はここにいないほうがいいのではないかと感じてしまう。(抜粋)
漱石がそう感じていた事は、『坊ちゃん』の母の死をめぐるエピソードで明らかである。
エピソードは坊ちゃんが母が病気で死ぬ二三日前に台所で宙返りをして肋骨を打って痛がった。そのことで母がたいそう怒って、お前のようなものは顔も見たくないというので、親類の家に泊まりに行っているうちに母が死んだというものである。
怒ったときに、顔も見たくないというのは怒りの強さを表すレトリックで誰も本当にそうだとは思わない、しかし、坊ちゃんは「じゃあ、目の前から消えてやるよ」とばかりに親類の家に行ってしまう。それは、僻んでいると受け取られても仕方ない行動である。
台所で宙返りをした行動も本当は、父母の気を引くための行為であり、愛されていると信じたい、そのことを確かめたいとい行為である。しかし、そのことが裏目に出てしまった。
じっさい、漱石自身、親類の家に泊まりに行って母の臨終に立ち会っていないのです。親類へ行っていて立ち会えなかったと、後年になって書いている。もちろん仔細に書かれているわけではないが、しかし心理的にはこれにたぐいすることがあったと十分想像できる。(抜粋)
著者は、漱石は坊ちゃんを借りて、自分の母への心理的なこだわりを書いていると言っている。
しかしここで、坊ちゃんが父母に愛されなかったとしても、それが単純に漱石に当てはまるかという疑問が湧いてくる。小説は小説であり漱石は漱石であるからである。著者はその疑問に対して
四国に赴任してからの坊ちゃんの行動は、おしなべて、母の臨終のときに坊ちゃんのとった行動の焼き直しなのだということになれば、話は違うでしょう。(抜粋)
と言っている。いたずらをして、母に顔も見たくないと怒られたときに「じゃあ、消えてやるよ」とばかりに親類の家に泊まりに行った行動の焼き直しだというのである。
まず、松山に来てから中学の校長に、生徒の模範になれ徳を及ぼせと訓戒されたときに、坊ちゃんは、そんなことはできないので辞令はお返しすると言うくだりがある。もちろん校長は建前として言っているのだが、それを額面どうりに受け取り辞令を返そうとするのは、基本的に母に顔を見たくないといわれて、本当に親類の家に行ってしまう行動と同じである。
また、坊ちゃんは松山の地についてから、喧嘩腰な態度で臨むのも、自分が愛されていない、愛してくれなくて当然であるという態度であり、それは、愛されて当然なのに愛されていないという不満の表れである。
坊ちゃんは、
評価にはぜんぜんこだわっていないとことさらに言うわけだが、これはもちろんまったく逆である。評価にこだわりすぎているからこそ、いつだって消えてやるという逃げ道を作って、評価そのものを無効にしようとしているのである。(抜粋)
坊ちゃんは「おやじはちっともおれを可愛がってくれなかった、母は兄ばかり贔屓にしていた」と言っているが、漱石自身もそう書きしるして不自然でない境遇にあった。
漱石は、母が晩年になってできた末っ子であるが、生まれると間もなく里子にだされた。姉が可哀想に思い家に連れて帰ってきたが、その後漱石は新たな家に養子に出され、養家のごたごたで実家に帰るのは小学校に上がってからであった。漱石はどこにも居場所がない状態で幼少期を過ごしたのである。
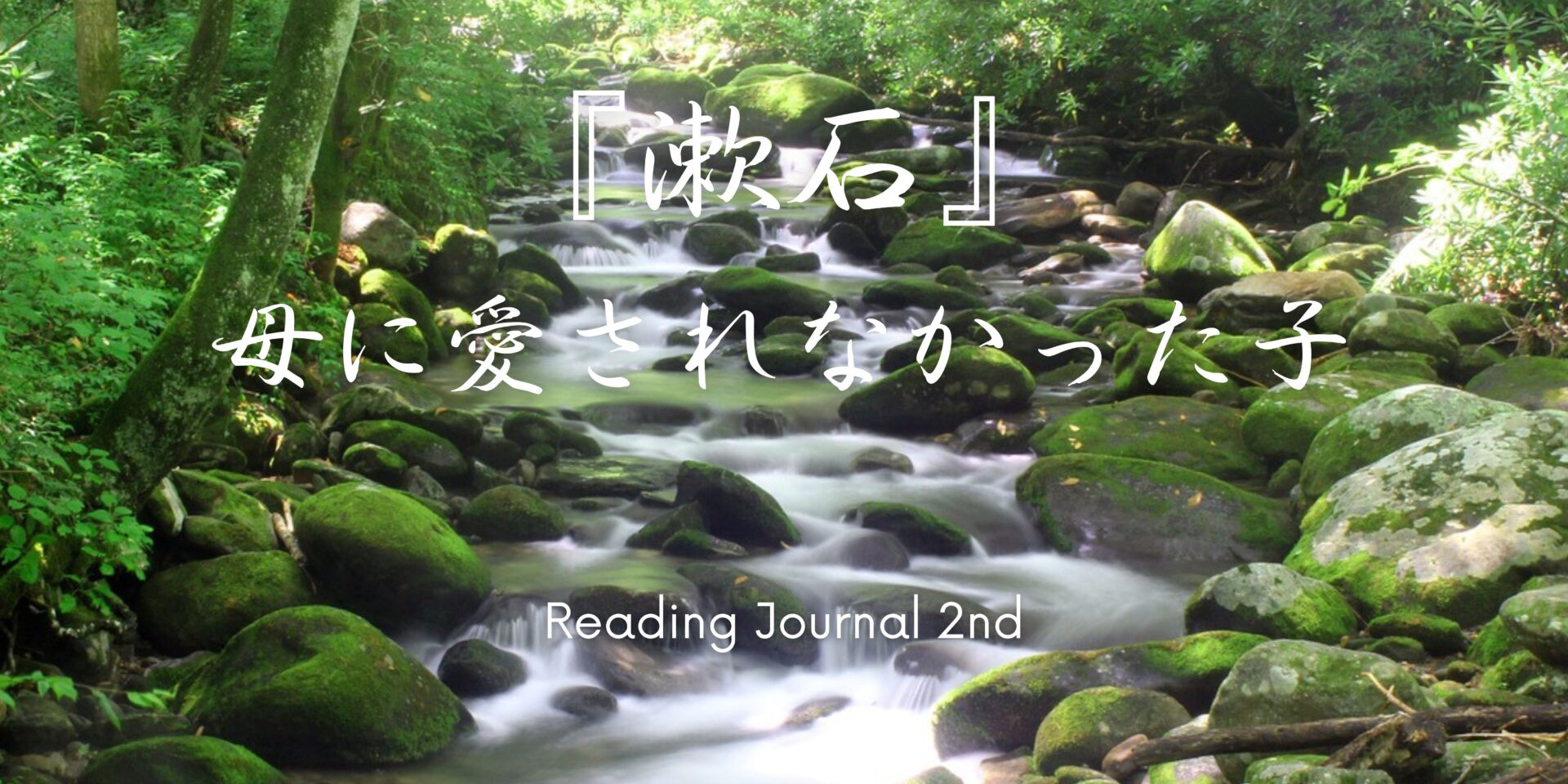
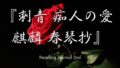

コメント