『日本仏教再入門』 末木 文美士 編著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第十四章 見えざる世界 日本仏教の深層4(末木 文美士) (その1)
今日から「第十四章 見えざる世界」に入る。ここでは、近代的な世界観、つまり合理的で科学的に理解できる領域のみを実在とする世界観ではなく、それを超えた非合理な見えざる世界について考察する。そして日本においてこの見えざる世界と中心的に関わってきたのは仏教である。
まず第一節で「顕と冥の世界観、歴史観」を取り扱い、そして第二節でキリスト教、儒教などとの関係や神道による見えざる世界の復権を取り扱う。そして最後に第三節において、近代日本でこの見えざる世界を探求した二人の思想家を取り上げる。
第十四章も各節ごとにまとめることにする。今日のところは、「顕と冥の世界」である。それでは読み始めよう。
1.顕と冥の世界
現世主義に抗して
ここでは、まず現在のような合理主義の時代にあえて宗教の問題を考えるかということについての著者の考えが示されている。
近代は、科学的合理主義の時代であり、宗教は時代遅れの迷信で、次第に過去のものとなり、人類は宗教なしも幸福になると考えられている。宗教は「アヘン」とまで言われ批判され、宗教学者の間でも近代化が進むと、俗世化によって宗教の影響力は弱まっていくという説が有力な時期があった。
しかし、このような科学技術を無条件に賛美できなくなっているのも確実である。原子力発電所の事故や遺伝子治療などの問題を考えれば、合理化が進むと宗教が消滅するという単純なものでないことが解る。さらに冷戦終了後の世界は、むしろ宗教の問題が大きくなってきている。
科学技術や合理主義では解決できない問題を宗教がどう扱ってきたかの検証が必要となっている。(抜粋)
顕と冥の世界観 — 「愚管抄」の場合
宗教は目に見える現実だけでなく、その裏にある見えないものとの関係を重視する。それを自覚的に論じるために使われていた術語に「顕」と「冥」がある。
- 顕:目に見える世界
- 冥(幽冥):顕の奥にある目に見えない世界
この顕と冥の対立概念は、中国仏教では広く使われ「冥顕」という術語は天台宗開祖の天台智顗の著作『法華玄義』にもみられる。
この語を使って歴史を解明しようとしたのが慈円だった。慈円は歴史を貫く法則がどのようなものかを考え、日本で最初の歴史哲学書『愚管抄』を書いた。そして、歴史と貫く「道理」を求めて「顕」と「冥」の関係というべき問題を追究した。
慈円は日本の歴史の展開を七段階に分けた。
- 第一段階:「冥と顕が和合して、道理を道理として通す」(過去の理想的な状態:神武から一三代まで)
- 第二段階:「冥の道理は次第に移り変わっていくが、顕の人はそれを理解できない」(仲哀~欽明)
- 第三段階:「顕では道理として誰もが認めても、冥衆[みょうしゅう]の御心にかなわない」(敏達~後一条の道長時代まで)
- 第四段階以降:「末の世」となり、もはや「冥」は直接かかわることが無くなり、「今は道理ということはないであろうか」という時代
ここで「冥」は日本の神々が中心であるが、死者の霊などのさまざまな「冥」の世界の者たちが考えられている。『愚管抄』では、「平家の怨霊」が大きな問題となっている。
このような世界観の根底には、仏教的な世界転換の思想がある。仏教では、世界は「成劫」「住劫」「壊劫」「空劫」、つまり世界が成立し、留まり、崩壊し、何もなくなる、という四つの時期が繰り返すと考えている。
現在の歴史もその中の一部分に過ぎない。天皇の継承もまた永遠ではなく、百王で終わるという。その終末まで、できるだけ秩序あるよい体制を維持していかなければならないというのが、『愚管抄』の政治論である。
王法と仏教
このような秩序を維持するためには仏法の力が重要となる。(抜粋)
中世は王法仏法相依の時代とされ、王法と仏法は車の両輪に喩えられた。仏法は「冥」の留まらず荘園による経済力や僧兵による軍事力をもち「顕」の世界でも一大政治勢力となっていた。
鎌倉時代になると、中世の八宗からなる顕密仏教に対して「禅」と「浄土教」という新しい仏教運動が盛んになる。十三世紀末になるとそれを含めて十宗体制となる。その中で王法・仏法の相依関係も変わってくる。日蓮宗において仏法は世俗の王法を超えたもの考えられた。また宗教と政治の一元化の流れとして、中世の終わりには、一向一揆やキリスト教の広がりなども現れる。
冥顕論の変転
冥と顕の理論は、『愚管抄』以降も変化を遂げる。北畠親房の『神皇正統記』(ココ参照)では、『愚管抄』の下降史観に対して、「神道」の思想に基づき天皇の永続性を認められるようになる。また伊勢神道に基づく神道理論を確立に尽力した慈遍は、『旧事本紀玄義』において、『愚管抄』の冥顕思想を展開した。
慈遍によると、もともと冥と顕の世界は隔たったものではなかったが、陰陽が分かれる中で冥と顕との区別が生まれたという。顕が生の世界であるのに対して、冥は死の世界である。(抜粋)
さらに仏教からの神道の自立を図った、吉田兼倶(ココ参照)の『唯一神道名法要集』では、仏法を「顕露の教え」とし神道を「隠幽の教え」と呼んでいる。
反本地垂迹説に基づいて、神道のほうが仏教より根源の隠れた教えと位置づけられている。(抜粋)
この世界の奥にある見えざる世界は、日本人の世界観の中で大きな役割を果たしてきた。そして、中世では、冥と顕という形を取り共通認識となっていた。


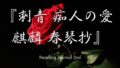
コメント