『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
五 ヨブの嘆き
今日のところは、「五 ヨブの嘆き」である。ヨブは、三つの試練を乗り越えサタンに勝利した(ココとココ参照)。ここからはプロローグの部分で用いられた散文ではなく、詩文となる。著者のいう絵画の部分に移る。今日のところは、その冒頭で、ヨブは、訪ねてきた三人の友人をまえに「自分の生まれた日を呪う」というのである。それでは読み始めよう。
暗黒を求めるヨブと光を賜う神
ここで、ヨブの独白が引用されている。
わたしの生まれた日は滅びうせよ。
「男の子が胎にやどった」と言った夜も、
そのようになれ。
その日は暗くなるように、
神が上からこれらを顧みられないように、
光がこれを照らさないように。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日をのろう者がこれをのろうように、
レビヤタンを奮い起こす巧な者が、
これをのろうように。(三ノ三―八)(抜粋)
ヨブは、まず自分の生まれた日を呪った。ここで「(神秘な怪獣)のレビヤタンを奮い起こす巧な者」や「日をのろう者」は、一種の魔術師を指す。
さらに引用が続く。
なにゆえ、わたしは胎から出て、死ななかったのか、
腹から出てとき息が絶えなかったのか、
なにゆえひざがわたしを受けたのか、
なにゆえ乳房があって
わたしはそれを吸ったのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なにゆえわたしは人知れずおりる胎児の如く
光を見ないみどり児のようでなかったのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なにゆえ、悩む者に光を賜い、
心の苦しむ者に命を賜ったのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なにゆえ、その道が隠された人に、
神がまがきをめぐらされたの人に光を賜わるのか。(三ノ一一-二三)(抜粋)
ヨブは、どうして悲惨な不幸に出会わなければならなかったかを自分の誕生にまでさかのぼって考えている。そして、その疑念を何故という言葉を重ねて訴えた。
このように自分の生を否定するほどの痛ましい疑念や苦悩は、大きい小さい、深い浅いの差はあっても人間の一生の間に一度や二度は必ず経験することであると、著者は言っている。
そして、ヨブ記では苦難の歴史を歩んできたへブル人だけの苦しみを記しているのではなく(ココ参照)、時代や場所を越えたすべての人間の苦悩という普遍的な問題が問われている。それは主人公のヨブを始め登場人物がヘブル人でなく外国人であることからもわかる(ココ参照)。
ここの「わたしの生まれた日は滅びうせよ」という部分は、同じく旧約聖書の『コヘレトの言葉』を思い出させる。「すでに死んだ人を、幸いと言おう」、「生まれて来なかった者こそが最も幸いではないか」と言っている(ココを参照)。
ヨブのように自分の誕生を呪うような悲劇は、いつの時代でも消えることはない。ここで著者は、『赤ひげ診療譚』の中の話を例にてこのような悲劇について説明している。
なにゆえ悩む者に光を賜い
心の苦しむ者に命を賜ったのか。
このような人は死を望んでも来ない。
これを求むることは隠れた宝を
掘るよりもはなはだしい。
彼は墓を見出すとき、非常に喜び楽しむものだ。(三ノ二〇-二二)(抜粋)
この言葉は、友人に語るというよりも神に訴えていると叫びと解するべきであると著者は指摘している。
ヨブは、苦しみに耐えきれず、自分の生まれたことを呪い、死を乞い願わざるおえない状況に陥っている。しかし、神は、その願いをかなえてはくれない。これは神の恵みなのか、愛なのか、むしろ神の残忍、冷酷なる愛ではないかと考えている。
ヨブの言葉のうちにも恵みの神受の神として今まで信じて来た、その神の残忍冷酷、それは神の不合理であり、それに対してヨブは今強く反撥しているわけである。(抜粋)
ヨブが求めているのは、光ではなく暗黒であり、その中で憩うことである。しかし、神はこのようなヨブに光を賜い、命を賜う。これは神の恵みでなく、愛でなく、むしろ残忍であり冷酷であるとヨブは感じている。
旧約聖書における生死の問題について
ここからしばらく旧約聖書は正詩の問題を如何に考えているのかに触れて置きたい。(抜粋)
まず著者は、今日の「生命の尊厳」や「人命の尊重」という思想は、私見と断ったうえで、アルバート・シュワイツァーの生命観に発するのではないかとしている。シュワイツァーは、この概念を、インドの教えから学んだとしている。
しかるに生命の尊厳という言葉は直接聖書から出ているものではない。(抜粋)
聖書では、生命は神が創造し、それを人間、動物、そして植物に与えた。その故、すべての生命が、ことに人間の生命は神のものであり、従って神の許しなくしては自己の生命といえどもそれを自由にすることはできない。聖書ではそのように考える。
例のモーゼの十戒にある「汝殺すなかれ」の禁令はただ他人の生命を奪うことを禁じているのみならず、自己の生命についてもまたしかりといわねばならぬ。(抜粋)
そして、著者はこの禁令は、積極的に見ると「汝生きよ」ということになり、キリスト教が自殺をもって罪とする理由であると説明している。
自分の生命は自分に内在するものであるからこれを生かすのも、殺すのも人間の自由だという考え方は聖書からは生まれてこない。(抜粋)
聖書の教えでは、人間が生きるということは生命の創造者であり賦与者である、神への責任であり、任務である。著者はこの命令は人間は誰でもことにキリスト教徒は厳粛に受けとめ守らなければならないと言っている。
人は生きることのほうが、死ぬよりもはるかに苦しいときがある。しかし、みずからの死によって人間の責任が解放されたわけではない。著者はやや逆説的としながら、聖書の「いのち」はという言葉は、「生命の尊厳」というよりは「生命への執着」と称してもよいと言っている。神の命令を絶対的なものとし、それに自己を服従させるための意思や努力から生まれてくる。
さらに著者は、「生命の尊厳」との関わりで、次のように補足している。旧約聖書では「聖戦」の名により敵の生命を奪うことを認めていて、さらに家畜を殺すことにより人間が生きることを認めている。これは生命の尊厳と明らかに反しているが、それは別の問題であるので、ここでは取り扱わないと言っている。
ヨブと生死の問題
ヨブは、その惨憺たる状況において死を乞い願った。しかし、神はそれを許さず、却って命を与え、光を賜った。ヨブはこれに激しく抗議をしたが、この抗議なしにはこの問題の最後における真の解決は与えられなかったと著者は言っている。
ヨブは生きる意義を全く失ってしまってもなお神に命令に従い、生の戦いを通して最後的な解決を得る。
ある意味でヨブが神の意志に服したということは反面から見れば彼自身に対して忠実であったということになる。「我々自身の生命に対して負う尊厳は我々自身に対して忠実であることなくしては偽善となるであろう」といっているシュワイツァーの言葉は深い意味を持つ。(抜粋)
関連図書:
山本周五郎(著)『赤ひげ診療譚』、新潮社(新潮文庫)、2019年
小友 聡(著)『コヘレトの言葉を読もう 「生きよ」と呼びかける書』 、日本キリスト教出版、2019年
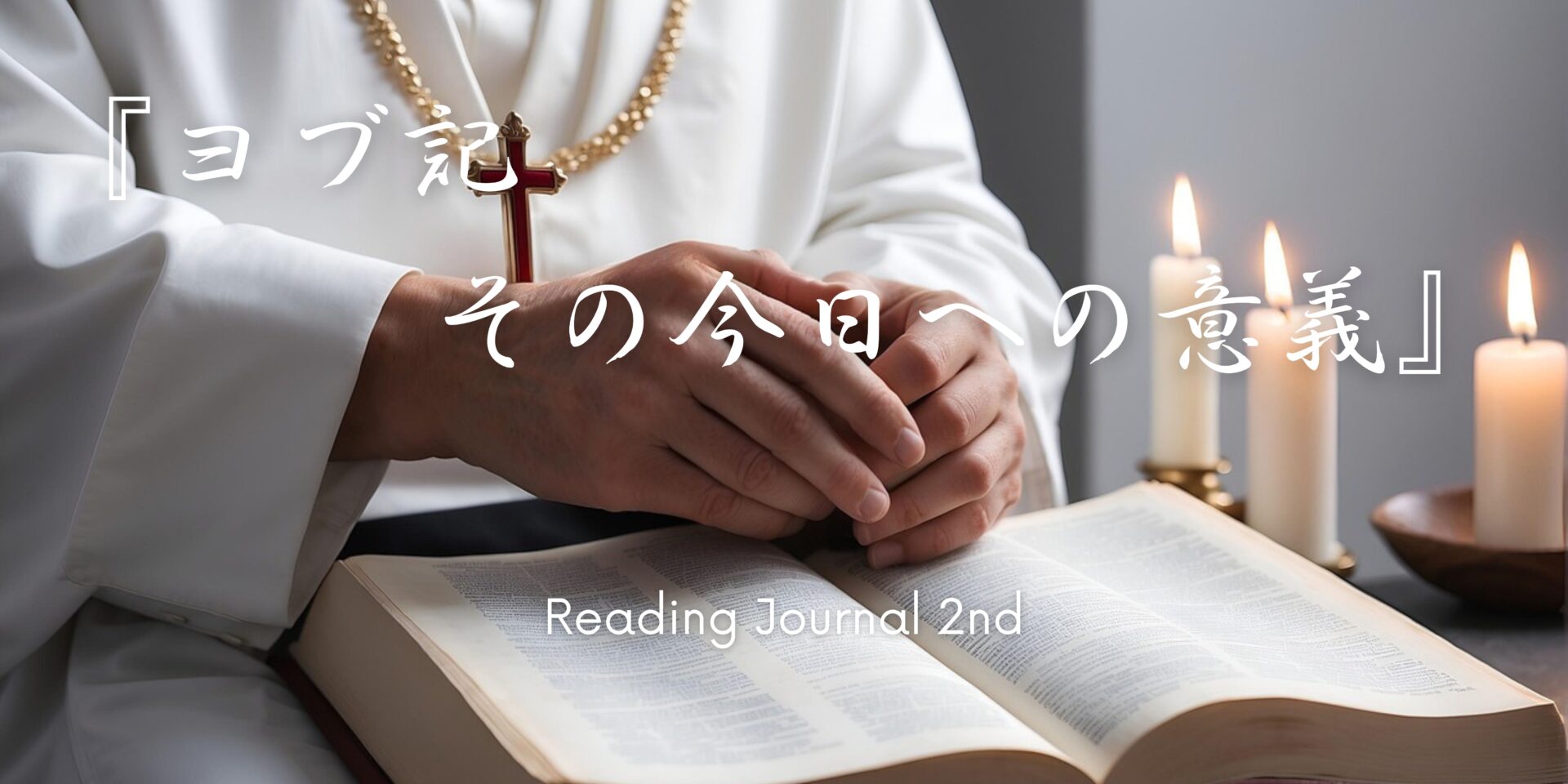


コメント