『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
四 義人ヨブ、その試練(二)
今日のところは、「四 義人ヨブ、その試練(二)」である。前回は、ヨブの第一の試練と第二の試練、つまりサタンによって全財産を奪われ、妻以外の家族を奪われた。しかしヨブは、「罪を犯さず、愚かなことをいわない」ことで、神の勝利となる。
今日のところは、ヨブへ与えられた第三の試練についてである。第一と第二の試練を乗り越えたヨブを神が賞賛した、しかし、サタンは尚も反論する。「人間は自分の命のためには持っているすべてを投げ出す」というのである。すると神は、ヨブをサタンに委ねる。それでは、読み始めよう。
神の勝利とサタンの反論
第一、第二の試練においてヨブはサタンに勝った。ヨブの勝利は神の勝利でもある。
そして第二回の会議で神は「お前(サタン)はわたし(ヤーウェ)を勧めて、ゆえなく彼(ヨブ)を滅ぼそうとしたが、彼はなお堅くおのれを全うした」といいヨブを賞賛した。
ここで「ゆえなく」は原語では、「いたずらに」(ヒーナム)(ココ参照)と全くおんなじ語でヨブ記のプロローグにおいてキー・ワードとなる語である。
サタンは反論した「皮には皮をもってします。人は自分の命のためにその持っているすべての物を与えます」。
ここで「皮には皮をもってします」について、著者は、さまざまな解釈があるが、ことわざのようなもの、日本語での枕詞のようなものであるとしている。
つまりサタンは、人は命のためならば、他のいかなるものも犠牲にすると考えている。人間はそのようなエゴイスティックなものであると考えている。
そしてサタンは「しかし今あなたの手を伸べてヨブの骨と肉とを打ってごらんなさい」と言った。
ここで、「骨と肉を打つ」とは、彼の苦痛のきわまる重病をさす。そうすれば、苦痛に耐えかねて今度こそ神を呪い、決別するだろうとサタンは言うのである。
一章で、サタンは、「神は人間のためのものであり、人が自己のために考え出したものであるに過ぎない」、「神は人間の妄想でしかない」、「もし神ありとすれば人間あればこそ神があるのであり、神があって人間があるのではない」、つまり、「人間こそ神の創始者」と考えていることが示された。
これを受けて二章では、「人間は自分本位」であり、「エゴイスティックなもの」「自分自身のために他の一切を犠牲にするのを厭わない」というサタンの人間観を明らかにしている。
このような人間と神とがいかなる関係を持ち得るのか、サタンはそのような問題を提出している。旧約は神中心の信仰によって貫かれている。しかし、現実の人間は自分本位である。この神本意と人間本意の二つの立場が如何に駆る関係にあるのか。このまったく対立する関係は何処で切り結ぶことができるのか、サタンはそれを問題にしている。
人間の持つ財産、家庭、地位、権力、さらには学識や名誉までも、それは衣装であり、それを脱ぎ捨てればエゴそのものとなる。そこに原罪的なものがあり、そのような現在的なものと神がどのように関わりを持つか、サタンはそれを問題にしている。
ヨブの第三の試練と神の勝利
神は、ヨブの生命だけは、触らないようにといって、サタンにヨブを委ねた。するとヨブは、悪性の腫瘍のため昼夜を分けず苦しめられた。それを見た妻は「あなたはなおも堅く保って自分を全うするのですか。神を呪って死になさい」という。この妻の背後にサタンの影を見ると著者は言っている。
この妻の立場から考えると、財産や子どもたちを奪われ、ただ一人頼りとしている夫は、瀕死の重病に苦しんでいる、
信仰とはこれほどまでに大きな犠牲を人間にしいるものであろうか。もしそうならば信仰など持たぬ人間は幸福なのではないか。宗教とは果たして命がけで信ずる価値のあるものか。もしそのようなものであれば信仰は人間を不幸にするばかりである。それ故宗教とか信仰とかはたかだか教養程度に止どむべきではないのか。信仰は人間生命そのものに関わるのか、或は他の教養の如く一つの装飾に過ぎぬのではないのか。(抜粋)
このように考えても不思議はない。このような言葉は、サタンの誘いの言葉だと言える。そして、後の登場する三人の友人のいうところも突き詰めるとサタンの誘いの言葉である。
しかし、ヨブは「あなたの語ることは愚かな女の語るのと同じだ、われわれは神から幸いを受けるのだから災をもうけるべきではないか」と語った。
ここで「愚かな女」の原語(ナーパルの複数)は、「愚」をあらわす語であり、それも知恵、知識がないということではなく、不信仰、不道徳という意味である。
ここで旧約では、知恵は信仰に通じ、愚かは不信仰に通じる。そして愚かものが「神はない」と言った場合、それはわれわれの言う無神論を意味するのではなく、神の存在は認めるが実際には神が無き如く行動すること、つまり「実際的無神論」を行っている。ヨブの妻は、理屈上は神の存在を否定しているのではないが、実際的にそれを否定している。
このヨブの返事は、第三の試練に対するヨブの答えである。この「幸」と「災」もともに神から出る。その一方だけを受け取って他方を拒むわけにはゆかない、ということである。これは一章の終わりの「主が与え主が取られた。主のみ名はほむべきかな」に通じる(ココ参照)。これは、善悪、幸不幸を全体として受け取る、そこにこそ人間にとっての真の祝福があると解してもよいと、著者は言っている。
つまり神からは善悪、幸不幸を全体として受け取る必要があるのに、人間はエゴイストであるから、その一方を受領し、他方を拒否しようとする。それがサタンの考えであるが、それでは、心から神を信じ宗教を奉じていることにはならない。
ヨブの妻に対する答えはサタンに対する勝利の宣言であるが、それはまた神の勝利でもある。(抜粋)
三人の友人の訪問、プロローグの終わり
この後、三章以下はヨブとの友人の論争になるが、サタンはその姿を現すことはない。それは、サタンが友人にその姿をかえているためだと見ることができる。
第二章の最後は、テマン人エリパズ、シュヒ人ブルダデ、ナマア人ソバルの三人が登場する。この三人は皆セム人ではあるが、へブル人ではない、ヨブを始めヨブ記に出てくる人物は旧約固有の民族でないことは注目すべきことである。
彼らは遠方からヨブを慰めるために来るのだが、痛ましく変わってしまったヨブの姿を見て、慰めと励ましの言葉を失ってしまった。
「彼らは目をあげて遠方から見たが、彼のヨブであることを認めがたいほどであったので、声をあげて泣き、めいめい自分の上着を裂き、天に向かって塵をあげ、自分たちの頭の上にまき散らした」(抜粋)
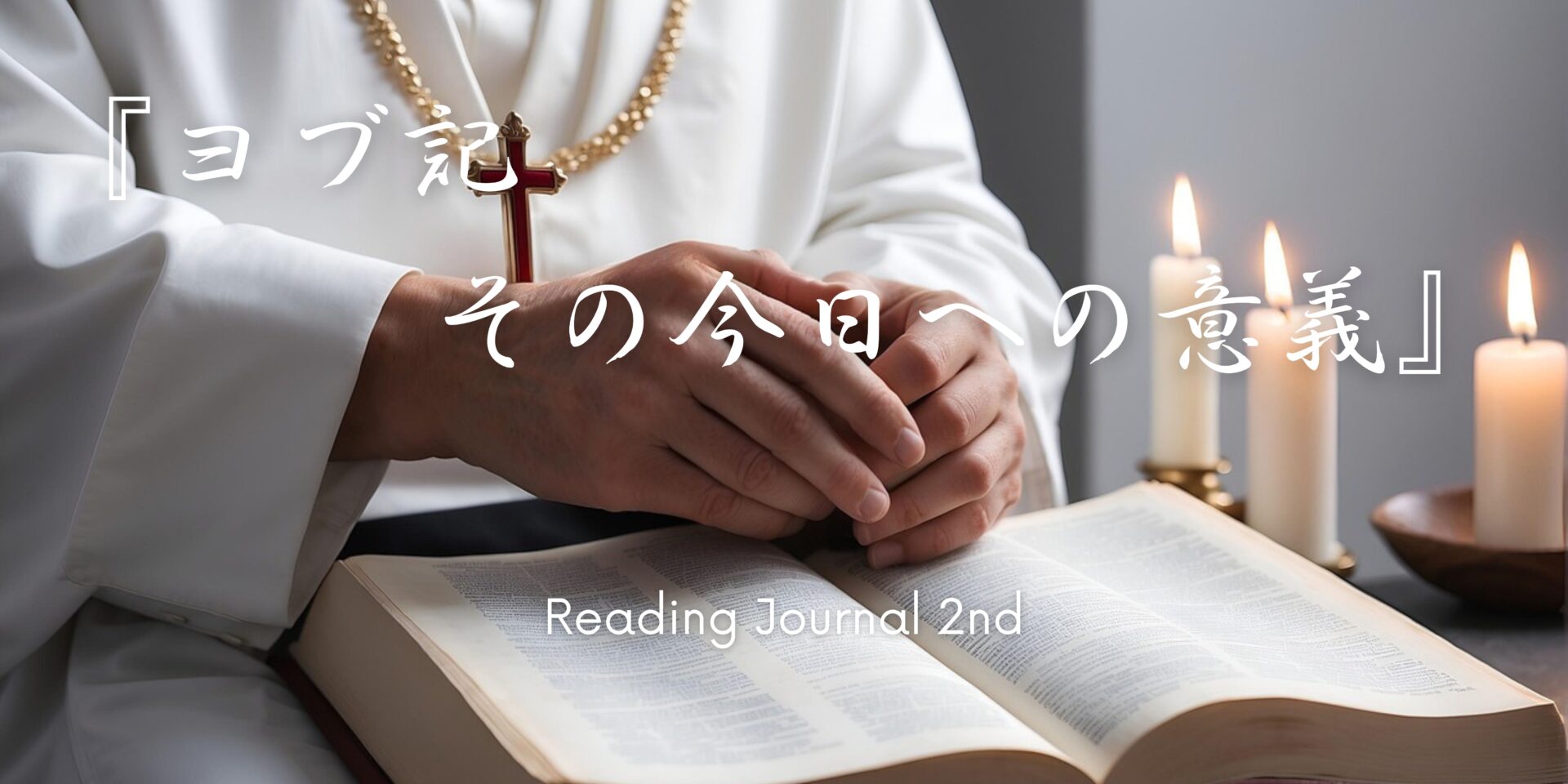


コメント