『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
三 義人ヨブ、その試練(一)
今日のところは、「三 義人ヨブ、その試練(一)」である。「一 旧約におけるヨブ記の位置」及び「二 ヨブ記の構造」は、『旧約聖書』や『ヨブ記』の概説的な話であった。ここより、いよいよ『ヨブ記』を読んでいくことになる。
今日のところ「三 義人ヨブ、その試練(一)」では、『ヨブ記』の第一章の内容について述べられている。つまりヨブの第一の試練と第二の試練についてである。(第三の試練は次節)。「ヨブのひととなりは全く、かつ正しい」という神の言葉にサタンが挑戦する。サタンは、ヨブの全財産を奪い(第一の試練)、幸福な家庭を破壊させる(第二の試練)。それに対してヨブは、「罪を犯さず、愚かなことを言わなかった」。そこには、信仰の深い意味が隠されている。それでは、読み始めよう。
義人ヨブとその幸福な生活
『ヨブ記』は、「ウヅの地にヨブという名の人があった」で始まる。このウヅは、アラビア地方の南エムドにあり、知恵の地として有名であった。そしてエムド人はセム人であるからヨブはセム人である。つまりヨブは、へブル人でもユダヤ人でもない。著者はこれを重要な点であるとしている。また、二章の後半に出てくる三人の友人も、へブル人から見れば外国人である。
へブル人の名には意味があるものが多いが、ヨブという名の意味については、「憎まれた者」「敵を持つ者」「悔い改めた者」「愛された者」などの解釈があるがあるものの、判然としない。
冒頭の言葉に続くのは「ヨブのひととなりは全く、かつ正しく」である。ここで重要なのは「全く(ターム)」である。この言葉は、宗教的、信仰的な意味に用いられ、道徳的な完全を指すものではない。つまり
神とヨブの関係が純粋であったということである。換言すればヨブは神に対して素直であったとか、誠実であったとかいう意に解せられる。(抜粋)
次に「正しい(ツァッディーク)」は、道徳的に正しいという意味である。ヨブ記では、これを「神を恐れ、悪に遠ざかる」と言い直している。
ここで著者は、この「神を恐れる」という言葉について、新約では、神を信ずることを「神を愛する」と言い換えるが、旧約では「神を恐れる」といい、それが信仰の根本的建前だったと指摘している。
これらを要約するとヨブは信仰的にも道徳的にも非の打ちどころがない人物であったということになる。(抜粋)
そしてヨブは、男の子七人、女の子三人、ヨブと妻を加えて一二人の家族であった。そしてヨブは裕福でその財産は家畜の数で表されている。ヨブの一家は非常に裕福であり、親子、兄弟が仲良く親密に暮らしていた。
天上の会議とサタンの登場
ここで場面は天上に移る。神ヤーウェが神の子(天使)たちを集め、天上の会議をするのである。そしてそこにサタンも加わっていた。
このサタンは、現在は「悪魔」と同一視するが、旧約ではサタンは「敵」という意味であり、人間であることもある。ヨブ記のサタンは、神の子の中にいるので一種の天使と考えられる。天使たちはそれぞれ神に仕える定位置を持っていたが、サタンは「地を行きめぐり」と書かれていて、行動範囲は広く、地上の何処へでも自由に行くことができた。そして、他の天使が神や人間の明るい面と交渉を持つものだとすると、サタンは暗い面にかかわりを持ち、検察官のごとく人間の弱点、欠陥、失敗、蹉跌を見つけ、摘発、暴露することを任務としていた。
ここで著者は、旧約ではサタンは神の使者であり、まだ原理的に相対する敵ではない、神とサタンが対立的になるのは旧約以後のことである、と注意している。
神とサタンの対決、信仰の意味
天上の会議において神はサタンに対して「お前はわが僕ヨブのように全くかつ正しく神を恐れ、悪に遠ざかる者はこの地上にはいないではないか。そのことに気づいたか」とヨブを誇った。するとサタンは「ヨブはいたずらに神を恐れましょうか」と答えた。
ここの「いたずらに」(ヒーナム)は、なはだ重要であると、著者は言っている。
サタンは、ヨブは神の求めに応じて敬虔な生活をし、道徳的な行いをする、そして神はその代償としてヨブやヨブの家庭や財産を保護し、ヨブの勤労を祝福している、と言っている。つまり、ヨブの信仰的、道徳的な生活は、それに伴う報酬すなわち反対給付を期待するからであり、また義人であるヨブは神からそのようにできる条件を与えられているからである、と考えている。
つまり宗教とか道徳とかというものはそれが成り立つ条件如何による。(抜粋)
サタンの「いたずらに」という一語は、このように重要な意義を持ち、彼の宗教観、道徳観が示されている。
ここには人間の信仰は神からの反対給付が予期されるときにのみ成り立ち、信仰のための信仰とか道徳の道徳などはない。神のための神、真理のための真理という信仰とか思想は、あり得ない。そのような考え方が示されている。
つまり神を中心とする旧約聖書の伝統的な信仰に対してサタンは根本的に挑戦していることになる。(抜粋)
サタンは神に向かって「あなたがそんなにヨブをお誉めるになるなら、一度あなたの手を伸ばし、彼のすべての財産を撃ってごらんなさい、そうすればヨブは必ずあなたに向かってあなたを呪うでしょう」と言った。
ここで、「呪う」の語は「祝福する」という意味であり、ここでは、それを「呪う」と訳されている。ある者はそれを「反語」であるというが、ある者はそれは「さよなら」という意味であるとしている。つまり、すべてを奪えば、神に向かって「さよなら」というということである。
信仰と幸福
ここで著者は、ここで問われている「信仰と幸福」という問題は、重要であるとして説明を加えている。
イエスは山上の説教において「心の貧しき者は幸なり」「悲しむ者は幸なり」「義のために迫害される者は幸なり」と言っている。しかし、通常では、このようなことはそのまま幸とは結びつかない。
これを著者は心の中の穴のたとえで説明している。つまり、人には生活や心の中に大なり小なり穴が開いているというのである。穴というのは例えば病弱のようなものである。そして、その穴を埋めることは大事であり、宗教はそれに無関係ではない。しかし、「その穴から何が見えるか」ということがもっと大事である。
しかるに我々はその穴を早く埋めることに心を奪われ、穴がなければ見えぬものを穴を通して見るという心構えを疎かにし、それを問題にさえしないということになりがちであるがそれで良いか。(抜粋)
この穴を埋めるということが宗教の一つの機能であるので、それを一概に否定できないが、それを突き詰めると「ご利益宗教」となってしまう。
宗教がご利益の面のみを主として強調する時、穴を通して見るべきものを見失うということになり、それはその宗教の重大な欠陥といわねばならぬ。(抜粋)
そしてサタンの言うような立場は、穴の存在を否定することになる。
苦しいこと、辛いこと、嫌なことがあっても、それを通して健康な時、幸福な時、平安な時には解らなかったことが解り、新しい感謝と喜びを感ずるのである。イエスが言った言葉はそのような意味であるのではないだろうか。
貧しいこと、悲しむこと、義のために迫害されることはそのままでは幸福に結びつかない。それは穴を埋めるだけでなく、むしろ穴を通して何かを見る、そのことによって不幸が幸福に変えられるのであり、ここに宗教のもつ重大な逆説が成立する。(抜粋)
第一と第二の試練とヨブの信仰
神ヤーウェは、ヨブの財産と家庭をサタンの手に渡した。それが第一と第二試練である。
ヨブの財産は、砂漠の民シバ人、カルデヤ人に襲われ奪われ、僕たちも殺されてしまう。そして大風が吹いて、子供たちの家が倒れみな下敷きになり死んでしまう。残ったのはヨブとその妻だけになってしまう。そのときヨブは言った。
わたしは裸で母の胎を出た。
また裸でかしこに帰ろう。
主(ヤーウェ)が与え、主が取られたのだ。
主のみ名はほむべきかな。(一ノ二一)(抜粋)
ここで「かしこ」は母なる大地を指し、ヨブは土から生まれ土に帰るという意味である。
そして、ここの「主が与え、主が取られたのだ。主のみ名はほむべきかな」がヨブの答えである。つづいて「ヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことをいわなかった」と続く。
ここで「愚か(ティフェラー)」という語は不合理なこと、味がわるい、不快なという意味である。つまりヨブは味のない、深さのない、不愉快なことを一切言わなかった、罪を犯さなかったということになる。
ヨブは大きな不幸に出会い、彼が幸福な時には見ることのできなかったものを鮮やかに見た。それは深い溝から遥かに天を仰いだということではなかったか。その時彼の口からは深さを意味する言葉以外は発せられなかったということになろう、華やかな、薄手の言葉のための言葉はもはや彼によって語られる余地はなかったといえる。(抜粋)
ここで著者は、宗教というものは、人間が不幸なときなお幸福であろうとする、幻想もしくは錯覚のようなものか真実にして内容のあるものか、ヨブ記においてはそのような根本が問題にされているとしている。
宗教における幸福は地上における幸福を越えたところに存在し、それに逆比例することさえある。
ヨブが厳しい試練の後に神を賛美した言葉は宗教が地上の幸、不幸に逆比例する、否それを超越したところにあることを意味する非常に深い言葉であるといわなければならない。(抜粋)
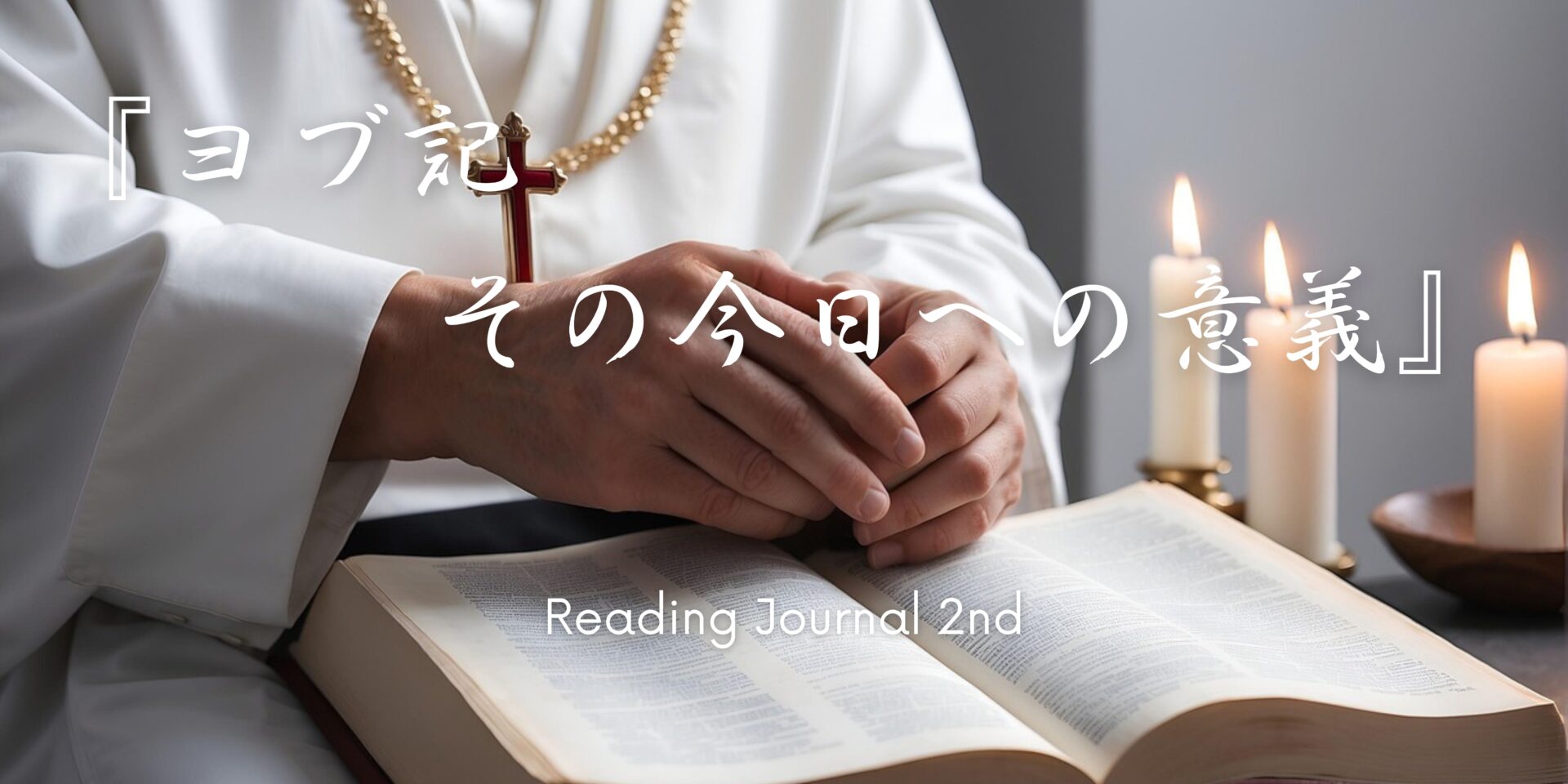


コメント