『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 アジア・太平洋戦争の長期化(前半)
今日から、「序章 アジア・太平洋戦争の長期化」に入る。ここでは、本編に入る前に、アジア・太平洋戦争を概観している。そして、その戦争死没者の数を概算し、日本人に関しては、その九割が戦争最末期「絶望的抗戦期」のものであるとし、戦争終結決意が遅れたためにこのような大きな悲劇となったことを指摘している。
序章は、”前半“と”後半“に分けてまとめることとし、まず”前半“では、日中戦争を取り扱い、”後半“で太平洋戦争を概観する。それでは読み始めよう。
日中戦争の展開とその行き詰り
一九三七年に始まった日中戦争は四〇年には行き詰り「高度分配配置」態勢となった。この「高度分配体制」とは、「小兵力の多数の部隊を広範囲な地域に分散して警備にあたらせる」態勢である。
ここで、著者は『兵士たちの戦場』などの文献から、その体制がいかに広範囲を少ない人員で対応しなければならなかったかを、書き記している。
日本軍兵士の多くは警備地区内の要所要所に構築された小規模陣地に分散して配置され、先の見通しもつかないまま日々の警備にあたっていた。(抜粋)
このような状況は北支部方面軍司令部も理解し始めていて、北部施策の成否は日本軍占領地における中国人の協力が不可欠であるという発言をしている。しかし、それは”征服者“にとって、極めて困難な課題であった。
このような「高度分散配置」の下での戦争の長期化は、兵士たちの戦意を蝕み、次第に厭戦的になっていく。さらに、前線の状況も苛酷さを増していった。ここでは、一九四〇年五月から七月に嫉視された「宣昌作戦」が取り上げられている。
「宣昌作戦」は、もともとは中国軍の主力を撃破し、街を破壊した後に撤退する作戦であったが、海軍が飛行場の設定を希望したため、宣昌を確保する作戦に代わった。そのため日本軍は苦戦を余儀なくされたが、そもそも遠隔地への進行作戦自体に無理があった。
ここで著者は、第三四師団歩兵第二一六連隊の戦記をもとに、その実態を記している。この作戦では、灼熱赤土の道を総重量三十キロの荷物を背負って日に二十キロ近く行軍した。そのため、兵士は、日射病・熱射病に襲われ、足の靴傷(靴ずれ)のため、歩くこともままならなくなった。そして、苦しみに耐えかねた兵士の手榴弾による自殺まで起きている。
このような日中戦争の行き詰まりに関しては、「大元帥」の昭和天皇自身も自覚していたことが「小倉庫次侍従長日記」の記述から伺われる。
長期戦への対応不備、歯科治療の場合
日中戦争は長期戦へ移行したにもかかわらず、軍内部で長期戦への準備が大きく立ち遅れていた。ここで著者は、従来ほとんど触れられていなかった「歯科治療」の問題を取り上げている。
陸軍の場合、日中戦争までは嘱託の歯科医が治療にあたっていた。日中戦争がはじまると陸軍省は、中国戦線の部隊に配属する嘱託歯科医を増員したが、人員不足のため、歯科医が各野戦病院などを巡回し治療する状態であった。
戦場において歯科医が必要とされた理由は、
- 戦場では、砲弾が飛び交う戦場では、歯磨きの余裕すらなく、虫歯を持つ将兵が増大したこと
- 歯と口を含む顎全体の負傷(顎顔面戦傷)の専門治療が始まったこと
- 大規模な兵力動因によって、年齢が上の召集兵が増大したこと
などが挙げられる。
このような状況で一九四〇年三月に陸軍省はようやく陸軍歯科医将校制度を創設する。しかし、その地位は軍医将校とは、区別され低かった。また、海軍でも一九四二年には、海軍歯科医科士官を採用している。
関連図書:
山田 朗(著)『兵士たちの戦場』、岩波書店(岩波現代文庫)、2025年
「小倉庫次侍従長日記」『文藝春秋』、2007年四月号
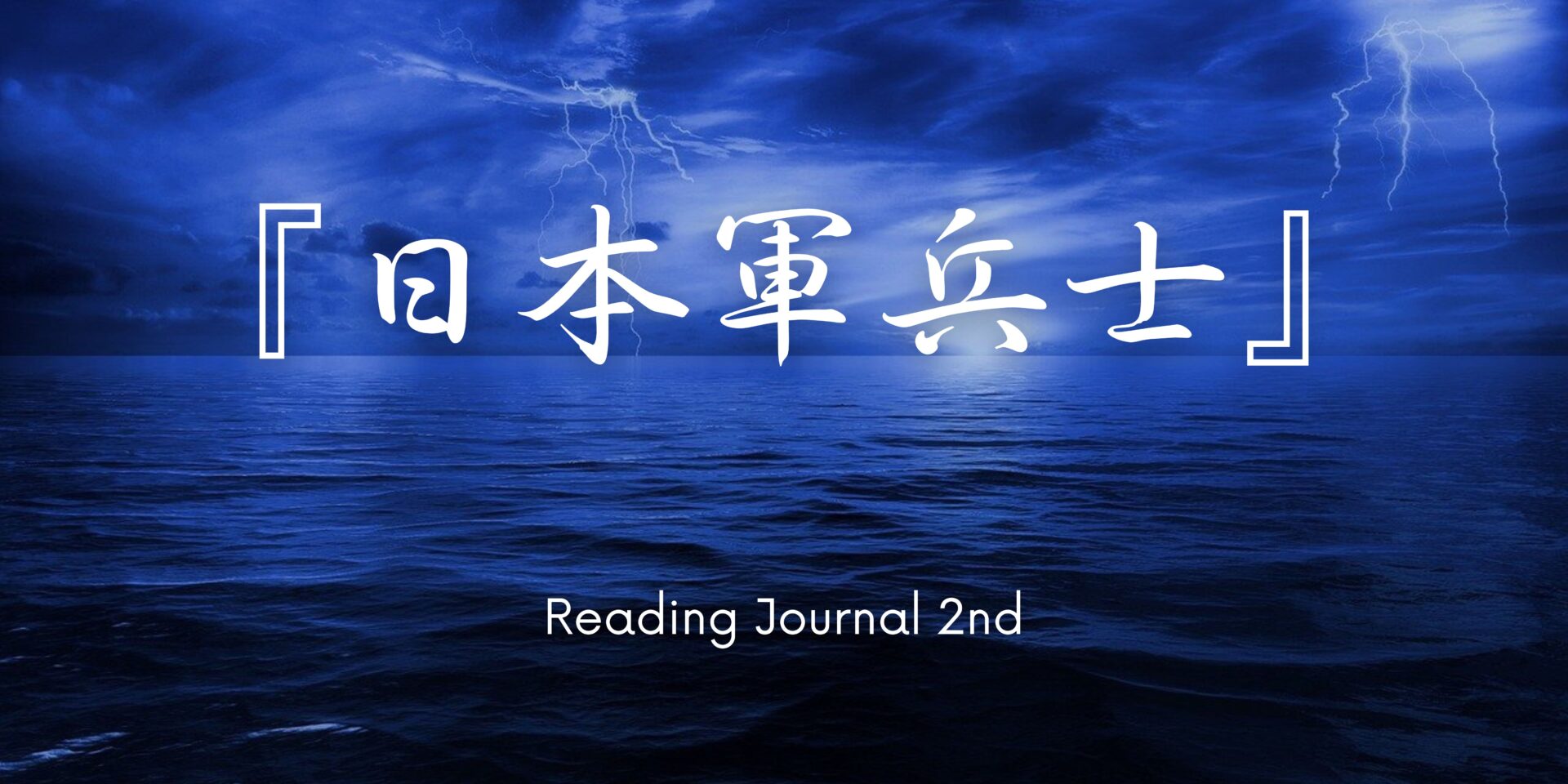


コメント