『日本軍兵士』吉田 裕 著、中央公論新社(中公新書)2017年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに
『続・日本軍兵士」という本が、ベストセラーとなっている。2025年2月16日の読売新聞・書評で読んで、切り抜いておいた。何で切り抜いたかというと、吉田 裕という著者名に心当たりがあったからである。
吉田 裕は、『餓死した英霊たち』の著者・藤原 彰の門下生である。なるほど、『餓死した英霊たち』も良かったし、これも読んでおくべきかな?と思ったが、問題は、“続”と書いてあるところ。やぱっり本書『日本軍兵士』から読まないといけないな。
それからこの本は、『飢死した英霊たち』の解説(一ノ瀬俊也)によると、藤原が扱わなかった「海没死」(乗船(艦)が撃沈されることによる溺死)の問題を取り扱っているそうである(ココ参照)。それでは読み始めよう
今日の部分、「はじめに」では、本書の狙いが書かれている。
アジア・太平洋戦争の規模
まず、アジア・太平洋戦争の規模として、
- 期間:1941年12月8日~1945年8月15日
- 地域:東はハワイ諸島、西はインド、北はアリューシャン列島から中国東北部地方(旧・満州)、南はオーストラリア北岸に及ぶ広大な地域
- 死者:軍人・軍属が230万人(日中戦争期を含む)、民間人が80万人、合計310万人に達する
日露戦争の戦死者九万人と比べてみるといかに大規模な戦争だったかが、よく理解できる。(抜粋)
本書の三つの問題意識
本書は、三つの問題意識を持って書かれている。
- 戦後歴史学を問い直す
- 「兵士の目線」「兵士の立ち位置」から戦場をとらえ直す
- 「帝国陸海軍」の軍事的特徴との関連性を明らかにする
戦後歴史学を問い直す
戦後の歴史研究を担った第一次世代は、直接の戦争体験者であったため、軍事史研究を忌避する傾向が強かった。そのため、ある時期までの軍事研究は、防衛庁防衛研修所(現・防衛省防衛研究所)などを中心とした旧陸海軍幕僚将校グループの専有物だった。
しかし、一九九〇年代に入り、著者を含む戦後生まれの研究者が、本格的に軍事史研究を行うようになって、この流れは変わった。またこの時期は、アジア地域で歴史認識問題が国際的に争点になり、侵略戦争の史実が戦争犯罪研究を中心に急速に進んだ時期と重なっている。
しかし、そこには大きな欠落があったと著者は指摘している。日本の研究は、開戦に至る経緯と終戦、戦後の占領政策が多く、その間の「戦争そのもの」を取り上げる研究者が少なかった。
本書では、歴史学の立場から「戦史」を主題化してみたい。(抜粋)
兵士の目線からの戦場
戦後の代表的な戦史研究としては、防衛庁防衛研修所歴史室が編纂した『戦史叢書』(全一〇二巻)(一九六六~八〇年)がある。
しかし、この『戦史叢書』は、旧陸海軍の幕僚将校であった戦史編纂官が執筆したため、軍中央部からみた戦争指導史、「帝国陸海軍」の将兵を顕彰するという性格が否定できなかった。実際、第一線から戦った元将兵から、同書の記述が一方的で恣意的なところがあり、現場の現実を反映していないという批判が刊行中から存在した。
著者は、このような『戦史叢書』の限界を克服するためには、二つの方法が考えらえるとしている。
- 連合軍側の記録と突き合わせ、旧軍関係資料を相対化するという方法。この方法は、軍事史研究者の秦郁彦が先鞭をつけた方法である。
- 「兵士の目線」を重視し、「死の現場」に焦点をあわせて戦場の現実を明らかにする方法。本書は、こちらの方法をとる。
・・・・・・・(区切り線)・・・・・・
ここに出てくる『戦史叢書』は、防衛研究所のHPの「戦史叢書シリーズ一覧」で閲覧できるぞ。また、軍事史研究家の秦郁彦に関しては、『餓死した英霊たち』の「解説(一ノ瀬俊也)」でも触れられていることを発見したよ。(つくジー)
「帝国陸海軍」の軍事的特徴との関連性
三つ目の問題意識は、「帝国陸海軍」の軍事的特性が「現場」で闘う兵士たちにどのような負担をかけたのか、あるいは兵士たちの置かれた苛酷な状況と「帝国陸海軍」の軍事的特性との関連性を明らかにすることである。ここでは、日米間の経済的格差を始め、「帝国陸海軍」の軍事思想の特質や天皇も含めた戦争指導のあり方、軍隊としての組織的特性などの問題を重視する。
この問題にこだわるのは、「死の現場」の問題をもう少し大きな歴史的文脈のなかに位置付けてみたいと思うからである。こうした分析を通して、アジア・太平洋戦争における凄惨な戦場の実相、兵士たちが直面した過酷な現実に少しでもせまりたい。(抜粋)
関連図書:
藤原 彰(著)『餓死した英霊たち』、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2018年
吉田 裕(著)『続・日本軍兵士』、中央公論新社(中公新書)、2025年
防衛庁防衛研修所歴史室(編)『戦史叢書』全102巻、朝雲新聞社、1966~80年
目次
はじめに [第1回]
序章 アジア・太平洋戦争の長期化 [第2回][第3回]
第1章 死にゆく兵士たち —- 絶望的抗戦期の実体 I [第4回][第5回][第6回]
1 膨大な戦病死と餓死
2 戦局悪化のなかの海没死と特攻
3 自殺と戦場での「処置」
第2章 身体から見た戦争 —- 絶望的抗戦期の実体 II [第7回][第8回][第9回][第10回]
1 兵士の体格・体力の低下
2 遅れる軍の対応 —- 栄養不良と排除
3 病む兵士の心 —- 恐怖・疲労・罪悪感
4 被服・装備の劣悪化
第3章 無残な死、その歴史的背景 [第11回][第12回][第13回]
1 異質な軍事思想
2 日本軍の根本的欠陥
3 後発の近代国家 —- 資本主義の後進性
終章 深く刻まれた「戦争の傷跡」[第14回]
あとがき
参考文献
アジア・太平洋戦争 略年表
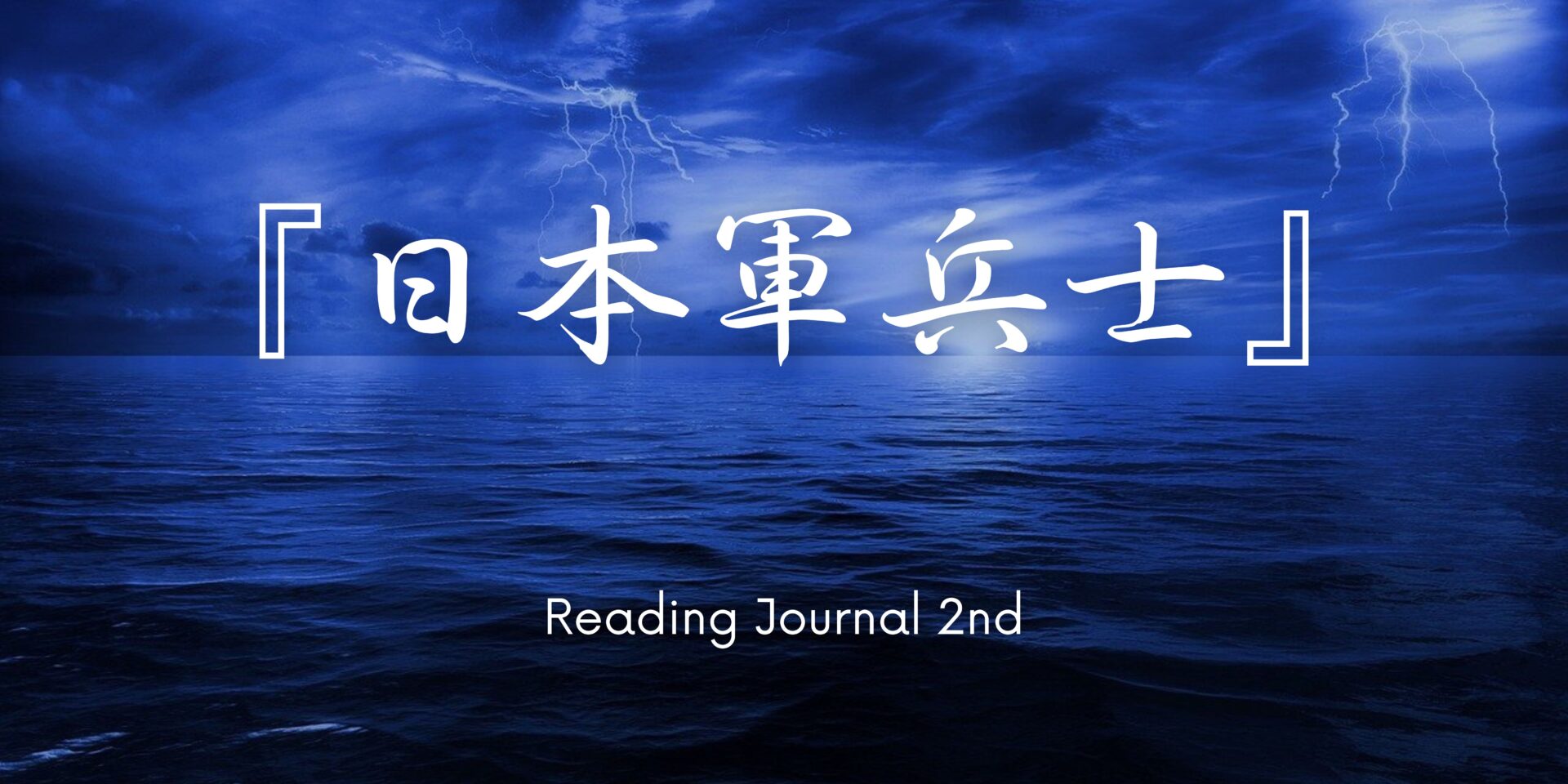


コメント