『アサーション入門』 平木 典子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 考えかたをアサーティブにする(後半)
今日のところは「第三章 考え方をアサーティブにする」の”後半“である。前回”前半“では、アサーションにブレーキをかける5つの考え方が紹介され、そのうち前半の二つについて、そのような考え方がどのようにアサーションに影響するか、それをどのように防げばよいかが解説された。
今日のところ“後半”では、”前半“引き続き、アサーションにブレーキをかける考え方の残りについて解説される。そして、その他、アサーションにブレーキをかけるその他の考え方が紹介され、まとめとしてアサーティブになるにはどのようにすればよいのかが説明されている。それでは、読み始めよう。
五つの考え方の影響を変えるためのヒント(つづき)
前回“その1”につづき、アサーションにブレーキをかける考え方を変えるヒント、C~Eについて。
C 「物事が思い通りにならないとき、苛立つのは当然」
私たちは物事が重い通りにならないと、戸惑ったり、がっかりしたり、慌てたりする。しかし、そのときに「苛立つのは当然」と思うと、現実的ではなくなる。このような考え方は、相手や物事に対する怒りを引き起こす。
また、「自分が苛立って当たり前」という考え方は、相手を変えようとして強硬に主張するもとにもつながる。このような考え方に陥ると、アサーションの「話す」「聴く」の相互作用が起こりようもなく、一方的に攻撃的になる。
こんなときは、「苛立って当たり前」という思い込みについて、考えてみる必要がある。私たちは、それぞれ異なっているため「当然と思っていること」も違っている。そのため自分と100%同じ人はいない。自分の思い通りに働いてくれない方が普通である。
アメリカのある心理学者は「過去と他人は変えられない」と言いました。彼はまた、「他人をかえることはできないが、自分を変えることはできるし、自分が変われば相手が変わる可能性がある」とも言いました。(抜粋)
いくら相手を変えようとして強引に働きかけても相手は変わってくれない。そのような時は自分の方が変わることを考える。それには2つの方法がある。
- 「人はそれぞれ異なる考え方をしているので、自分の思い通りに動くことはない」ことを認めて、相手の考え方を理解しようとする。そして、苛立つのではなく、具体的に変わってほしいことを相手に伝え、頼む。このとき「いいえ」という返事の場合は歩み寄りのアサーションが必要である。
- 「感情は何かに触発されて起こる。その感情は自分のものである」と受けとめる。この感情が自分が起こしていることに気が付けば、「思い通りにならないときに苛立つ」という自分の傾向が、相手の言動がきっかけになって刺激されたことに気が付く。
このように感情は、自分の状態を知る重要な手掛かりとなっている。自分の感情を善悪で判断せずに、その感情が自分にとってどんな意味があるかを確かめてみることが必要である。そして、苛立つのではなくその感情を相手に伝え「お願い」として表現するとよい。
D 「誰からも好かれ、愛されなければならない」
人は誰からも愛された愛と望むのが普通であるが、「誰からも愛されなければならない」と考えてしまうと、ぎごちなくなり、相手の反応を気にしすぎたり、自分らしくない八方美人的言動をしたりしてしまう。
しかし現実には、誰からも好変えることは無理であり、みんなに好かれなければならないということのない。もし誰かに好かれなくてもそれは、自分の問題でなく、相手の好みの問題なのかもしれない。
すべての人に気に入られるのは不可能です。また、相手の好みに左右されないように自分らしさを追求しましょう。(抜粋)
アサーションとは、誰にも好かれるための方法でなく、自分を知り、自分を最大限に発揮するための方法である。
E 「人を傷つけてはならない」
人を傷つけてはならないし、自分が傷つくのは嫌なことである。しかし、「人を絶対に傷つけてはならない」と考えると、自分に対しても他者に対しても神経質になり、自分は相手を傷つけないように気を使いすぎ、他者に対しては、他人に配慮すべきと厳しくなる。
しかし、実際には、他者を絶対に傷つけないようにすることは不可能である。なぜならば人が何によって傷つくかは人それぞれ違うからである。
そのような時は「いくら気をつけても、人を傷つけることはある」と覚悟し、もし傷つけてしまった場合は、自己弁護したり相手が悪いと言ったりせずに、相手が傷ついたことを認めることが大切である。反対に、自分が傷ついたときは相手を責めずに、穏やかにそのことを伝え、わかってもらうようにした方がよい。そのようなやり方がアサーティブな方法である。
自分の考え方の再点検
ここまでアサーションに影響を与える代表的な考え方を五つ選んで検討した。
これらの考え方には、共通して「~べきだ」「当たり前だ」「当然だ」という思いこみがあり、それがアサーションのブレーキとなってしまう。
しかし、このような考え方は、各自の生き方の指針や信念である。そのため対人関係の中で変化させることもできるが、各自を支える指針としても活用できる。
ここで著者は、極端な思い込みにより自分や相手を縛って、身動くが取れない場合はその縛りを緩めるとアサーティブになれる。一方でその人の信念や価値観は人生の道しるべとなり、それにより物事の選択や決断をするとしている。そして、
自分が息苦しくならない限り、自分の考え方を大切にすることが、自分らしくアサーティブに生きることでもあります。
と言いている。
その他の「自分を縛る」可能性のある考え方
ここで著者は、ここで解説した五つ以外に「自分を縛る」可能性のある考え方を列挙している。
- 自分の感情をコントロールすることはできない
- 困難や責任のあることは、直面するより避ける方が簡単だ
- 無気力になったり、怠惰になったりすることは必要だし、また快い
- 常に有能で、業績をあげていなければならない
- 過去の人生経験や過去の出来事は現在の問題の原因となっている
自分らしくあるために
私たちは、ある基準や価値観により物事を判断し、より良い言動を選んでいる。しかし、自分が正しいと思っていることは必ずしも真実ではなく、他人は別の価値観により生きている。そのため状況によってはその価値観を変える必要もある。
自分のものの見方を確かめて、それがどのようにして形成されたかをふり返えることで、自分らしさが分かり、自分を受け入れることができるでしょう。受け入れることで自分が楽になったら、そのままでもよいし、考え方をかえることがより自分らしいと思ったら、変えてもいいわけです。(抜粋)
ここは、いいことが書いてある。自分の信念や価値観は大事にすることが大切だが、しかし、それで苦しくなってしまったら・・・・変えてもいいんだよ。ってことだよね。そうそう、案外つまらないことに意地を張って、本当に大切なものを失ってしまいがちだもんね。(つくジー)
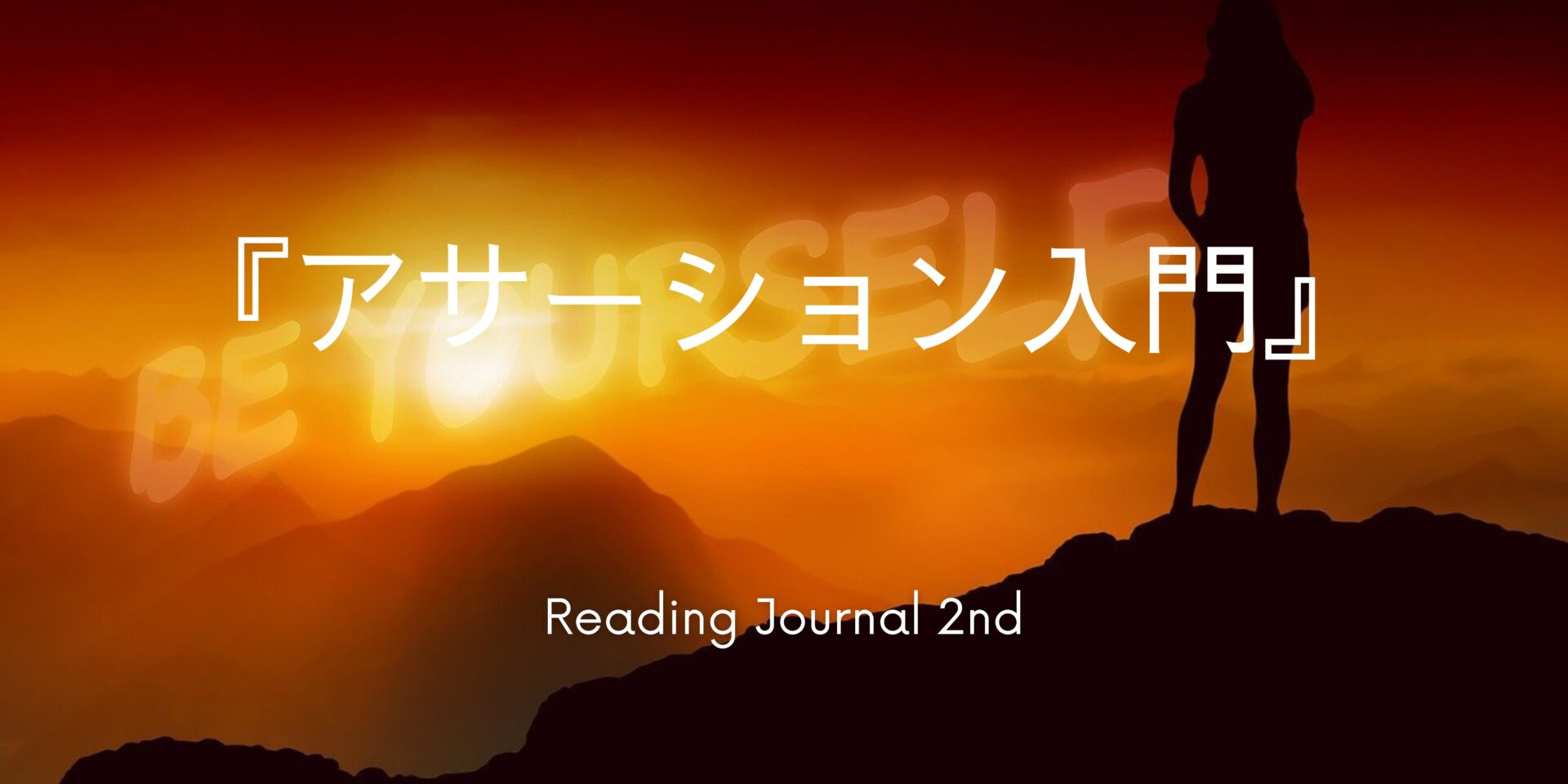

-1-120x68.jpg)
コメント