『『空海の風景』を旅する』NHK取材班 著、中央公論新社、2002年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『『空海の風景』を旅する』
NHKの番組「空海の風景」に触発されて、ただ今、司馬遼太郎の『空海の風景』を読んでいるところですが、なんと・・・・・その特番が本になっていた。『空海の風景』は今読んでいて、なかなか面白い。それに絡めて時々NHKの番組も思い出したりしている。
なので、この本『『空海の風景』を旅する』を買ってみた。『空海の風景』を追いかけながら読んでいこうと思う。
『空海の風景』につづき、『『空海の風景』を旅する』も読み終わった。『空海の風景』を追いかけながら読んだのだが、なるほど、それなりによかったと思う。
この本は、『空海の風景』を題材にしているので、取材時の写真と共にところどころ司馬遼太郎の文を引用している。それが絶妙な部分を引用するので、『空海の風景』を時々復習するようになり、『空海の風景』の理解も助けていた。
また、もう一つこの本が『空海の風景』を読む上で役立ったのは、その写真や図版である。『空海の風景』は、中央公論に連載されていたため、写真や図版はもとより、挿絵の一つもない。そのためこの本の満濃池や空海が修行した室戸岬の洞窟などの写真、長安の地図や空海の名筆などは、興味深く双方の本を面白く読むことに役立った。
もともと司馬遼太郎も空海を追いかけて取材をしているのだが、この本はさらに空海を、そして司馬遼太郎を追いかけて独自取材をしていて、『空海の風景』の世界をさらに広げているように思った。
満濃池では、その水を田に引き込むための法流の儀式「ゆるぬき」を取材し、室戸岬では、空海の籠った「御厨人窟」の取材をドキュメント風に記述している。さらには、空海を乗せて漂流した遣唐使船がたどり着いた福建省を訪れている。そこは現在、空海ゆかりの地となっていて、現地の「空海研究会」まである。さらには、司馬遼太郎も取材に訪れている長安まで足を運び、空海が、そして司馬遼太郎が登った「大雁塔」にも足を運んでいた。
NHKの特集番組「空海の風景』のラストに印象的なシーンがある。取材班は空海が行ったはずがない地方に残る伝説を取材するために東北地方のある村を訪れた。そこで、白菜を持ったお婆さんが、その白菜の名を「空海」というんだと紹介していた。その村には、空海が杖を突いた場所に水が湧き今も涸れないという泉がある。
この部分がエピローグの冒頭に書かれていた。そしてこのような映像を残すことについての思いが書かれている。
この番組の私の当初のモチベーションは、『空海の風景』という文学作品の映像ビデオガイドを作ることではなかった。原作はあくまでも導線に過ぎず、司馬遼太郎が当時は捨象したもの、切り捨てた様々な「空海」の風景が、現在を生きる私たちにとっては重要なものかもしれなかった。例えば、司馬遼太郎の『空海の風景』において、一九七〇年代の社会や信仰のありさま、市井の人々の祈りや表情に目を向けていたとはいいがたい。活字と違って番組は一過性のものかもしれないが、だからこそ、現在を記録する必要があり、普遍的であるともいえる。(抜粋)
そういう言葉を読んでから、もう一度、番組を思い出すと、確かに司馬遼太郎の『空海の風景』を追ってはいるが、さらにひと回り大きな範囲を取材し、映像に記録していることを改めて感じた。
関連図書:司馬遼太郎(著)『空海の風景 新版』(上)(下)、中央公論社、2024年
目次
プロローグ 『空海の風景』への旅はこう始まった
第一章 なぜ、今、空海なのか
第二章 讃 岐
第三章 奈 良
第四章 室戸岬
第五章 渡 海
第六章 長 安
コラム 時空を超える碑の森
第七章 博 多
第八章 空海と最澄
第九章 東 寺
コラム 「弘法大師行状絵詞」撮影記
第十章 高野山
エピローグ 「空海」現在の風景
あとがき
主要参考文献
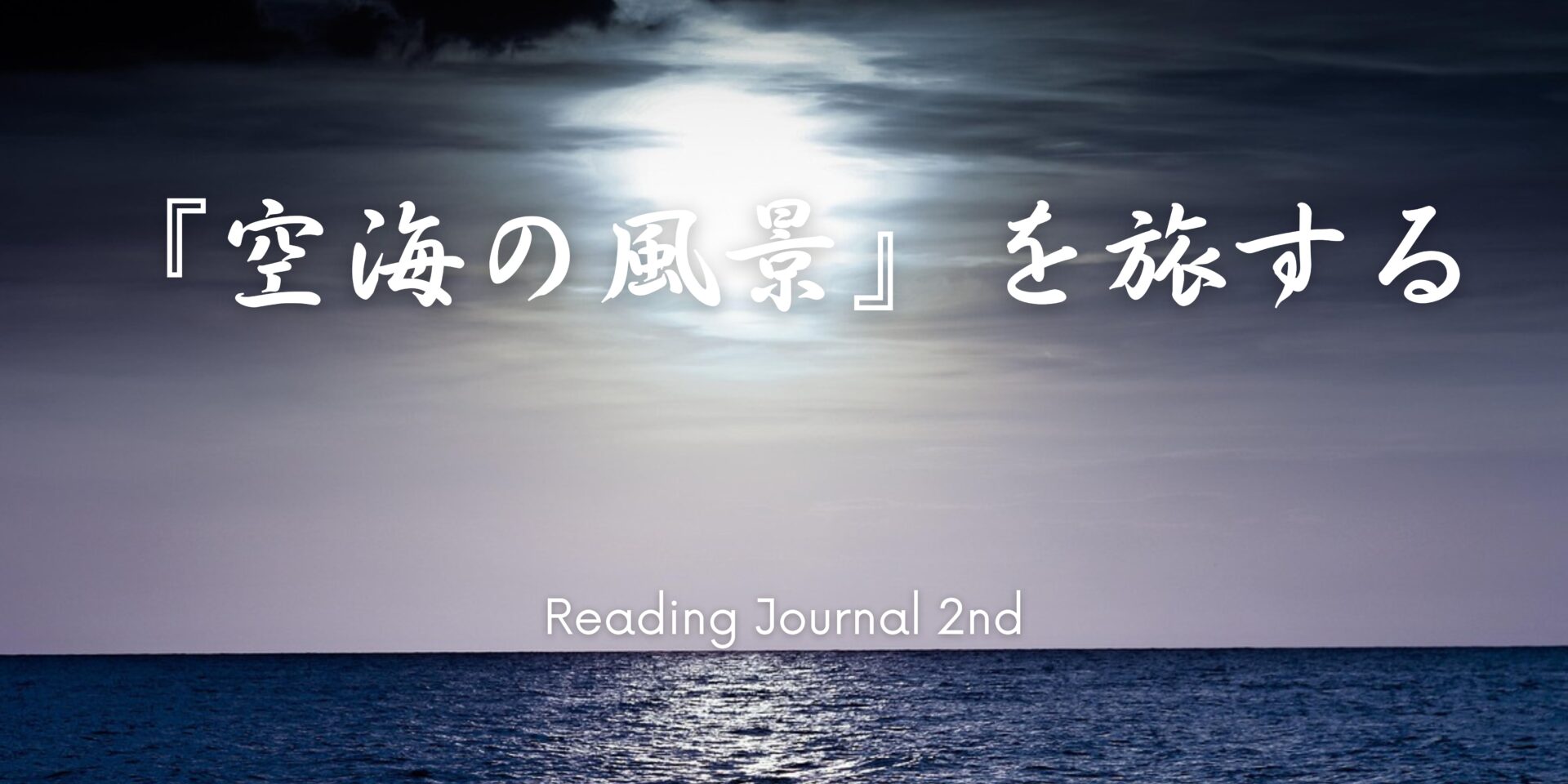
-1-120x68.jpg)

コメント