『空海の風景 新版』(上)(下) 司馬遼太郎 著、中央公論新社、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『空海の風景 新版』
撮りためてあったテレビの録画の中から「空海の風景」という番組を見た。この番組は、司馬遼太郎の著書『空海の風景』を、日本や中国に取材した映像と共に紹介したもので、2002年制作の再放送であった。空海の生い立ちから長安での密教の習得、そして日本での活躍を2回シリーズで追っている。
その後、ひと月ぐらいたってから、録画の中にもう一つ「空海の風景」という番組があったので、それも見てみた。冒頭が違っていたので、別の番組だと思ったら、2002年の番組をもとに、『僕はお坊さん。』『マイ遍路』などの著作がある白川密成住職と著名な仏教哲学者の山折哲雄さんのインタビューなどを新たに差し込んだ2023年放送の番組だった。
結局、ほぼ同じ番組を・・・短期間に2度も見てしまったのでした。
あ~あ、これは読むしかないよね。と思って、amazonで調べると、なんと今年(2024年)の3月に単行本の新刊が出ている。
Amazonによると
「著者自身が最も愛した小説にして、積年の思想が結実した記念碑的大作のハードカバー版を、空海生誕1250年を記念し復刊。」(抜粋)
とある。さらに上巻には旧版には未収録の講演集「『空海の風景』 余話」を、そして下巻には、これも未収録のインタビュー「『空海の風景』の司馬遼太郎氏と一時間」、書評「「形而上学の壮大な展開」(歴史学者・貝塚茂樹)も収録しているとのことである。
こ・・・・これは、新版で読むしかないですか?無いよね(・・・・シカタナイヨネ・・・・お金も無いよね)。
『空海の風景』を読み終った。上巻・下巻の2冊組でなかなかの分量だった。しかし、司馬遼太郎の語り口もあり、それほど苦なく読み進められたと思う。また、もともとが、雑誌の中央公論に掲載されたものであるため、各章のページ数がおおむね一定なのも読みやすかった。
「天才とは何か」ということを空海という人物を通して描くこの伝記は、現代からあまりにも遠くその風景としか描けないと司馬遼太郎がいうように、空海の生涯を少ない伝記的事実を膨大な量の知識と現地取材で補強し、しばしば想像の範囲と断りながら生き生きと写実している。
その文章は、空海の出生、その一族佐伯氏の由来、佐貫の風景から始まる前半は少し重いが、空海が遣唐使船に乗り込むあたりから、しだいに勢いがつき、そして最後まで軽妙な筆づかいでつづられている。
空海の風景と密教
そして、ここで思うのだが、この『空海の風景』は、司馬遼太郎の宗教告白とは、言えないまでも宗教、仏教への見解を書き記しているようにも思えた。
この真言密教への司馬遼太郎自身の傾倒は、戦中に行った徒歩旅行の体験に始まる。学生のまま兵隊にとられる運命だった司馬遼太郎と友人は、熊野の山に分け入り徒歩旅行をした。そして、山中をさまよっている時、偶然に山上に都会が出現した。それが高野山だった。この不思議な体験が、本書の、そして真言密教との出会いの原点である。
上巻の付録として収録されている「『空海の風景』余話」の冒頭を長文引用する。
日本という島国の向こうには太平洋が広がっているばかりです。
これまでこの国には外から人間や文化が一方的に入り込んでくるばかりで、逆に世界に対してお礼をしたことのない国であります。アメリカの占領軍が飛行機に付着させて持って帰っていったススキが現在繁殖して困っているそうですが、日本の文化がよそにいったのは、まあススキぐらいなのかもしれません。
こういう日本からは世界的な人物が出にくく、大文明は起こりにくい。
ですから日本の歴史のなかで出現した偉人はいずれも、「日本の」菅原道真であり、「日本の」源頼朝であり、「日本の」西郷隆盛であります。みな、「日本の」という接続詞がつく。
ところが一人、弘法大師だけは例外ですね。
彼だけが「人類の」空海です。
お大師さんの思想はアメリカであれ、アフリカであれ、どこへ行っても通用する。鎌倉時代のお祖師さんたち、親鸞や日蓮といった人々でさえ、日本の地理的な条件のなかでこそ通用する思想家ですが、弘法大師空海だけは珍しく世界観を持った思想家と言えましょう。(抜粋)
司馬遼太郎は、このように空海をたたえている。もっともこの文章が高野山で行われた真言宗参与会の設立を記念した特別講演のものであるため、かなりのサービスがあったのだろう。しかし、表現が大げさでもそう思ってなければそうは言わないのである。特に、親鸞や日蓮という空海のライバルと目される最澄の系列の偉人とくらべ、空海の方が圧倒的に偉大であると言っている。
「理趣経」と性欲の問題
そしてまたこの小説の底流には、「理趣経」と性欲の問題があるようにも思った。
この小説のまだほんの冒頭である。司馬遼太郎が空海の生まれた地を訪ね。そこにいた犬の仕草から、しだいに宗教的な考察にいざなわれる部分がある。
奇妙な感じがした。人間も犬もいま吹いている風も自然の一表現という点では寸分かわらないということをひとびとが知ったのは大乗仏教によってであったが、空海はさらに抜け出し、密教という非釈迦的な世界を確立した。密教は釈迦の思想を包摂しはしているが、しかし他の仏教のように釈迦を教祖とすることはなかった。大日という宇宙の原理に人間のかたちをあたえてそれを教祖としているのである。その原理に参加 --- 法によって --- しさえすれば風になることも犬になることも、まして生きたまま原理そのものに --- 愛欲の情念ぐるみに --- なることもできるという可能性を断定し、空海はこの驚くべき体系によってかれの同時代人を驚倒させた。(抜粋)
司馬遼太郎が密教をどのように捉えているかを示したこの部分は、まだ話も始まっていないイントロの部分に置かれている。そのため、読者には、なぜ密教が「非釈迦的な世界」なのか、なぜ「愛欲の情念ぐるみ」なのか、わからない。もちろんそれは読んでいくうちに解き明かされるのであるが、ここの「愛欲と情念ぐるみ」という部分は、唐突でもあり何かを秘めているようである。
これは密教の根本経典である「理趣経」が関連する。そして、理趣経は性欲を肯定する経典である。この『空海の風景』を読んでいると、ところどころに「理趣経」、そして性欲の問題が顔をのぞかせる。それは、底流に流れる司馬遼太郎の問題意識があるからであると思った。最後に「理趣経」の解説部分を引用する。
理趣経(般若波羅蜜多理趣品)というのはのちのちの空海の体系における根本経典ともいうべきものであった。他の経典に多い詩的粉飾などなく、その冒頭のくだりにおいてきなりあらわれもないほどの率直さで本質をえぐり出している。
妙適清浄の句、是菩薩の位なり
欲箭清浄の句、是菩薩の位なり
触清浄の句、是菩薩の位なり
愛縛清浄の句、是菩薩の位なり
妙適とは唐語においては男女が交媾して菩薩の境に入ることをいう。
・・・・中略・・・・
妙適清浄の句という句とは、文章の句ではなく、ごく軽く事というほどの意味であろう。
「男女の交媾の恍惚の境地は本質として清浄であり、とりもなおさずそのまま菩薩の位である」
という意味である。
以下、しつこく、似たような文章がならんでゆく。インド的執拗さと厳密さというものであろう。
・・・・後略・・・・・・(抜粋)
関連図書:
白川密成(著)『マイ遍路―札所住職が歩いた四国八十八ヶ所―』、新潮社(新潮新書)、2023年
白川密成(著)『僕はお坊さん』、ミシマ社、2010年
目次
(上巻)
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
「『空海の風景』 余話」
(下巻)
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
あとがき
「インタビュー『空海の風景』の司馬長太郎氏と一時間」
解説 形而上学の壮大な展開
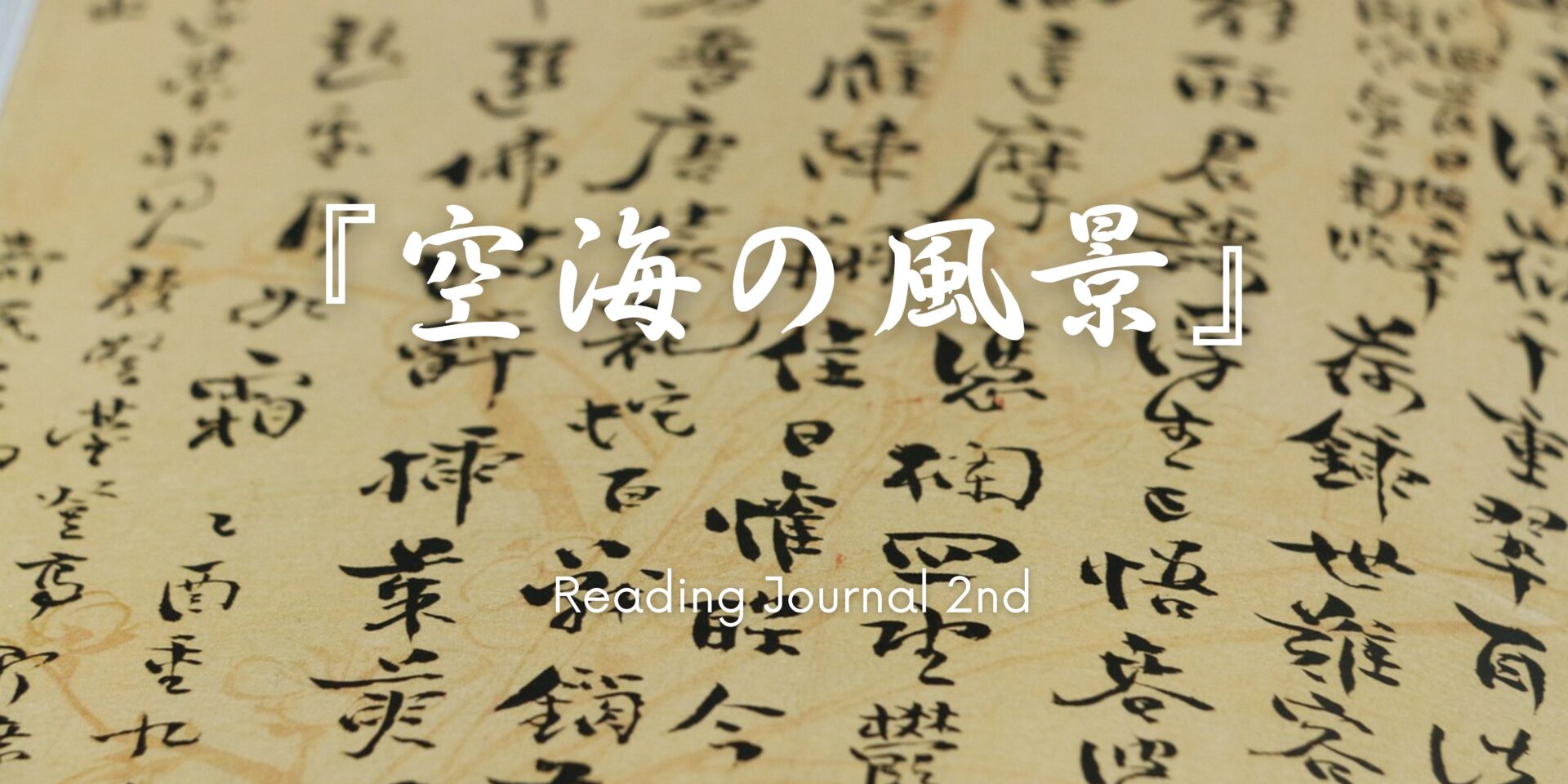
-1-120x68.jpg)

コメント