『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 独立 ― 一七六三~一七八七年 (その3)
今日のところは「第2章 独立」の“その3”である。ここまで“その1”、“その2”において、英本国との争いが激化、戦闘の勃発、大陸会議の招集、そして有名な独立宣言などを見てきた。今日のところ“その3”は、州政府での憲法の制定や州を束ねる連合への議論、さらにはワシントンの進撃などの独立戦争の様子についてである。それでは読み始めよう。
州政府での憲法制定
一七七六年以降、各邦ごとに憲法が制定された。これは独立宣言と同じくらい重要である。
これらの邦の憲法は、第二代大統領になったジョン・アダムズの『政府論』がモデルとなった。この『政府論』は、トマス・ペインの『コモン・センス』の急進的な議論に対抗するという意図があった。そして、その特徴は、「混合政体」的なところである。
ここで著者は、各邦で定められた憲法には、独自色があるとして、いくつか紹介している。
- ヴァージニア憲法(一七七六年):ジョージ・メイソンにより起草された。初めての成文憲法として知られる。権利章典が存在し、政治制度として、執行権を持つ知事の権力が諮問機関である参議会や代議院(議会)によって弱められている。
- ペンシルヴェニア憲法(一七七六年):ペインの『コモン・センス』に影響を受けた政治家により制定され急進的。一院制、白人男子の普通選挙などそれまでに類を見ない民主的な憲法である。後のフランス革命に影響を与えた。
- ニューヨーク憲法(一七七七年)、マサチューセッツ憲法(一七八〇年):知事の権限を強固なものにしようとした。修正参議会という政治制度を打ち立て、これにより議会に対して知事と判事とが合同で拒否権を持つ。これは連邦憲法の制定時に参考にされた。マサチューセッツ憲法は、マサチューセッツ人民の投票によって憲法が批准された。この憲法制定の経緯により、憲法制定は通常議会でなく、特別な制定会議によって行うという方法が誕生した。これは、一七八七年の連邦憲法制定会議やフランス革命以後の憲法制定権力論に引き継がれる。
大陸会議での連合案とモンテスキューの『法の精神』
このような各植民地の憲法制定と並行して、それぞれの邦を束ねた連合をどのように作るかも検討された。
大陸会議でリチャード・H・リーが連合案を作ることを提唱し、委員会が作られた。そこでの案は、戦費の捻出を考え、邦同士の通商についての課税権限を連合に与える、というものだったが、これは反対され撤回された。
このころの連合、連邦の概念は、現在のアメリカの連邦の概念と大きく異なる。
当時はあくまで一つ一つの邦が国家として考えられていた。(抜粋)
この当時の連合の模範例はスイスとオランダとスイスであり、著作としてはモンテスキューの『法の精神』の議論がある。
モンテスキューは、政体を君主制と共和制に分類し、
- 共和制:小さい規模の国家にふさわしい、君主制の大国が攻めてきた場合は、軍事的に対抗できない。
- 君主制:内部の腐敗が進行し、外部からの侵攻がなくても瓦解してしまう。
と考察している。そして、モンテスキューは双方の良い面を合せたものとして連合を考えた。
彼の言う連合(連邦)共和国は、「いくつかの政治体が、より大きな国家の市民になることに同意する」というものである。これによって侵攻に強いという対外的利点と、腐敗しないという対内的な利点とを兼ね備えた国家ができるのである。(抜粋)
このように一つ一つの邦が主権を持つという考えのため、連合に課税権限を与えるという案は、反対が多かった。
その後、戦況が悪化したため連合についての議論はいったん放棄された。
なるほど、ヨーロッパの国がEUを作っていて、何でそんなことをしているんだろう?と思っていたが、モンテスキューなどなどヨーロッパの思想家たちの知恵が生きているんですね。
ちなみに『ポピュリズムとは何か』では、EUの設立もヨーロッパが再び全体主義の国にならないための包括的な試みの一部であると言っている(ココ参照).
なんかいろいろと考えられているんだよね。(つくジー)
ワシントンの反撃
英軍はボストンを陥落させた後、ニューヨークに向かい、ワイントン軍を撃破してニューヨークを占領する。そして、当時首都のようなとしてあったフィラデルフィアに向った。
ここでワシントンが起死回生の策をとる。ワシントンは厳寒期に行軍し英軍を撃破する。このような起死回生の作戦の成功には、大陸軍の地の利に加え英軍の補給と通信の難しさと、戦略的訓練を欠いていたことが影響している。また、英軍は単に大陸軍を撃破するだけでなく、王党派、中立派を味方につける必要があり、それも英軍の勢いをそいでいた。また、広い大陸を後退していく大陸軍を追いつめるだけの戦力も無かった。英軍は陸軍の鈍さを反省し海軍を投入しフィラデルフィアを海から攻め落とす。
攻防の一つの転機は、一七七七年のサラトガの戦いであった。カナダとの関係から北部で続いていた戦闘は、英軍の敗北で終わった。その後、戦局はアメリカ側に傾く。
ここで著者は、このような独立戦争の過程で、多くの血が流れ、多くの人々が苦境に陥ったと注意をしている。
戦闘のため成人男性の多くが従軍したため、労働力が不足し、また、奴隷や従僕などが逃亡も起こった。そして英軍による強奪、性暴力などが横行し、反対に大陸軍による王党派の土地の徴収、売却などが行われる。戦争に敗れた王党派の人びとは、命からがらカナダなどに落ち延びていった。
戦闘により一部は利益をあげ富むが、財産をほとんど失ったものもいた。また、この時期には黒人や先住民族の部族対立などあらゆる対立が顕在化した。
このように、ある人にとっては輝かしい歴史でも、他の人にとってはトラウマのような歴史でもある。これは多くの戦争の場合と同様、アメリカ独立戦争にも言えることである。(抜粋)
関連図書:
モンテスキュー(著)『法の精神(上・中・下)』、岩波書店(岩波文庫)、1989年
ヤン=ヴェルナー・ミュラー(著)『ポピュリズムとは何か』、岩波書店、2017年
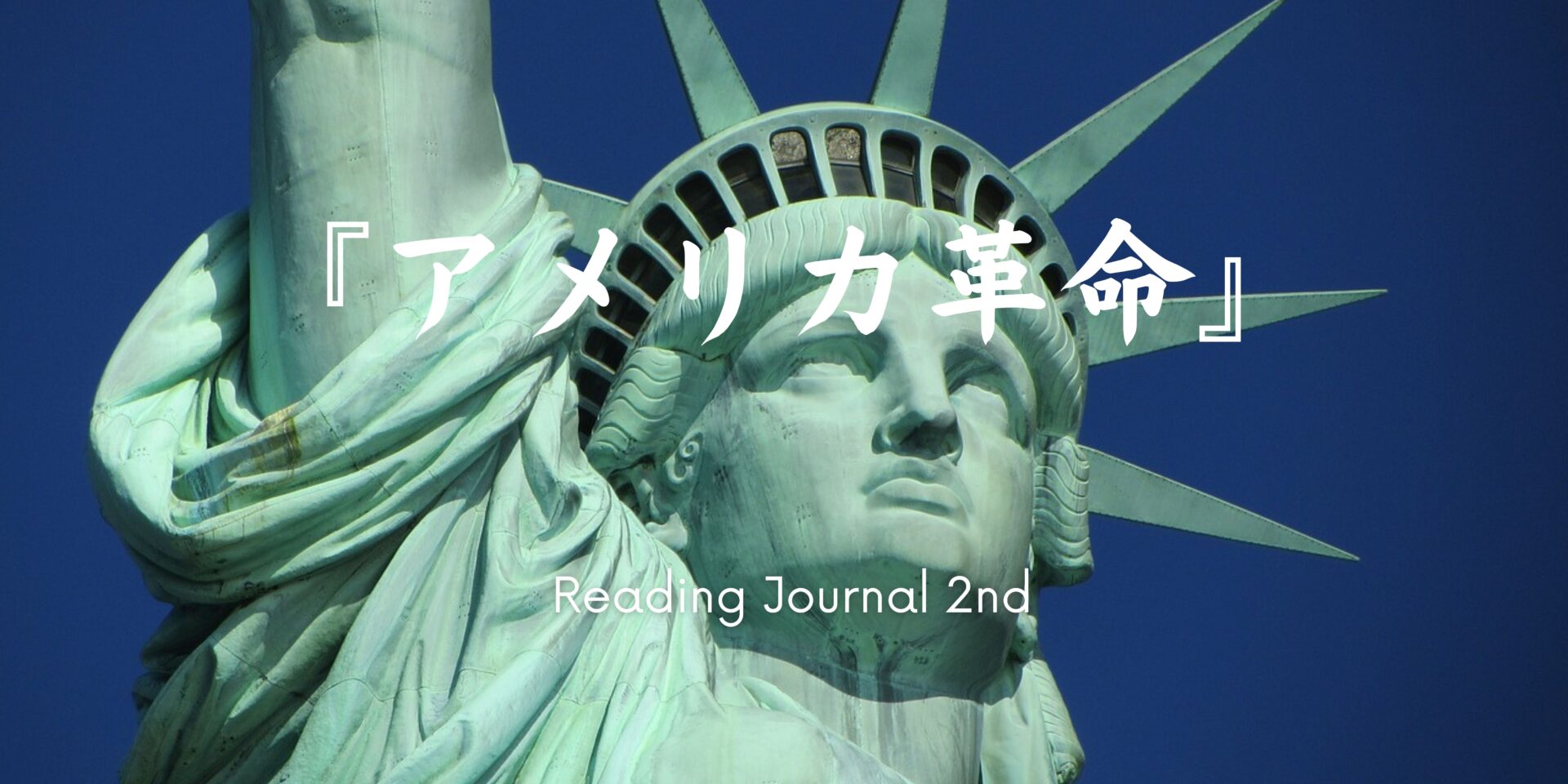

-1-120x68.jpg)
コメント