『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 独立 ― 一七六三~一七八七年 (その2)
今日のところは「第2章 独立」の“その2”である。“その1”では、イギリスのパリ条約を契機とした帝国化とそれによる本国と植民地の争いを、今日的な視点でなく、当時の植民地と本国の視点で検討した。それを受けて今日のところ“その2”では、争いが激化し、戦闘が勃発した経緯と有名な独立宣言の内容とその妥当性について検討する。それでは読み始めよう。
争いの激化と王党派の存在
植民地とイギリス本国の争いは、一七七〇年のボストン虐殺 – 投石などで抗議した市民に英軍が発砲し、五名が死亡した事件 – を契機に激化していった。そして、植民地では、どのような態度を表明すべきかで意見の対立が起こった。とりわけ問題になったのが、王への忠誠を保つかどうかである。
この当時、アメリカの植民地の人の多くは依然として国王に愛着があり、表象としても、政治制度の点でもその影響下にあった。
政治制度も、独立前後の連続性があった。植民地には、本国の国王にも似た総督という感触があり、それは知事として各植民地に共通の役職として残った。ここで総督と知事は訳を分けているだけで、英語では両方ともgovernorである。
これは決して国王と同一視してはならないが、独立以降の邦の国制や合衆国憲法においても、植民地時代の総督の制度構造と、連続したものがある。(抜粋)
これは決して国王と同一視してはならないが、独立以降の邦の国制や合衆国憲法においても、植民地時代の総督の制度構造と、連続したものがある。(抜粋)
大陸会議の招集
一七七三年に東インド会社の茶を独占的に運ぶ英本国に対するボイコットのために、茶を海に放り投げるという事件(ボストン茶会事件)が起こった。これを問題視したイギリスは、マサチューセッツ統治法を含む強圧諸法(アメリカ側では「耐えがたき諸法」)を可決した。
これに対してマサチューセッツ支援のために、一三の植民地が一七七四年にフィラデルフィアに集まり「第一回大陸会議」を行った。ここでマサチューセッツ統治法が撤回されるまで、交易を拒否するサフォーク決議が議論される。しかし、軍事的な抵抗を認めるか、和解を急ぐかは意見の一致をみず、翌年の第二回大陸会議の開催を決定して、解散した。
ここで著者は、なぜ一三植民地だけが集まったかという問題に触れている。この一三植民地はイギリスの植民地の半数にも満たさず、ジャマイカ、バルバドスなどのカリブの島やケベックなどは含まれていない。
その理由として、カリブの島々の社会、経済構造が北アメリカと違うことが重要である。
- 島々の土地所有者は、基本的に英国在住のまま利益を上げていた。
- 黒人奴隷の割合が一三邦より高く、その反乱をおそれ英軍を歓迎していた。
- 砂糖の生産により本国との経済関係が格段に重要だった.
などの状況により英植民地として残ったほうが有利と見ていたと考えられる。
ジェファソンの論説
このころになると、植民地側の本国批判も新たな様相を見みせ、国王に対しての批判も現れた。後に第三代大統領となるトマス・ジェファソンも『意見の要約』(一七七四年)で直接的に国王を批判した。また、ジェイムズ・ウィルソンは『ブリテン議会の立法権の性質』において、混合政体を否定し庶民院のみがイングランド国制の中核いう解釈を示した。これらは、トマス・ペインの『コモン・センス』と共に独立の機運を高めることに貢献する。
独立戦争の勃発
一七七五年にレキシントン・コンコード間で戦火が切られ独立戦争が始まった。
戦争がはじまると第二回大陸会議が招集され、一三植民地を束ねた軍の創設が決まり、ジョージ・ワシントンが総司令官となった。ワシントンはヴァージニアを代表する軍人で、カリスマ的な人気があった。
また大陸会議は、ワシントンを派遣するとともに、ジョージ三世に戦争を止めてほしいと請願(オリーブの枝請願)を出した。しかし、これは失敗に終わる。
独立宣言
一七七六年七月四日、独立宣言が採択された。
その一説、「我々は、次の真理は自明のものと信じている。すなわち、人はすべて平等に造られている。人はすべてその創造主によって、誰にも譲ることのできない一定の権利を与えられており、その権利のなかには、生命、自由、そして幸福の追求が含まれている」はとりわけ強烈な印象を残す。(抜粋)
独立宣言は、ジェファソンが草稿を書き、そこにジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリンらが手を加え、最後に大陸会議全体で加筆訂正を加えた。
しかし、この表現は「奴隷制」の問題で本国から反論される。また、奴隷制と共に「女性の問題」がこの宣言の限界を示している。
奴隷制の問題
先ず奴隷制の問題だが、このころ英本国では、徐々に奴隷の解放運動の動きが高まっていた。そのため、本土側からすると「人はすべて平等に作られているというなら、なぜ新大陸には奴隷がいるのか」という反撃は当然のことになる。
著者は一七六〇年代以降に植民地でも奴隷解放の動きがあると注意している。しかし、これは英本土側が奴隷たちにプランター(農園主)から独立して本土側につけば、解放を確約するという極めて政治的なものだった。
女性問題
奴隷制と同じく独立宣言の限界は、この宣言には女性が一人も入っていないことだった。
ジョン・アダムズの妻アビゲイルは、あなたたちは代表なくして課税なしといった批判をしているが、女性たちもまた代表がいないので、それなら法にしたがわないぞ、と言った批判をしている。
栄光あると思わしき歴史にはつねに敗者や弱者が存在するという難しさゆえである。例えば、明治維新(明治革命)について、石光真人[いしみつまひと]『ある明治人の記録』を読むと読まないのとではかなり印象が違う、といったように。(抜粋)
むむむ、ここで著者は唐突に、石光真人の『ある明治人の記録』を出してきたけど、これはよほど感銘を受けていると見た!っというか、「当然、読んでますよね」って感じを醸し出してるぞ!。確かに、この本の名前は知ってるけど・・・・う~~ん、読んでないんですよね。(つくジー)
関連図書:石光真人 (編著)『ある明治人の記録 改版 — 会津人柴五郎の遺書』、中央公論新社(中公新書)、2017年
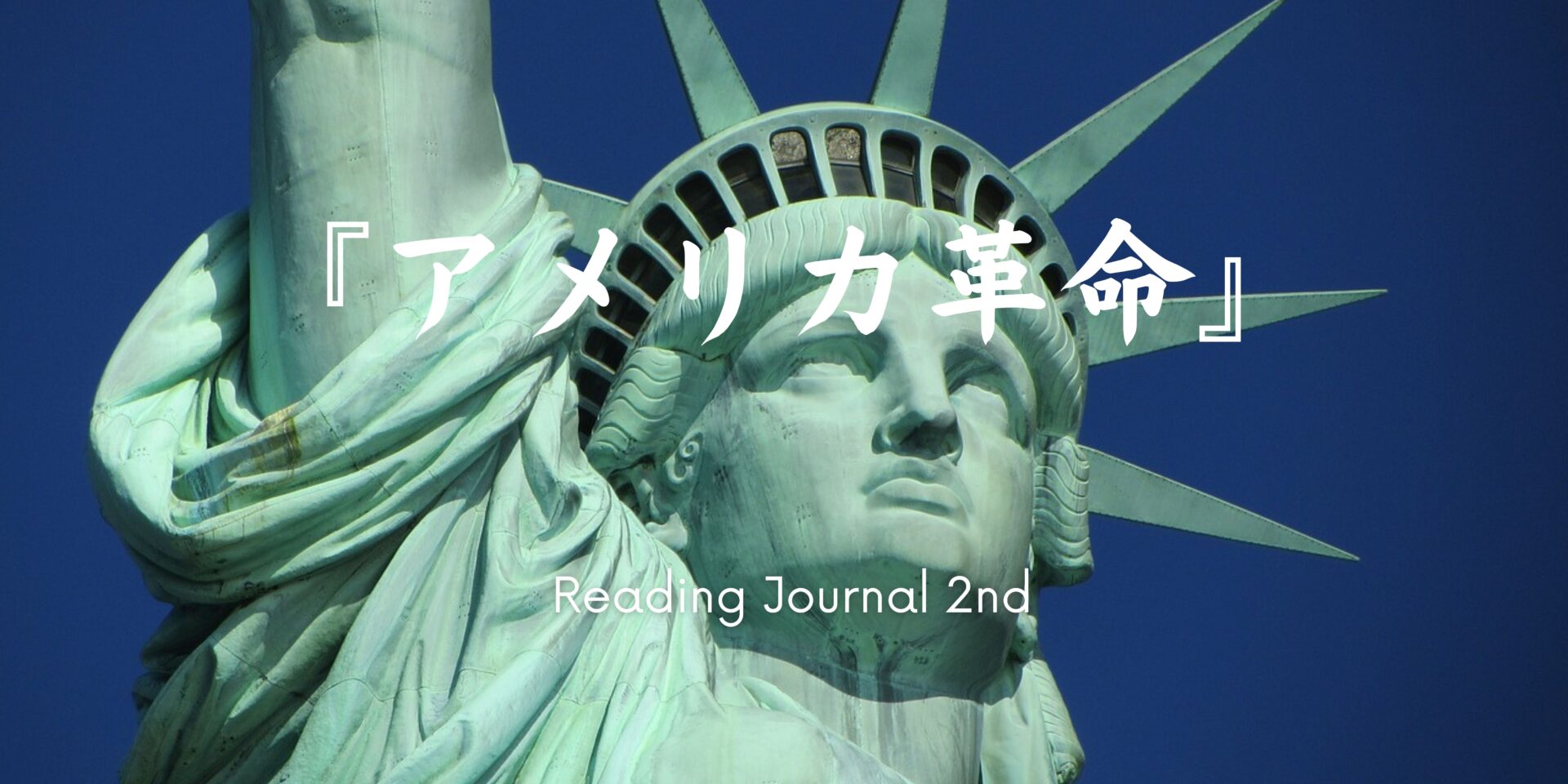


コメント