『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 植民地時代 ― 一六〇七~一七六三年 (その3)
今日ところは、「第1章 植民地時代」の“その3である。ここまで”その1“、”その2“において、現代的な視点に立ったうえで、植民地時代についての全般的な解説があった。今日のところ”その3“では、アメリカ独立への流れを具体的に年代、「①エリザベス女王〜ジェームズ一世まで」「②チャールズ一世・イングランド内乱期」「③共和政期」「④復古王政期」「⑤名誉革命体制前期」「⑥ウォルポール政権とそれ以降」に分けイングランドの政治、外交史を踏まえ詳細がつづられている。それでは、読み始めよう。
「有益な怠慢」は誤り
英国本土の政治家エドマンド・パークが「有益な怠慢」と呼んだように、植民地と本国があまりにも遠いため、政治的行動を勝手にできた、という欲説がある。著者は、これを否定し、実際には英本国が植民地をコントロールしてきたとしている。
ここでは、実際にどのようなことが行われたかを時代時代に分けて説明されている。
①エリザベス女王〜ジェームズ一世まで
イギリスがアメリカの興味を持ちだしたのは一六世紀の後半であるが、これはスペインとの対立という外交上の理由があった。イギリスとスペインは一五八五年~一六〇四年まで戦争状態にあった(スペインの「無敵艦隊」の時代)。これは、スペインから独立しようとしていたオランダをイギリスが支援したことが直接の原因だが、カトリックのスペインと宗教改革時にカトリックと対抗してプロテスタントの国教会を立てたイングランドとの対立でもあった。
女王エリザベス一世はウォルター・ローリーをアメリカに派遣したが、当初はまったく定着しなかった。エリザベス女王が亡くなりジェームズ一世が国王となると、彼はスペインと融和的政策をとり、ロンドン条約を結んだ。これにより、イギリスはスペインの手が及んでいない領域のみ植民が許可された。そのころヴァージニア会社などに特許がおり、植民が送り込まれる。
ジェームズ一世や枢密院は、利益が上がらない植民にあまり興味がなかった。そのため、特許状を発行して臣民に開拓を委ねた。国王はスペインの領域に侵入したり、諍いを起こすことに厳罰を処し、先住民との争いに対しても厳しくのぞんだ。
イギリスの植民が、外交上の問題、宗教上の問題、経済的な問題と不可分に結びついていることは、リチャード・ハクルートが一五八四年に著した『西方への植民』によくあらわされている。
②チャールズ一世・イングランド内乱期
ジェームズ一世の次のチャールズ一世の時代になると、植民者の数が次第に増え、制度的な発展も進んだ。チャールズ一世は、領主植民地を好み、自分の気に入った貴族を領主としてアメリカに土地を与えた。
これらの動きに対して、ニューイングランドなどは、本国の介入を逃れて独自の発展を遂げたが、経済的な関係という意味で本国と協力関係にあることは、変わらなかった。
このように国王、本土との関係で植民地の政治経済が進展したが、国王と議会の関係が険悪となり、一六四九年に国王が処刑されてしまう(「イングランド内乱」あるいは「ピューリタン革命」)。そしてわずかいうち一一年であるが、共和制が誕生する。
ここで困ったのは植民地である。もともと国王に従属していた彼らの多くは、内乱において国王に忠誠を誓うか、議会の側につくかを迫られた。
③共和政期
共和政期の各植民地の対応は、それぞれの風土や置かれている状況によってさまざまだった。ニューイングランドでは、王政派があまり多くなかったため、利害の一致した植民地同士で同盟を形成した。しかし、多くの植民地では、本国の争いにより植民地内で争いになることを恐れ、中立を保った。
ここでチャールズ一世が処刑されると状況は悪化した。もはや中立を保てなくなった六つの植民地(アンティグア、バルバドス、バーミューダ、メリーランド、ニューファンランド、ヴァージニア)が反旗を翻す。しかしこの反乱は、新政府軍によって鎮圧された。
このとき新政府の指導者クロムウェルは、航海法を制定し、イギリス商人に大西洋での貿易を許可したが、オランダ商人を締め出した。そして、植民地に対しては強権を発動する。しかし、植民地の人たちは、本国の命令を無視してひそかに他国との貿易を続けることもあった。
その後クロムウェルが亡くなると、すぐにイングランドの共和制は終わった。
④復古王政期
イングランドは君主制に戻りチャールズ二世が即位する。この時期の、植民地統治は二面性を持つ。国王やその側近たちは、共和制期の強圧的政策を嫌ったが、すでに多くの変化が生じていて、それまでの政策を継承した例も多かった。
その一方で、領主植民地(ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルバニア)を設置し自治を許すことで植民を増やそうとした。背景には、それらの植民地が持つ民族的多様性(スウェーデン、ドイツ、フランスから移民も多かった)である。またペンシルバニアは、宗教的マイノリティのクェーカーのウィリアム・ペンに与えられた領地であり、宗教的な寛容という目的もあった。
他方で、自由貿易を望み、航海法従おうとしなかったニューイングランドに対しては本国の権限を強めた。最終的には、ニュージャージーと合わせて一つの植民地、ドミニオン・オブ・ニューイングランドへ統合された。
⑤名誉革命体制前期
このとき、本国で名誉革命が勃発した。これにより植民地をいかに統治するかが再び議論の的となる。その結果、一六九六年に植民地の監督のため商務省が発足した。商務省は各植民地の総督に対して指示を下し、日常的な行政を担当した。
本国がゴタゴタしていたこのころ、植民地では特許状の更新により自治権の拡大したところもあった(マサチューセッツ、ペンシルバニアなど)。その結果、植民地の下院議会の興隆が各地で起こり、植民地の政治エリートが生れた。彼らの本国への劣等感が政治的権限の拡大をもたらした。
⑥ウォルポール政権とそれ以降
一七二一年から一七四二年にかけて、ロバート・ウォールポールは、自由放任主義の経済政策を行い、それを植民地にも援用した。すると、本国から派遣されてきた総督は、本国の支援に期待できなくなったため、現地で政治的な支援者を求めことが必要となる。そのため植民地側の自治が進んだ。
しかし、そのころのイギリスは財政軍事ともに中央集権化が拡大し、次第に商務省の権力も強化され徐々に植民地に介入し始める。そして、一七六三年のパリ条約によりイギリスは帝国としての道を歩むことになる。
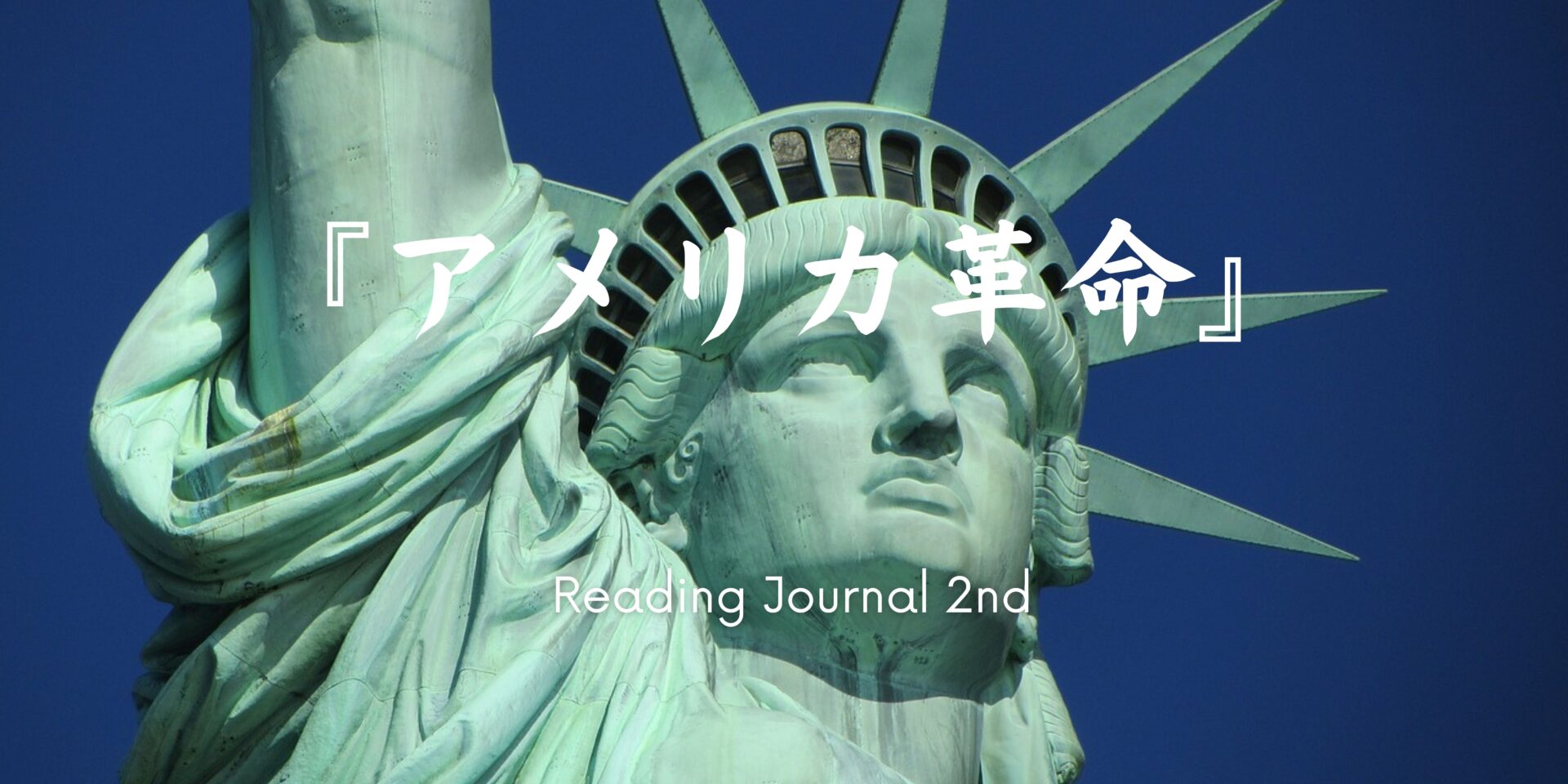


コメント