『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 植民地時代 ― 一六〇七~一七六三年 (その2)
今日ところは、「第1章 植民地時代」の“その2である。”その1“では、アメリカの起源について古典的な見方が、未来から見た歴史の見方(「目的論的誤謬」や「時代錯誤」)であることにふれたのち、最新の研究によるアメリカ起源の4つの視点についての説明がなされた。
それに続いて今日は、植民地が「王領植民地」「領主植民地」「自治植民地」に分かれること、会社を起源とする国家、自治植民地での特許の持つ意味、などについて説明される。それでは読み始めよう。
三種類の植民地
イギリスの植民地には、王領植民地、領主食植民地、自治植民地の三種類の植民地があった。
- 王領植民地:イギリス国王の領地(ヴァージニア、ニューハンプシャーなど)
- 領主植民地:国王から有力者に下賜された植民地(ペンシルバニア、メリーランド、デラウェアなど)
- 自治植民地:特許状を団体に付与し、広範囲な権利をゆだねた植民地(ロードアイランド、コネティカットの二つ)
このような植民地の国制(憲法に準ずるもの)は、異なった次元
- イギリスの国制
- 植民地の国制
- 本国と植民地を一括りにする帝国の国制
に分かれる。
まず、植民地の国制はどこからやってきたかについて考える。
ここで植民地はイギリス国王と枢密院が統括していたことが重要になる。一六世紀末の植民地開拓の端緒においては、本国議会は植民地開拓に対して政治権力を持ってなかった。
そのため国王と枢密院は特許状を発行することで開拓者に対してさまざまな権限を委譲する。
今日では国家と会社という別の形態に思われるものが、かつては同根であり、さらに言えば国家のスタイルを形作ったのは実は会社でもあったということである。(抜粋)
ここで著者は、ヴァージニア植民地はもともとヴァージニア会社として始まったと指摘している。
会社を起源とする国家
会社を起源として国家を理解することは、アメリカの国家の起源をめぐる理論的刷新につながる。(抜粋)
これまでのアメリカ合衆国の理論的根拠は、人民の契約(自然状態において人々が集まり社会を形成し、統治者を選んでそれに従うことに同意する)というものであったが、この考え方にはいろいろな難点がある。
それに対して、会社を典型とする団体論では、特許状を通じてこの難点を回避できる。会社には構成メンバーがいて、その権限は会社に委ねられた特許状により明示されるというものである。
これにより社会契約というフィクションのようなストーリーを回避できるため近年はこのような議論が流行っている。
特許状という武器
この特許状を植民者の側から見ると、「自分たちが他のイングランド人に対して権利を主張できる」という利点があり、つまり土地や財産についての所有権を排他的に主張できる。
そして、この自分はイングランドの臣民としての権利があるということは、他のヨーロッパ人に対しても威力を発揮する。
先住民に対しては、イギリスの政治的立場に影響を受けた。
それまでのスペインのようなヨーロッパ人の考え方は、先住民が「異教徒であるがゆえに、キリスト教徒の征服が認められる」というものであった。しかし、イギリスはカトリック支配に対抗した国教会を持っていたため、それとは違う論理を取り入れた。つまり、先住民を条約の結べる対等な地位にある人とみなした。それにより、戦闘を回避し、スペインと違う態度をとることにより、イングランドのアメリカ大陸における権利を主張した。
一方では征服は人道に反するというような論理をスペインに突きつけつつ、他方で実効的支配を条約という手段によって広げていくというしたたかな戦略である。(抜粋)
また、特許状は、植民地に裁判所をつくる根拠となり、決着のつかない場合は、本国の枢密院を上級裁判所として活用できるという利点もあった。
政治的な仕組みについては、本国の政治体制をコピーし、自らの議会を形成した。
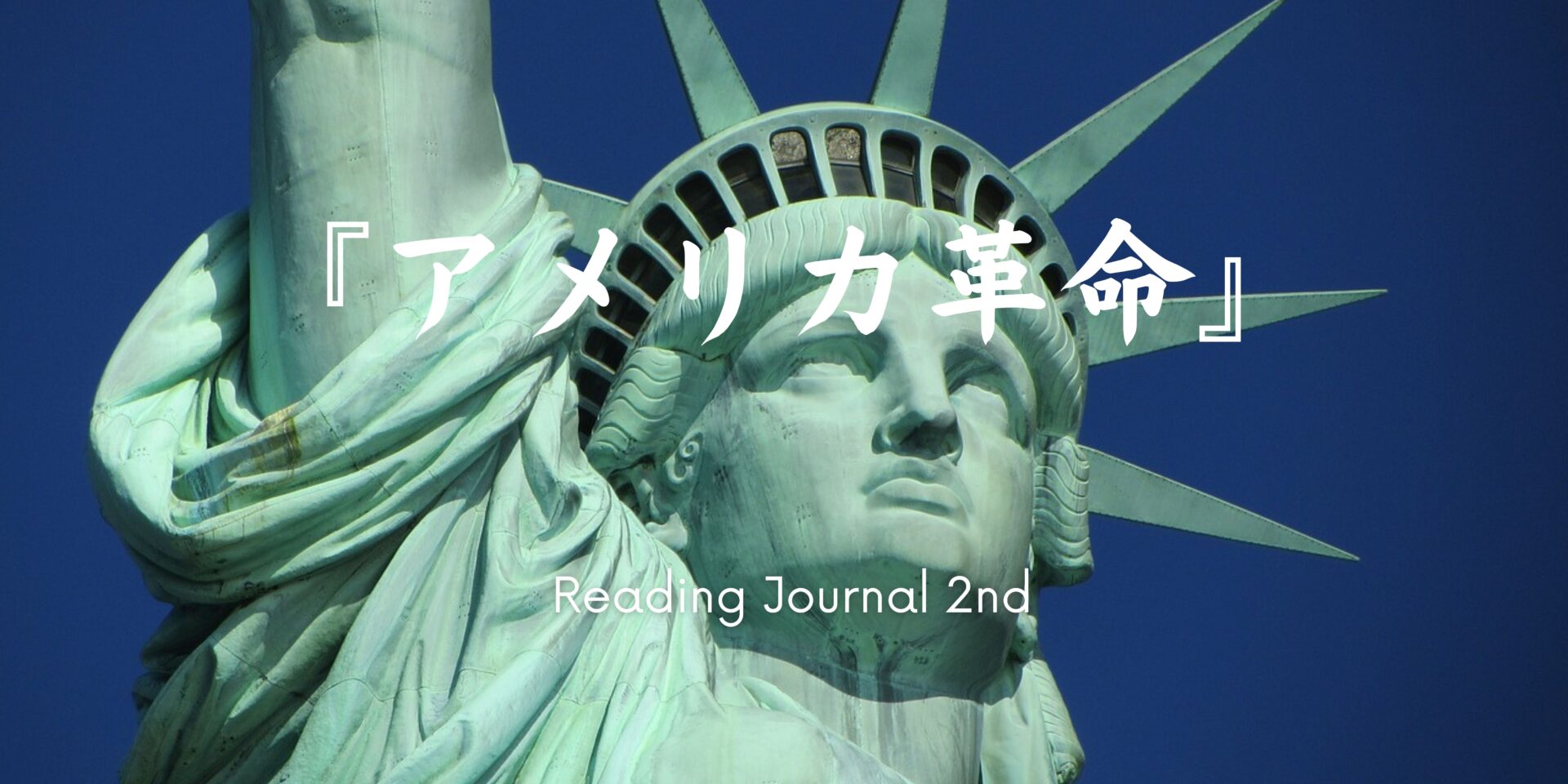

-1-120x68.jpg)
コメント