『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 12 読書の補助手段
今日のところは、「第二部 分析読書」「12 読書の補助手段」である。前回までで、分析読書の解説の解説が終わった。この「分析読書」は、その本だけを読む「本質的読書」の方法であるが、ここでは、関連書の力を借りながら読む「付帯的読書」について書かれている。それでは、読み始めよう。
「本質的読書」と「付帯的読書」
一冊の本を他の本の力を借りずに読むことを「本質的読書」、そして、関連書の助けを借りながら読むことを「付帯的読書」という。
これまでは、外部の力を借りずに一冊の本を読む「本質的読書」を取り扱ってきた。それは、自分の力だけで本を読み通すことを一番に考えてきたことと、関連書などに頼りすぎる読者が多すぎるからである。
他に助けを求めるまえに、自力でできることをすべてやってみることが第一である。(抜粋)
ここで、「付帯読書」における外部からの助けは、
- 読書に関連のある経験
- 読書の手助けとなる他の本
- 注釈書や抜粋
- 辞書などの参考図書
の4つに分類できる。
読書に関連のある経験
まず、難解な本を理解するときに手助けとなる経験は、「普通経験」と「特殊経験」の二種類ある。
- 「普通経験」:家庭生活上の経験などたいていの人間ならば誰でも持つことが出来る経験。
- 「特殊経験」:研究室での実験やフィールドワークなど、積極的に求め、望まないと経験することが出来ない経験である。
小説などは「普通経験」と関連があり、科学書などは「特殊経験」が関連する。また歴史書などのように「普通経験」と「特殊経験」の両方に関連するものもある。
読書の手助けとなる他の本
著者は、同一の主題について二冊以上の本を読む「シントピカル読書」については、第14章で示すとして、ここでは、他書の助けを借りた読書についていくつか述べるとしている。
まず、多くの名著は、互いに関連をもつだけでなく、ある順序で書かれている。読者は、この順序を見落とさないようにするべきである。
作品が書かれた順をおって読むということは、付帯的読書の基礎的、常識的な心得である。(抜粋)
一冊の本を単独に読むとき、文脈が言葉の意味や名辞、命題を見つけるために役立った。それと同じように、付帯的読書では、一冊の本が文脈となり、関連のある数冊の本は、これから読む本の理解を助ける。
また、すぐれた著者は、同時にすぐれた読者であるため、その著者が読んだ本を読むのも、その著者の本の理解となる。
また、関連書を読む時間軸は、過去から現在へというのが自然であるが、現在から過去という読みかたでも構わない。
このような相互に関連する本を読む行為は、科学書やフィクションよりも、歴史書や哲学書を読むときに必要となる。
注釈書や抜粋
読書に対して外部から助けになる第三は、注釈書や抜粋である。
ここで著者は、この注釈書や抜粋は、あまり利用しすぎないようにすること、と注意している。その理由は、注釈書の注釈が正しいとは限らないこと、たとえ正しくても完璧でない可能性があるからとしている。
注釈者が知らない重要な意味を、読者が見つける可能性も残されている。(抜粋)
そして、注釈書に限らず付帯的読書の基本的な心得は、「読み終わってしまうまでは、その本に関する他人の注釈書を読まない」ということである。まずベストを尽くして一冊の本を読み、その後注釈書によって自分の疑問を解決する、のが正し注釈書との付き合いかたである。
この注釈書を読む時の注意は、抜粋や梗概を読むときにも当てはまる。抜粋や梗概が役に立つのは、
- 読んだことのある本の記憶を取り戻したいとき(出来れば自分が分析読書をした時に作ったものがよい)
- 「シントピカル読書」をするときに、ある著作が読者の選んだ主題とかかわりがあるかどうかを知りたいとき
の二つのケースだけである。
参考図書の使い方
まず、著者は参考書といっても、種類が多いため、こおでは「辞書」と「百科事典」についてのみ説明するとしている。
参考書を使う場合は、
- 何を知りたいかという、はっきりとした意図が必要
- 自分が知りたいことが、どこを見ればわかるかを知ることが必要
- 参考書の編集に関する知識が必要
である。
また参考書に取り上げられるのは、一般に広く認められた事実だけであることにも注意しなければならない。
辞書
辞書には、暇つぶしに読むような使い方もあるが、辞書を正しく使うには、辞書という特殊な性格の本の読みかたを学ばなければならない。
また本を読むときに片手に本、片手に辞書という方法では、本全体の調和がわからないので好ましくない。辞書は専門用語や始めてであった単語があったときに引くものだが、それでも著者の言わんとすることがわかる場合は、さし合って引かない方が良い。
辞書は、言葉について次の四つの事項について情報を与えてくれる
- 言葉変遷(書き言葉、話言葉):単語のつづりや発音には、一定の決まりがあるが、これは永久不滅のものではなく、つねに変遷する
- 単語の品詞
- 単語の意味 : 単語は記号であり、複数の意味を持つ
- 言葉の慣習的なもの : 単語は、それぞれの歴史などの影響を受けある種の変形をしている
百科事典
次に著者は百科事典の使い方について説明している。
多くの人は、辞書で単語のつづりや発音を調べるように、百科事典で、日付、場所などの簡単な事実を調べることがある。しかしこれは百科事典の正しい使いかかたではない。辞書と同様に百科事典にも教育的な使い方がある。
百科事典が提供する知識とは、単なる情報ではなく、関連性をもった情報である。(抜粋)
この点については、アルファベット順の百科事典では漠然としているが、部門別の百科事典では、はっきりしている。しかし、部門別の百科事典にも使いにくいところがあり、したがって部門別とアルファベット順の二つの性格を兼ね備えたものが良い。しかし、そのような理想的な百科事典は作られていない。そのため、読者は百科事典の編集者が書いている使用法を読むことが大切である。
百科事典も辞書と同じように名著を読むときの助けになるが、それに一冊の本を他の本の力を借りずに読むことを「本質的読書」、関連書の助けを借りながら読むことを「付帯的読書」と呼ぶ。付帯的読書における外部からの助けは、関連のある経験、関連する他の本、注釈書や抜粋、参考図書などである。:『本を読む本』より
が必要である。意見の相違から生じる議論を決着に導くために、百科事典を使ってはならない。また、百科事典は基本的に事実だけが載っているが、その事実の評価には百科事典ごとに大きく異なっていることがある。
ここで著者は百科事典を引くときには、事実に関する知識が必要としている。
- 事実とは意味がある命題である
- 事実とは意見ではなく、真理に関する命題である
- 事実は現実の反映である:事実とは、唯一の情報か比較的疑う余地のない情報である
- 事実は、ある程度慣習によって決まるものである。現在、真実とされている命題のすべてが、いつまでも真実であるとは限らず、新しい発見などにより、その命題が誤りと立証されることもある
最後に、著者は百科事典に欠けているものとして、「論証がないこと」と「(詩や文学に関する事実は載っているが)詩や文学そのものは載っていないこと」をあげている。
百科事典かぁ~、そんなものあったなぁ~、感じがしますね。今はネット検索でいろいろな情報が拾えるから便利になりました。でも、ある意味権威があるというか、載っていることが真実であると十分信用できるものがあるってのも良いことですよね。ネットには、意識的な偽情報もあるからね。(つくジー)
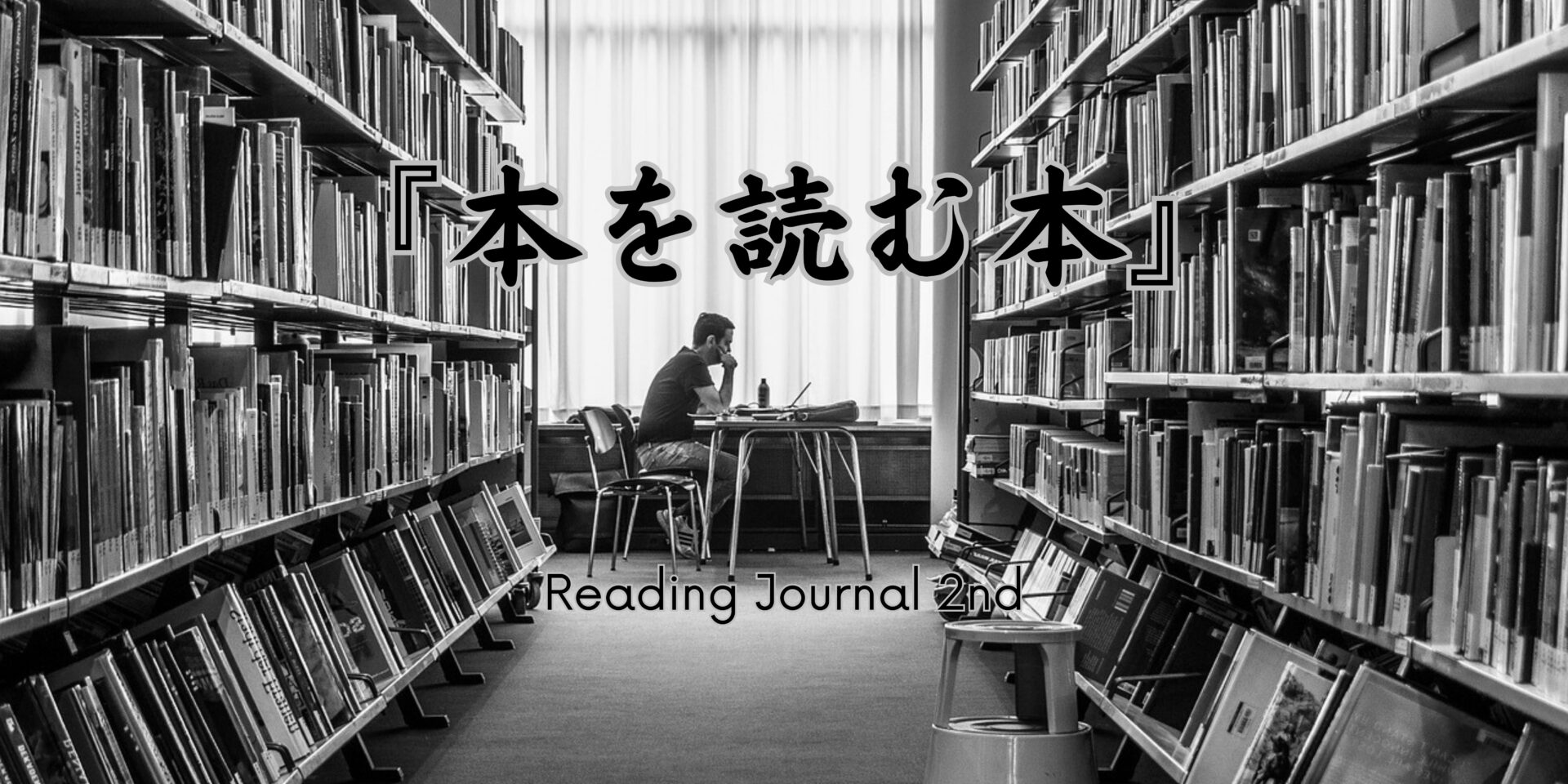


コメント