『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 11 著者に賛成するか、反対するか(前半)
今日のところは、「第二部 分析読書」「11 著者に賛成するか、反対するか」である。ここでは、“前回”に続き分析読書の第三段階「本を正しく批評する」を取り扱う。“前回”は、批評する時に必要な知的エチケットについてであったが、今日のところは、批評に関しての注意点(内容を理解したうえでの反論)である。そして最後に分析読書の三つの段階をまとめている。
ここでは、”前半“で分析読書の第三段階「批評」の注意点について、”後半“で分析読書の三つの段階のまとめをまとめることにする。それでは、読み始めよう。
読者が「わからない」という場合(知的議論のエチケット)
本を読んで「この本がわからない」という場合は、「わからない」ということが批判となっていなければならない。つまり読み手が根拠をあげ裏づける必要がある。
理解できないのが本のせいだということが立証できれば、それ以上読者に批評の義務はない。(抜粋)
ここでは、良い本を考えるとして、読み終えて「わかった」と言えただけでは、分析読書が完了したわけではない。著者に対して納得したか、反論があるか、判断を保留するか判断して初めて次の段階に移る。
ここで知的議論のエチケット、「著者の議論についていくだけでなく、それを受けとめてはじめて、賛成、反対が意味を持つ」ということを忘れてはならない。
このエチケットは、読み手が著者の精神と出会い、著者とある了解が成立してから、賛成や反論をするということである。ここで、理解が成立しても、読者は著者に反論することが出来るということに注意が必要である。
内容を理解した上での反論
ここで著者は、内容を理解した上での反論について解説する。
まず読者が反論するのは、著者に誤りがあるとはっきり指摘できるからである。そしてその場合、
- 人間は理性もあるが感情もあるので、感情的になることがあるということも認める必要がある
- 自分の立場を明らかにする、つまり自分の先入観を心得る必要がある。そうでないと著者もまた著者の立場があることを忘れてしまう
- 議論には党派性がつきものだが、相手の立場に立って、冷静に考えることが必要である
の3つの条件があることが理想的である。しかしこれは理想の条件である。
そのため著者は、もっと簡単な四つの処方を紹介している。
読者が著者に向って「あなたの言うことはわかったが、賛成できない」という場合は、以下の四つの場合である。
- 知識が不足している
- 知識に誤りがある
- 論理性にかけ、論証に説得力がない
- 分析が不完全である
ただし、いずれも読者は、どの部分に問題があるかを明確に指摘できなければならない。
(1)著者の知識が不足している
著者の知識が不足しているとは、著者が解決しようとしている問題に必要な関連知識が十分でないということである。この知識が不足でしていることを理由に著者に反対する場合は、読者が著者に欠けている知識とは何か、それが本当に関連知識といえ、結論に影響するものであることを明らかにする必要がある。
(2)著者の知識に誤りがある
著者の知識に誤りがあるということは、事実に反することを主張しているということである。これは著者の知識不足でも起きるが、それ以外に事実に反すること、ありそうにないことを、真実とか、大いに有りうると主張したり、持っていない知識を持っていると主張したりする場合にも起こる。このとき読者は、この種の欠陥を指摘することが必要である。
(3)論理性にかけ説得力がない
論理性に欠けるとは、推論に誤りがあるということである。この種の誤りは、ふつう2種類ある。
- 「不合理な推論」:結論が仮定された論拠にまったくもとづいていない場合など
- 「推論のおける矛盾」:著者が言おうとする二つのことが相いれない場合
ここでも読者は、著書の議論のどの点で説得を欠いているかを指摘しなければいけない。ただし、この欠点は、主要な結論に影響をもつ場合に限って指摘すればよい。
ここで著者は、ある本が「わかった」と言って(1)(2)(3)の反論の条件に沿った立証が出来ない場合は、読者は著者の主張に賛成しなければならないと注意している。もしそうでない場合は、単に「気に入らない」と言っているだけである。
(4)分析が不完全である
(1)、(2)、(3)の反論では、「著者の主張や推論が妥当であるかが問題」になったが、第四の批判では、「著者意図が完全に果されたか、つまり問題が論証しつくされたか」を問題にする。
分析が不完全である、ということは、著者が最初に提示した問題をすべて解決していないとか、資料をあまさず十分に活用していないとか、あるいは、論証に関連した特徴的な記述がみられない、という場合である。ここでも読者は、とういう点で不完全であるかを、読者自身であるいは他の本の力を借りて、明確に指摘する必要がある。
(1)(2)(3)の反論の根拠がないため、著者に、ある程度賛成する場合でも、この(4)の批判に照らし合わせて、全体について判断を保留することはできる。
ここで著者は、この第四の批判は、分析読書の三つの段階の最終ステップと密接な関係があるとしている。つまり、「概略」の最終ステップは、「著者が解決し用としている問題がなんであるか、を見極めること」、「解釈」の査収ステップは、「解決された問題と未解決の問題を見極めること」であった。そして、「批判」では、第四の批判に照らし合わせて分析の完全さが問われる。
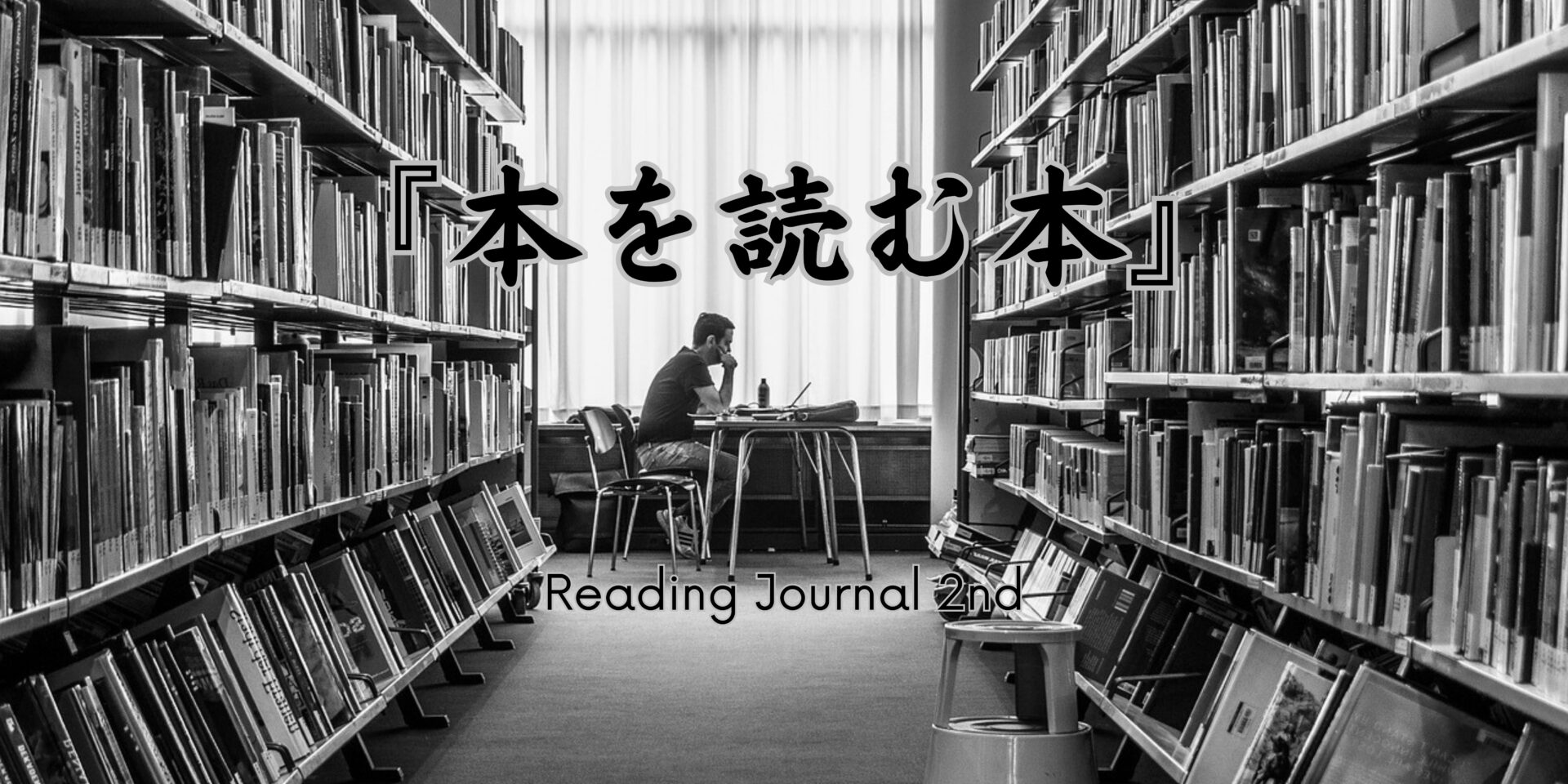

-1-120x68.jpg)
コメント