『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 10 本を正しく批評する
今日から、「第二部 分析読書」「10 本を正しく批評する」に入る。ここから、分析読書の第三段階となる。
分析読書の第一段階は、「本の構造をつかむ」が目的であった(ココとココ参照)。そして第二段階の目的は、「内容を解釈する」であった(ココとココ参照)。そして第三段階の目的は「本を正しく批評する」である。それでは、読み始めよう。
著者の意見を判断する(批評)と分析読書の第三段階
分析読書の第一段階、第二段階を通して、著者の意見を正しく理解することができる。しかし、積極的な読書は、そこで終わってはいけない。
「批評の務めを果たして、つまり判断を下して、はじめて、積極的読書は完了する」。(抜粋)
そのため、分析読書の第三段階は「批評」に関することである。
著者は、この分析読書の第三段階に規則があり、それは知的エチケットの一般的な心得であるとしている。
読者が批評するためには、内容を理解することが前提で、内容を理解した対等な立場になってはじめてこの特権を施行することができる。
学ぶということは、一般に受身の作業であると考えられるが、むしろきわめて積極的な活動である。良き読者は読み終えて、本に語り返し、自分自身の判断を下す。
この判断を下す方法が、分析読書の第三段階の規則である。
修辞と第三段階の規則
解釈に「文法」と「論理」が働いていた(ココ参照)ように、批評では、「修辞」が問題になる。この「修辞」はコミュニケーションが成り立つ場面で問題となる。話し手は、誰でも理解してもらうだけでなく、自分の思うことを伝え、納得してもらいたいと思う。この「修辞」は、相手を納得させ説得するための技術である。
分析読書の第一段階、第二段階の技術は、文法と論理の習得によって得られるが、第三段階の技術は、修辞の習得によって得られる。(抜粋)
「その本が理解した後、賛成、反対、保留の意思を示す」批評の第一規則
ここでは、エチケットが大事である。それは、著者の言い分を完全に理解するまでは、読者は語り返さないということである。つまり分析読書の第三段階に入る前に、分析読書の第一、第二段階を完全に完了したことを確かめなければならない。
したがって、批評の第一規則は、「まず、<この本がわかった>と、会う程度、確実に言えること。そのうえで、<賛成>、<反対>、<判断保留>の態度を明らかにすること」である。
ここで、注意することは、批評と言っても反対するだけでなく、賛成することも含まれること、さらに、納得も説得されるまでにも至らないが、態度の表明を差し控えるという判断の保留も一つの批判行為である、ということである。
この規則はあまり守られていないことが多く、読者はしばしば理解していないのに、批評をしてしまう。
またこの批評の第一規則には、ほかに
- 良い本の場合あっさりわかったと言わないこと
- 「わからない」と言うときは、精いっぱい理解に努めてから「わからない」というときはじめて正当な非難となること
- 一部を読んで「わかった」と言うことは、通読して「わかった」というよりもむずかしいこと
などの注意点がある。
「けんか腰はいけない」批評の第二規則
批評の第二の規則は「反論は筋道をたててすること、けんか腰はよくない」である。
一般に自分が間違っていることを知りながら、相手を言い負かしたところで何もならないが、特に読書の場合は、自分が勝ちたいと思えばいともたやすく勝てる。なぜなら著者は、反論できないからである。
著者との対話をする意義は、相手なら学ぶことであるので、いたずらに論争をしても仕方ない。そのため反論するにも賛成するにもそれなりの準備が必要である。
「反論は解消できる」批評の第三規則
そして、批評の第三の規則は「反論は解消できるものだと考えること」である。つまり著者と、歩み寄る余地はつねにある。
理性のある人間なら、必ず同意に達することができる、ということを念頭においていないと、実りある議論は期待できない。(抜粋)
ここで重要なのは「できる」ということである。他人と意見を異にしても、他人を認めることはできるはずである。人間は他人と意見を異にする場合でも、他人の意見をいれることはできる。
人間は理性があるので、異なった意見を持っていても、他人を認めることはできる。一方、人間は感情と偏見があり、言葉も不完全であるため、感情にくもらされ、利害によってゆがめられる。
だが、人間が理性を失いさえしなければ、理解を防げるこうした障害を取り除くことはできる。単なる誤解から生じた反論は、解消の余地がある。(抜粋)
また知識不足が原因の反論もある。知識不足のため著者の意見に見当違いの反論をしてしまう場合である。この場合は知識を補えば解消できる。
ここの、人間は感情に曇らされ、利害にゆがめられる、という部分は、今読んでいる『問いかける技術』のORJIサイクルの議論(ココ参照)にちょっと似ていると思った。全く関係ない分野なんですけどね。まぁ、蛇足っちゃ蛇足です。(つくじー)
知識は伝達できるものであり、議論によって何かを学ぶことができるはずである。本物の知識がうまく伝達できないときは、
- 意見の食い違いを、お互いに歩み寄ることにより一致できる場合
- 反論が本物の場合
もし②である場合にも、事実に照らし理性に訴えてこれを解消する必要がある。この理性を失ってはいけないという鉄則は、根気良く守る必要がある。
そして、著者の主張に十分な根拠がない場合は、それはあくまでも個人的な意見の域を出ないと考えて差し支えない。そのためこの第三の規則は、「いかなる判断にも、必ず根拠を示し、知識と単なる個人的な意見の区別を明らかにすること」と言い換えることもできる。である。がある。
関連図書:エドガー・H・シャイン(著)『問いかける技術』、英治出版、2014年
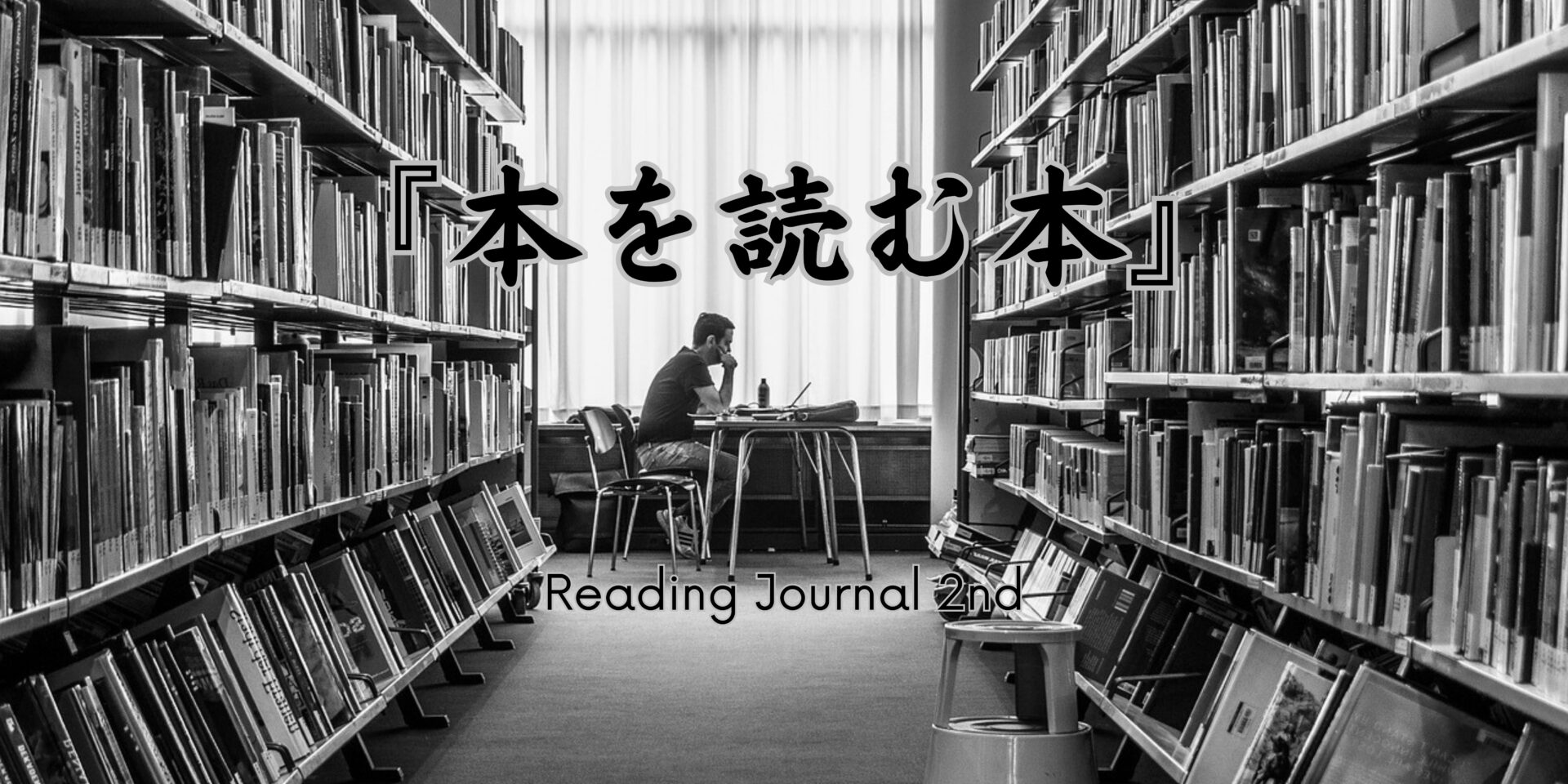
-1-120x68.jpg)

コメント