『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第六章 「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」 — 故事成句をあやつる人びと 2 最後の王朝
今日のところは、「第六章 山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」、「2 最後の王朝」である。ここが本書の最終節。この節は、明を倒した満州族の清王朝についてである。清王朝は中国全土を制圧し、比較的安定した時期もあり『紅楼夢』などの名作も生まれた。しかし、政治はしだいに乱れ内憂外患の状態となり、さらに西太后の登場などがあり、結局は辛亥革命により滅びた。それでは、ラストスパート。
清の中国統一と江南の知識人の反戦運動
清王朝は、もともと金王朝を樹立した女真族でした。この女真族からヌルハチ(清の太祖)が現れ、女真族を統合し、後金王朝を樹立する。そしてその息子ホンタイジ(清の太宗)の代になり、国号を清と名づけ、女真族を満州族と民族名を改めた。かれは中国本土の攻略をつつけるが、要衝の山海関を抜くことができずに亡くなる。そして、中国本土に進撃して、李自成を追い払い、首都の北京を制圧したのが、後継の息子順治帝である。しかし、順治帝は当時六歳であり、実際に進撃作戦をつづけたのは、叔父のドルゴンであった。
清軍は北京を制圧した後、江南に軍を進める。江南はもともと、明王朝の宦官派と激しく対立した良心派の官僚グループ東林党知識人の本拠地だった。明末の政治腐敗を批判した彼らは、清の攻略にあっては、反清運動の中心となった。
しかし、彼らの反清運動にもかかわらず、清王朝は難なく江南を平定、全中国を平定するに至った。
「国家の興亡は匹夫も責めあり」明の遺民、顧炎武
江南の知識人の中には、清に仕えることを拒否し、自ら命をたったり、明の遺民として生涯を終えた人がたくさんいた。その中の一人に考証学の始祖といわれる大学者顧炎武がいた。彼は明の滅亡後、反清運動に加わる。そして、清が全土を統一した後も、清王朝に仕えるのを潔しとせず、膨大な著書をあらわし、明の遺民として生涯を終えた。顧炎武は、「天下を保つ者は匹夫の賤も与って責め有るのみ(天下を保っていくこに関しては、卑賎な一人の男にも責任がある)」と言った。
この言葉がもとになり「国家の興亡は匹夫の責めあり」という清末の改革派や革命のスローガンとなった。
清王朝の政治の安定
清王朝の四代目の皇帝康熙帝は、有能な皇帝であった。彼は、清の中国支配に功績があり特別待遇を受けてきた漢民族の三人の降将、呉山桂・尚可喜・耿仲明の領地を没収する。そしてそれに伴い発生した「三藩の乱」を平定する。
この三藩の乱の後、清王朝は安定して繁栄に向かった。
清の官僚制は、基本的に明のものを踏襲しているが、各長官に満州族から一名、漢民族から一名を任命して複数制をとった。これは元がモンゴル優先方式をとり失敗したことの反省からである。また、清王朝では、現皇帝の息子から一番優秀な人物が次の皇帝に選ばれるシステムをとり、優秀な皇帝が続いた。この頃が清朝の最盛期となる。
『紅楼夢』曹雪芹の傑作
中国古典小説の最高峰と目される曹雪芹の『紅楼夢』が書かれたのも、この清朝の最盛期である。
曹雪芹の家系は代々実入りによい官用織物製造処の長官「江寧織造」をしていたが、公金の使い込みのかどで、全財産を没収され没落した。
没落当時、十歳前後の少年だった曹雪芹は、豪華絢爛たる生活から貧乏のどん底に落ちる劇的体験をしました。以後、曹雪芹は不遇に耐えつつ、曹家の栄光から転落への過程を『紅楼夢』と名付けた小説のなかでたどりなおすことに、情熱を傾けました。(抜粋)
著者は、この『紅楼夢』の第一回に収められた五言絶句に『紅楼夢』創作にすべてを賭けた曹雪芹の思いがにじんていると言っている。
「書かれたことはすべて荒唐無稽、しぼる涙はどこまでも苦い。人はみな作者は阿呆だと言い、そのなかにこめられた意味を読み解いてくれる者もない。」(抜粋)
曹雪芹は推敲を重ねる日々の過労がたたり、『紅楼夢』全百二十回のうち八十回まで書き上げたところで死去した。残る四十回は曹雪芹の構想をもとに高鶚が書き継いだとされている。
ここの『紅楼夢』の部分を読んでいて、本書と同じ井波律子による『中国の五大小説 (上)(下)』を思い出した。この本は、中国の五大小説つまり『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』そしてこの『紅楼夢』についての解説書である。その本を読んでいた当時、『紅楼夢』はなかなか面白そうな本だな?と思った。そして、ここでの著者の熱量を考えると、きっと著者の大のお気に入りの小説なのでないかな?と感じました。(つくジー)
「内憂外患」外国の侵略と西太后
繁栄を誇っていた清朝も、後期になると白蓮教徒の反乱などが勃発するようになる。そして、国内の動揺に加え、西洋世界から強烈な衝撃、すなわちウエスタン・インパクトにさらされるようになる。
イギリスとの「アヘン戦争」に敗れたのちは、次々と西洋によって租借地をむしり取られるようになった。
国内でもキリスト教的秘密結社「上帝会」の蜂起が発端となり、瞬く間に大規模な反乱組織「太平天国」となり、江南を大混乱に陥らせた。
すなわち「外患」と「内憂」の挟み撃ちにあった。
そうしていたころ、咸豊帝は、享楽におぼれしだいに政治的関心が高い西太后が政治の表舞台に立った。彼女は、咸豊帝の死後は自分の息子を皇帝にし、それを背後から操り君臨した。そして、権力を握ってやりたい放題、贅沢三昧を尽くしている間に、中国は外国勢力の侵入によってずたずたにされてしまった。
黄遵憲の「日本雑事誌」
こうした転換期において知識人たちは積極的に外国文化を学ぶ努力を重ね、外国留学など経験した人が増え、膨大な量の外国章が翻訳された。
その中に日本との関わで知られる詩人・黄遵憲がいる。彼は日本・アメリカ・イギリス・シンガポールなどに滞在し、激動の世界情勢を目の当たりにした。日本に滞在したときは多くの日本人たちと交流を結び見聞を広めた。
彼は二百首にものぼる七言絶句を収録した「日本雑事誌」を残した。
その中でかな文字について、それは奇妙だが、覚えやすくて使いやすいということを言っている。
「みみずは蛇ののたり歩くような字で紙をいっぱいにして、このごろご機嫌いかがですかと、おかあさんに手紙をかくこともできる」(抜粋)
清王朝の滅亡
西太后が死去した後、宣統帝溥儀が即位した。しかしその三年後に清王朝は辛亥革命によって滅亡し、中華民国が成立した。
関連図書:
井波律子(著)『中国の五大小説 (上) 』、岩波書店(岩波新書)、2008年
井波律子(著)『中国の五大小説 (下) 』、岩波書店(岩波新書)、2009年
おわりに
本書の最後に短い「おわりに」がある。ここで著者は、中国の成句について次のようにまとめている。
本書で見てきたように、神話・伝説の時代から清王朝の滅亡に至るまで、無数の故事成句が生まれ、中国の歴史を豊かに彩ってきました。全体的にみれば、時代が下がるほど、中国の人々は故事成句を作りだすことよりも、すでに存在する故事成句をここぞという場面で、臨機応変に使いこなすことに力点を置くようになります。この傾向は現代に至るまで変わりません。(抜粋)
そして、誰でも知っている故事成句を引用することは、即座に人々の共鳴を得ようとする巧みな表現方法であるとしている。
[完了] 全28回
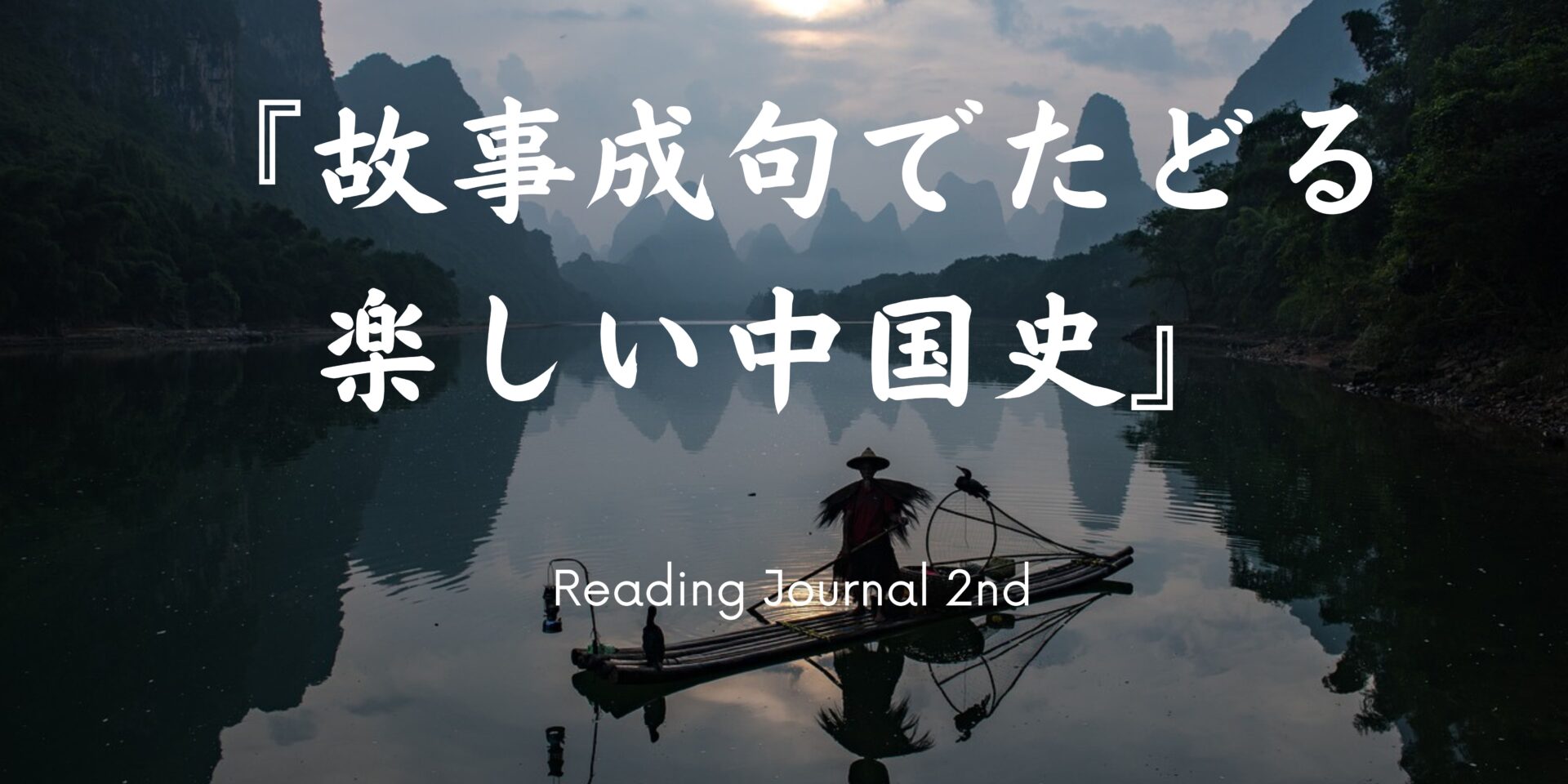


コメント