『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一部 読書の意味 5 意欲的な読者になるには
今日のところは「第一部 読書の意味」の第5章「5 意欲的読者になるには」である。これまでに「読書の4つのレベル」に沿って「初級読書」と「点検読書」について学んだ。そして第二部(第6章~第12章)において本書の中心である「分析読書」が取り扱われる。今日のところ「5 意欲的な読者になるために」では、「分析読書」の準備として、どのような態度で読書に臨む必要があるかが書かれている。それでは読み始めよう。
積極的な読書は、精神や心の成長をさせるなど、そこから利益を得ることを目的とする。そして良い本は積極的に努力して読む価値がある。しかし、その読書計画はなかなか成し遂げられないことが多い。
こういう失敗は意欲的な読者になる方法を知らないために起こるのである。その方法とは、読書によってしか得られない利益を得るために、読書に精神を集中することである。(抜粋)
積極的読書への四つの質問
積極的読書(ココ参照)では、単純な約束事がある。それは、
「読んでいるあいだに質問すること。その質問には、さらに読書をつづけているあいだに、自分自身で回答するように努力すること」。(抜粋)
である。第二レベル以上の読書では、正しい筆問を正しい順序でする習慣を身につけることが重要となる。
この質問は次の4つである。
- 全体として何に関する本か:本のテーマとトピックスの順序
- 何がどのように詳しく述べられているか:著者の思考、主張、議論の要点
- その本は全体として真実か、あるいはどの部分が真実か
- それにはどんな意義があるか
これらが質問の形をとっているのは、第二レベル以上の読書ではつねに読者がといかけをし、これに自分で答えようとする努力が必要であるからである。
「点検読書」は、四つの質問のうち最初の二つの質問に答えるのに役立つ。「分析読書」は、この四つの質問に最後まで答えないと完全にできたことにならない。そして「シントピカル読書」では、最後の質問が最も重要となる。
良い本は読者にとって難解である。また難しいくらいの本でないと良い本とは言えない。このような本を読むときは背伸びをしなければならない。そして読者がその本にくたびれてしまうのは、背伸びをしているからではなく、うまく背伸びが出来ないことから来る。
積極的な読書をつづけるには意志の力だけではだめだ。ちょっと見ただけではとても歯がたたないと思われるものに手をのばし、自分を引き上げることのできる技術を身につけることが要求されるのである。(抜粋)
書き込みの効力
本に問いかけ、それに答えながら読書するには、手に鉛筆を持っていた方がやりやすい。
著者は、「鉛筆は読み手の精神の活発のしるしである」とし、「行間を読む」だけでなく「行間に書く」ことを勧めている。この行間に書く行為が有効な理由として
- 目覚めていられるから:単に起きているだけでなく頭をはっきりさせておける
- 考えたことをまとめることにより、自分がわかっているかがわかる
をあげている。
ここで、効果的な書入れの仕方として、いくつかの例が示される。
- 傍線を引く。重要語な箇所や、著者が協調している箇所に線を引く
- 行のアタマの余白に横線を入れる。すでに傍線を施した箇所を強調するため、または、下線を引くには長すぎるとき
- ☆印、※印、その他の印を余白につける。これは濫用してはならない。その本の中でいくつかの重要な記述を目立たせるために使う
- 余白に数字を記入する。議論の展開につれて要点のうつり変わりを示すため
- 余白に他のページのナンバーを記入する。同じ本の他の箇所で著者が同じことを言っているとか、これと関連したり矛盾したことを言っているということを示すため、各所に散在する同じ種類の発想をまとめるためである。 —-を比較参照せよ、という意味で cf. を使う人も多い
- キー・ワードを○でかこむ。これは下線を引くのとだいたい同じ効果をもつ
- ページの余白に書入れをする。ある箇所を読んでいて思いついた質問や答えを記録するため、または複雑は議論を簡単な文にまとめるため、主要な論点の流れを追うために、これをする。裏表紙の見返しを使って、出てくる順番に要点をメモし、自分専用の索引を作ることもできる
読書レベルと書込み
この本に書き込みをする方法は、読書のレベルによって3つ種にわかれる。
① 「点検読書」の場合
この段階では、書込みをする時間はないが、この段階でも重要な問いかけをしながら書きとめておく方が良い。
書きこむべきことは「一 それはどんな種類の本か」「二 全体として何を言おうとしているか」「三 そのために著者は、どのような構成で概念や知識を展開しているか」である。これを目次やタイトル―ページにするとよい。
この段階の書き込みは、内容に関係ない構成についてである。
② 「分析読書」の場合
「分析読書」になると、読者は本の真実性や意義という質問に答えねばならない。そして、書込みも著者の概念に関するものになる。
③ 「シントピカル読書」の場合
複数の本を同時に読む「シントピカル読書」でも、書込みは概念に関するものになる。しかし、その覚え書きは同じ本の他のページだけでなく、他の本の内容にも及ぶ。
シントピカル読書をする場合は、覚え書きのしかたも複雑となり、複数の著者全員についてその議論の進め方の覚え書きを作る。著者はこのような書込みを「弁証法的」と呼ぶとしている。これについては第四部で扱う。
読書習慣を身につける
熟練した技術を持つ人は、それぞれの技術のもつ規則どおりに仕事をする習慣を身につけている人である。これは読書でも同じである。
規則を守って仕事をする習慣を身につける道は実行以外にない。「習うより慣れろ」と言うではないか。(抜粋)
いったん習慣を身につけると多くの規則も自然にしかも流暢にできるようになる。
規則を守ることと習慣を身につけることは同じではなく、習慣というのは、規則を知っているという意味でなく、身についているという意味である。
この習慣を身につけるには、一つひとつの部分的な動作に注意を払って練習し、それが次第に全体として滑らかな動きになるまで行う必要がある。
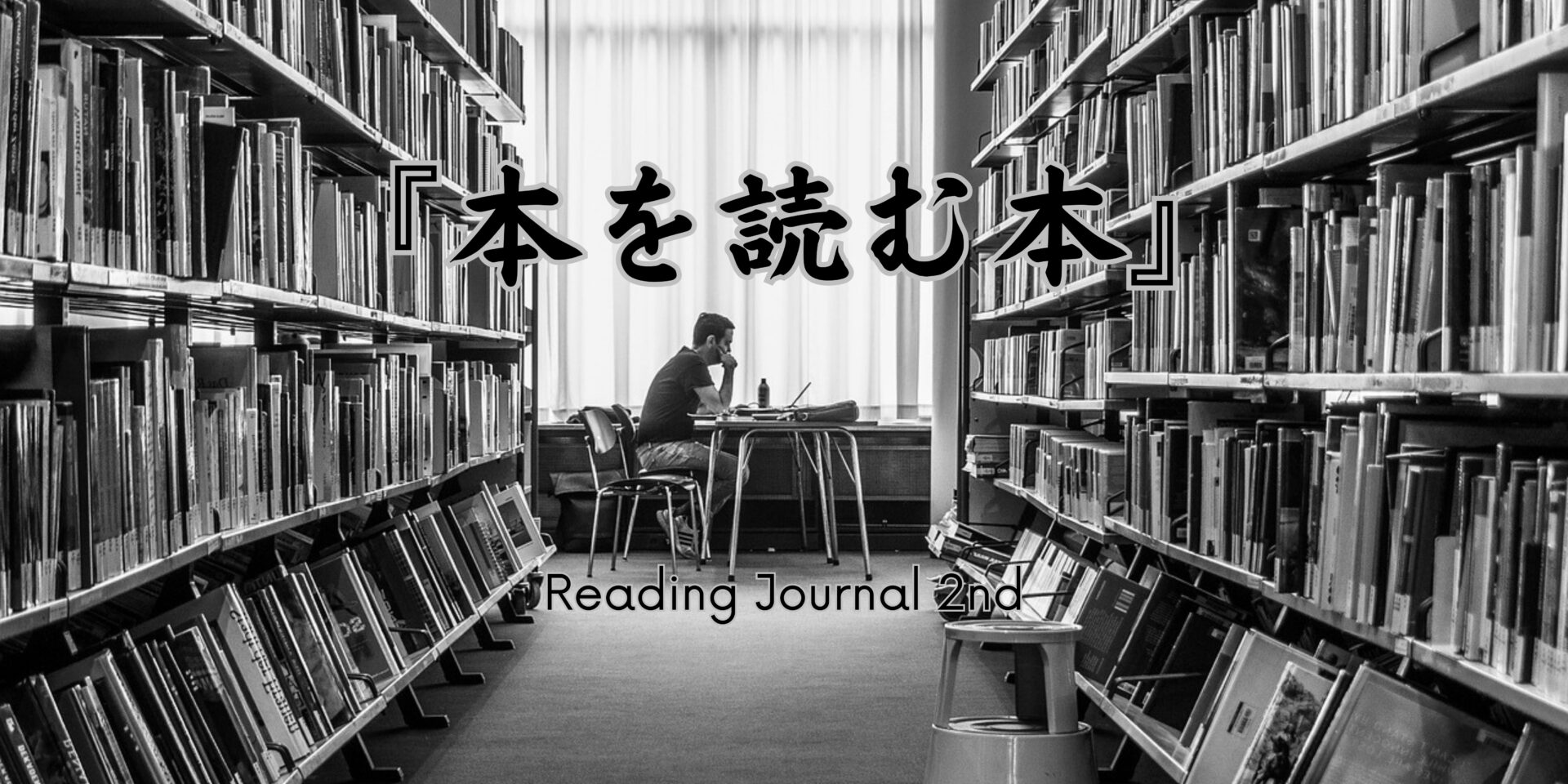


コメント