『本を読む本』M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一部 読書の意味 2 読書のレベル
前回「1 読書の技術と積極性」において、この本の目指すものは、「積極的な読書」を通して「理解を深めるための本」を読む技術であることが示された。今日のところ「読書のレベル」では、読書のレベルについて検討される。そして後の章においてレベルごとの読書法が示される。それでは、読み始めよう。
読書は手助けを借りない「発見」と同じで、姿の見えない教師から学ぶことだが、そのやり方を知っていなくてはうまくいかない。(抜粋)
ここでは読書の四つのレベルについて述べられる。ここで「レベル」と言うのは「種類」違い、低い方から高い方へ段階的に積み上がり、一つのレベルは次のレベルに吸収され累積されるようなものである。
初級読書 ‐ 第一レベル
最初のレベルの「初級読書」とは、読み書きの全くできない子供が初歩の読み書きの技術を習得するためのものである。ここで大切なのは、「その文は何を述べているか」を理解することである。
この本の読者ならばこのレベルはとっくに習得ずみであると思われるが、高い読書力がついていてもこのレベルをなおざりに読書することはできない。また不慣れな外国の本を読む場合でも初級読書の原則に従わなければならない。
母国語で書かれている本でもこのレベルの問題にぶつかる読み手も多く、その場合は、そのような欠陥を強制する必要がある。速読の訓練で第一レベルの習得に重点を置くのは、そのためである。(初級読書及び速読については3章、4章で述べる。)
点検読書 ‐ 第二レベル
第二のレベルは、「点検読書」である。これは時間に重点を置くもので、一定の時間内に割り当てられた分量を読むことを要求される。点検読書の目的は、与えられた時間内にできるだけ内容をしっかりと把握することにある。
この「点検読書」は「拾い読み」「下読み」と呼んでも良い。ただし「拾い読み」と言っても気ままに読みかじることではなく、「系統立てて拾い読みする」ことである。
この「点検読書」では、「この本が何について書いたものであるか」を問題とする。具体的には「この本はどのように構成されているか」「どのような部分に分けられるか」、「どのような分野の本か。小説か、歴史か、科学論文か」を検討する。
この点検読書については、4章で詳しく述べる。
分析読書 ‐ 第三レベル
第三のレベルは「分析読書」である。これは読み手にかなりの努力が必要な読み方である。
「分析読書」は、徹底的に読むことで読み手として可能なかぎりの極めて高度な読み方であり、積極的な読書である。
分析読書とは、取り組んだ本を完全に自分の血肉と化するまで徹底的に読み抜くことである。「書物には味わうべきものと、呑[の]みこむのとがある。また、わずかだが消化すべきものもある」とフランシス・ベーコンも言っているが、分析的に読むとは、本をよくかんで消化することである。(抜粋)
この分析読書は第二部(6~12節)で取り扱う。
シントピカル読書 ‐ 第四レベル
最後の第四のレベルの読書は「シントピカル読書」である。これは最も複雑で組織的な読書法である。
これは「比較読書」とも呼ぶことができ、一冊だけでなく一つの主題について何冊もの本を相互に関連づけて読むことである。
単にテキストを比較するだけでは、シントピカル読書として十分とは言えない。熟達した読者は、読んだ本を手がかりにして、「それらの本にはっきりとは書かれていない」主題を、自分で発見し、分析することもできるようになるはずである。(抜粋)
シントピカル読書は第四部(14、15節)扱う。
ここでの読書のレベルを、『難解な本を読む技術』の内容と比較すると、
点検読書・・・「準備」の節で書かれていた棚見の技術、そしてその進化系の「さらに進んだ読書」の「包括読み」だろうか?
(包括読みは点検読書というには高度すぎるかな?)
分析読書・・・これは、「通読」(ココとココ)+「詳細読み」(ココとココ)で決まりである。
シントピカル読書・・・これは「さらに高度な本読み」(ココとココとココとココ)全体ですかね。
(つくジー)
関連図書:高田 明典 (著)『難解な本を読む技術』、光文社(光文社新書)、2009年
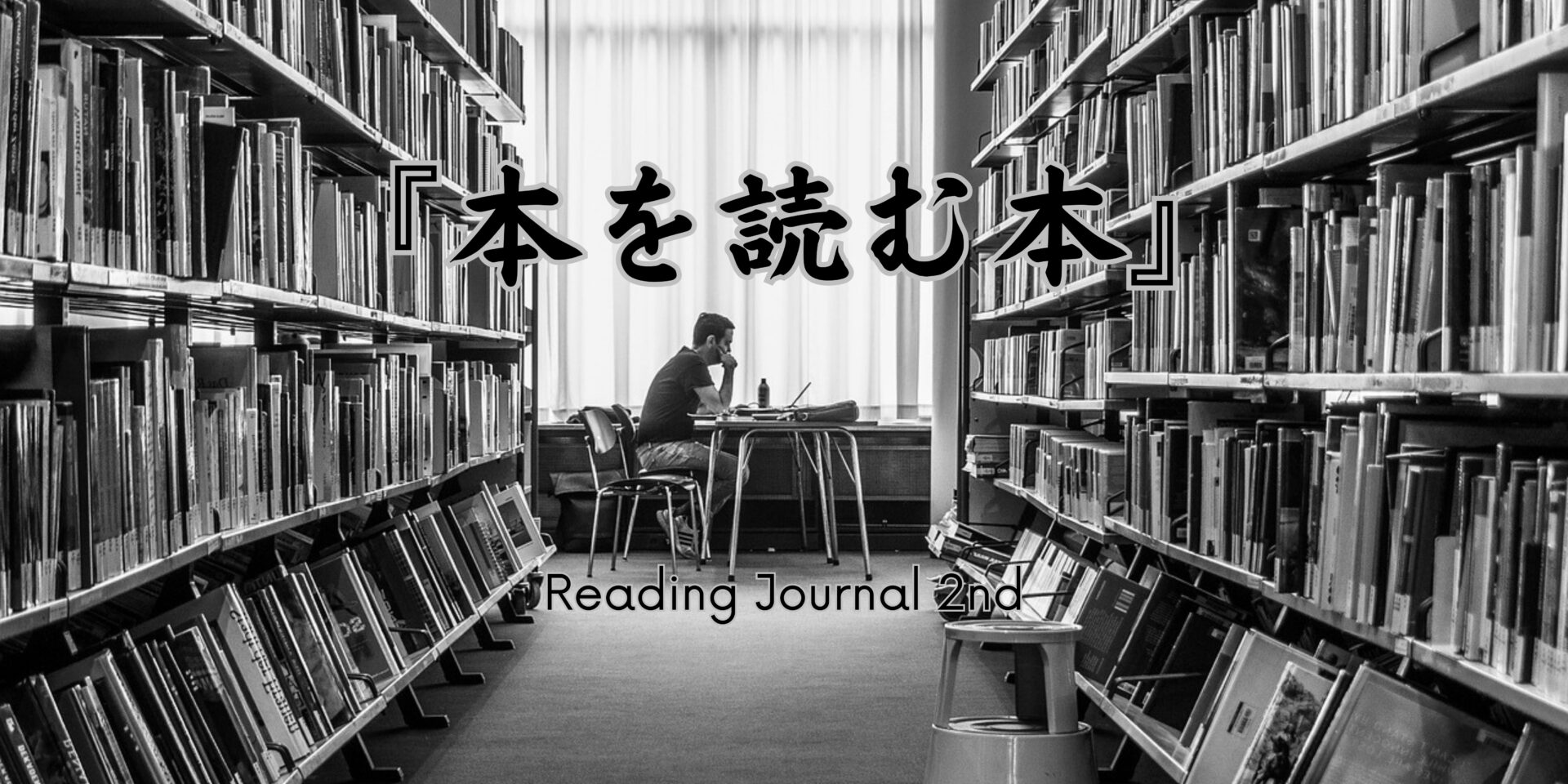


コメント