『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに 良好な人間関係と強い組織を築くために
今日のところは「はじめに 良好な人間関係と強い組織を築くために」である。前回は、監訳者の金井壽宏による序文であったが、今日のところ「はじめに」は、著者シャインによる序文である。ここでシャインは、この本の執筆の動機や前著『プロセス・コンサルテーション』、『人を助けるとはどういうことか』との関係について述べている。
前回の「監訳者による序文」に指摘されていたが、シャインは「自分が働き、自分が話す文化」に警笛を鳴らし、それとは反対に位置する「謙虚に問いかける」ことが人間関係やチームワークなどの鍵であるとし、本書ではこの「問いかける技術」が主題となる。それでは読み始めよう。
「謙虚な問いかけ」とは
今の世界は複雑化し、文化的な多様性が増し、人々は互いに依存し合うことにより成り立っている。だからこそ、良好な人間関係を築くためには適切な質問をして、相手の考えていることを聞くこと、互いに尊重し合う気持ちを大切にすることが必要である。
シャインは、その質問がどんな質問でも良いわけではないとし、『人を助けるとはどういうことか』で「謙虚な問いかけ(Humble Inquiry)」と名づけた。そしてそれを以下のように定義している。
「謙虚に問いかける」は、相手の警戒心を解くことができる手法であり、自分では答えが見出せないことについて質問する技術であり、その人のことを理解したいという純粋な気持ちを持って関係を築いていくための流儀である。」(抜粋)
自分が話す文化と「謙虚な問いかけ」
ここで著者は、そのコンサルタントとしての経験から組織とこの「謙虚な問いかけ」の関係について説明する。
組織、特に安全を第一に考えなければ危険な業界には、良好な人間関係と信頼や高いコミュニケーションが人事の垣根を越え共有されていることが重要である。
各地で起こる重大事故の事例を調べると、共通するのは、現場の従業員たちは事故の発生や抑制にかかわる情報を持っていたが、それが組織の上層部まで届かなかったということである。
悪い知らせを伝えて上司の反感を買うことを恐れて、高いリスクを孕んだ選択肢を選びとってしまうということが、驚くほど頻繁に組織のなかで起こっている。(抜粋)
つまり、現場の従業員たちが安心して声を出せるような風土の醸成が、事故が起こってしまった職場ではできていなかったということである。
このような風土づくりをするためにはどうすればよいか?
答えは、これまで米国文化において重要視されてきた価値観とは対極に存在している。われわれの社会は話す力を過大評価しているが、むしろ発言を控えて問いかける力を高めていくべきなのだ。(抜粋)
相手に尋ねることによりも以下に自分がしゃべるかに注力しがちであるが、人間関係を築くにも、問題を解決するにも、物事を前進させるにも、すべて適切な質問がなければうまくいかない。
そのため著者は、特に高い地位にある幹部や指導者こそ「謙虚に問いかける」ことを身につけ、オープンな組織づくりの第一歩を踏み出す必要があると言っている。
本書の目的と前著との繋がり
著者は、本章に至る前に書いた2冊の本の内容を
- 『プロセス・コンサルテーション』では、的確な質問は助言よりも効力が発揮することまとめた。
- 『人を助けるとはどういうことか』では、援助の現場でも助ける側がいきなり助言をせず、相手にいろいろと尋ねることが重要であることについて述べた。
であるとしている。
そして著者は「話すことよりも問いかけること」これが人付き合いにおいてもっとも根本的なものであり、それがもっと注目されるべきであるとの気持ちが強くなったとしている。
すべての人が自分の役割を果たすことが必要であり、そのためには良好なコミュニケーションが欠かせない。その良好なコミュニケーションには信頼関係の構築が不可欠であり、信頼関係の構築には「謙虚に問いかける」ことが求められる。
関連図書:
エドガー・H・シャイン (著)『プロセス・コンサルテーション―援助関係を築くこと』、白桃書房、2012年
エドガー・H・シャイン (著)『人を助けるとはどういうことか』、英治出版、2009年
本書について
ここで著者は、各章のアウトラインを示している。
- 第1章では「謙虚に問いかける」の定義について述べる。ここでい「謙虚」は、年長者や身分の高い人、偉業を成し遂げた人に対していだく気持ちではなく、われわれが(仕事を達成するために)誰かにたよるときの(「今ここで必要な」)謙虚さのことである。
- 第2章では、「謙虚に問いかける」の理解のために、いくつもの例が挙げられている。
- 第3章では、「謙虚に問いかける」で使われる質問形式がほかの場合と、どう違うのかが説明される。
- 第4章では、「自分が働き、自分が話す文化」について解説され、このような文化のもとでは、「謙虚に問いかける」ことがいかに難しいかを考える。
- 第5章では、リーダーシップを担う立場の人こそ「謙虚に問いかける」ことが必要であることについて述べられる。
- 第6章では、この「謙虚に問いかける」ことを難しくしているのは、世間の暗黙の了解や社会規範だけでなく、人間の脳の複雑さや社会の様々な人間関係も制約や障壁を作り出すことが説明される。
- 第7章では、この「謙虚な問いかけ」の力を高め、実践するためにどうしたらよいかということについて、著者の意見が述べられる。
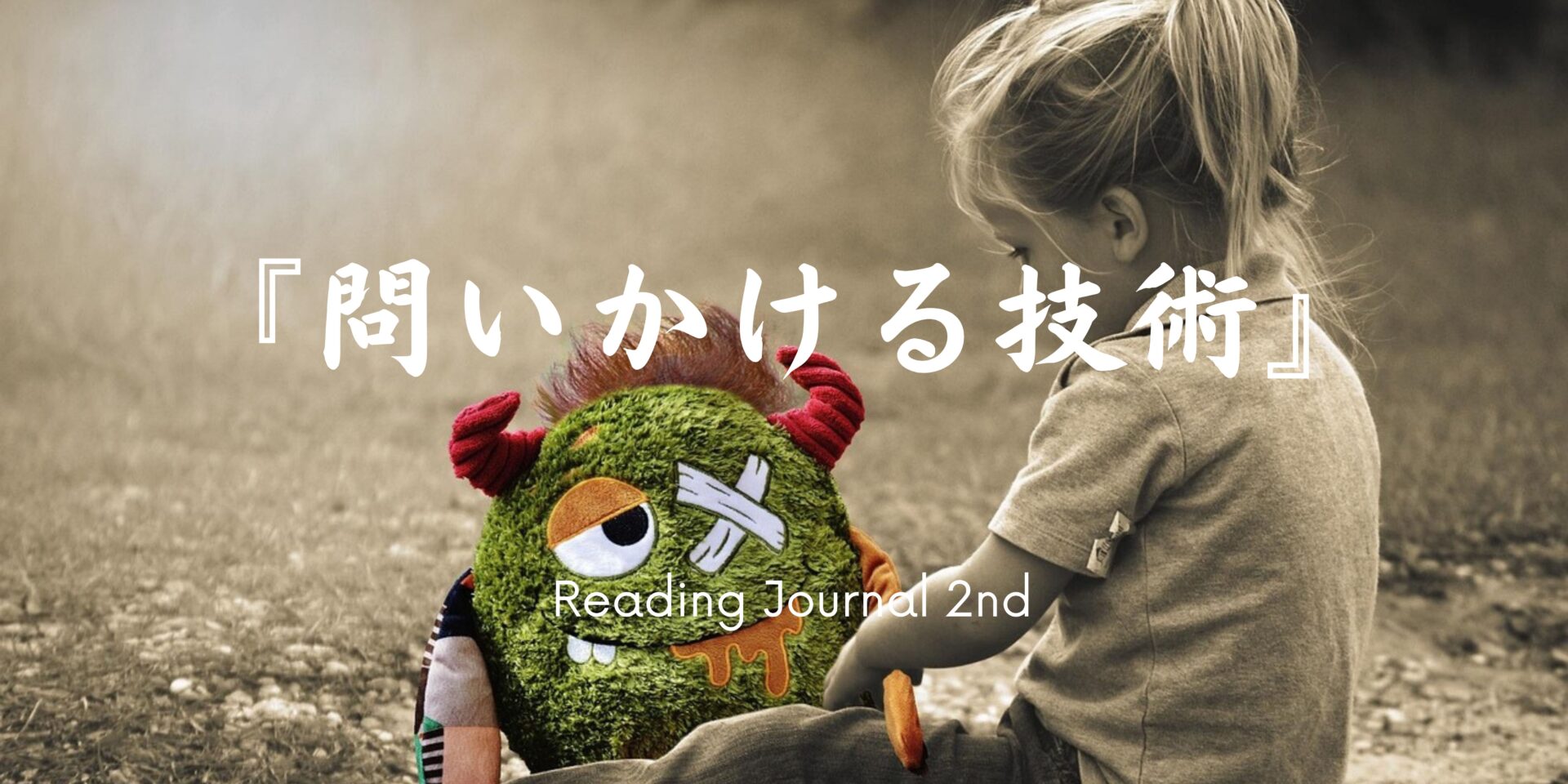


コメント