『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
解説 金井壽宏(後半)
今日のところは、監訳者・金井壽宏による解説の”後半“である。”前半“においては、支援学と「シャイン経営学」「シャイン組織心理学」との関連やシャインの研究歴、さらに支援の3つのモードについての解説があった。
今日のところ“後半”では、この支援学と関係性・相互依存について、さらには、それを日本という枠組みで考察する。それでは読み始めよう。
関係性・相互依存と支援学
この後、著者はシャインの生い立ち、そして愛弟子だった著者ならではのサインのエピソードに触れた後、他者との関係性・相互依存という視点から支援学を解説する。
ここで金井は、お互いが相手に依存状態になる相互依存は、困るとしながら、
お互いに自立した人間同士が、自律性をないがしろにすることなく、お互いを助け合い、支え合えるなら、理想的だ。(抜粋)
と言っている。
そして、支援を求めることが、それをうまくできる人が、相互作用の中で、ネットワークの中でいい人生、いい働き方を享受できるとしている。
このようにお互いに足りない部分を補完的につながる関係性は、垂直的な関係性と異なる対等な水平的な関係となる。このように対直的な依存、他律、庇護的立場ではなく、自立、自律、独立独歩のような水平的な独り立ちが洋の東西を問わず大人になる第一歩である。
このように自律しつつも共同できる人間になることが大事だと最も明示的に述べたのは『7つの習慣』で名高いスティーブン・コヴィーである。彼は、人間の発達は、幼少期の依存から始まり、依存から独立、独立から相互依存への道のりと考えた。
自律するためには親や先生の支援がどこかにあり、成人になっても、自律したが孤立しないためには相互依存して生きていくことが大切である。
助けを求めることは、依存というだけでなく、水平な関係でも必要で健全な相互依存は、悪くないという発想はシャイン支援学の思考や行動にも表れている。
日本人にとっての支援学と関係性・相互依存
ここで金井は、さらに進んでこのような相互依存と支援学の関係を日本社会に当てはめて考えている。この人との関係の中で生きるということは、日本社会ではより重要であるからである。そして金井はそのような関係性の文化がいま綻び始めていると危惧している。
精神病理学者の木村敏は、人と人の間が人間理解の基本と述べ、社会学者の浜口恵俊は西洋の「個人主義」に対して、日本では「間人主義」の社会と特徴づけ、日本人にとってのキャリアは、社会的脈絡と呼ばれる関係性に根付いているとした。さらに著名な心理療法家の河合隼雄は、イーチアス(eachness)という造語を作り、西洋の個性(individuality)と対比させ、日本人に個性がないのではなく違う意味での個性があり、日本人は創造性に乏しいのではなく異なる種類の創造性を持っていると言った。
ゴフマンからシャインへと継承された「社会的」経済学の「社会的」つまり関連性にかかわる機微は、そもそも日本社会でより濃厚だったはずだ。(抜粋)
そうであるため、日本人ならばこそ、この支援学をいい形でマスターし、さらに世界に向けて発信できるのではないかとしている。
プロセス・コンサルテーション 10の原則
金井は最後に、シャインの本書では、シャインと到達点として知られる「プロセス・コンサルテーションの10の原則」(『プロセス・コンサルテーション — 援助関係を築くこと』 白桃書房、2002)について触れられていないとして、その原則について解説を加えている。ここでは項目のみを引用しておく。
原則1 絶えず人の役に立とうと心がける。
原則2 今の自分が直面する現実からけっして遊離しないようにする。
原則3 自分の無知を実感する。
原則4 あなたがどんなことを行っても、それは介入、もしくはゆさぶりになる。
原則5 問題を自分の問題として当事者意識を持って受け止め、解決も自分なりの解決として編み出していくのは、あくまでクライアントだ。
原則6 流れに沿って進む。
原則7 タイミングがすごく大事。
原則8 介入で対立が生じたときには、積極的に解決の機会を捉えよ。
原則9 ないもカモがデータだと心得よ。誤謬はいつでも起こるし、誤謬は学習の重要な源泉だ。
原則10 どうしていいかわからなくなったら、問題を話し合おう。(抜粋)
関連図書:
スティーブン・R・コヴィー(著)『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』、キングベアー出版、2013年
エドガー・H・シャイン(著)『プロセス・コンサルテーション — 援助関係を築くこと』、白桃書房、2002年
[完了] 全22回
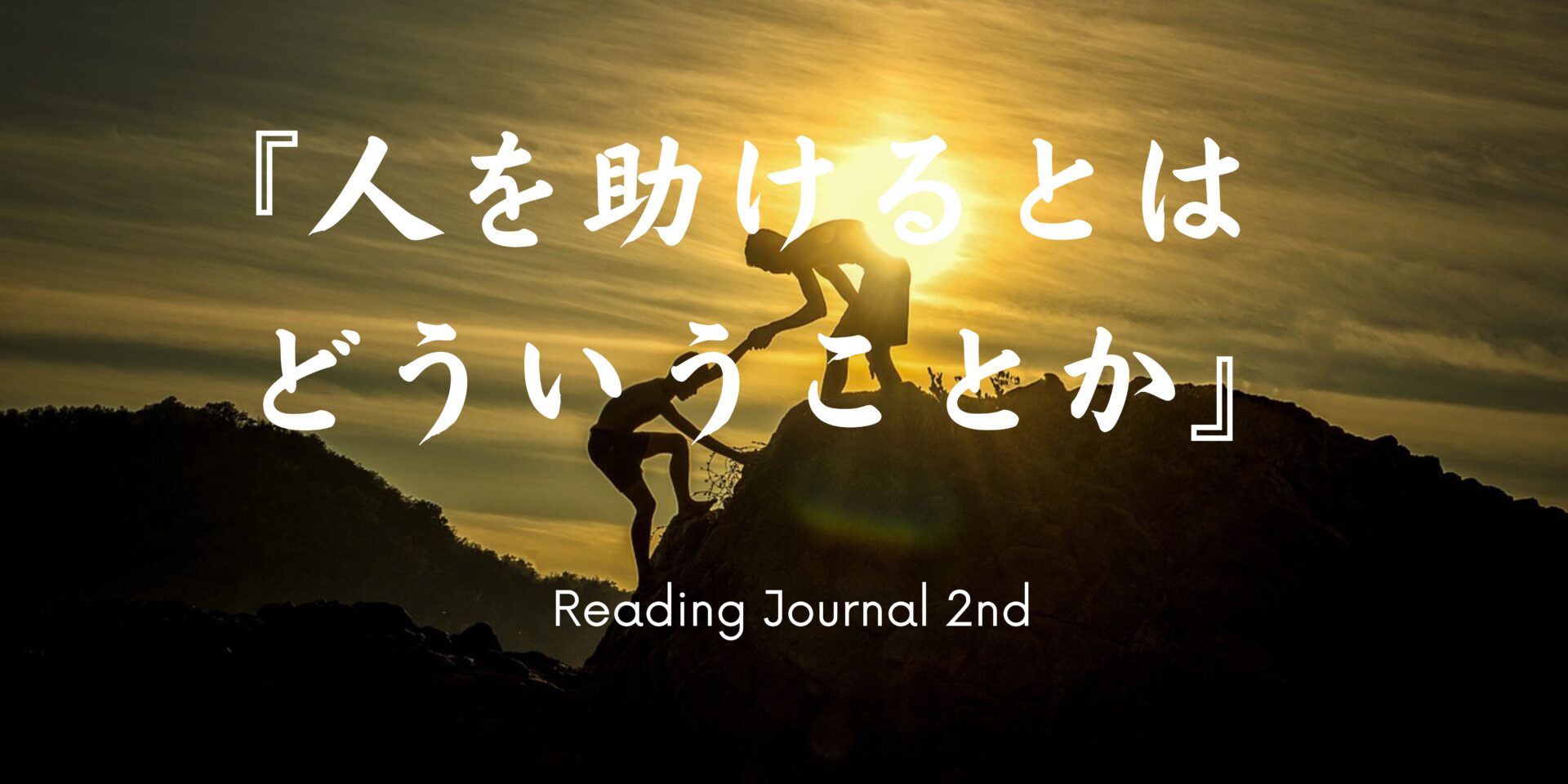
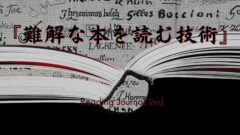

コメント