『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 本読みの方法(2) 二度目:詳細読み(後半)
今日のところは「第4章 本読みの方法(2) 二度目:詳細読み」の“後半”である。”前半“では、「わからないを大切にする」をキーワードにして、どのように詳細読みの方法が具体的に書かれていた。今日のところ”後半“では、「開いた本」の読み方や「本当にわからない」場合の本を寝かせる方法と人に聞く方法について説明される。それでは、読み始めよう。
「開いた本」の読み方
「開いている」タイプの本を「閉じている」として読み進めると、理解に決定的な差が出る。
「開いている」本には、主張のようなものが無く、時に著者の思考が矛盾していると思われる部分も現れる。それは「開いている」本は、ある考え方の正当性を主張するのではなく、さまざまな概念や思考、論理からを提示して、読者が自己決定をすることを要求するものだからである。
開いている本を読む目的は、知識を得ることではなく、読者自身が自らの思考によって何らかの帰結を紡ぎだすことです。(抜粋)
開いている本では、読者は自らの思考で答えを自己決定しながら進んでいく必要がある。そして多くの場合、次の節や章などで、その自己決定に対して新たな疑義や問題点が提示される。このような著者との「戦い」が開いている本の狙いであり、自身の思考がさまざまに変容していく様子を自覚しながら読み進める必要がある。
ここで著者は、この開いている本での著者との戦いは、後述の「批判読み」での闘いとは違い、「著者の想定している戦いの中に身を任せる」という意味で「同化読み」の一種であると注意をしている。
どうしてもわからない時
努力してもどうしてもわからないと感じる時の対処は二つある。ひとつは一旦諦めるというもの、もう一つは、誰かに聞くというものである。
一旦諦める — 本を寝かせる
どうしてもわからない時は、潔く一旦諦めるという方法がある。ここでは、「諦め方」が重要である。
ここで著者が行っている方法は、本は書棚のよく見える位置に置く、読書ノートはいつでも手に取れる位置のおく、というもので、ときおり本の背表紙を見たり、読書ノートを読み返したりする。これを「寝かせる」という。
この「寝かし」ておくことにより、その問題が次第に自分の身近な問題と重なったり、折に触れてその問題が思考を刺激して思考がその方向に向ったりすることがある。その時がもう一度読み始める瞬間である。
「寝かす」とは、その瞬間を待つ、という作業であり、読書における一つの重要な技術であると言えます。(抜粋)
誰かに聞く
もう一つの対処法は「誰かに聞く」というものである。ここで大切なことは「わかっている人に聞かなければ、何も意味がない」ということである。したがって、この方法はまわりにまともな研究者がいるということが前提となる。
そしてもう一つ重要なことは、まともな人に聞いたとしても、その質問が「まともな質問」でなければ答えづらいということである。「まともな質問」とは、自分でその疑問と格闘した痕跡が認められるものである。考えて考えて考えても分からなかったんだなと、感じられるときにのみ答える側も真剣に向き合うことができる。「聞いた方が早いや」と言った質問にはおざなりな返答しか返ってこない。
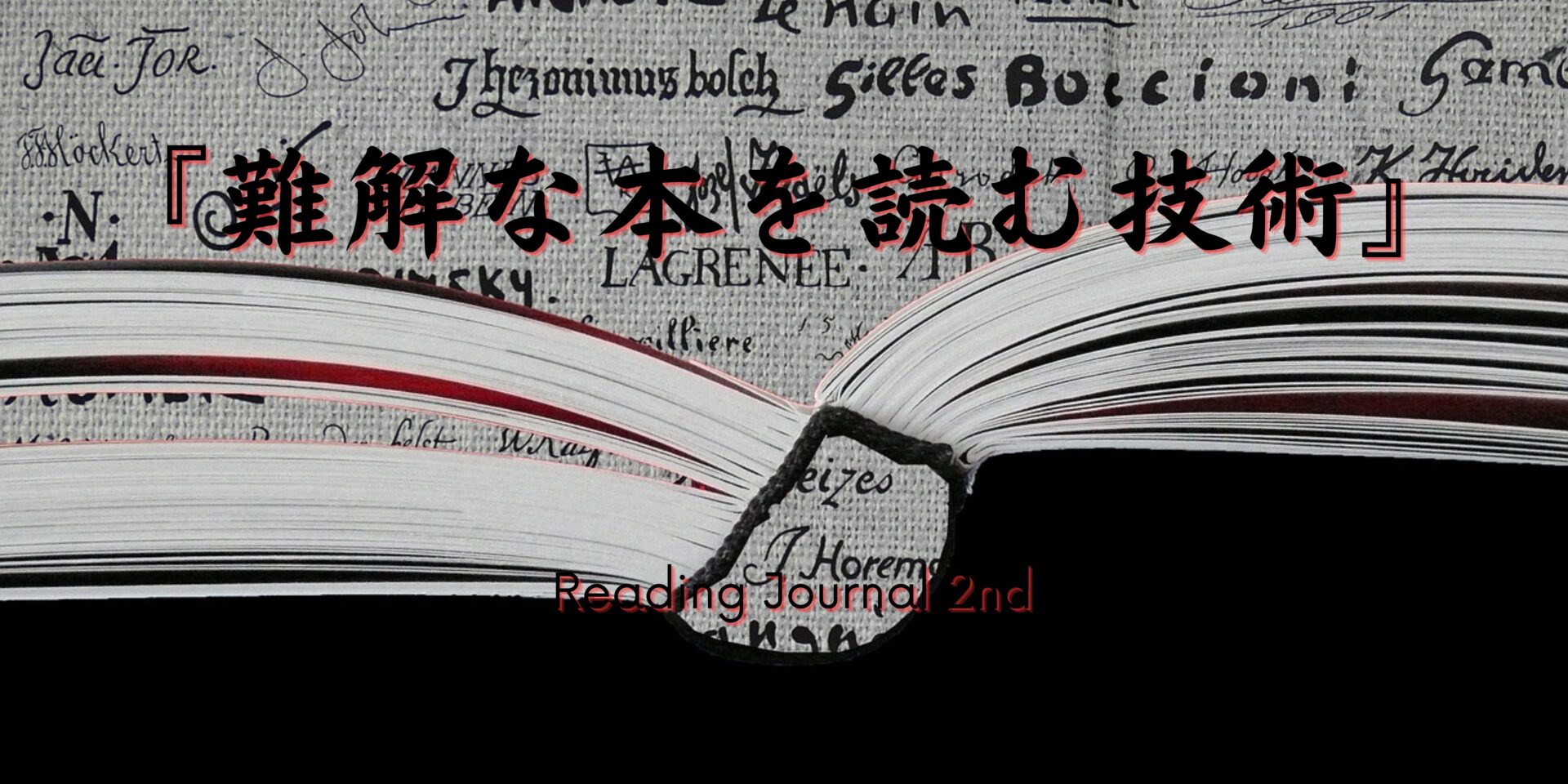


コメント