『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
六 友人の説得(後半)
今日のところは、「六 友人の説得」の”後半“である。”前半“は、前章「ヨブの嘆き」に対する友人エリパズの説得の話であった。ここでエリパズは、ヨブに伝統的な賞罰応報的立場で話をする。しかしそれにヨブは容易に同意できなかった。なぜならば今ヨブが置かれている状況は、義が勝ち、悪が常に敗れるような現実ではなく、むしろその逆の状態だったからである。
これを受けて今日のところでは、ヨブ記の主題にもなっている、この「人生の矛盾、不合理」というものがどのように旧約聖書の中でとらえられているかを、「エレミヤ書」、詩編の「知恵の詩」などからたどっていく。それでは読み始めよう。
「人生の矛盾、不合理」とエレミヤ
ここから著者は、ヨブ記から少し離れ、この人生の矛盾・不合理と信仰の問題についてさらに追及している。
著者は、このようないわば人生の矛盾、不合理を旧約の歴史において始めて問題にしたのは予言者エレミヤであると思うと言っている。
主よ、わたしがあなた(ヤーウェ)と論じ争う時、
あなたは常に正しい。
しかしなおわたしはあなたの前に、
さばきのことを論じてみたい。
悪人の道のさかえ、
不誠実な者がみな繁栄するのは何故ですか。(エレミヤ書一二ノ一)(抜粋)
ここで「正しい」と形容詞で書かれているが、その名詞は「正義」である。この正義は神の支配の原理と考えられる。そして「裁き」は、この原理の具体化となる。つまり「正義」と「裁き」は、プリンシプルとプラクティスの関係となる。
聖書の立場では、義しくない神は言葉の矛盾で、ことに旧約聖書では、正義は基本原理である。しかし、その具体化はどうであろうか。エレミヤは、「不誠実な者がみな繁栄するのは何故ですか」と疑問を呈している。そして、
あなたが彼らを植えられたので、
彼らは根づき、育って、実を結びます。
彼らは口ではあなたに近づきますが
心はあなたから遠さかっています。(一二ノ二)(抜粋)
と言ってこのような現実に対して抗議している。
このようなプリンシプルとプラクティスとの矛盾は国や民俗の如何を問わず、時代の如何を問わず常に起り来る問題であり、平たく言えば正直者が馬鹿を見、悪がしこい人間が得をする、それが現実の人生だということになる。(抜粋)
このような訴えはエレミヤの人生から出てきている。エレミヤは予言者として神に召されたが、エレミヤのいう神の言に対して、人々は彼を嘲笑し、軽蔑し、攻撃し迫害した。そのため、神に「欺かれて」予言者とせられたのではないかと真剣に悩む。
主よ、あなたがわたしを欺かれたので、
わたしはその欺きに従いました。
あなたがわたしよりも強いので、
わたしは説き伏せられたのです。
わたしは一日中、物笑いとなり、
人はみなわたしをあざけります。
それはわたしが語り、呼ばわるごとに、
「暴虐、滅亡」と叫ぶからです。
主の言葉が一日中、
わたしのはずかしめと、あざけりになるからです。(二〇ノ七、八)(抜粋)
知恵の詩 三七篇
旧約聖書の詩編にある知恵の詩の三七篇がこの問題をとりあげている。
人の歩みは主によって定められる。
主はその道を喜ばれる。
たといその人が倒れても、
全くうち伏せられることはない。
わたしはむかし年若かった時も、年老いた今も、
正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が、
食物を請いあるくのを見たことがない。(三七ノ二三-二五)(抜粋)
この詩は、神の正義が必ず地上において成就するという確信を歌ったものである。ただし、それには時間を必要とする。
天上における神の正義が地上において見るためには時間が必要であるとし、忍耐が肝要である。そして、
主の前にもけだし、耐え忍びて主を待ち望め、
おのが道を歩んで栄える者のゆえに、
悪いはかりごとを遂げる人ゆえに、心を悩ますな。
怒りをやめ、憤りを捨てよ。
心を悩ますな、これは悪を行うに至るのみだ。(三七ノ七、八)(抜粋)
この詩編三七篇では、神の正義は地上において行われるが、それには長い時間をかけ、さまざまな経験を経て承認されるとしている。詩人はこのように神の応報賞罰を確信している。
知恵の詩 七三篇
この問題と同じ問題を取り扱っているが、どんなに長い時間をかけても、忍耐してもそのような結果とならないと歌っているのが知恵の詩の七三篇である。
見よ、これらは悪しき者であるのに、
常に安らかで、その富が増し加わる。
まことに、わたしはいたずらに心をきよめ、
罪を犯すことなく手を洗った。
わたしはひめもす打たれ、
朝ごとに懲らしめを受けた。
もしわたしが「このような事を語ろう」と言ったなら、
わたしはあなたの子らの代を誤らせたであろう。
しかしわたしがこれを知ろうと思いめぐらしたとき、
これはわたしにめんどうな仕事のように思われた。(七三ノ一二-一六)(抜粋)
詩人はこのような矛盾のため心からは確信を失いよろめいた。
神は正しい者に向かい、
心の清いものにむかって、まことに恵みふかい。
しかし、わたしは、わたしの足がつまずくばかり、
わたしの足がすべるばかりであった。
これはわたしが、悪しき者の栄えるのを見て、
その高ぶる者をねたんだからである。(七三ノ一-三)(抜粋)
このように詩人は、考えれば考えるほど理由がわからなくなりそして、
わたしがこれを知ろうと思いめぐらしたとき、これはわたしにめんどうな仕事のように思われた。わたしが神の聖所に行って、彼らの最後を悟り得たまではそうであった(詩編七三ノ一六、一七)(抜粋)
ここで「めんどうな仕事」とは直訳的には「労苦」である。この「労苦」は伝道の書(「コヘレトの言葉」)にしばしば用いられている。つまり人間が如何に労苦しても甲斐がないということである。詩人はその後に神の聖所に行って悪人の終わりがどうであるかを考えたとき、なにがしかの理解を得たと感じたのである。
ここに出てくる「伝道の書」=「コヘレトの言葉」については、『コヘレトの言葉を読もう』を参照のこと。確かに、「労苦」ってことが言われていましたね。
それから、この部分は、引用の順番がひっくり返っていて意味が取りづらいので注意してね。(つくジー)
アウグスティヌスの刺繡のたとえ
要するに神の正義の問題、換言すれば神の世界支配、その秩序の問題は、倫理的に見るだけでは究極の解決は得られない。(抜粋)
アウグスティヌスはこの問題を『秩序』という論文の中で、「刺繍のたとえ」を用いてそれを説いている。世の中の矛盾にのみ目を止めるということは刺繍の裏側から見ていることであり、そこにはいろんな糸が絡まり、何をあらわしているかわからない。しかし、その表側を見ると、始めて美しい景色が描かれていることが分かるのである。
この世界の秩序の問題を倫理の問題としてのみ取り上げることは刺繡の裏側を見ていることになる。しかしその刺繍の表側を翻して見る時、すなわち信仰の問題として取り上げるならば始めてそこに整然たる秩序を発見することができるというのである。それ故アウグスティヌスは我々がこの問題を正しく取り上げようとするならば自分の眼を外から内にむけなければならぬ。すなわち目を外に対して閉じ、内に向かって開かねばならぬといっている。(抜粋)
そして著者は、このような問題を旧約の中で始めて問うたのは、エレミヤであり、ヨブ記もまたこのエレミヤの問題を徹底的に取り組もうとしている文学である、といっている。
関連図書:小友 聡(著)『コヘレトの言葉を読もう 「生きよ」と呼びかける書』 、日本キリスト教出版、2019年
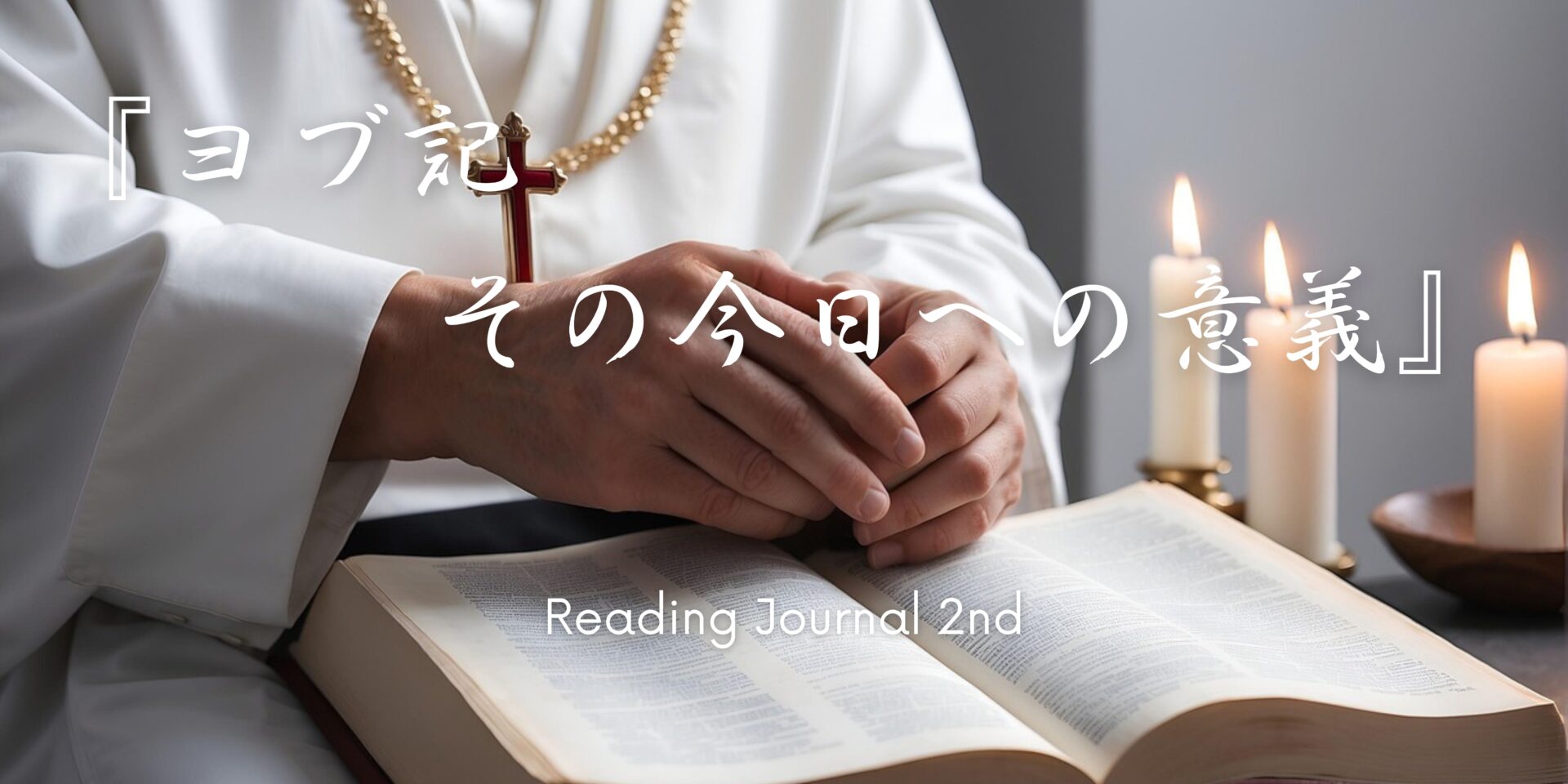


コメント