『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
二 ヨブ記の構造
今日から、「二 ヨブ記の構造」に入る。前回「一 旧約におけるヨブ記の位置」では、旧約聖書では、ヨブ記は知恵文学の一つに数えられら、知恵文学には、「個人的」「人間の経験の要素」「民族を超えた国際性」「人間から神への方向性」の4つが挙げられた。
今日のところ「二 ヨブ記の構造」では、ヨブ記の著者、書かれた時代などの背景、そしてヨブ記構成について説明される。さらに『ヨブ記』は、プロローグ(一章・二章)とエピローグ(四二ノ七以降)が散文で書かれ、他は詩の形式で書かれているが、これを著者は、散文の部分が額縁であり詩文の部分が絵画であるとし、その絵画を眺めることが重要であると言っている。それでは読み始めよう。
『ヨブ記』とは — 名称・作者・成立時期
まず、『ヨブ記』の名称は、主人公のヨブから来ている。この『ヨブ記』の著者については、相当な学識があり、文学的才能に恵まれた敬虔なユダヤ教徒としかわかっていない。著者は、おそらくはヨブのように深刻な苦しみを実際に経験した人と想像されると言っている。
この物語の成立時期については、旧約文学史の後期、それも知恵文学において比較的遅い時期であると推測される。もともとヨブ記の物語の種となる話は古くからあったとしても、現在の形になったのはずっと後世のことである。ギリシャ文化がパレスチナに浸透した時代・紀元前三世紀、四世紀とみる見方もあるが、著者はそれよりも少し早い時代と推測している。
『ヨブ記』の主題・義人の苦難
ギリシァの悲劇・エスキョロスの『縛られたプロメテュース』がヨブ記に近く、これらを比較する研究もあるが、ギリシャ文学の影響をヨブ記に認めることは躊躇すると著者は言っている。
ここで著者は、この時代ヨブ記に取り扱われた主題が、民族や文化の相違を超えて広く真剣に取り上げられざるを得ないような時代背景があったのではないかと言っている。
しからばその問題とは一体いかなるものか。それは詳しく説明するまでもなく、人間は何故苦しまなければならぬのか。しかもある者は自分の責任でないのにかかわらず苦しまなければならぬ。一言にしていえば義人の苦難は何故かということである。(抜粋)
この苦しみは、その原因が不明な場合には、倍増する。義人ヨブは何故苦しまなければならなかったのか、それがこのヨブ記の問題の中心である。
『ヨブ記』の構成
一章と二章は、序曲である。そこには、裕福な家長であったヨブが、一朝にしてその全財産を失い、幸福な家庭を破壊されてしまうこと、さらにヨブ自身が極めて悪病に冒されるという三つの試練について書かれている。
ここで、ヨブの病は、ハンセン氏病と言われるが、聖書では「いやな腫物」(シェヒーン・ラー)と呼ばれ、それは象皮病のことを指すようである。
当時人間の病のうちで考えられる最も重きもの、最も苦しいもの、最も厭うべきもの、それがいやな腫物という語によってあらわされているのであろう。(抜粋)
そしてヨブ記の終曲(四二ノ七以下)では、神の前に懺悔したヨブが、神との和らぐことを得て、彼は不幸以前の繁栄と幸福を回復したことが記されている。悲劇のいわゆるハッピーエンドである。
このプロローグとエピローグは、散文で書かれているが、三章以下は詩の形式で書かれている。
- (イ) 三―三一章:不幸なヨブのもとに遠くから三人の友人(エリパズ、ビルダデ、ゾパル)が訪ねてきて呼ぶと対話する。対話はヨブへの励ましから次第に激しい論争となる。
- (ロ) 三二-三七章:若いエリフの語り。対話でなく独白。
- (ハ) 三八-四一章:神がヨブにたいして嵐の中から語りかける。神の自然創造また自然支配という問題が主として語られる。
- (二) 四二ノ一-六:ヨブは自己の誤りに心から気づき、神の前に懺悔し新しい出発をする。
額縁と絵の関係
ここで著者は、散文と詩文の部分の関係を、散文は額縁、詩はその中の絵である言うことができるとしている。
聖書の大部分の読者は額縁すなわちプロローグとエピローグだけを読み、ヨブ記を大体理解したと考えるのではないかと思う。しかしダイアローグその他の部分を注意深く読むのでなければこの書を正しく理解したとはいえない。(抜粋)
もちろん額縁も重要であるが、絵の方が一層大切である。何故かというと、ヨブの三つの試練の叙述の終わりに一応の結論がでているかららである。
- 一ノ二一:「主が与え、主が取られたのだ。主のみ名はほむべきかな」
- 二ノ一〇:「われわれは神から幸をうけるのだから、災をも、うけるべきではないか」
とあり、試練に対するヨブの信仰の告白が表明されている。
これはヨブ記の結論と言える。しかし、ヨブはこの試練から一直線にこのような結論に到達したわけでなく、義人の苦難という問題の解答を得るまでには、大いなる苦悩を経過しなければならなかった。それが三章以下の友人との対話・論争の中で繰り返し述べられる。ヨブはジグザグ・コースを巡って、何度も同じ主題を巡りながら、ようやく結論に達している。
このようなわけであるから額の額縁のみを見てその中の絵をよく見なければヨブ記が真に解ったとはいえない。(抜粋)
関連図書:アイスキュロス(著)『縛られたプロメーテウス』、岩波書店(岩波文庫)、1974年
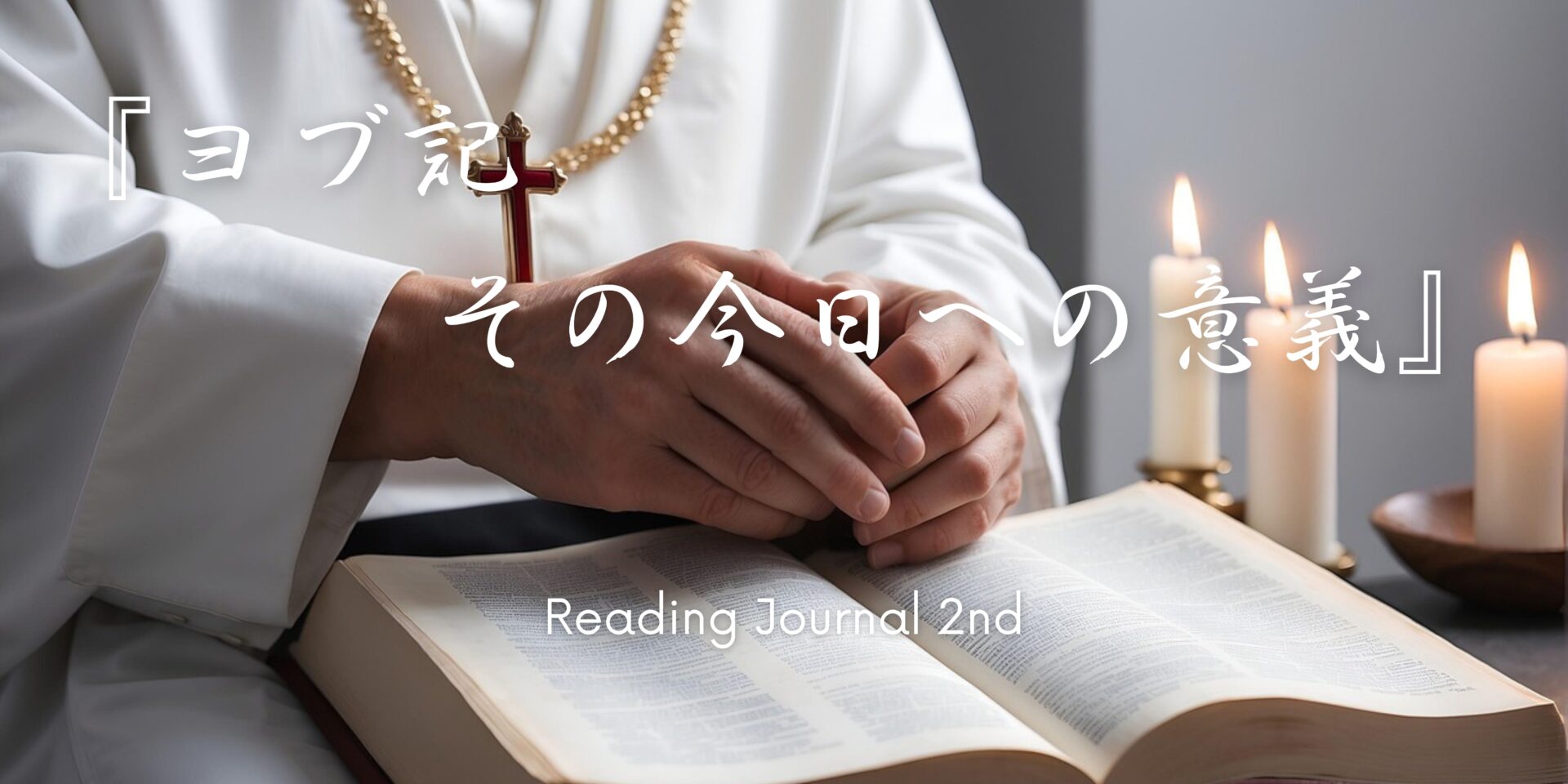


コメント