『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
一一 宗教の益
今日のところは、「一一 宗教の益」である。一〇章(“前半”、“後半”)では、第一三章と共に『ヨブ記』の大きな峰である第一九章を取り扱った。ヨブは、ヨブを贖う者としての神が、地上に降り、彼の義を明らかにすることを確信をもって待ちわびていることが明らかとなる。
それを受けて、今日のところでは、まず一九章に付け加えることとして「ヨブの孤独」について考察され、それに続いて「宗教の益」について言及される。それでは、読み始めよう。
ヨブの孤独
著者は、まず『ヨブ記』の一九章に関連して「ヨブの孤独」について考察している。ヨブは、知人、友人、家族、妻、兄弟に見放され、まったくの孤独の状態となった。しかし、その孤独には積極的な意味もあった、のではないかと言っている。
ヨブは、決死の立場で神と一対一の立場で対決した。孤独はその結果であった。
旧約においても新約においても指導的立場に立たされた者はしばしば一人荒野に退いてその決意を促されている。モーセしかり、エリヤしかり、イエス、パウロ皆しかりである。そこには神と彼らのほか何者もいない。との時彼らは神の聞こえざる声を確かに聞いたわけである。(抜粋)
現代のようなマスの時代では、すべてが数を頼みとするように見えるが、そうなればなるほど一人の意味の重さが大きくなる。ここで著者は、国連事務総長であったダグ・ハマーショルドの遺書『道しるべ』の言葉を引いて、孤独の意味を考えている。
自分の条件でこの星の下に生きるのは、自分の人生が如何なる道筋を辿るかを孤独という代価を払って学ぶことである(二八頁)
自己減却という道を通って完成に赴くためには一人一人が完全に一人切りで進まねばならぬ(三七頁)(抜粋)
現代のようなマスの時代に、自分の立つべき立場に立ち、進むべき道に進む、そして他を容れつつなお自分を守る。そのような生き方は孤独でなければならない。そして、そこにこそ真実な人間としての生き方がある。
以上のことはヨブにもまた通ずるのであって、彼が孤独の悲哀に生きぬき、最後に神から力強い呼びかけを受けるためには一人淋しく荒野の道を歩み通さねばならなかったのであり、そのことによって始めて今一度新しい出発を許されたのである。(抜粋)
「宗教の益」とは
次に著者は、このことに関連して「宗教の益」について考察をする。
不信仰者の言葉とヨブの疑念
「われわれを離れよ、
われわれはあなたの道を知ることを好まない。
全能者は何者なので、
われわれはこれに仕えねばならないのか、
われわれはこれに祈っても、何の益があるか」。(二一ノ一四、一五)(抜粋)
この言葉は、括弧の中にあり、ヨブの言葉ではなく、彼と対立する「悪しき者」「不信仰者」の声である。
この「悪しき者」「不信仰な者」は、放恣的、享楽的な生活をしているが、神に罰せられることはなく、災いや不幸に出会うことがない。これについては詩篇七三篇を参照。ヨブ記にも同じような主旨のことが述べられている。
なにゆえ悪しき人が生きながらえ、
老齢に達し、かつ力強くなるのか。
その子らは彼の前に堅く立ち、
その子孫もその目の前に堅く立つ。
その家は安らかで、恐れがなく、
神のつえは彼らの上に臨むことがない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
彼らは手鼓と琴に合わせて歌い、
笛の音によって楽しみ、
その日をさいわいに過ごし、
安らかに陰府にくだる。(二一ノ七 – 一三)(抜粋)
悪人の家は栄えるのに、ヨブのような義人は、次々と災難に襲われ、そして死を願っても許されない。前掲の言葉は、悪人、不信仰者の言葉であるが、それはヨブの抱いた神の正義についての疑惑もある。
不信仰者が幸福であり、信仰者が不幸である。それゆえ、神に仕えるということは一体どういう「益」があるのか、意味を持つものかということを問題にしている。(抜粋)
この問題は、プロローグでサタンが提出した問題である。サタンは「ヨブはいたずらに神を恐れましょうか」と言っている。この「いたすらに」という言葉は、ヨブの疑念もそこに関連し、悪人の言葉にはサタンの声を聞くように感じる。ここでサタンの言葉や「いたずらに」の意味については、ココを参照。
マラキ書、伝道の書(コヘレトの言葉)と「宗教の益」の議論
著者は、この「宗教の益」に関連して、旧約聖書の最後の予言書であるマラキ書から次の一説を引いている。
あなたがたは言った、「神に仕えることはつまらない[・・・・・]。われわれがその命令を守り、かつ万軍の主の前に悲しんで歩いたからといって何の益があるのか。今われわれは高ぶる者を祝福された者と思う。悪を行う者は栄えるばかりでなく、神を試みても罰せられない。(三ノ一四、一五。傍点著者)(抜粋)
この「つまらない」という語は、「空」という語で、空しいという意味である。この「悲しんで歩く」という語は、「喪服を着て歩く」「陰うつな顔をして歩く」という意味である。つまりまじめな信仰者が陰うつな顔をして歩くというのでは、何の意味があるかということである。
宗教とか信仰とかが我々の日常生活の力とならず、却って重荷になるくらいなら、それは潔く捨ててしまった方が良いのではないか。(抜粋)
このような言葉は、ヨブ記のプロローグでの妻の言葉(ココ参照)に通じるものである。
さらに著者は同様な例を旧約聖書の『伝道の書(コヘレトの言葉)』にもあるとしている。
「伝道の書」は、「空の空、空の空、いっさいは空である」から始まる。そして、旧約の創造という直線的な時間の流れに反して、時間は循環的で、永遠に繰り返され、新しいものは何もないとしている。
この「伝道の書」の「空」は、元来「息」を指している。寒い時に白い息を吐いてもたちどころに消えてしまうように、今あったものがたちどころに消え失われてしまうという意である。この「空」の対義語は「益」である。それも「伝道の書」にたびたび登場する。この「益」は、商用用語での「黒字」の意味である。
「益がない」とはバランスシートに赤字ばかりが出て黒字が残らないことであり、それがまた空ということになる。伝道の書は人間が何をしても益がなく、その意味で空だと言っているのである。(抜粋)
ここの「伝道の書(コヘレトの言葉)」については、小友 聡の『コヘレトの言葉を読もう』に詳しい。小友によると「空」はヘブライ語の「へベル」なのだそうである(ココ参照)。(つくジー)
ヨブ記における「宗教の益」
ヨブ記は宗教は地上的な幸福すなわち「益」を約束しないものだという。絶対的にそういっているとはいえぬにしても、原則的にはそういである。むしろこの書は地上的幸福に問題を感じ、それに挑戦している書物だと思われる。(抜粋)
人間が真に信仰に生きる時、場合によっては生命を危険な状態に置く必要がある、ヨブはそういう態度で神と対決している。
キリスト教の歴史は、聖徒達が死を賭して信仰のために戦った歴史である。著者はそこにこそ信仰の益があると思われると言っている。
信仰とは人間が空とするところに益を見出すことであり、それはいわば無益の益であり、無用の用と見るべきものではないであろうか。(抜粋)
ここで、著者は山本周五郎の『赤ひげ診療譚』を引き合いにだす。主人公の医者は、「徒労に賭ける」と言っている。彼は自分が貧しい人のために働いていることは、その時代の医療制度を考えると無駄であることを十分知っていながら、なおその仕事をやっている。
それは自分の一生を徒労に賭けているからだというのである。(抜粋)
著者は、今日のように人間が絶望を感じ、空虚にならざるを得ない時代にあって、我々が目指すものは、「無益の益、無用の用」というものではないか問うている。
聖書の信仰、広くは宗教といわれる者の持つ時代的な意味はかえってそういうところにありはしないか。それを我々は今日本気で問いつめて行かねばならぬのではないであろうか。(抜粋)
関連図書:
ダグ・ハマーショルド(著)『道しるべ【新装版】』、みすず書房、1999年
小友 聡 (著)『コヘレトの言葉を読もう 「生きよ」と呼びかける書』、日本キリスト教出版局2019年
山本周五郎(著)『赤ひげ診療譚』、新潮社(新潮文庫)、2019年
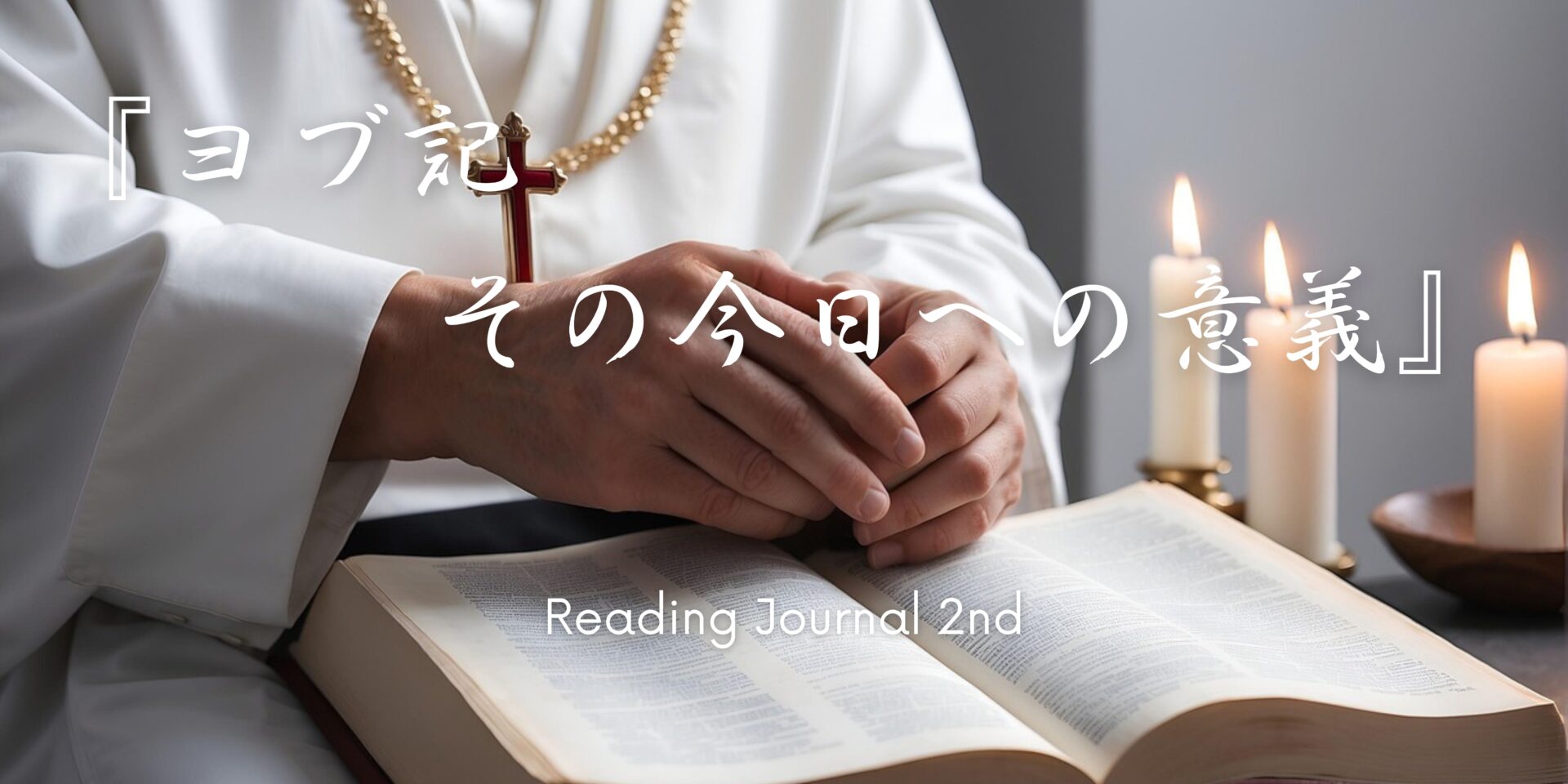


コメント