『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
一〇 ヨブを贖う者 (後半)
今日のところは、「一〇 ヨブを贖う者」の”後半“である。”前半”において、「隠れた神」の考察の後、いよいよ『ヨブ記』の大きな峰である第一九章の話題に移った。そこでは、友人にも神にも頑固なヨブの弱い面が描かれ、それを含めて人間ヨブの全体像であることが示された。
今日のところでは、ヨブを「贖う者」というテーマに差し掛かる。ここでは、「贖う者」の意味を考察し、それが神であり、生きている間に必ず地上に現れるとヨブは確信をもって臨み焦がれていることを読み取っている。それでは読み始めよう。
ヨブの第一の希望
一九章の後半においてヨブは二つのことを願っている。
どうか、わたしの言葉を書きとめられるように、
どうか、わたしの言葉が書物に記されるように、
鉄の筆と鉛とをもって、長く岩に刻みつけられるように。(一九ノ二三 -- 二四)(抜粋)
これがヨブの第一の希望である。ヨブにとって、今彼を理解してくれる人はいない。そのため彼は、知己を後世に求め、言葉が書きとめられ書物のとして残ることを希望している。
ヨブの第二の希望:ヨブを「贖う者」
そして第二の希望として、次のように述べている。
わたしは知る、わたしをあがなう者は生きておられる。
後の日に彼は必ず地の上に立たれる。
わたしは皮がこのように滅ぼされたのち、
わたしの肉を離れて神を見るであろう。
しかもわたしの味方として見るであろう。
わたしの見る者はこれ以外のものではない。
私の心はこれを望んでこがれる。(一九ノ二五 -- 二七)(抜粋)
これが有名なヨブを「贖う者」についての発言である。
「贖う者」の部分の解釈上の問題点
しかし、この箇所は原文の解釈の上で問題が多いとし、それを簡潔にまとめている。
問題点1:「贖う者」の解釈
まず「あがなうもの」の解釈は、旧約では
- 血讐者:人が殺されたときに仇討ちをした血縁者
- ある人の財産を回復する者:これは近親者の責任だった。
- 神ヤーウェ:バビロニアからユダヤ人を解放したのは、神ヤーウェであるが、ヤーウェはイスラエルにとって贖う者である。
- 他の罪を代わって負い、犠牲となった者:イザヤ書の「主の僕」。ここで贖う者に贖罪者という意味が生じイエス・キリストに通じていく。
しかし、ヨブ記の贖う者をこの何れにも当てはまらない。ここでの贖う者はヨブの立場に立って彼の義、その潔白を弁護する者である。それは内容的には「仲裁者」に通ずる。また、九章以後の天にある「証人」、高き所にある「保証人」も贖う者に無関係ではない。
地よ、わたしの血をおおってくれるな。
わたしの叫びを休むところに得させるな。
見よ、今でもわたしの証人は天にある。
わたしのために保証してくれる者は高いところにある。
しからばこのような贖う者は人であるのか神であるのか、それが問題であるが次の言葉は人ではなく神であることを暗示している。曰く
どうか、あなた(神)自ら保証となられますように、
ほかにだれがわたしのために、
保証となってくれる者があろうか(一七ノ三)(抜粋)
ヨブは、神自身が義の保証人になることを切望している。
ここで、ヨブの保証人となる神は、今さまざまな災いでもって彼を打つ、怒りの神である。しかし、神は彼を癒すものでなければならない。ここで、怒りの神を第一の神とすれば、和らぎの神は第二の神となる。しかし第一の神と第二の神は複数の神を指しているのではなく、神の二面性を指していると解釈される。
ここの部分は、上の引用部の問題点の1,2,3,4の問題点1の中に、贖う者の意味1、2、3、4が入れ子に入っているので読みづらいので注意。(つくジー)
問題点2:「後の日」の解釈
第二の問題点は「後の日に彼は必ず知の上にたち」の「後の日」の解釈である。
原文では、ただ「後」であるので、「後のもの」「最後のもの」という解釈もでき、それが「神」という解釈もある。しかし、著者は「後の日」と解釈するのが妥当としている。
問題点3:「地」の解釈
同じく「後の日に彼は必ず知の上にたち」の「地」の解釈が第三の問題点である。
この「地」の原文は、「塵」である。そのため、この地は塵の中の陰府(死んで降りていくところ)であると解釈することもできる。しかし、「塵」は「地」とも同義語であるため、ここでは「地」と解釈するのが妥当である。つまり、ヨブを贖う者は、陰府ではく地上に現れるということになる。
問題点4:「肉を離れて」の解釈
つぎに「わたしの皮がこのように滅ぼされたのちわたしは肉を離れて神を見るであろう」の「肉を離れて」の解釈である。これは伝統的な解釈では、「地上の生命が終わってから」神を見ると解釈され、復活の生命を約束している言葉だと言われるが、この「肉を離れて」は「肉をもって」と解釈することもでき、やはり贖う者として神を見るのは生きている間とするのが適当である。
「贖う者」による義の証し
要するに贖う者は最後において必ずこの地上に立つ時がある。その時、彼の義が明らかにされ、その義しさが証しされるとヨブは言っているのである。(抜粋)
ヨブは、たとえ死の一歩手前であっても、必ず贖う者・神が地上に降り立ち、彼の義を明らかにすると確信している。ヨブは死後に対して何も積極的な期待をしていない(ココ参照)。そのため贖いの神を見うるのはこの地上であり、彼の生命がなお消え尽きる前である。
贖う者が現世において地上に降り立つことの意味
ここで著者は、癌のために斃れた高見順の最後の詩集『死の淵より』から一節を引いて、
人間にとって肉体というものの重要さ、それが死に臨めば臨むほど重要な意味を持つことが率直に歌われているとみてよいであろう。(抜粋)
と言っている。聖書では霊肉の両面から人間の問題としている場合、霊を重要視するのはもとよりであるが、決して肉の働きを軽視してはいない。
角度を変えてみると、へブル人は肉の生活つまり地上の生活を重要視し、信仰の戦いにおける勝敗も地上で決せられるべきと考えていたと考えられる。新約においては、来世と永遠の生命が重要視されるが、それも旧約において地上に重点が置かれているからこそ、来世も重要視されるようになったのである。
我々は現世における問題を現世において取り上げ、それと取り組み、最後まで戦い抜くことにより始めて、来世への正しい期待を持つ資格がある者とされるであろう。もしそうでなければ死後の生御影は一種の迷信、偽りの希望の如きものとなってしまうであろう。(抜粋)
関連図書:高見 順(著)『死の淵より』、講談社(講談社文芸文庫)、2015年
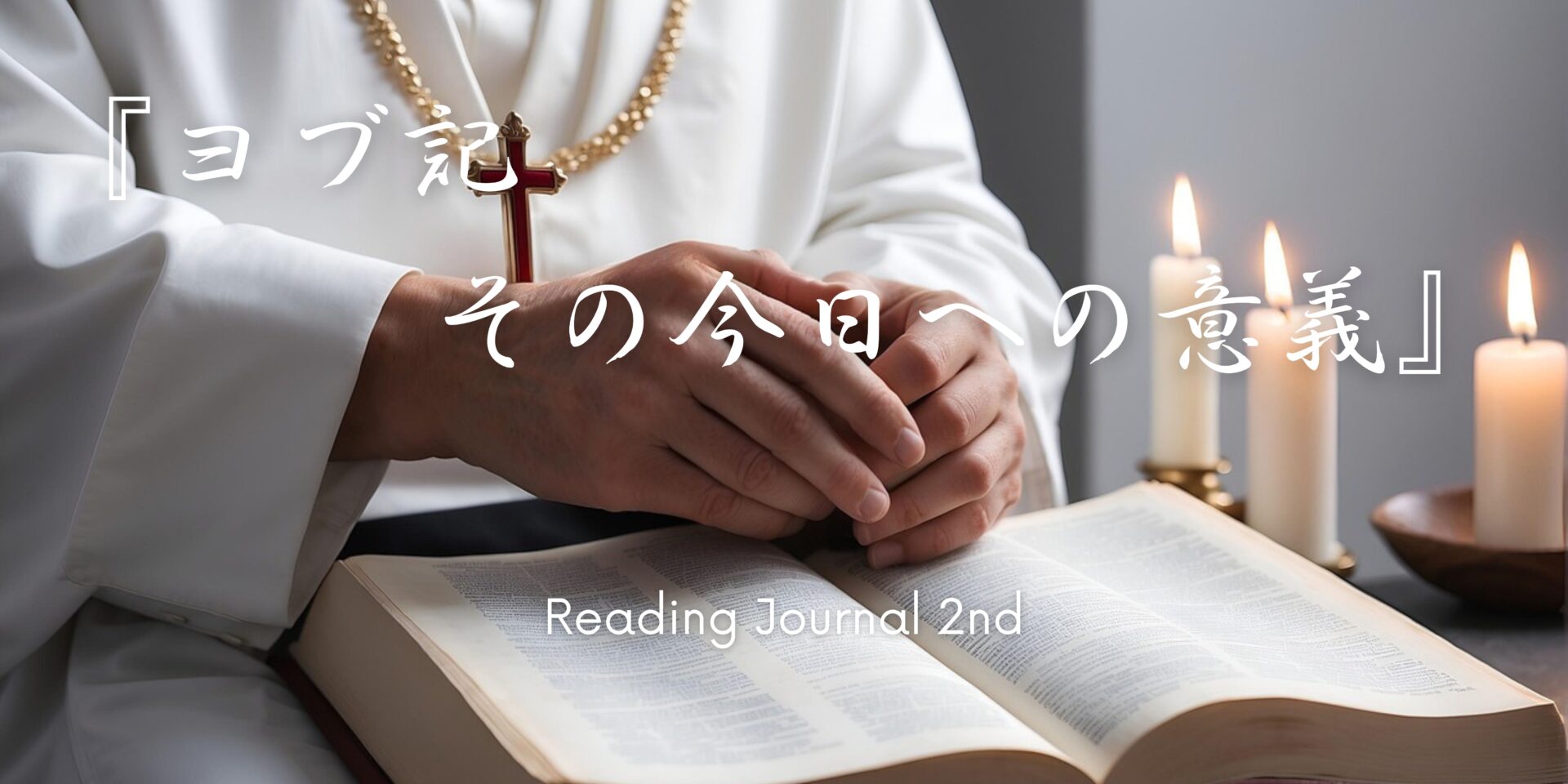


コメント